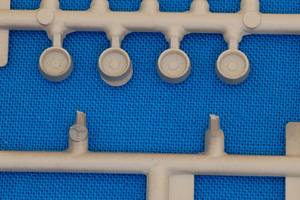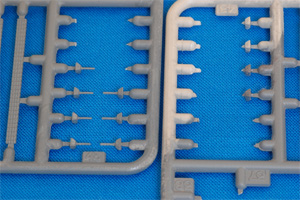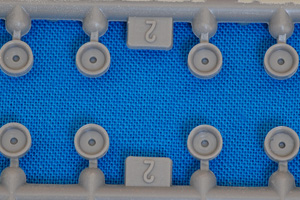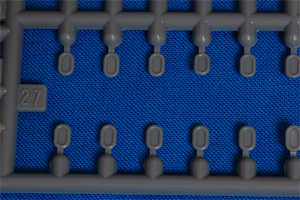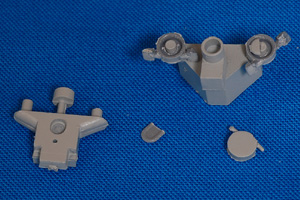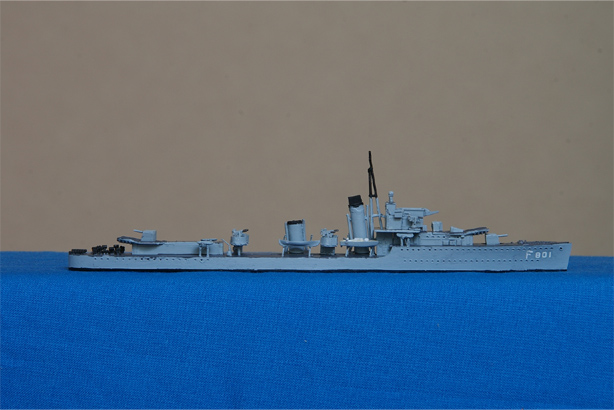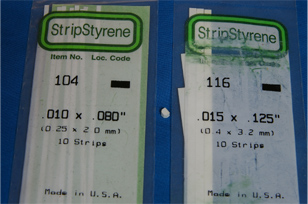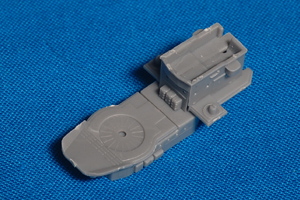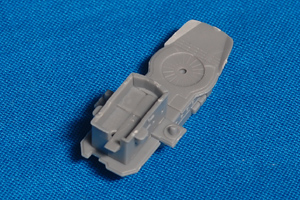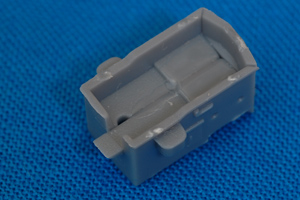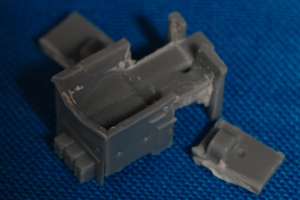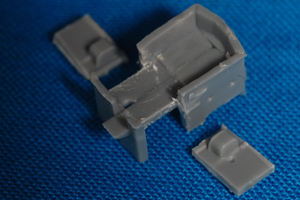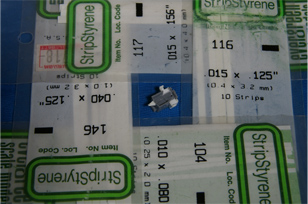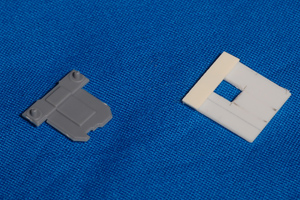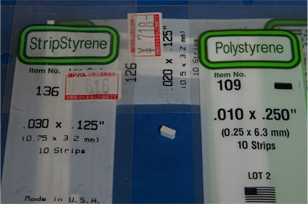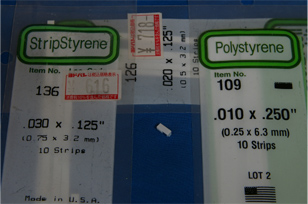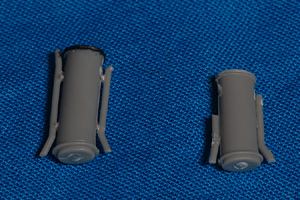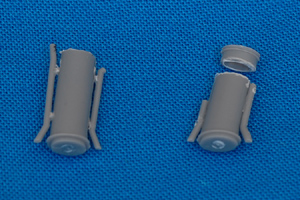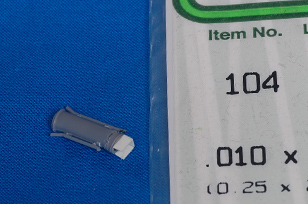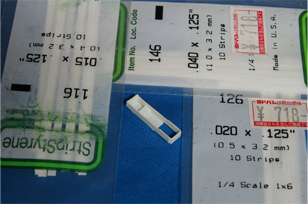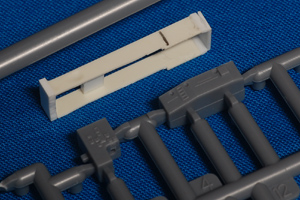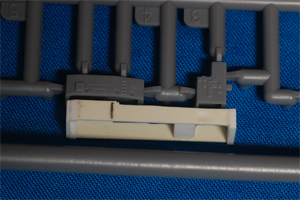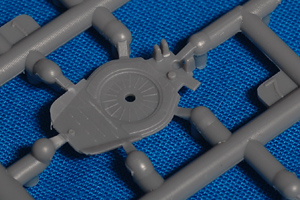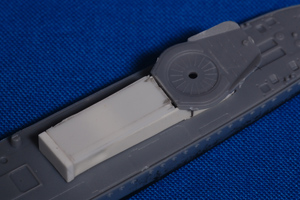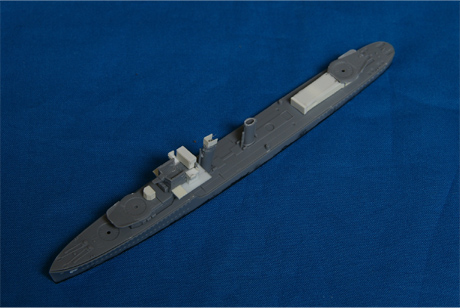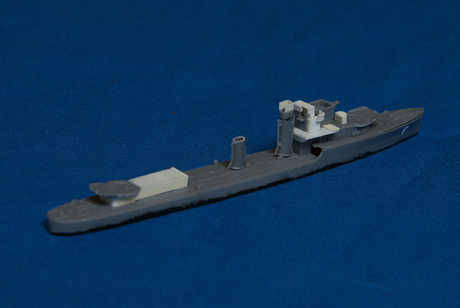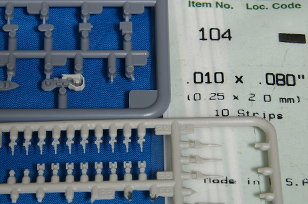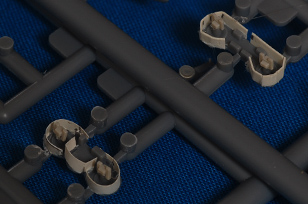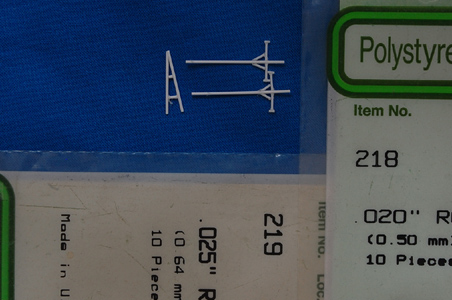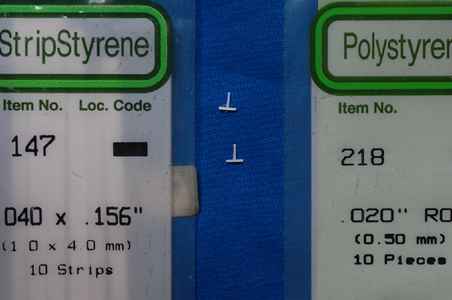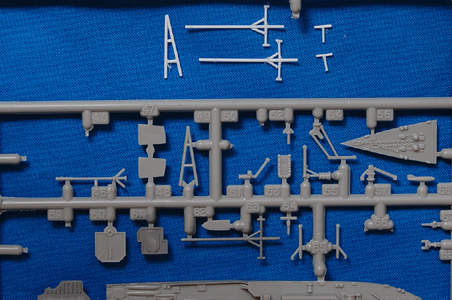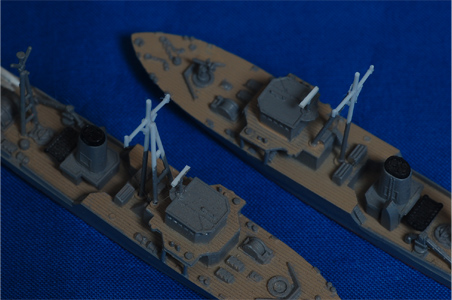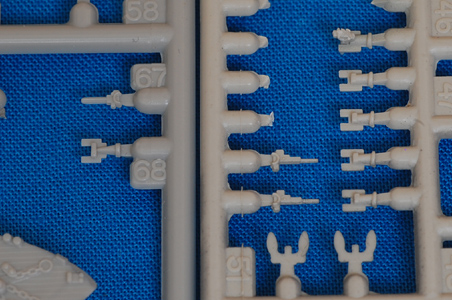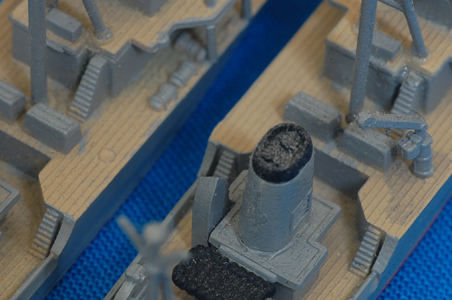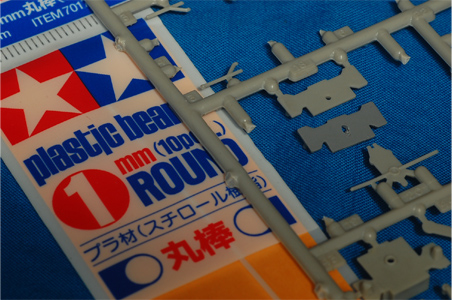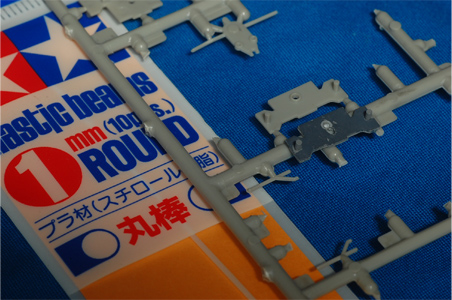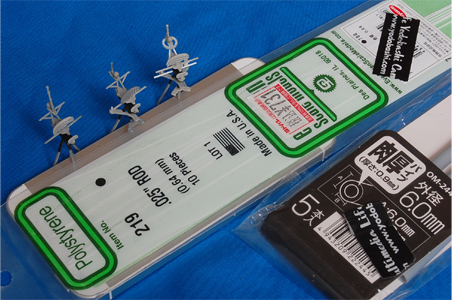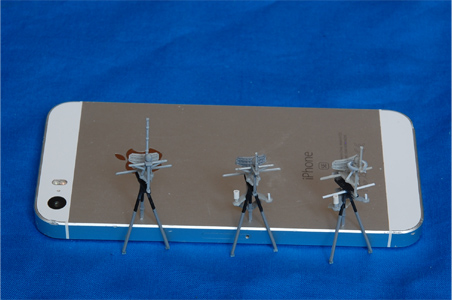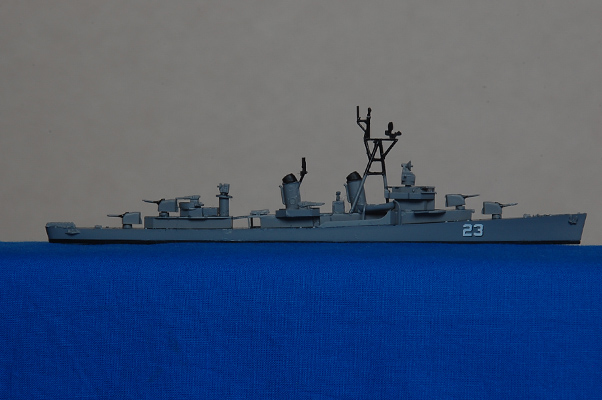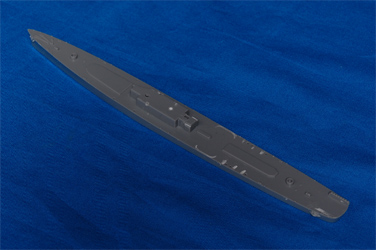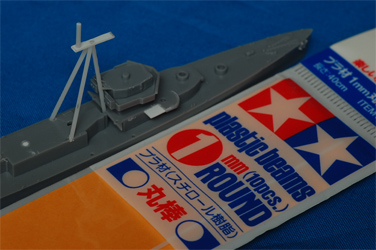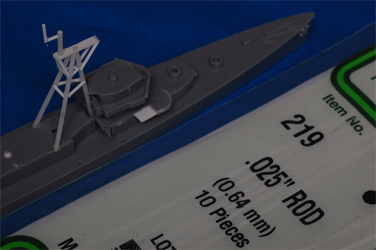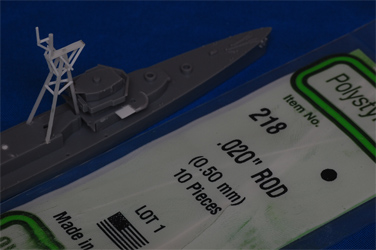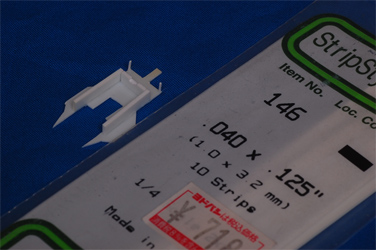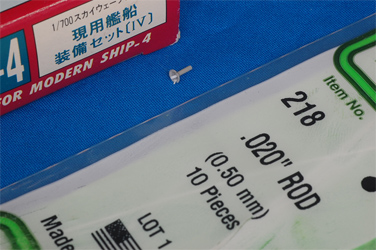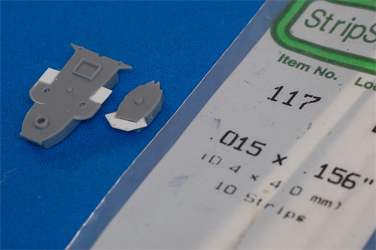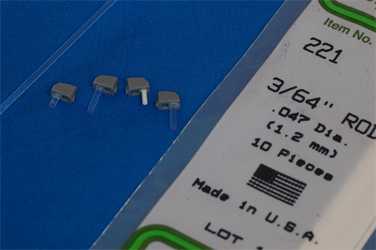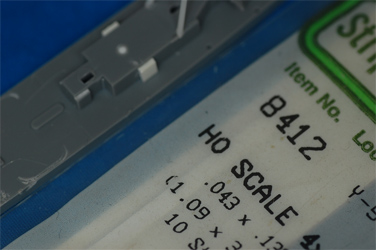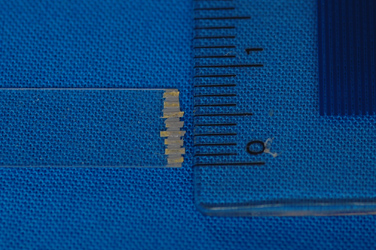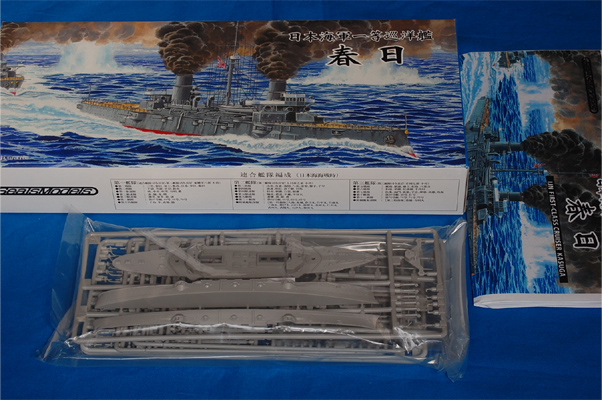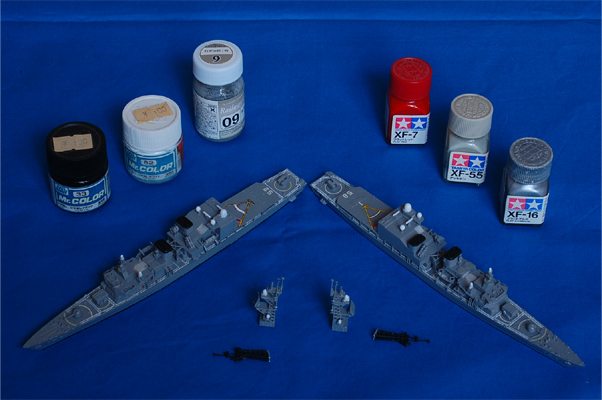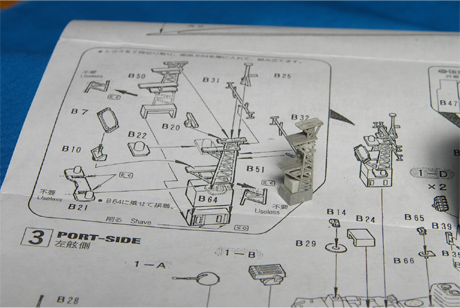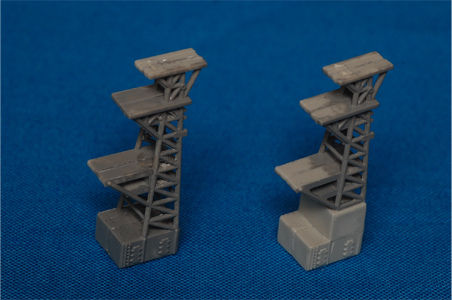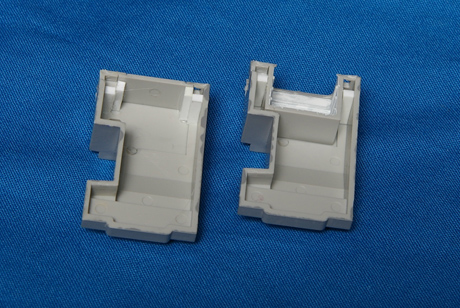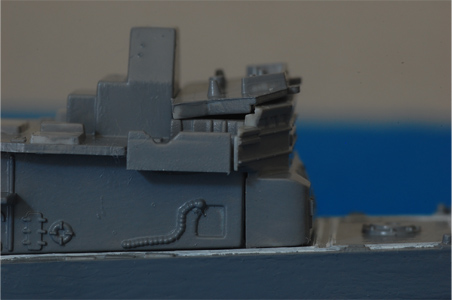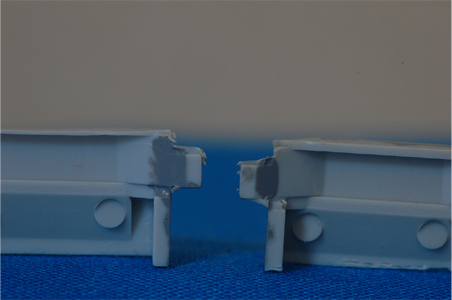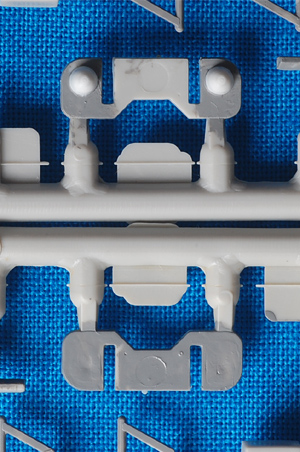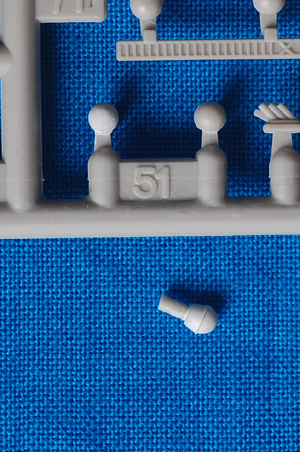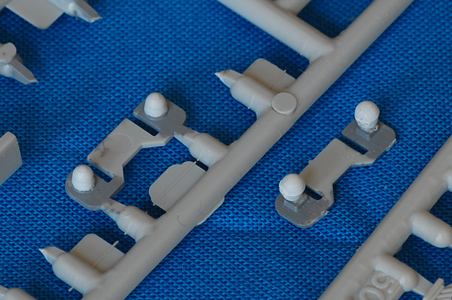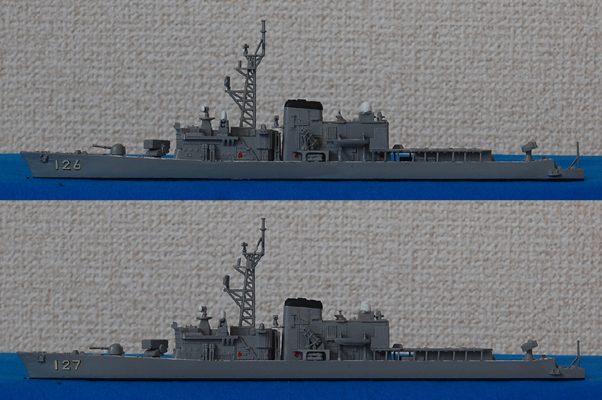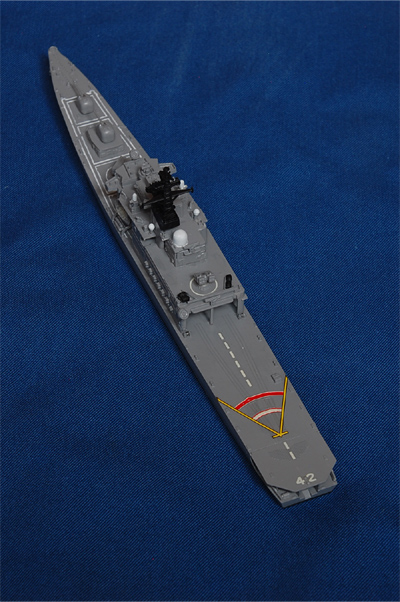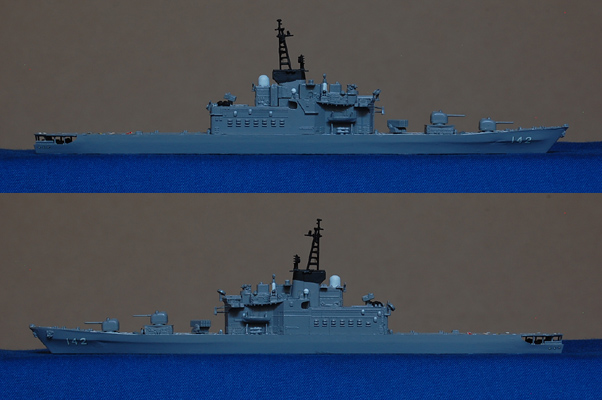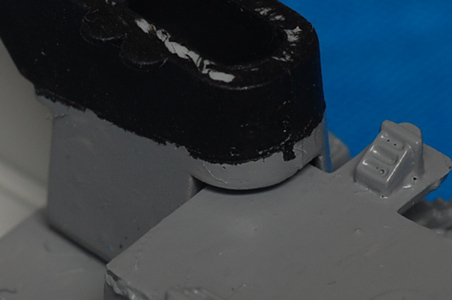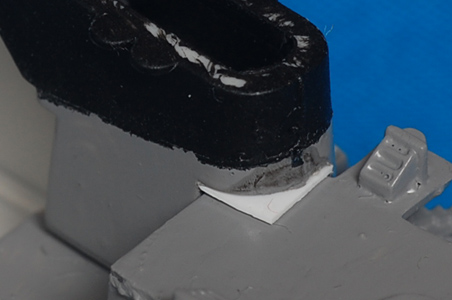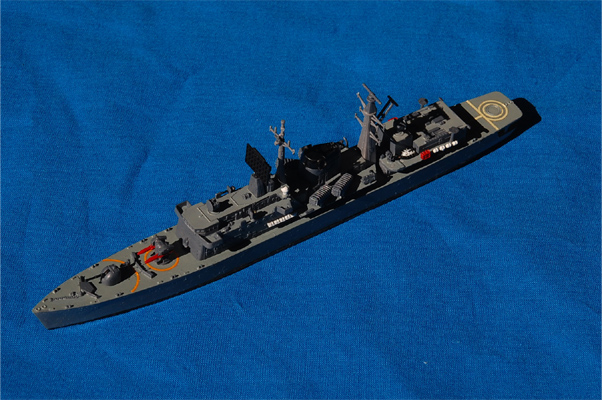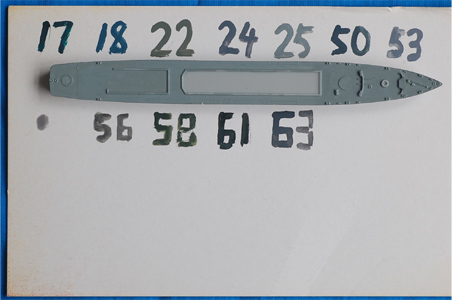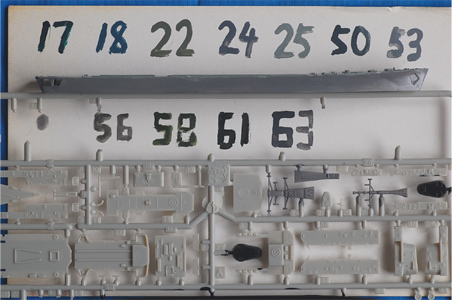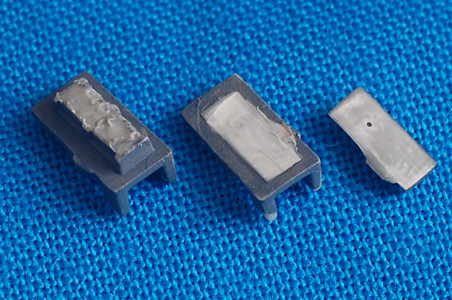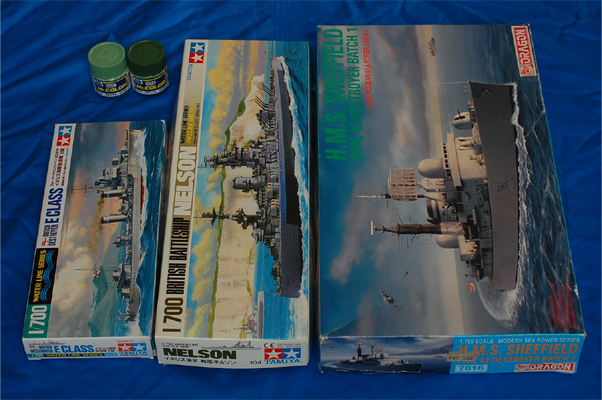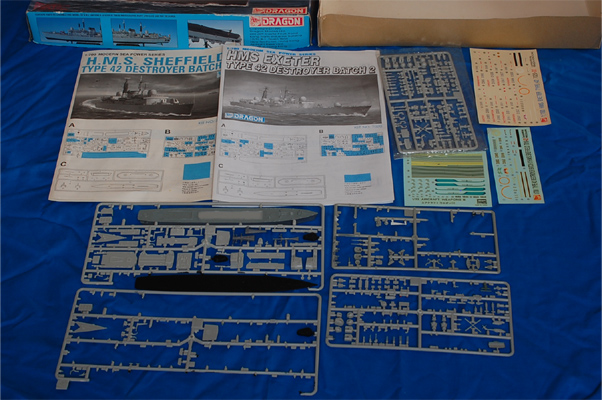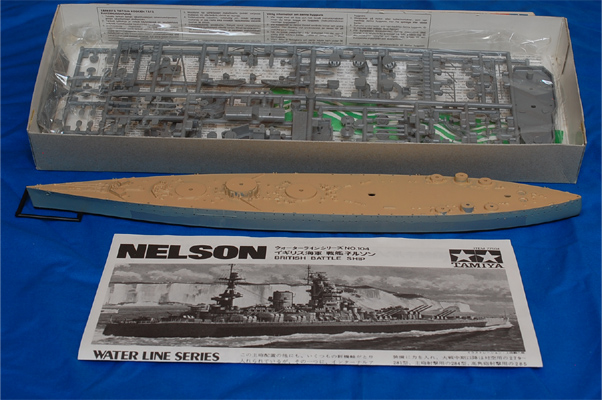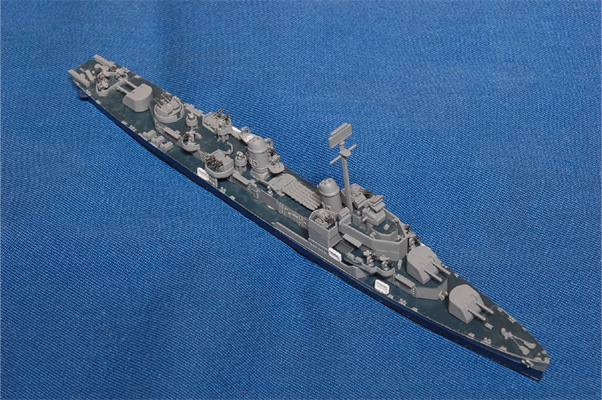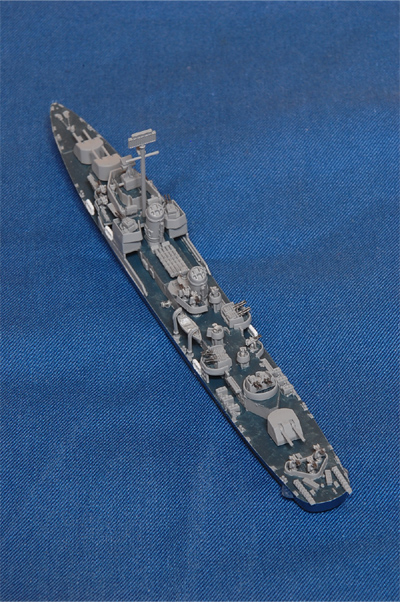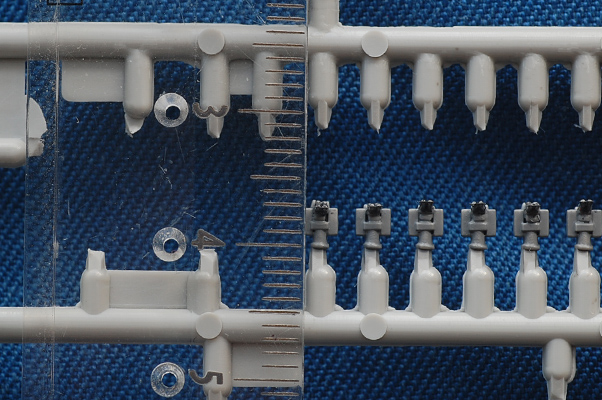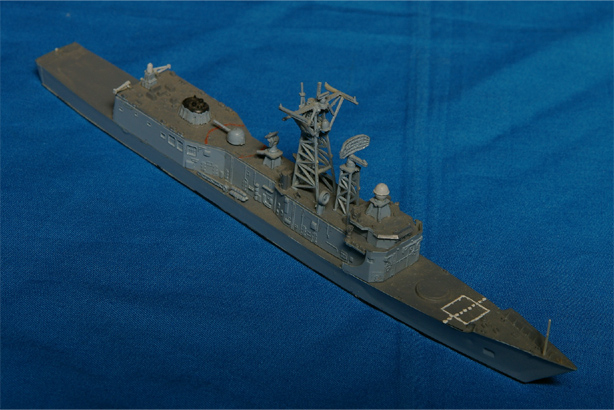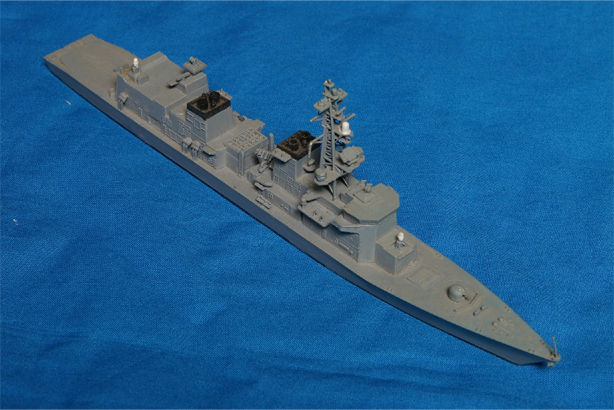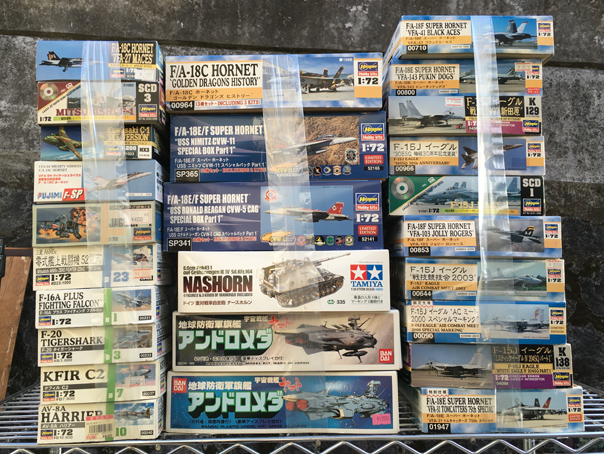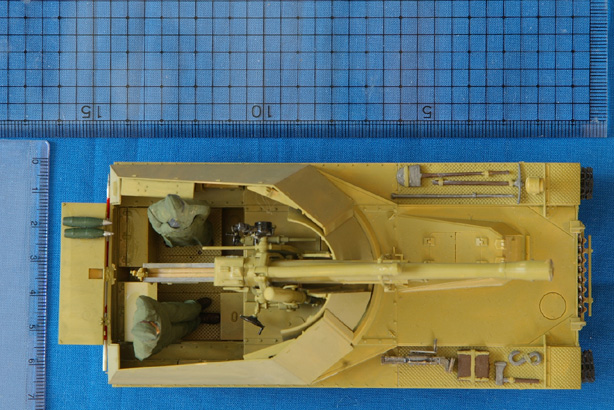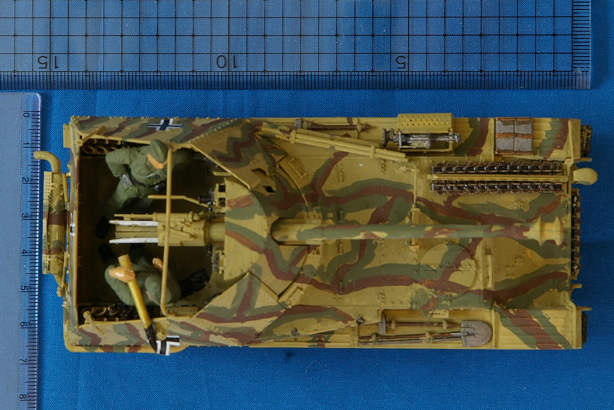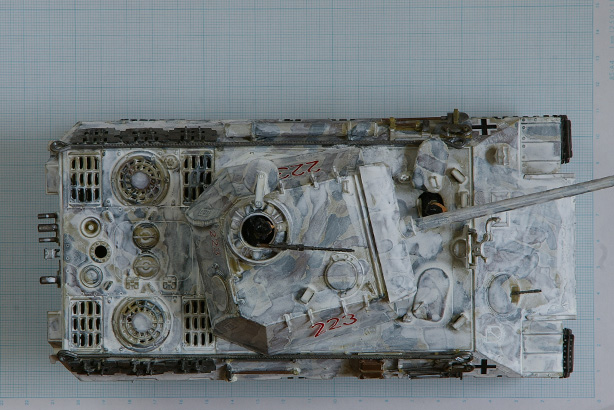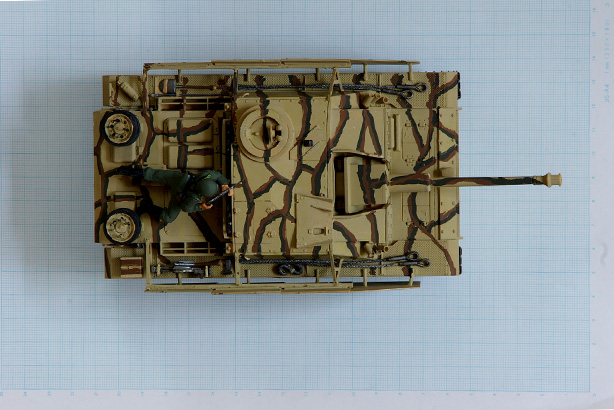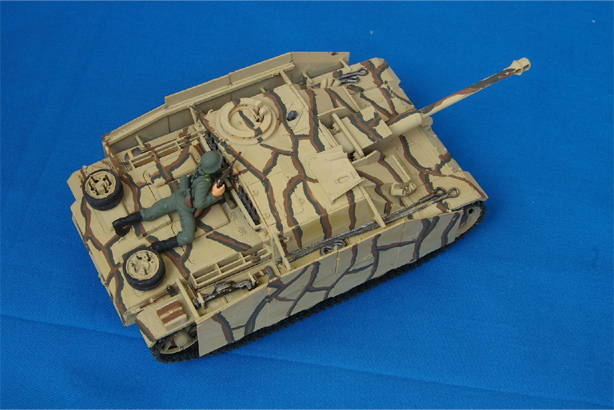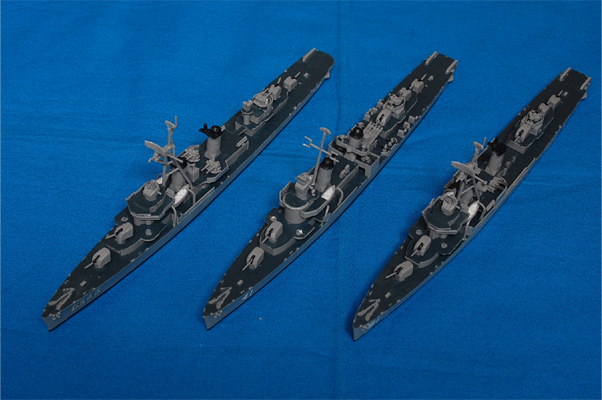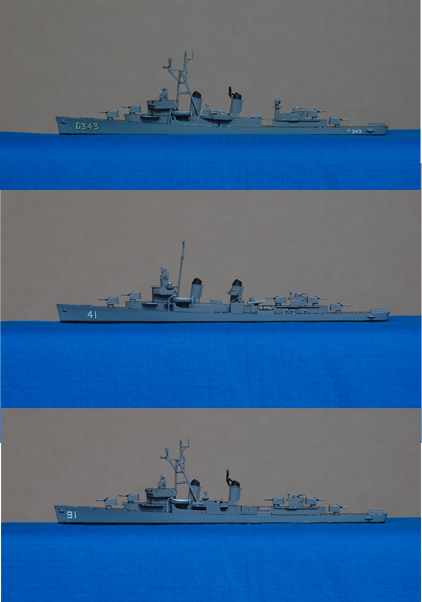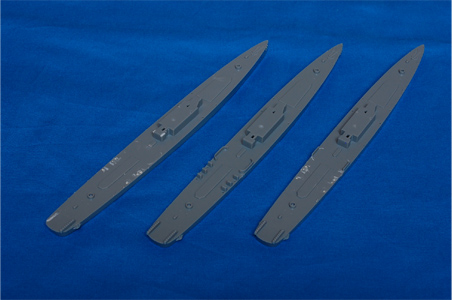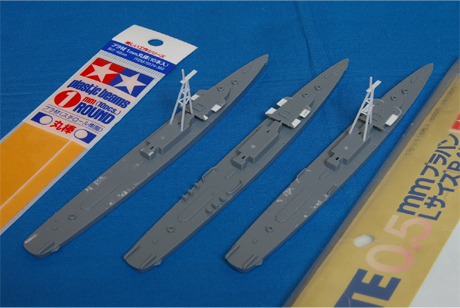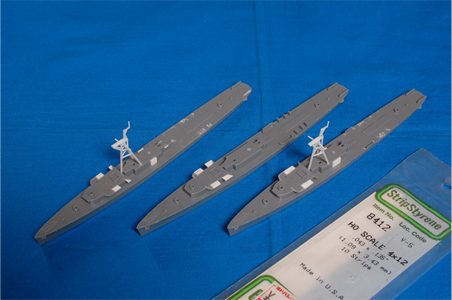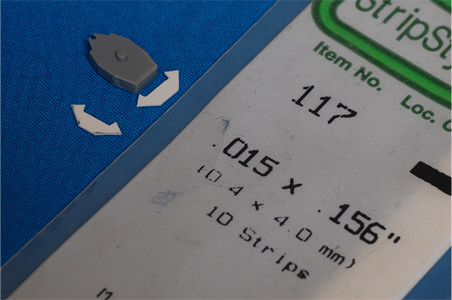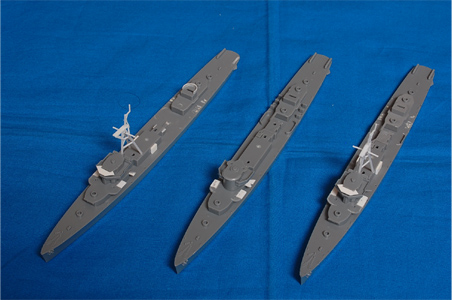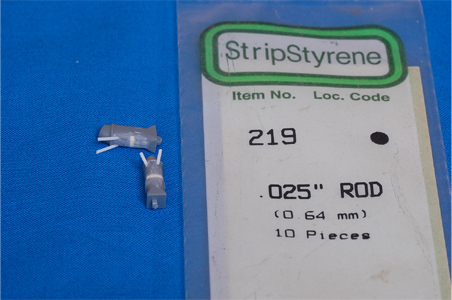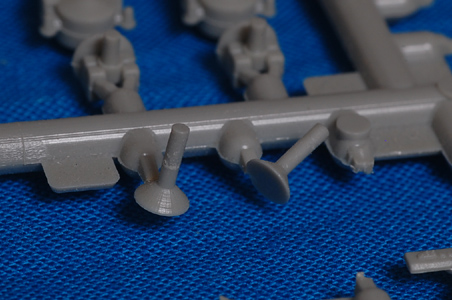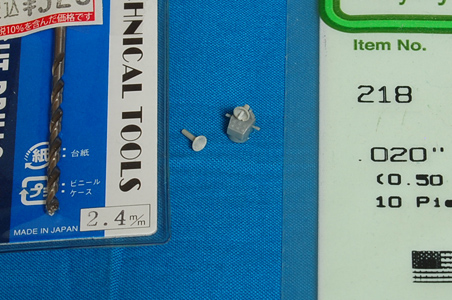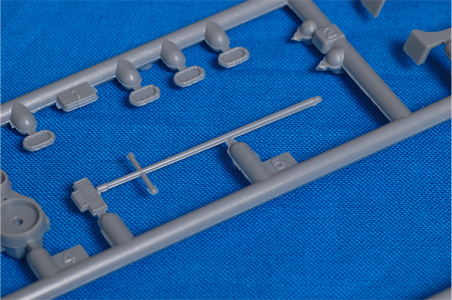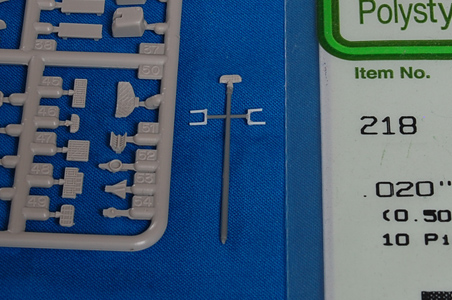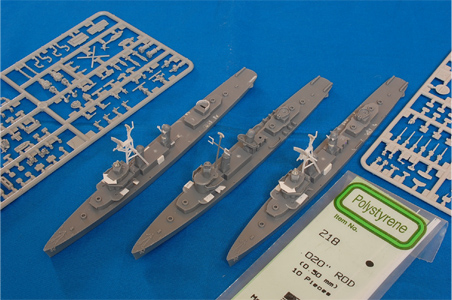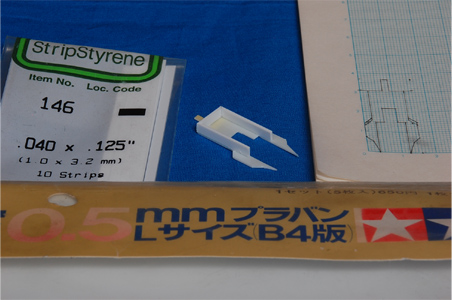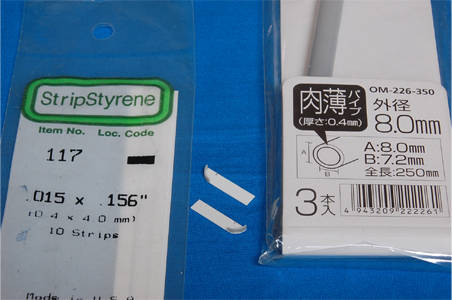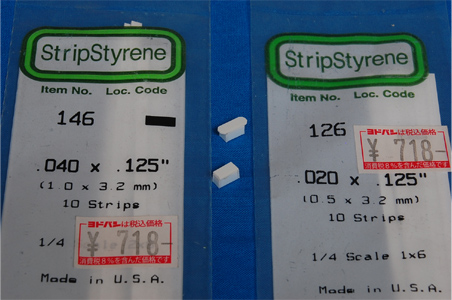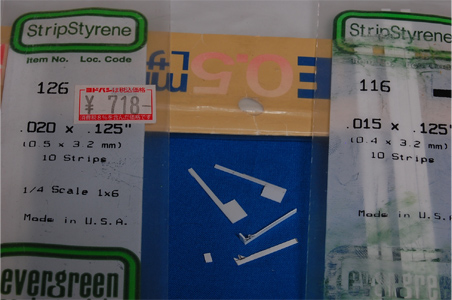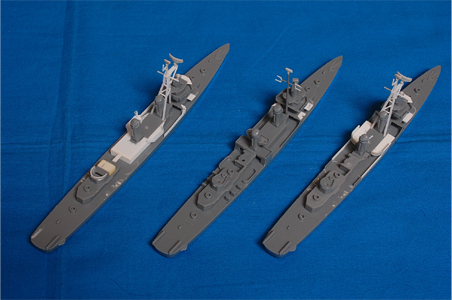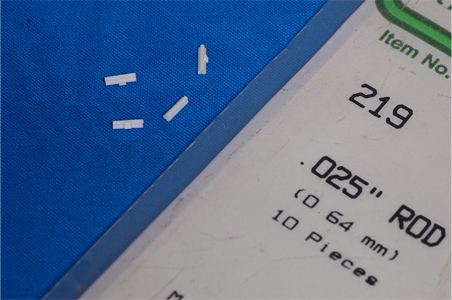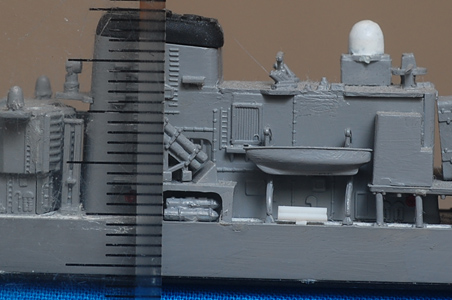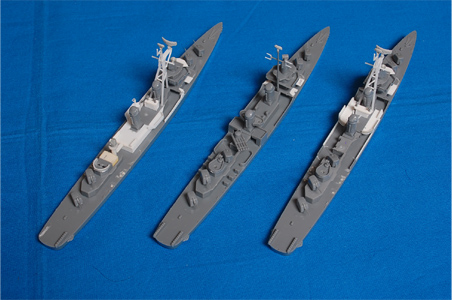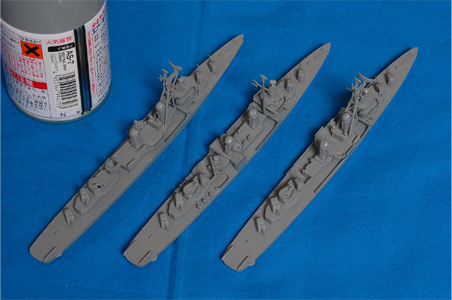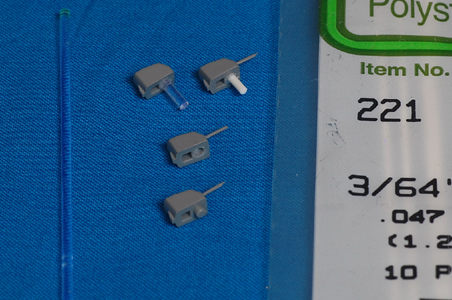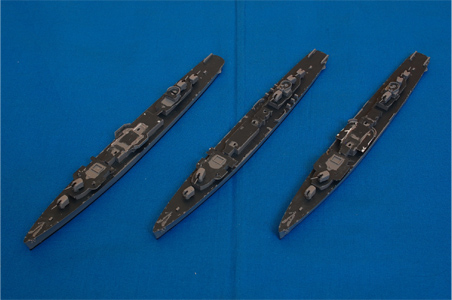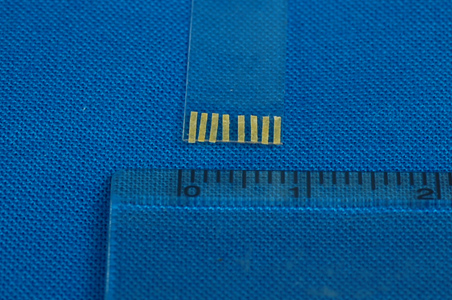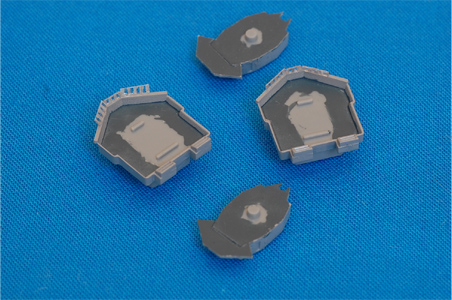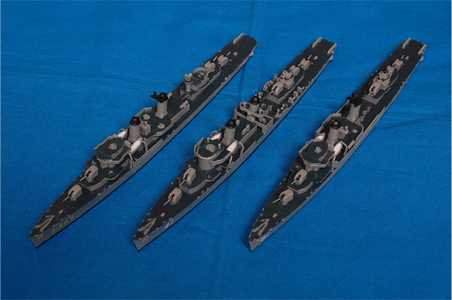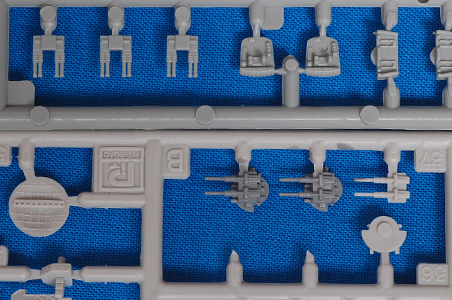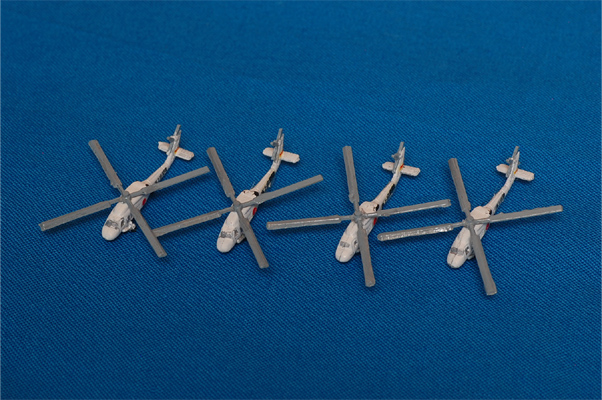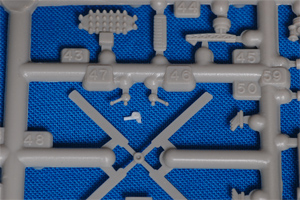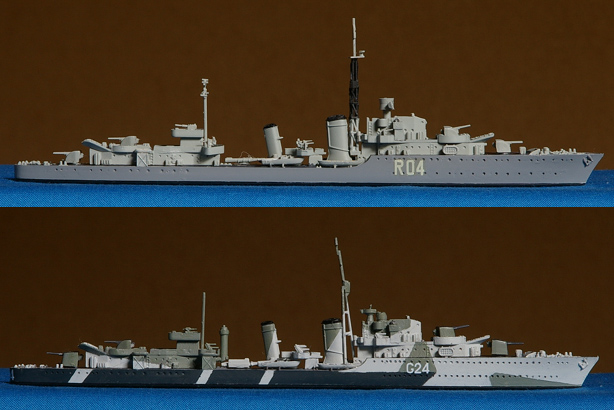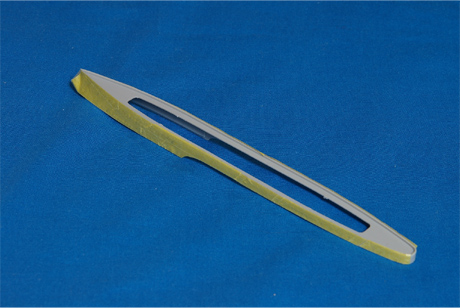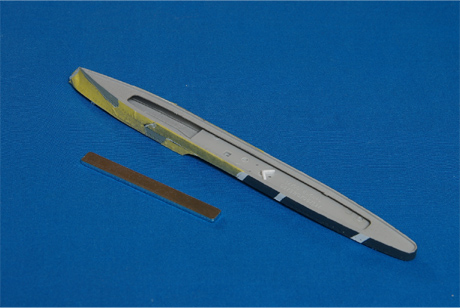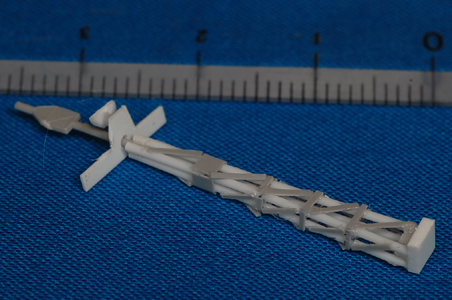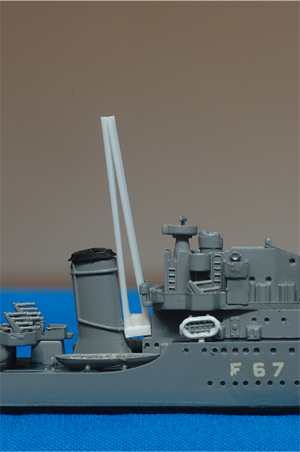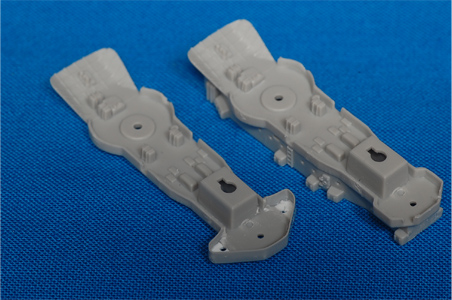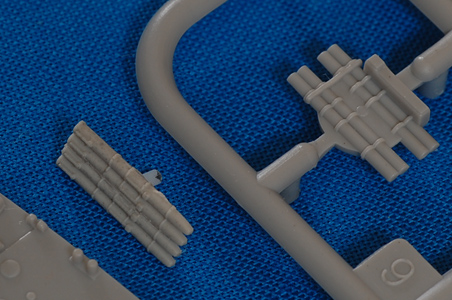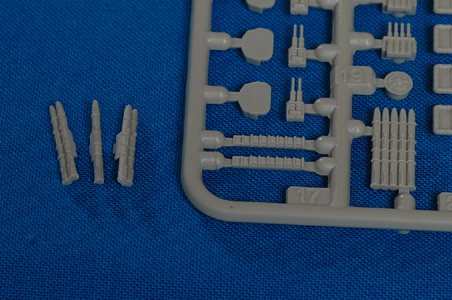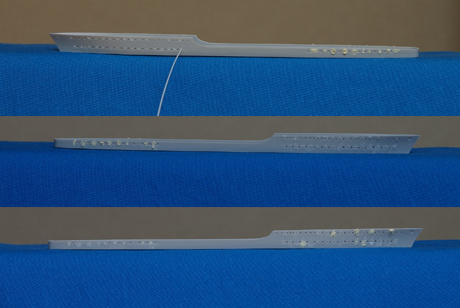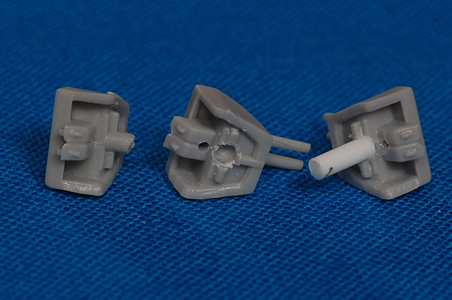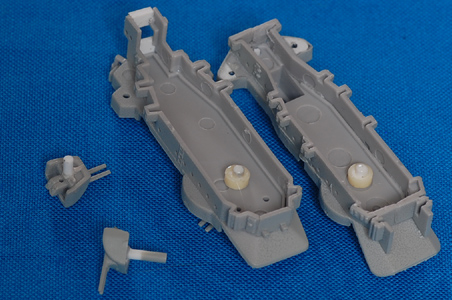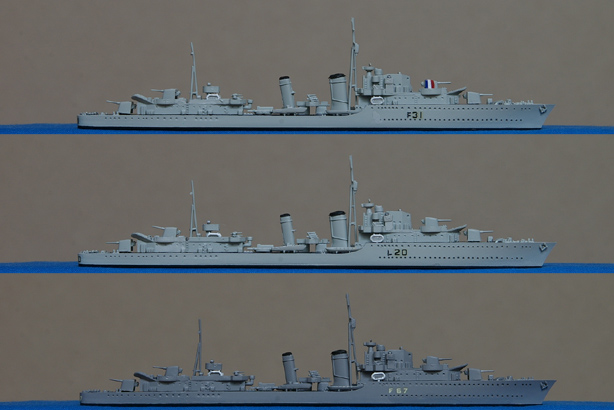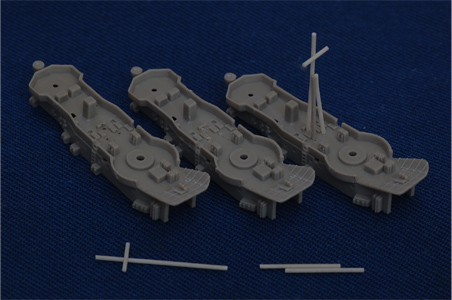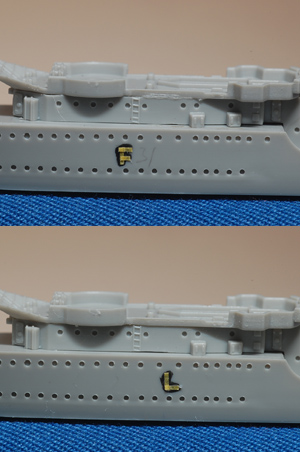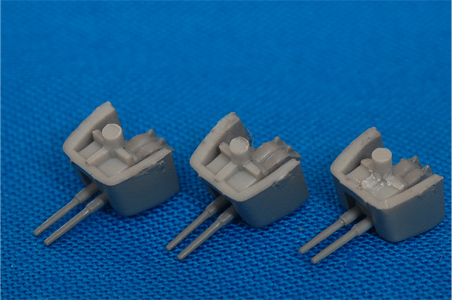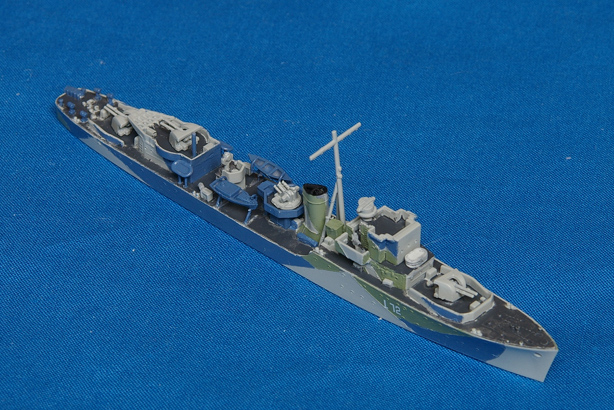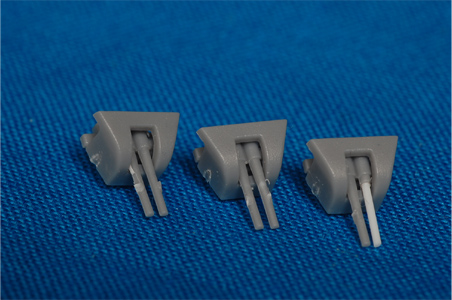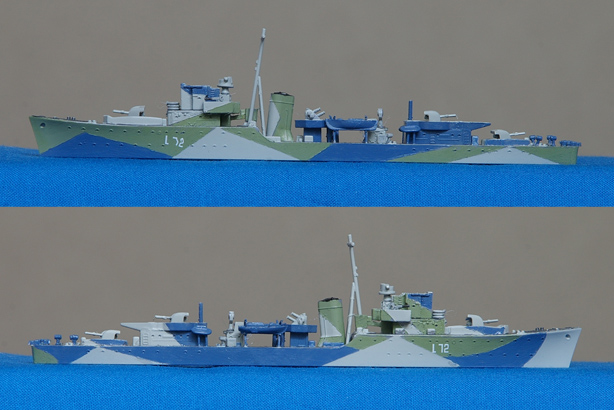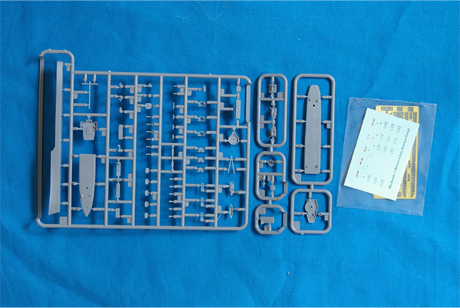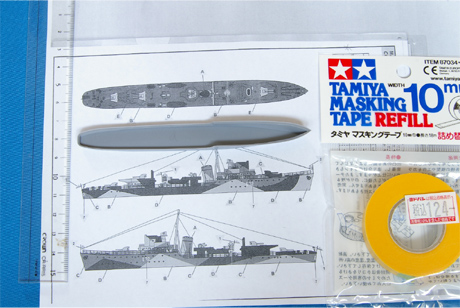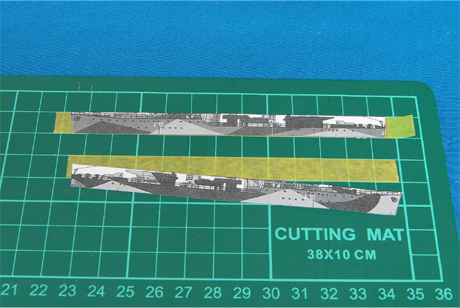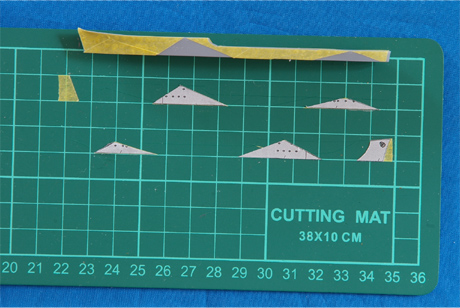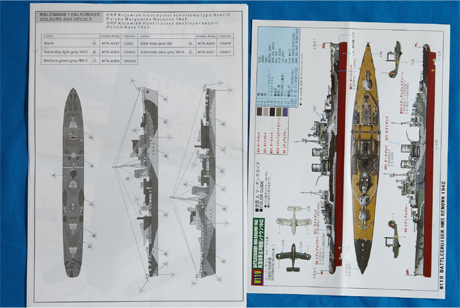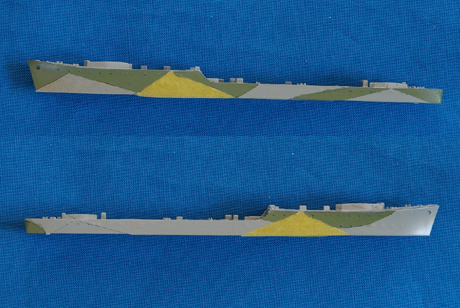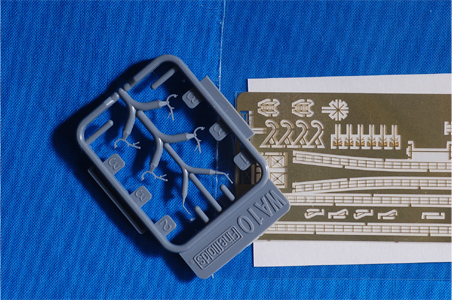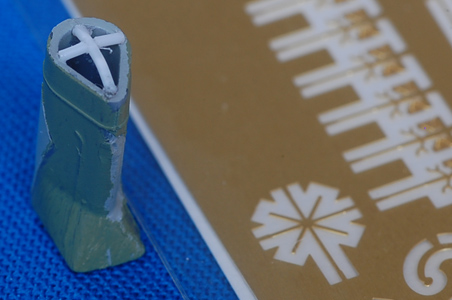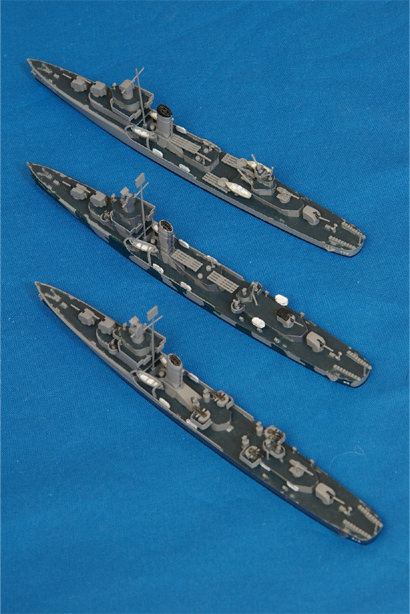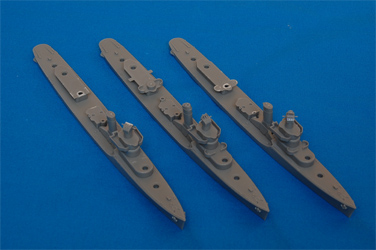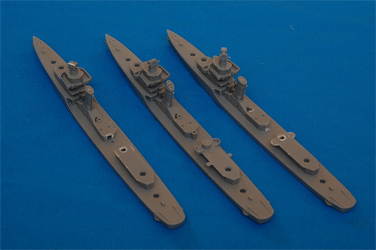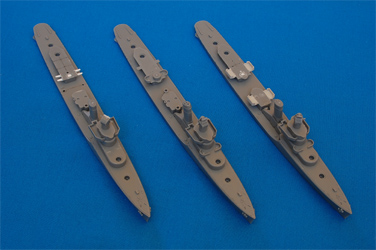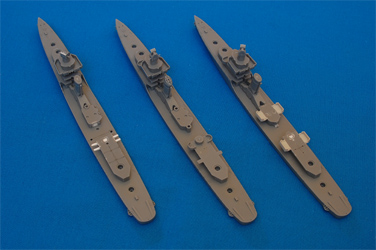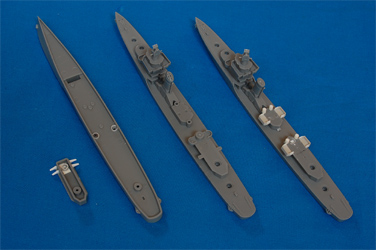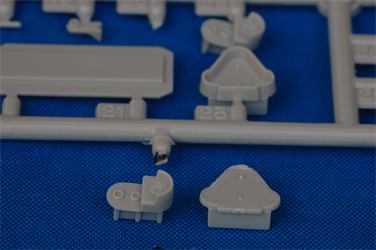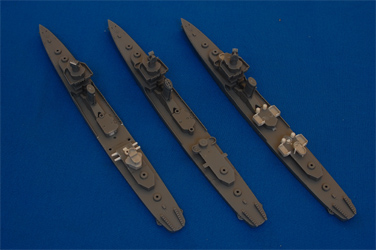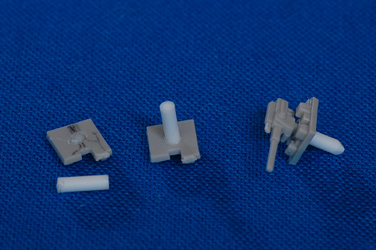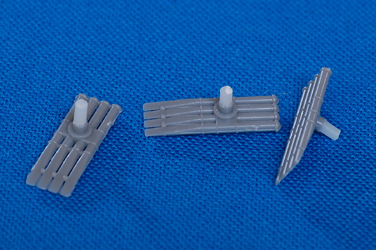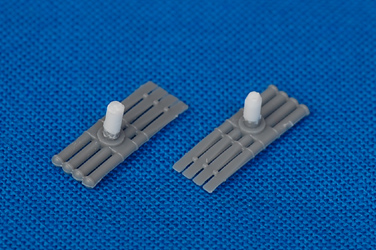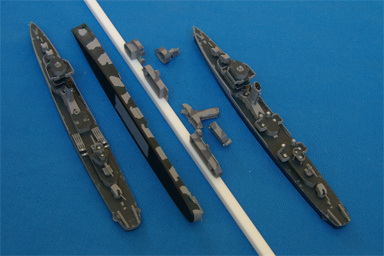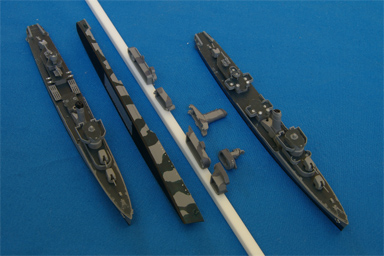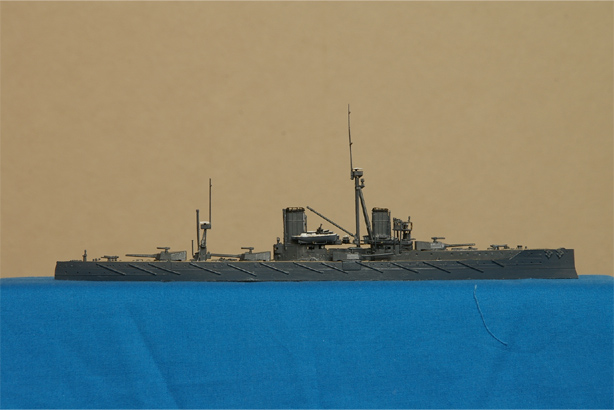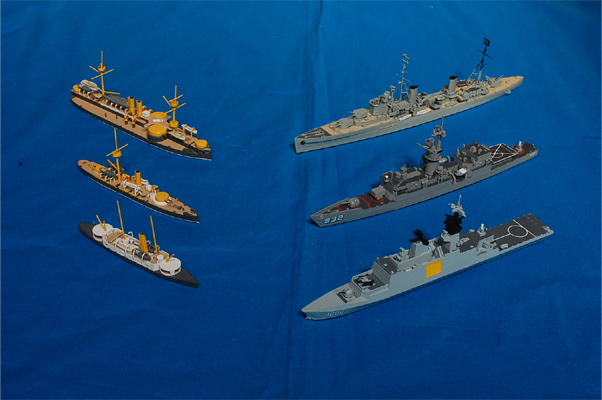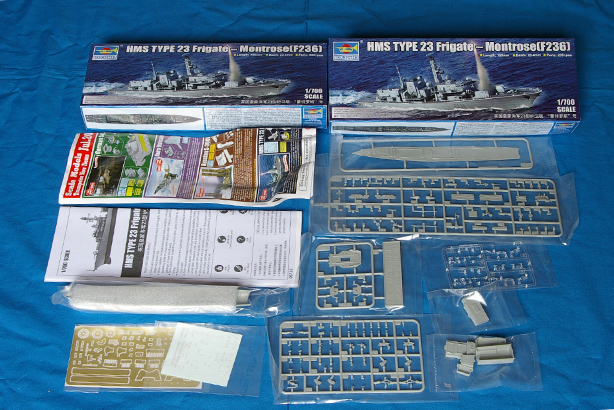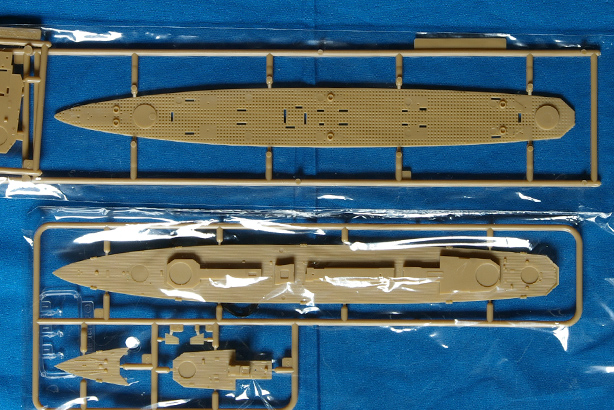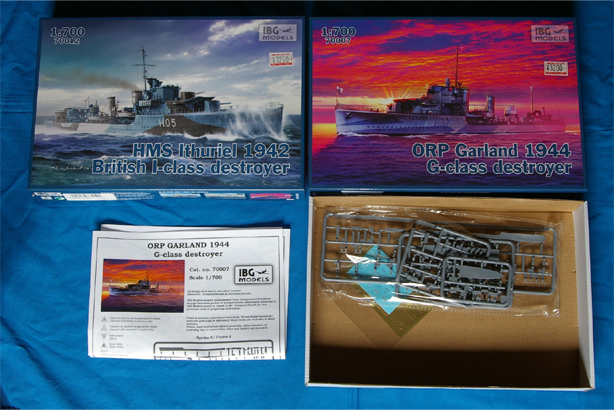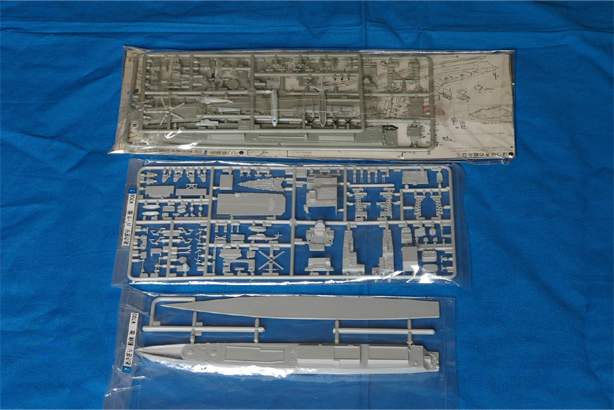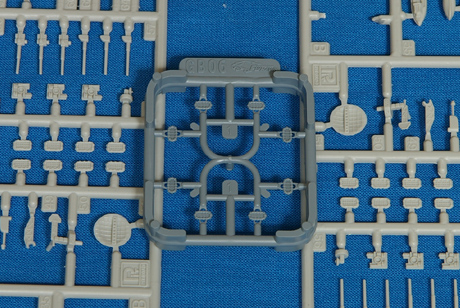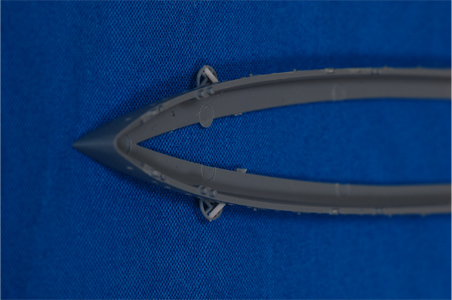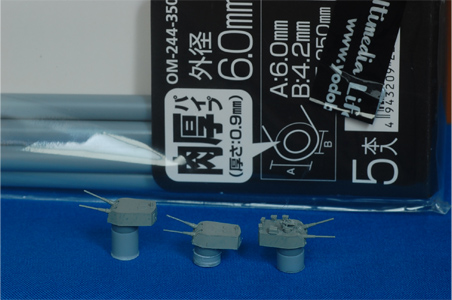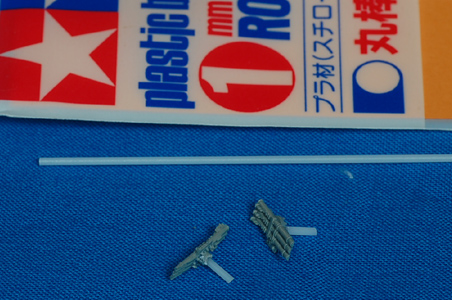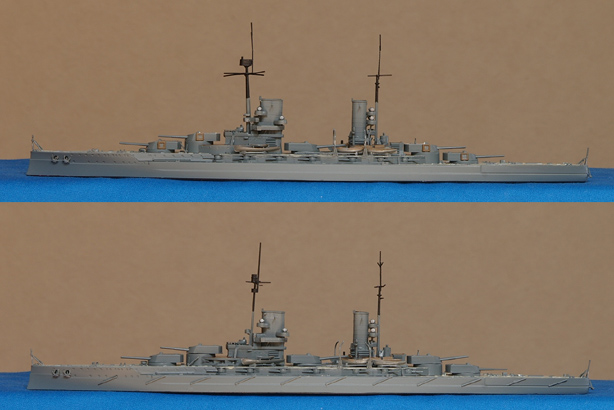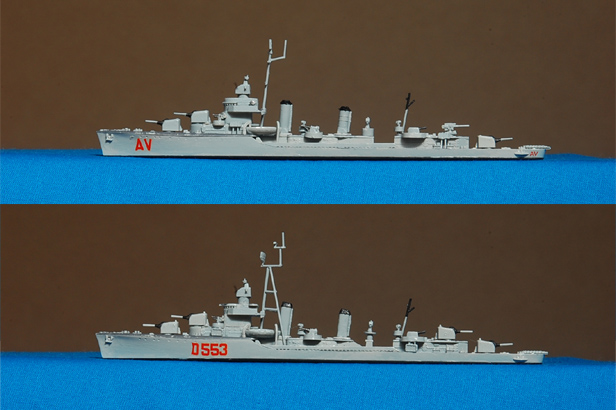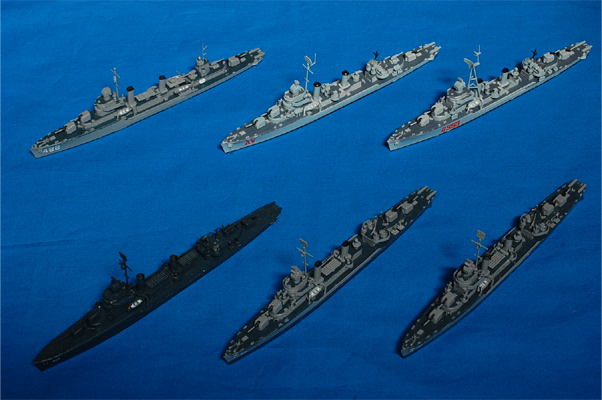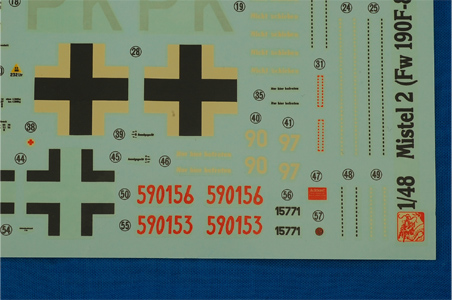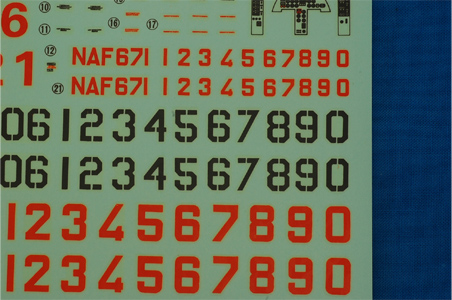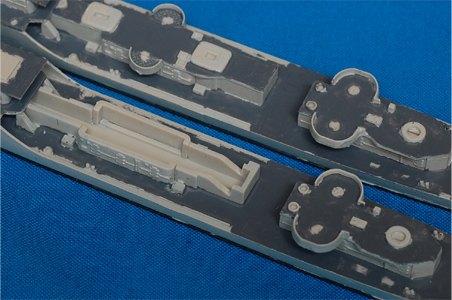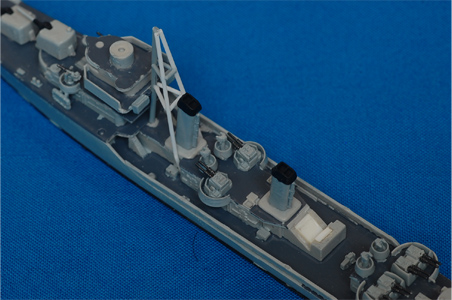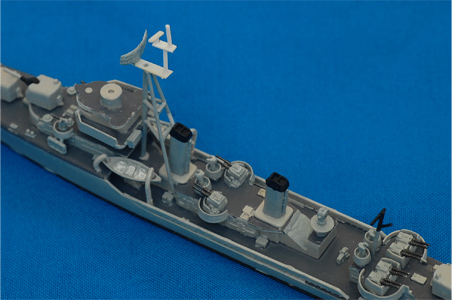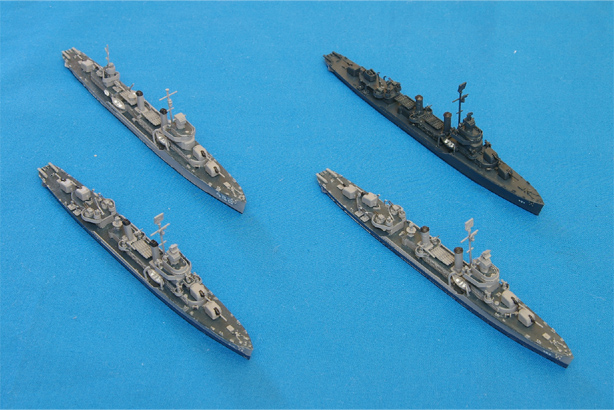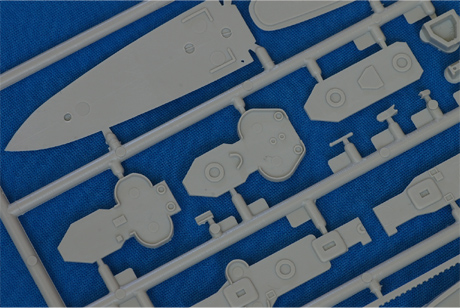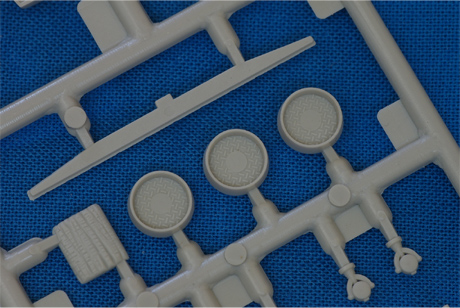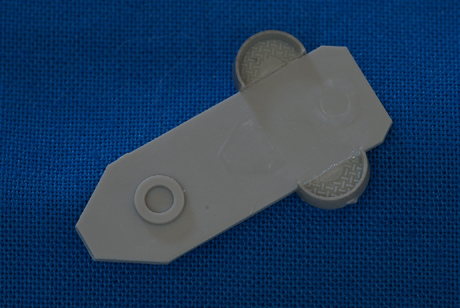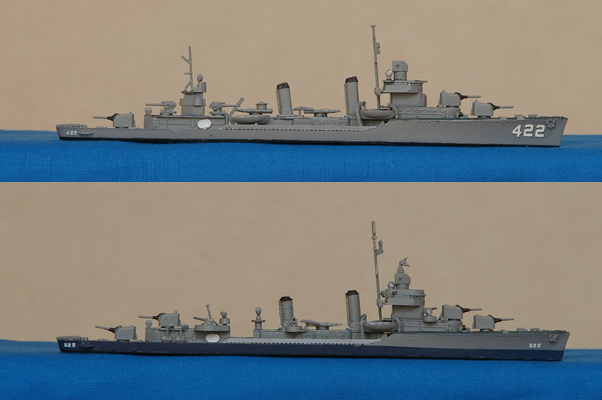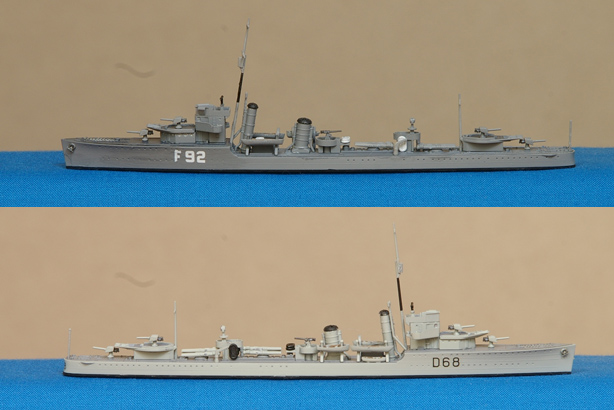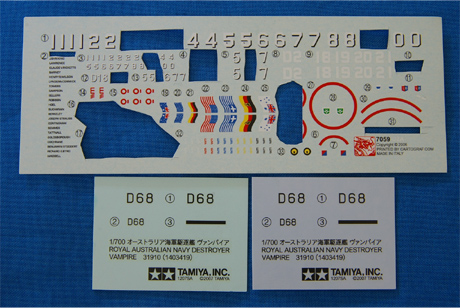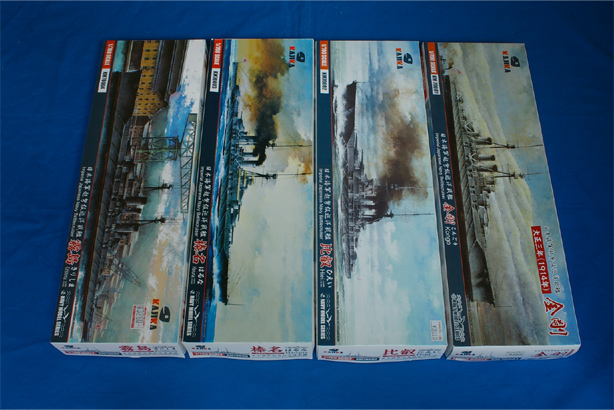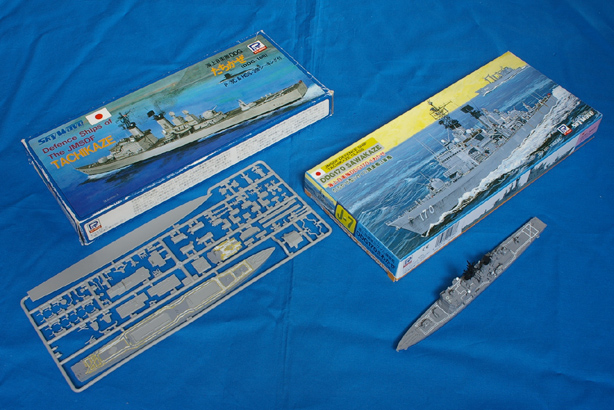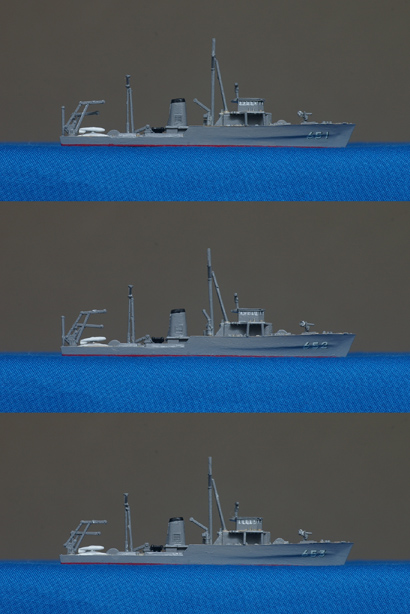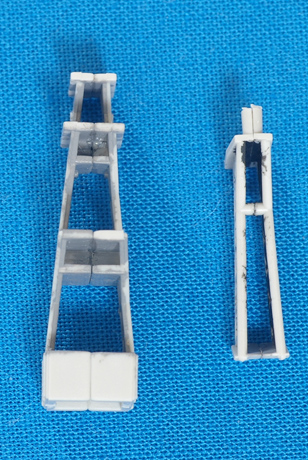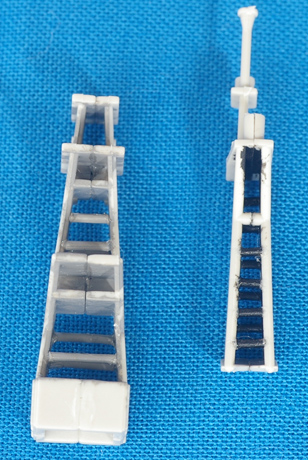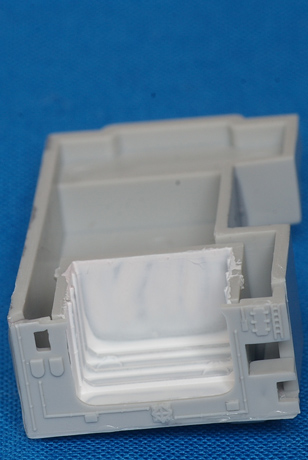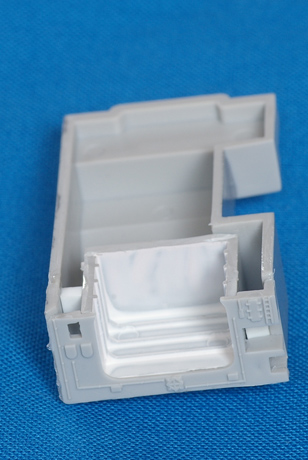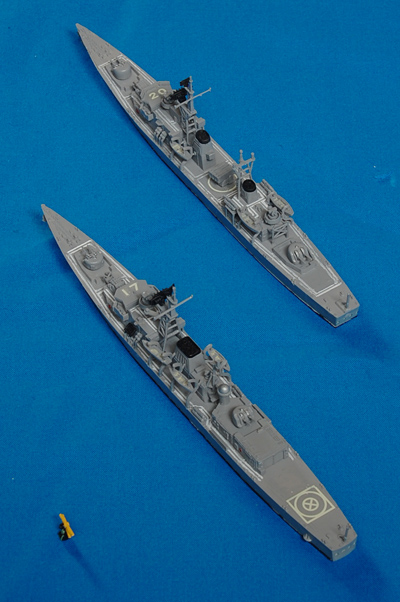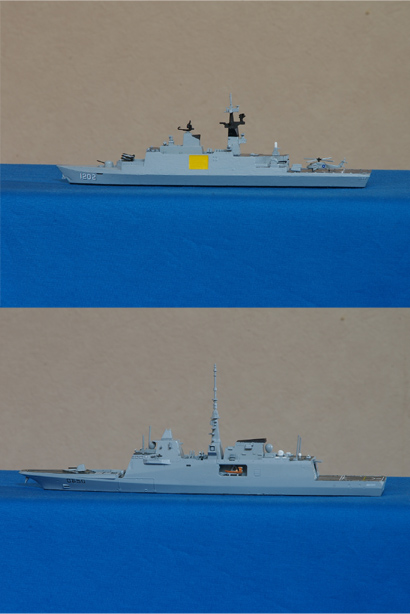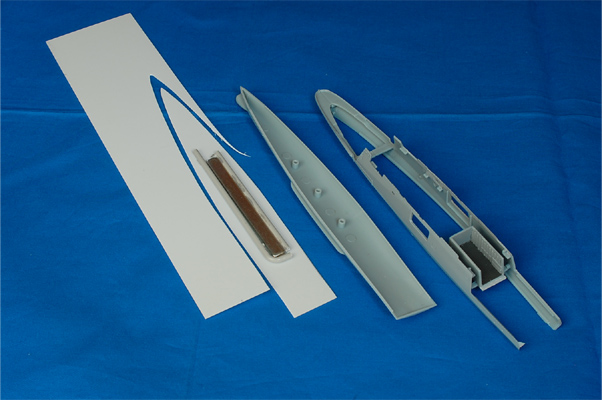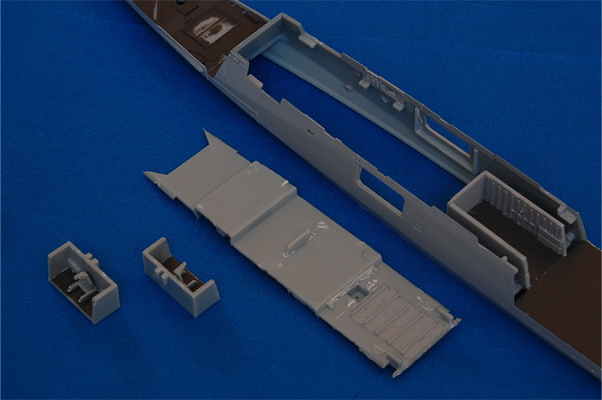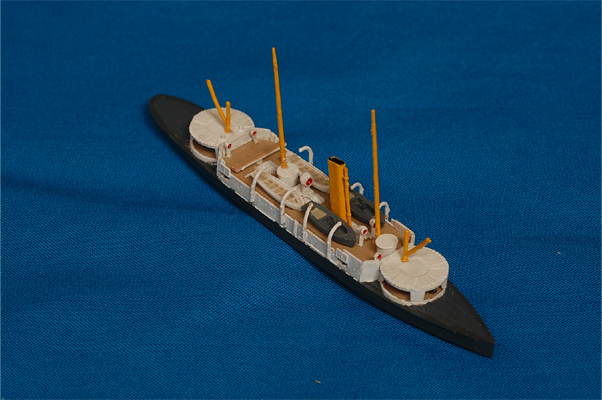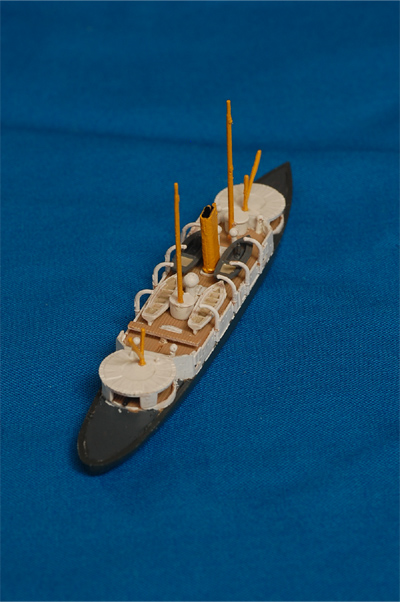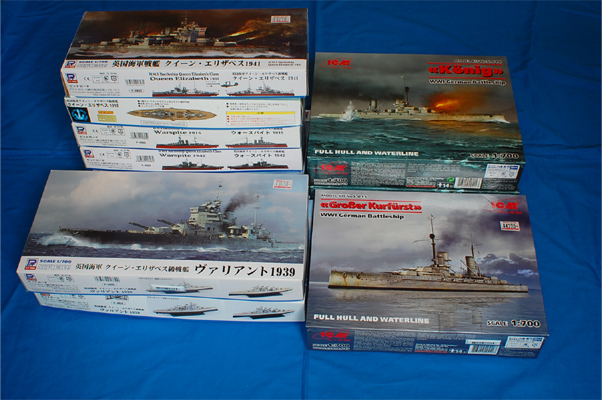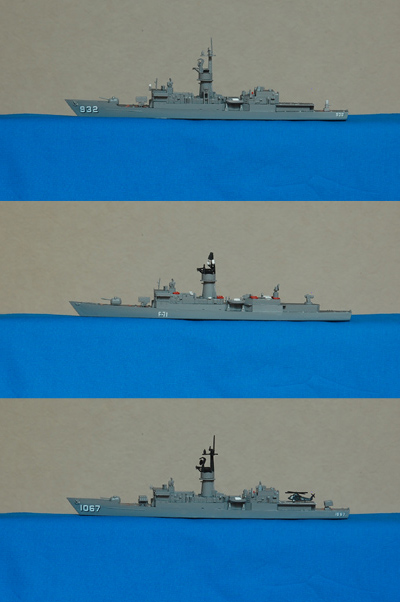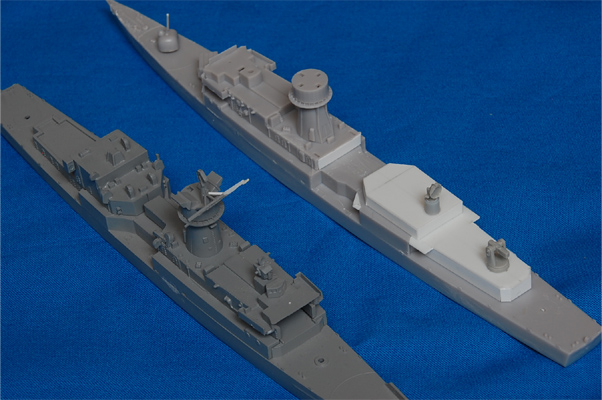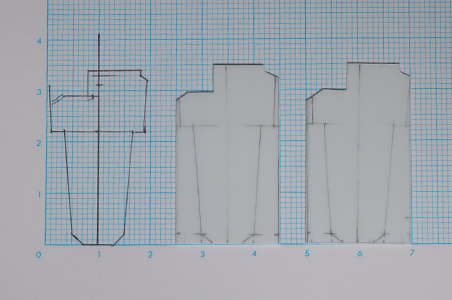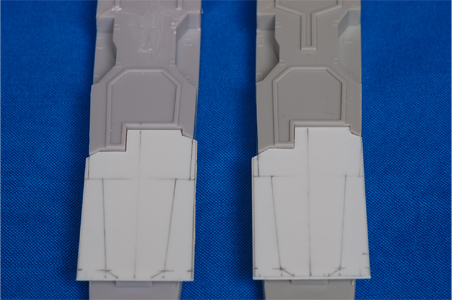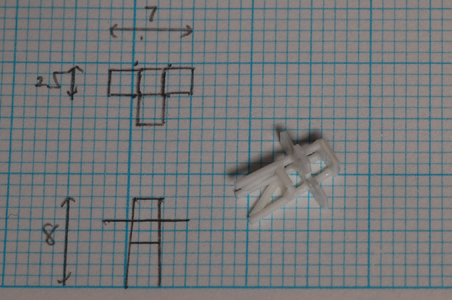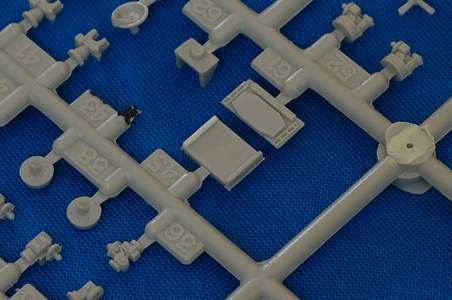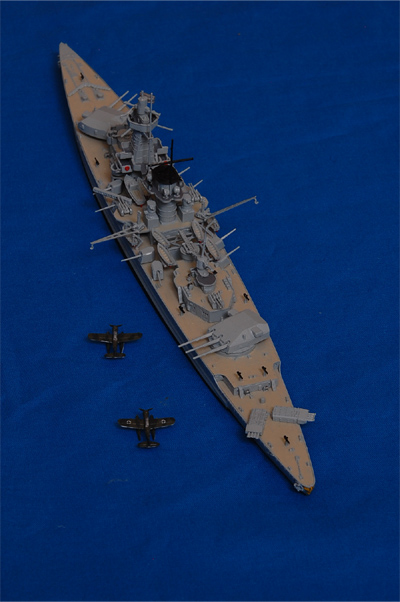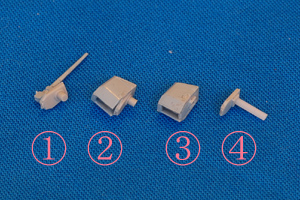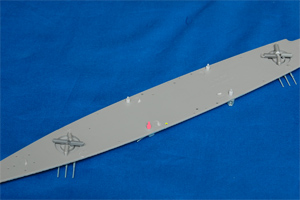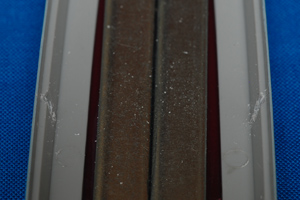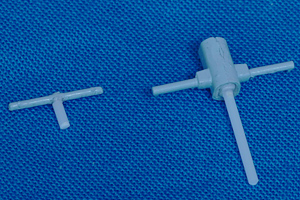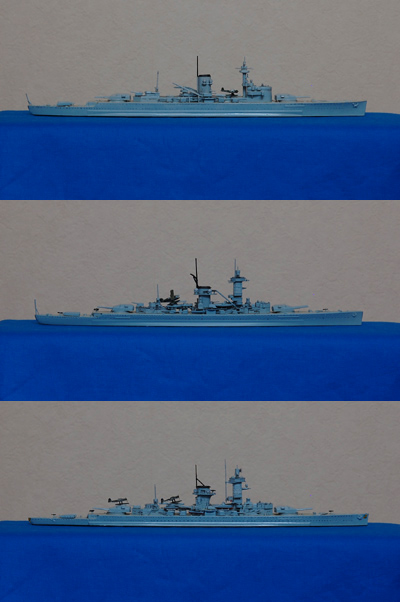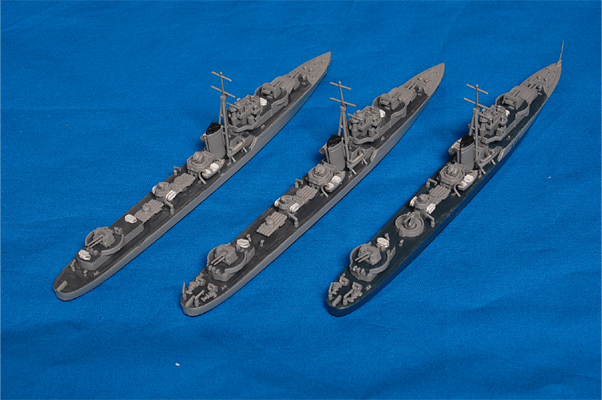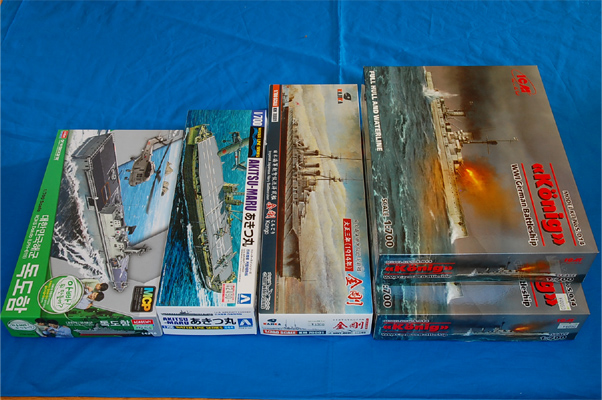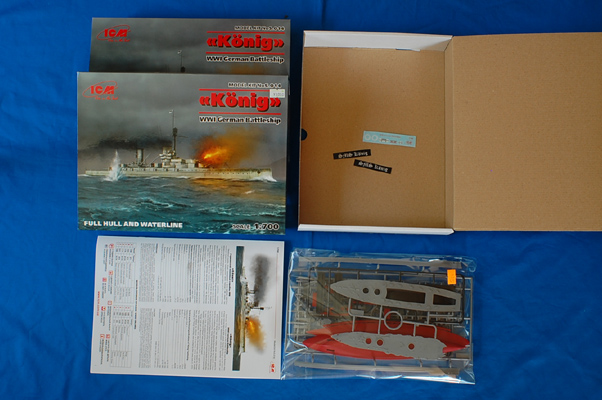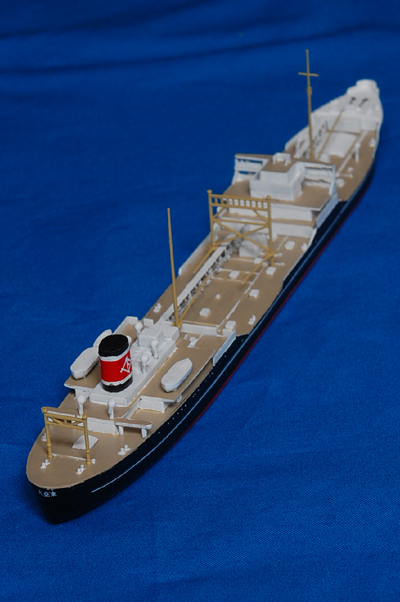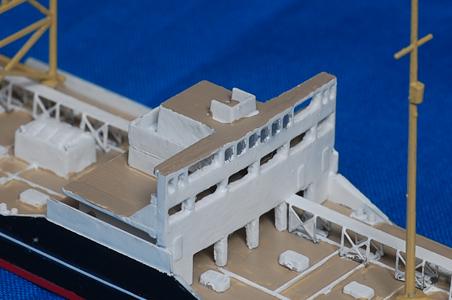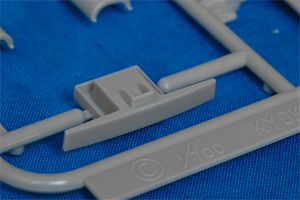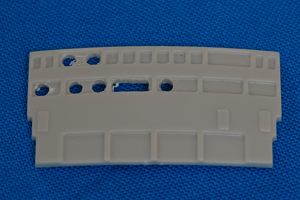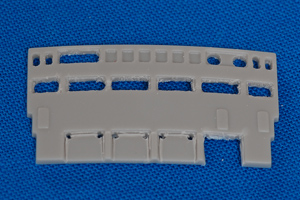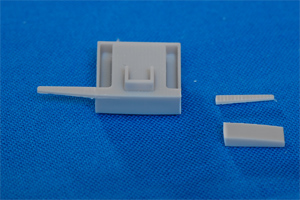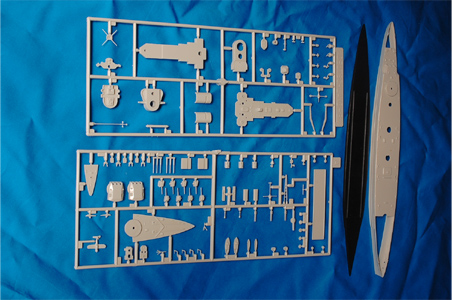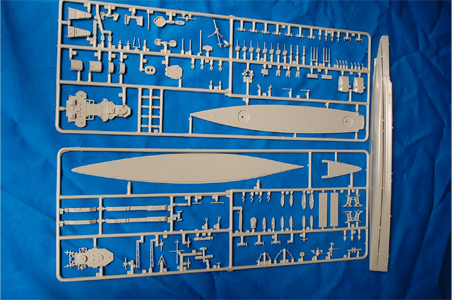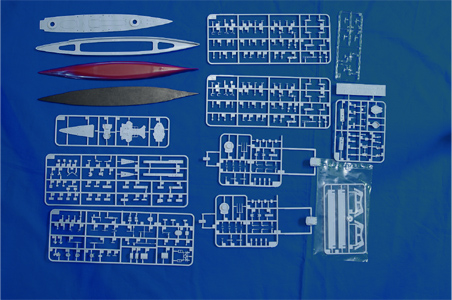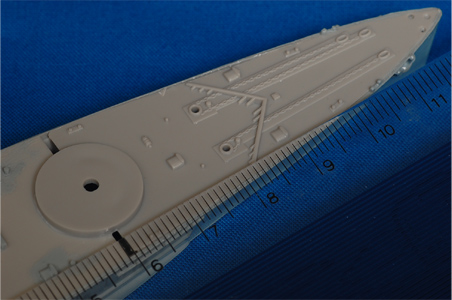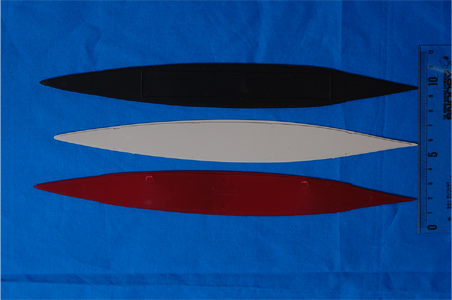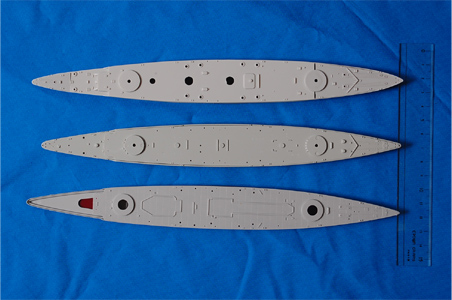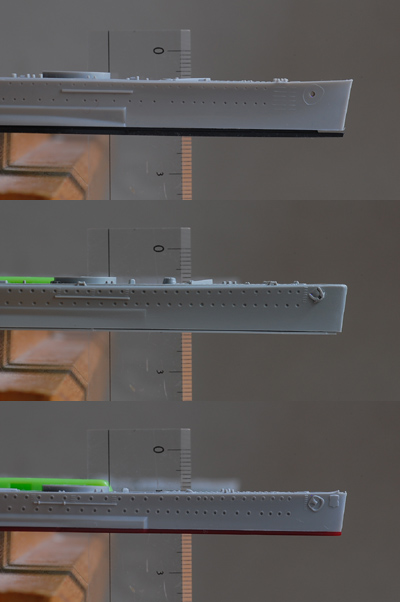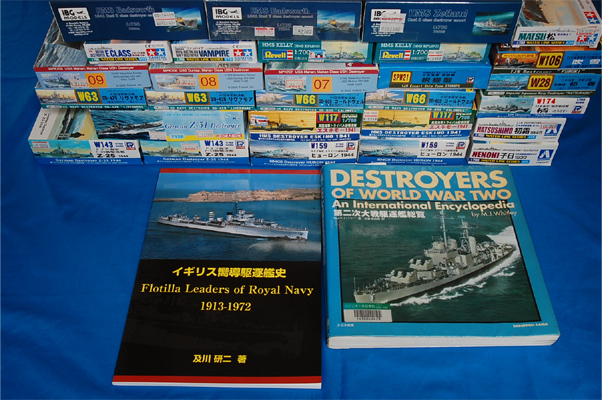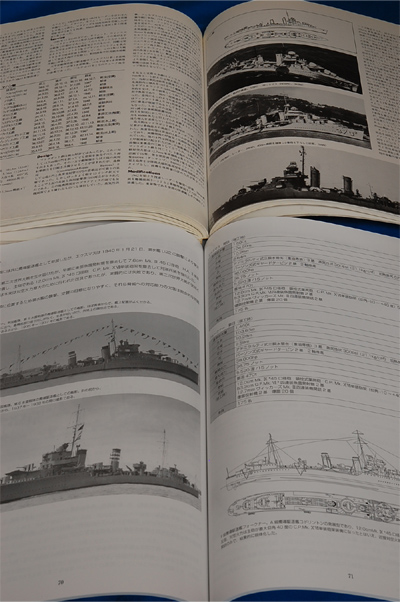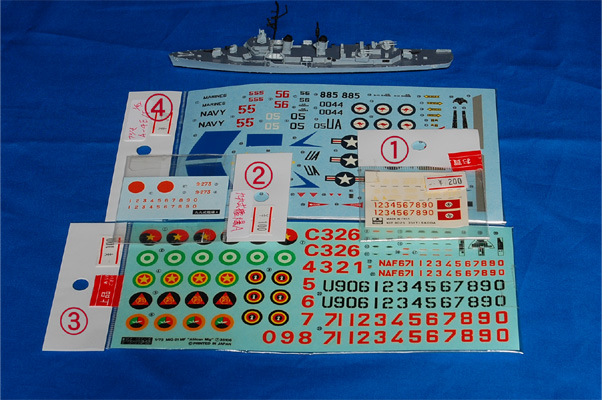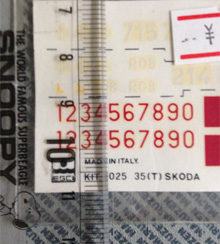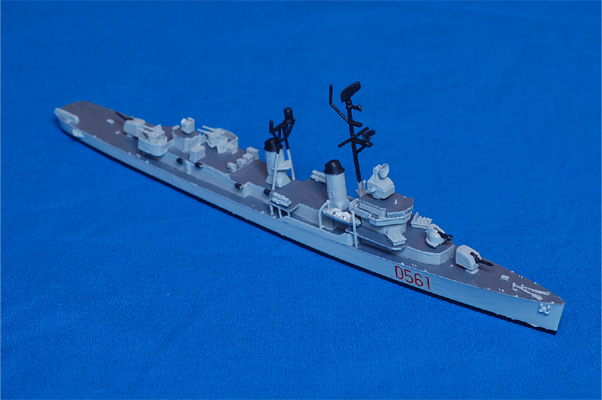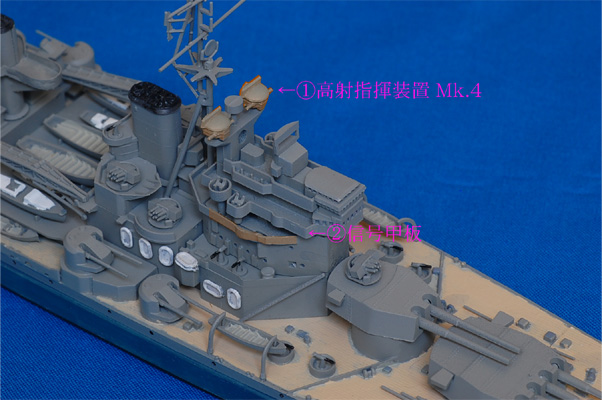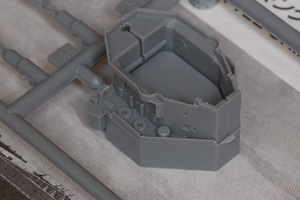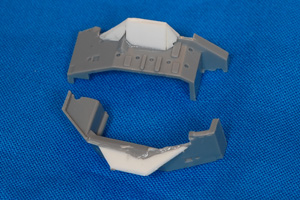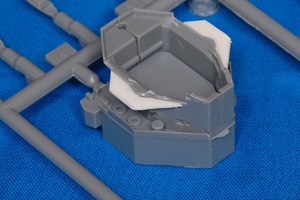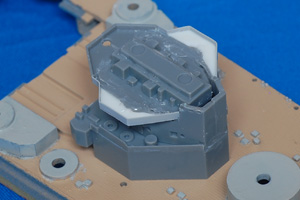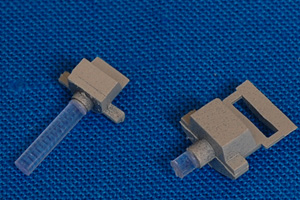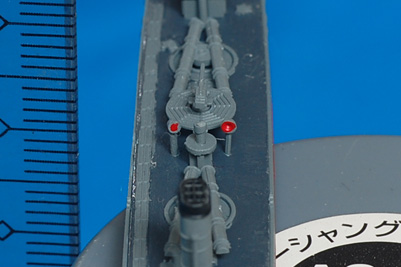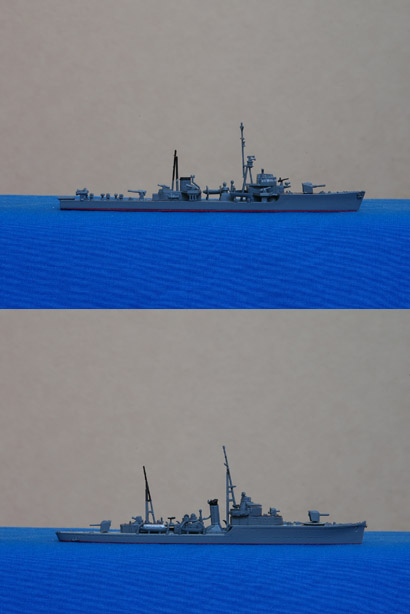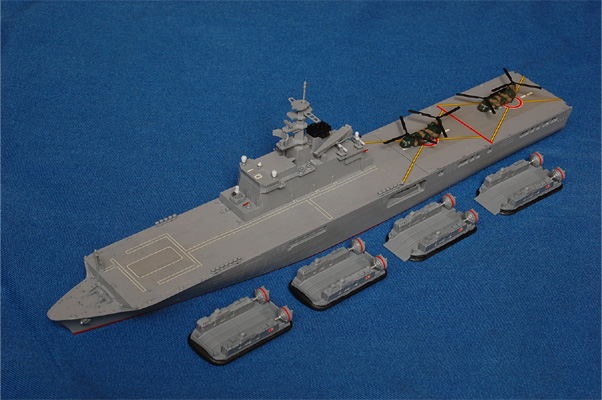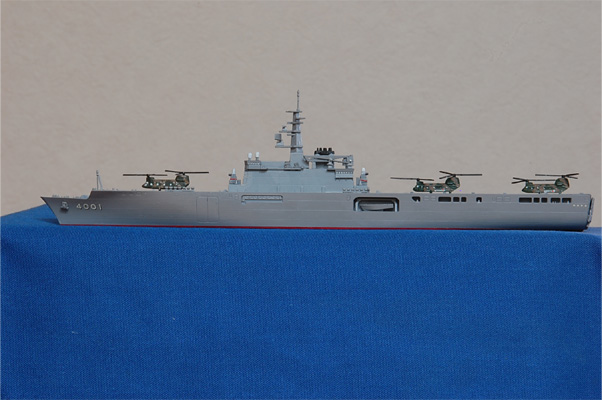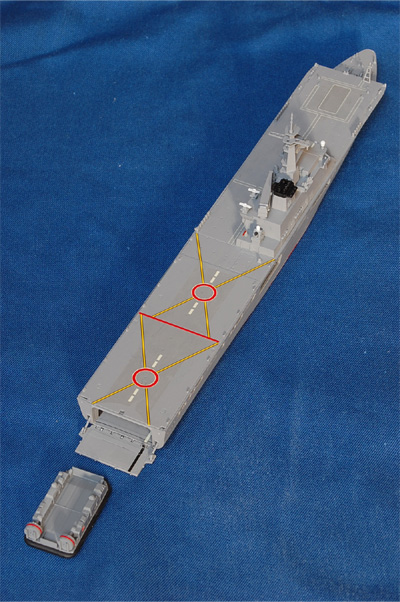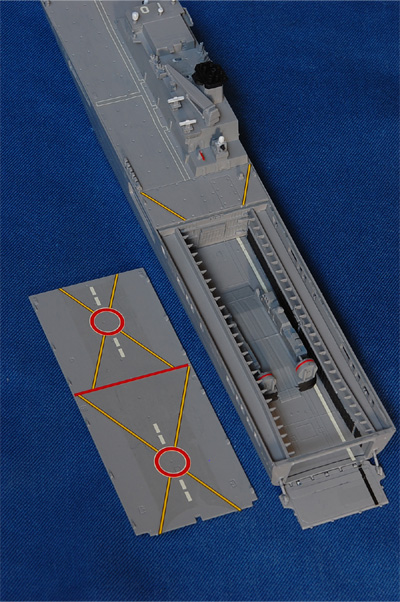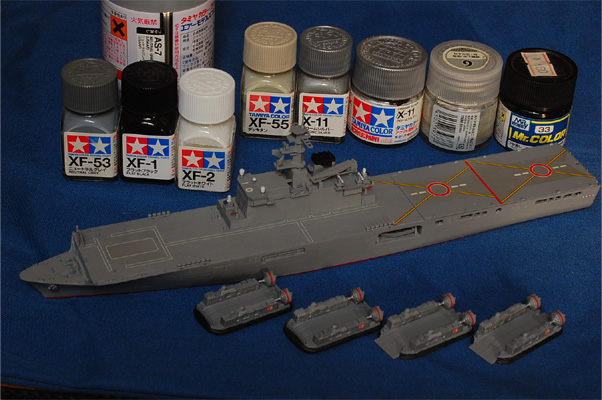���ΔR���N���̕���
�܂��A�����̎B�e�����ł͂Ȃ��ƌ������ŁB
��{�I�ɂ̓v���C���W�F�N�V�����L�b�g�̑f�g�݂ŁA�����k���ɍ��̂ł͂Ȃ��A�Ԃ����Ⴏ�e�������ł��B
�ق�̂��ډ����ł����A�ɂ��������猩�Ă���ĉ������B
R04/09/22 �W�� �p�쒀�� �����A�� ���e�̈�u�K�[�����h�v->���u�}���j�b�N�X�v
9/8�ɏ������o砂���܂������A�ʂɒǓ����ĈӖ��͖����A�P�Ȃ���R�ł��āA���瑽��3�ǂ���p�쒀�͂̉����A��ł��B
����ڂ̍���́AG���쒀�͂́u�K�[�����h(Garland)�v�ł��B
�{�͂́A�����̂܂ܐ풆�ɔg���ɑݗ^����A����U�ԋp����܂����A�X�ɘa���ɔ��p����ăt���Q�C�g(!!)�u�}���j�b�N�X(Marnix)�v�Ƃ��čݐЂ��A'64/1/31�ɑޖ����܂��B����͂��̘a��������Č����Ă݂܂����B
���l�^��IGB�̂���u�K�[�����h�v�ł����A������ł��B
���A�B�e�́AISO200�AF16�ŁA���ߒ�
�uistDs�v��PENTAX istDs�{smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
�uD40�v��Nikon D40�{TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
�̎g�p���Ӗ����Ă��܂��B
|

1.
ttps://onzemarinevloot.weebly.com/hrms-marnix-f-801.html
ttps://assets.marinemuseum.nl/app/uploads/2020/10/WS-Hr-Ms-Paets-van-Troostwyck.pdf
�ƌ������ӂ��700/700�̎ʐ^�����\�������̂ŁA�������{�Ƃ��܂��āA���`��A�D��O������͗ǂ�����ʁB�E���^������̕s�N���ʐ^������ɖ������ŗǂ����낤���Ďn�߂܂����B
�܂��A����ł��͋������̉����͂��Ȃ��K�͂Ƒz��͂���܂����B
istDs
1/1

2.
�ŁA���肵���̂ł����A
ttp://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5796:schulfregatte-marnix&catid=511:falk-pletscher
���āA�����Ă��܂��܂����B
���Ɋ͋��͘M��n�߂Ă��܂��Ă���A�߂�Ȃ����A���͔̊����̊g���ɂ��ẮA�E���^���̎ʐ^���猩��ƁA�٘_�L��ƌ��������L���āA���̂܂܉������s���܂����B
istDs
1/1
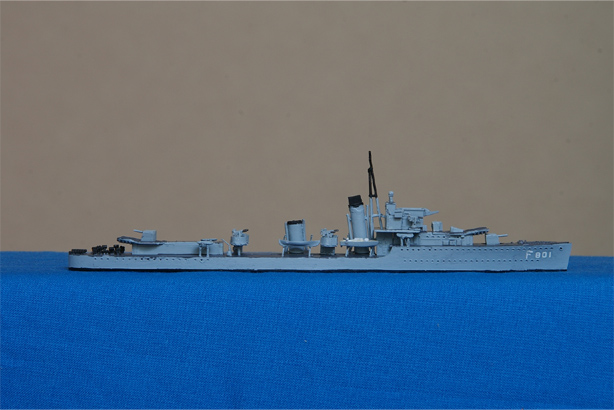
3.
����ɂ��Ă��A����Ȓm���x�̒Ⴛ���ȁE�E�E�ƍl����̂́A�a�����牓������Ă��邩��Ȃ̂ł����ˁB�܂��A������HP���ƈ��ŋL�q����Ă��܂����˂��E�E�E�t�l���A����Ȃ�Ɋ撣���Ď����W�߂č��グ����ĉɐl������̂��Ə��X�h���ł��B
���O�͂ǂ��Ȃ�??�ƌ�����A�d�ԓ˂����āA����͈͂̎ʐ^�����łł����グ�悤�ƌ������C�y�A�蔲���ł�����˂��`�B����ɂ͂ƂĂ��ƂĂ����ꑽ���āB
istDs
1/1

4.
����A��LHP�݂�����������??������??�̂́A�h���ł��B
�����A��\���ʓ���"Vallejo 155"�A�b��"Revell 74"���̗p�ƌ����Ă���܂����A����Ȃ�A�ɂ��Ă��Ȃ����A���B����̂��Ɩʓ|�B
�������F�X�Ɠd�Ԃ�˂����Ă���̂ł�����A�X�Ɏ��O�[���T����������A���x�́A
ttps://acrylicosvallejo.com/wp-content/uploads/2021/09/CC070-Model_Color-Rev18-baja.pdf
ttps://www.mech9.com/p/mr-color-to-vallejo-paint-conversion.html
�ӂ�ɂ��H�蒅���܂��āA���ʁAC308��LP17���̗p���鎖�Ƃ��܂����B
�����Ƃ��A���������ɏo���Ă���700/700�̉E���^���̎ʐ^������ƁA�����͂����ƔZ���F��������Ȃ��낤��??�Ƃ��v�����ł�����ǂ˂��E�E�E�B
�����͌����Ă��A�����͌����Ă���͔ԍ��Ɩ��x�ɑ傫�ȍ����������A���Ȃ蔖���F���ɂ��v���܂��B�܂����Ǝv������Ǎ��E�ŐF�������Ⴄ??
Mr.�J���[�ɂ�C337 �O���C�b�V���u���[FS35237����C367 �u���[�O���[ FS35189���̂ƌ������Z���߂��p�ӂ���Ă���̂ŁA�������̈��C���j�݂̗l�ɍ��E���̓h����ς��Ă��܂�����??���ƈ�u�n���Ȏ����l���܂������A�܂����˂��`��
istDs
1/2
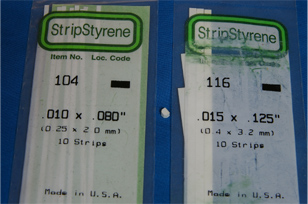
5.
��������́A�����̂��ꂱ��ł��B
�悸�́A�͂�˂��݂̒���̍\�����ł��B��L��HP�ɂ͗v���ޔ����Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă��܂��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/4
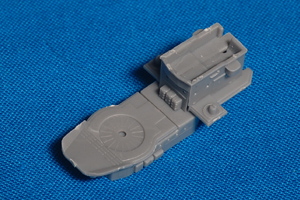
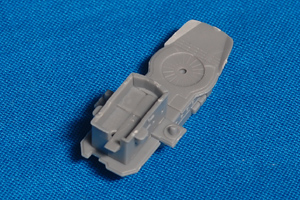
6.
�͋��A�f�őg�ނƂ���Ȋ����ł����E�E�E
D40
1/8,1/8
���������2�����x�g���~���O

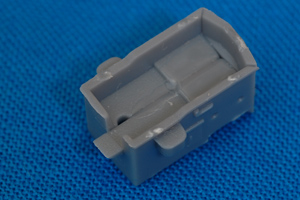
��������������������������
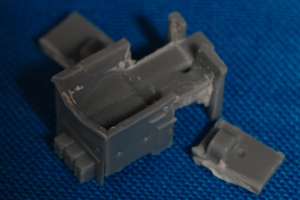
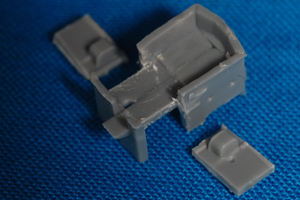
7.
���������݂���Ă���ׁA����ȋ�ɂ�����Ɛؒf���܂��B
D40
4/1,4/1,1/4,1/4
�����5�����x�Ƀg���~���O
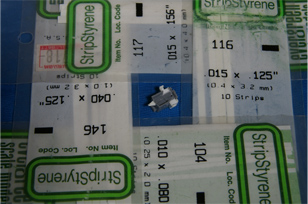
8.
�藣������ɁA���ꂱ��Ƒ��ݕ�����lj����܂��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/15
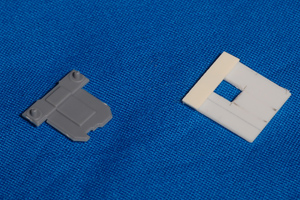
9.
7,8�̑��삪�ڂ�01�b���g�傳��Ă���ׁA������͖{���i(��)��M��̂ł͂Ȃ��A�܂������V�K(�E)�ɍ쐬���܂��B
D40
1/8
����2,3���g���~���O
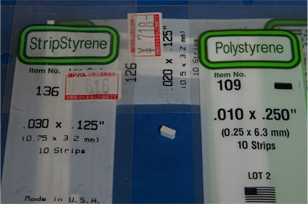
10.
7,8�̓V�W��ɂ��b�������đ�������Ă��܂��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/4
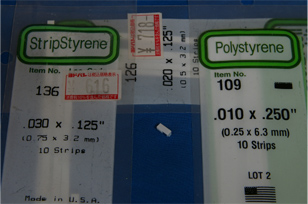
11.
10�̔w�ʂł����A7,8�̔w�ʂ̚Ɨۂ��c���Ă���̂ŁA����ɍ��킹��`�ɂ��܂����B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/4


12.
�D��O�̖��[�ɐڑ����镔�i�ł����A���̏�ɍڂ�01�b���g��E�E�E�O�L9�E�E�E����A�����Ă���������������킹�܂��B
�͋��\�����͂������B
�����H�O�A�E���H��ŁA�E�̓}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
D40
2/1
����2,3���g���~���O
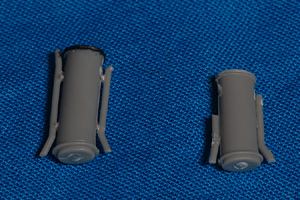
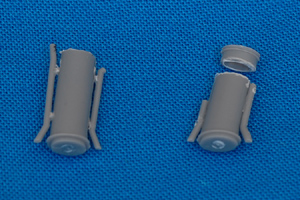
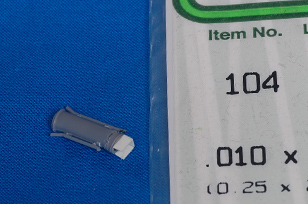
13.
����2�{�̉��˂ł��B
����ꉌ�ˁA�E��˂ł��āA���X�͍������R�����Ȃ��̂ł����A��ꉌ�˂������A��˂��Ⴍ�Ȃ��Ă���̂ŁA��˒�����1mm������Ɛ藣���đ�ꉌ�˂ɏd�˂܂��B
�X�ɁA��ꉌ�˒����ɂ͔�̗U���ƌ������Օ��ƌ����������đ�������Ă��܂��B
D40
1/8,2/1,1/1
�����������4,5���Ƀg���~���O
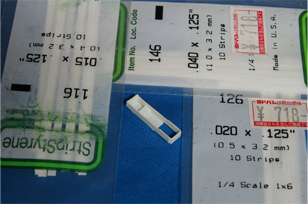
14.
�����Č㕔��\�ł��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/30
������2,3���Ƀg���~���O
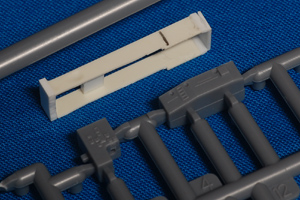
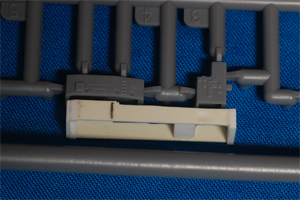
15.
�ǂ��ς������??�ƌ������ŁA�{���̕��i4�Ɣ�ׂĂ݂܂��B�͎�����ɔ{�������Ȃ��Ă��܂��B
�����Ƃ��A���̒����́A�b��̑����i��t�������B���ړI�Őݒ肵�܂����̂ŁA���ƒ��߂������m��܂���B
D40
istDs
1/8,1/4
������1,2���g���~���O
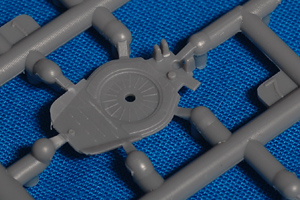

16.
�㕔��\���[���̖C���͎g���܂����A�ꕔ�������s�v���ۂ��̂Ŏ��암���Ƃ̍����Ղ������Ă��āA�r���Őؒf���܂��B
D40
1/8,1/8
���������2,3���g���~���O
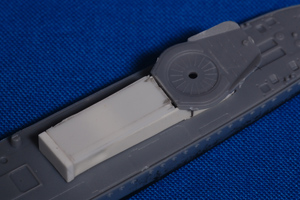
17.
14�`16�����킹��Ƃ���Ȋ����ł��B
D40
1/15
����1,2���g���~���O
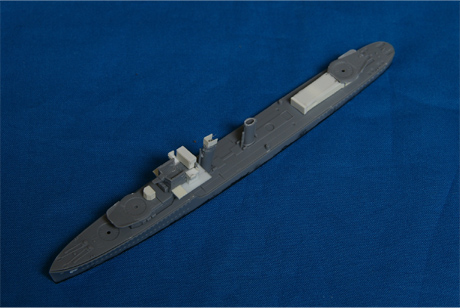
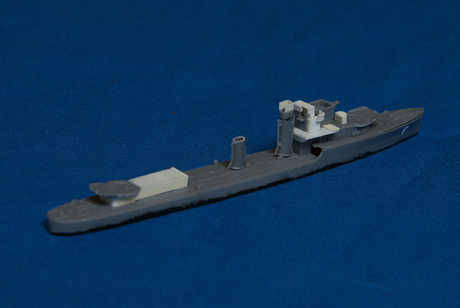
18.
�X��5�`16��S�ڂ����܂��ƁA����Ȋ����B
istDs
1/1,1/1
�E���͎�g���~���O

19.
��C�́A���̕s���̓ƈ퐻4�D���p�C�Ɋ�������Ă��܂��B
���ꂪ�A���ɒZ�C�g�ō����Ȋ����ŁA�ɗ]��i�ɓK���ȕ��������炸�A�v�����Ȃ�3mm�p�_�ŖC����218�ŕ��j������Ă��܂��B��]���́A�܂��s���s���Ŏʂ����߂܂���ł�������1mm�ł��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
D40
1/8
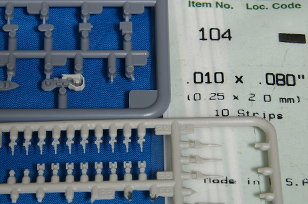
20.
���ˊԂ̋@�e���ł��B����͉����ł͖����A�������i�̎g�p���������ĉ����i�ɒu���������̂ł��B
���ǂ̓v�����A�@�e��P�Ђ́u�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�gIII�v��20mm�P���@�e��]�p�ł��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/2
����2,3���g���~���O

21.
��˂ƌ㕔��\�Ƃ̊Ԃ̋@�e���ł��B�����20�Ɠ��l�ł��āA���ǂ�104�A�@�e��P�Ђ́u�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�gIII�v��20mm�P���@�e��]�p�ł��B
�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B
istDs
1/2
����1,2���g���~���O
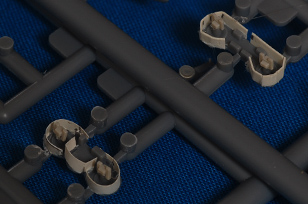
22.
20��21�͉�����E�����̂݉��H���ł������A�S���u�����ς܂��Ƃ���Ȋ����ł��B
D40
1/1
����1,2���g���~���O

23.
����͎O�r������Ă���̂ŁA�㕔��2�r�̎��t���ē��p�ōb�ɐ��E���܂��B
D40
1/1
����2,3���g���~���O

24.
�S���V�K�ō쐬��������ƁA�~������t�̋������i�������i�ł̒u���ł��B
����͂�A��ςł�����B���͓������ɂ����ƊȒP�ȉ�����2�ǂ���ƊJ�n�����̂ł����A���Łu�}���j�b�N�X�v���ŏ��ɏv�H�����̂���܂���B������ꂽ�A���������B
D40
1/1
R04/08/17 �W�� �c�����������\���グ�܂�
�ҏ��ł��B����A�����ł��B
���̎����A���̓��y�͓�V�ł��B�L�@�n�܂ƕt�������s����A��ƒ��͊��C���������܂���B�ƌ������́A��[�̉��b�ɗ������ł���ˁB
�����͐^�~���ꏏ���낤�E�E�E�ƌ�����Έ�ʘ_�Ƃ��Ă͂��̒ʂ�ł����A�l�I�ɂ͐���Ƃ���ꏊ�����Ɍ����Č���������Ղ��A�t�ɖk���̒����͎Ȃ��̂Ő^�Ē��������ł͂���܂���B
�Ƃ܂��A����Ȗ�Ŕ~�J��������H�J���薘�A����ǂ��ł��B�ŁA���N�����{�I�ɕ�C�Ƃ��̌y���Z���ȍ�Ƃ𒆐S�ɂ��鎖�Ƃ��܂����B
�E�E�E�ƁA�������͂��̈��N�Ƃقړ������e�ł��B�܁A��^�̌�����ł��ˁB
�ŁA����͉����������BP�Ђ́u��܂����v���ɂ��܂��ŕt���ė���u�͂��܁v���|�C���B����̏C����v���܂����B
Nikon D40�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|


1.
�悸�͏C���O�̏ł��B
������H24/02/12�`H25/02/06�W���́u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�AH30/06/30����W���́u�݂₶�܁v�A�u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B���Ă��܂������i�͊e���̑O�ɂ��ƒu���Ă���܂��B
���������ɁA�u�ɂ̂��܁v�Ɓu���̂��܁v�͑O���Ɠd�T�����Ă��܂��A��������ꂽ���i�������̂Ŏ��삵�Ȃ���Ȃ�܂���B
�܂��A���̎ʐ^�ł͗ǂ�����܂��A���Ȃ蚺�����Ă���܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1,4/1
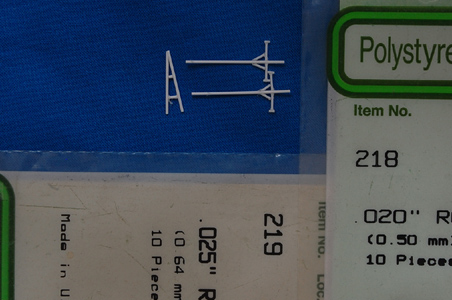
2.
�O���̎���ł��B
219�ŋr���B218�ʼn����������܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
���E1���A��2�����x�g���~���O
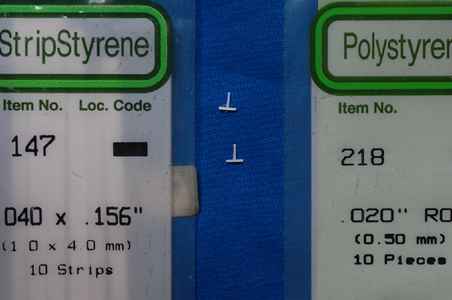
3.
�d�T�̎���ł��B
218�͋r�����B147�͓d�T���̂��̂ƌ���������g�@�ł��āA4mm�̕��͂��̂܂܍̗p�ł����A1mm�̌����͌��߂��Ȃ̂Ŕ������x�ɍX�ɕ����ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
����1�����x�g���~���O
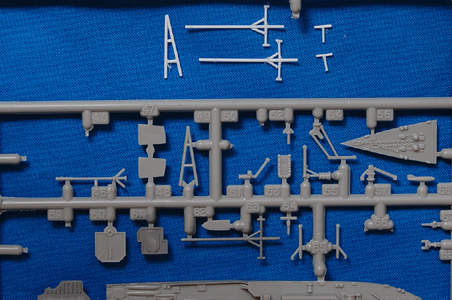
4.
�{��(^^;;;�Ɣ�r����Ƃ���Ȋ����ł��B
��r���ׂ���49,63,64�ł��ˁB
�O�r�̓�r�����̕��i�̉����̈ʒu�����Ȃ����Ă��܂��Ă��܂����A��������킹�钷���ɐ�o���͍̂���Ȃ̂ł��̂܂܍s���Ă��܂��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
����1�����x�g���~���O
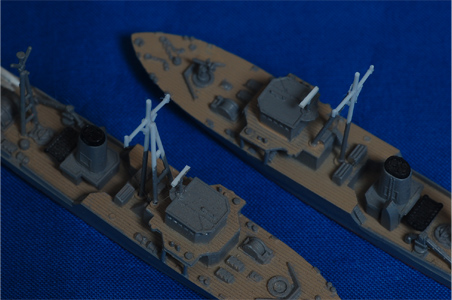
5.
���r���[�ȓh����Ԃł����A�O���Ɠd�T��ς�ł݂܂����B���u�ɂ̂��܁v�A�E�u���̂��܁v�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
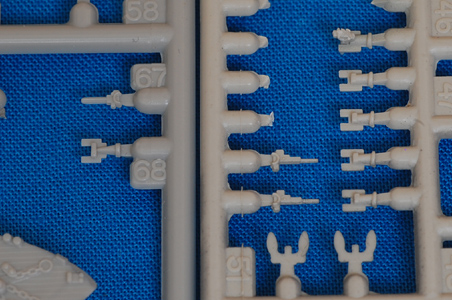
6.
�u�ɂ̂��܁v�͋@�e�����ĉ������s���Ă��܂����̂ŁAP�Ђ́u�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�gII�v��20mm�P���@�e��]�p�ł��B
�����{���i�ʼnE���]�p�ł��B�{���i�A68�̊�Ɩh���͂Ƃ������A67�̏e�g�e�c�͂��Ȃ�Â������ł��ˁB�����Ƃ��A�]�p�i�͂���͂���ŏe�g���߂��ł��B700/700�̏e�g�S����2.21m�������ł����A1/700�̎������͖{��3.5mm�A�]�p4mm�B�{���ł����߂��銴���ł��B�܂��AP�Ђ̂��̎�̑����i�͏k�ڒ��ߋC���ɂȂ菟���̗l�ł͂���܂��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
����1�����x�g���~���O
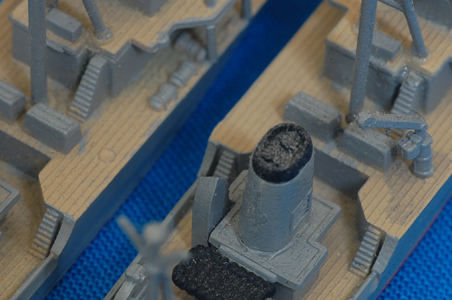
7.
�������̂��E���������̋N�d�@�ŁA�u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�A�u���̂��܁v�Ŏ��Ă��܂��čs���s���B
�ƌ������u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�ɂ͐ڒ��������Ղ������Ȃ��̂ł����A�ǂ��������̂��B���������čŏ�����t���Y��??����ƒT���Ώo�ė���??���[��A���̎R�̒����炩���E�E�E�B����͂��Ă����A���Ȃ蕡�G�Ȍ`��ł��āA������Ǝ���͖����B��芸�������������ɕ��u���܂����E�E�E�B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
����1�����x�g���~���O

8.
�Ƃ܂�����Ȃ���ȂŁA���t������̎��t���A�u���A�[��ʑ��M�Ś������C�������ł��B
��ƌ��������ƌ������A������u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�A�u�݂₶�܁v�A
���ƌ�������O�ƌ������A������u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B
���āA7�ŋL�ڂ̋N�d�@�̌��͂ǂ��������̂��B4,6�ł�����ƌ����Ă���ʂ�A�����������ɂ��L��܂��B���^���̒����牽�ǂ��AYCS��MCL�ɓ]�Ђ��Ă��܂����A�����]�Ќ�ɂ��̋N�d�@��P�����Ă���Ⴊ�L��A�c�]�ɂ��炻���̎p���쐬���A���̋N�d�@��P�o����̂��L�肩??���Ǝv���Ă��܂����A��肭�s�����̂��E�E�E�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/21
R04/07/12 �W�� �u�`���[���Y.F.�A�_���Y���v("C.F.Adams")�t�@�~���[�e��2�ǖ�
H23/9/22�`H24/8/30�W���́w�u�`���[���Y.F.�A�_���Y���v("C.F.Adams")�t�@�~���[�����x�ȗ���10�N�U��ɁA�����̊e���ł�1�ǂÂł����グ�܂����B
����́A���B���͏�����2�Ԋ́u�W�����E�L���O(John King)�v����{�I�ɑg�ݗ��Đ����ʂ�ɁB���Ƃ͊e�X1�Ԋ́u�p�[�X("Perth")�v�Ɓu�����b�`�F���X("Lutjens(u�̓E�����E�g�t��)")�v��Navsource��1968�`1970���̎ʐ^���Q�l�ɏA��̈�ۂɂł��������܂����B
�ȉ��A������܂��͏ォ��u�W�����E�L���O�v�A�u�p�[�X�v�A�u�����b�`�F���X�v�̏��ɍڂ��Ă��܂��B
|

1.
��26��Q�c�@�c���I�����I�����܂����B�܂����n�]�ʂ�^�}�����B������3�N�ԂƂ�炪�n�܂�̂������ȁB����͏O�Q�����ɂȂ�̂���??
�C�������ł����A���̎���ł��Ђ�����Ԃ�Ȃ���A�������͂��Ȃ�̒�����ۂ��ɂȂ肻���ł��B
������W�Ԃ��Ă���c���������@����2/3���߂Ă��܂����A�����ٖ��ȕ������L�肻���ŁA�ǂ��Ȃ���̂��B
��芸�����A�O���́u���a�������鏔�����v���ĕӂ�̕������O���ė~�������ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200

2.
�Ƃ���ŁA�����I���Ő��Ă���Ȃ��̂́A���J�[�̑O�X���ɋN�����������̎ˎE�����ł��ˁB
�啽���F������Y�̌̎����ӂ݂�ƁA�����Ɠy������I�Ȉ���I�Ȍ��ʂɂȂ�̂ł�??�Ƃ��v���Ă����̂ł����A�ӊO�ɂ������܂łɂ͂Ȃ�܂���ł����B
������A�e�}�}�̉����Łu�e���ɂ͋����Ȃ��v�Ƃ��u�����`�����v�݂����Ș_���𑽂������܂������A�l�I�ɂ͂��Ȃ��a���������܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

3.
���Q�ҌN�͍ŏ�����A��Q�҂̐����M���ɑ��Ăł͂Ȃ��A�@���Ɋ֘A���Ă̖�肾�ƁA����Ύ������Ɩ������Ă����ł���ˁB
�Ȃ̂ɁA�e�}��̊F���������B�܂��������y���˂Ȃ���Ԃł͗L�����̂����ł����E�E�E�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2,1/2,1/2
f16
ISO200

4.
�{���A�c��̐ς݂͐��K���i�����r�����i��3�Ǖ��B�O���3�ǁuC.F.�A�_���Y("C.F.Adams")�v�A�u�z�o�[�g("Hobart")�v�A�u�����_�[�X("Molders"(o�̓E�����E�g�t��))�v���ꏏ�ɕ��ׂāB
������e���ł���肽���ł��ˁB1990�N��ɓ����ė���ƁA����SUM��������CIWS��ς݁A�Ƃ�RAM�ZSAM��ς�ł��܂��̂ŁA���̕ӂ�̎p��z�肵�Ă��܂��B���B���́E�E�E�ǂ����悤�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

5.
��̔@���g�p�h���ƁB�~�����ւ�h������GM29���s���s���Ō��ł��B
��̔@������A�O����͖؍H�p�ڒ��܂ʼn����ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
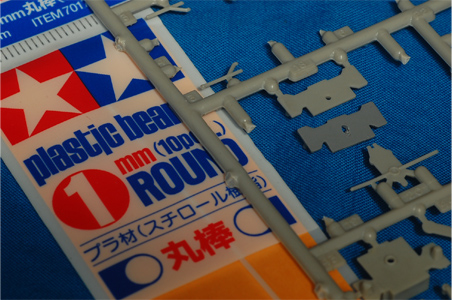
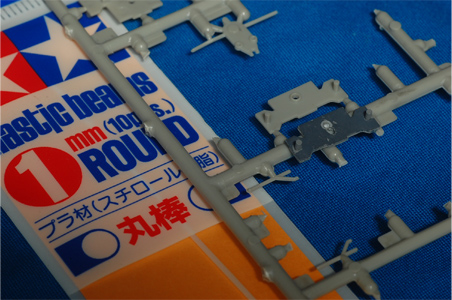
6.
��������́A���H�������ꂱ����B
�O���ƌ���������ƌ������A�O�r�Ȃ̂ł������̒����r�����t���镔�i18�̎�t���̈ʒu���ǂ�����낵������܂���B
�u�W�����E�L���O�v�ɂ��ẮA����������ɕύX�ƌ������ŁA���̌�����1mm�̃v���_�Ŗ��߁A��1.2mm�̃s���o�C�X�ŐV���ɐ��E���܂����B
�u�p�[�X�v�Ɓu�����b�`�F���X�v�ɂ��ẮA���̕��i�̑��̑��ݗ��R����SLQ-32�̉ˑ�?�x��??�ɂ��āASLQ-32���ڂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�����������i���̎g�p����Ӗ��������Ȃ�ƌ������ŕs�g�p�A����ɂ��̓y��ƂȂ�b���̓V�W��������Ƃ����s���o�C�X�ş����Ă݂܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/8,1/8
f16
ISO200

7.
�u�p�[�X�v�Ɓu�����b�`�F���X�v�̞��̏ォ��O�i�ڂ̕���̍����ɂ͏c���̓d�g�@�킪�ݒu����Ă���̂ł����A���i�Ƃ��Ă͗p�ӂ���Ă��܂���B
�Ȃ̂ŁA��1mm�̃v���_�����ɏ���0.1mm�̃v������6mm�ɒZ����ɐ�o�������t���܂����B
���M�̌r���������܂����A�����Őؒf����2�Ǖ��P�o���Ă��܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
ISO200
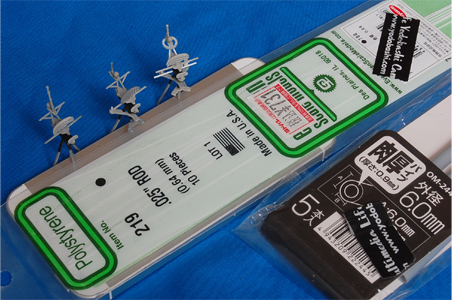
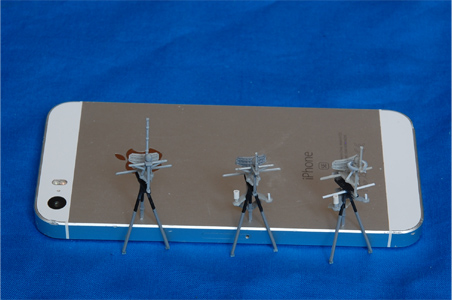
8.
���̞��ł��B�ǂ����������u�W�����E�L���O�v�A�u�p�[�X�v�A�u�����b�`�F���X�v�ł��B
�u�W�����E�L���O�v�ɂ��Ă͉��H�����ł��B
�u�p�[�X�v�ɂ��Ă͏�L7.�̎��앨��3�i�ڍ����ɐݒu���A�E�����ɂ��ׂ��_��\������������̂Ń�0.64mm�v���_�𗧂Ă܂����B
�u�����b�`�F���X�v�ɂ��Ắu�p�[�X�v�Ɠ������H�����A�X�ɁA�����Ɋ�\�������A2�i�ڕ���ɉ����������t���܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1,1/1
f16
ISO200
| R04/05/02 �W��
|
���̃t���b�`���[�B��ܒe�`�p������40���N
|
|
�����R���C�R�쒀�́u�A���~�����e�E�h���N�E�K���V�A("Almirante Domecq Garcia") �v
|
40���N�ł��B30���N�̍ۂɂ͉p�C�R�𒆐S�ɐF�X�Ɠo�ꂳ���܂����B�Ȃ����͈����R���̊͒����ƌ������ŁA�������A�B��Ђ̎c���Ă����u�t���b�`���[(Fletcher)�v���́u�A���~�����e�E�h���N�E�K���V�A�v���쐬���܂����B�悸�́E�E�E�Ƃ��A���߂ɁE�E�E�Ƃ��͐ړ��ŕt���܂���B1�ǂł��I���ł��B�����R���A�ǂ��ɂ������l�^���L��܂���̂ŁB
�u�A���~�����e�E�h���N�E�K���V�A�v�́ANAVSOURCE�����Ă��e���������摜�����Ȃ��A���̎p���������ĐЂ̖����ƕς��Ȃ����낤�Ɣ��f���āA�u�u���C��("Braine")�v����́A1965�N�����ɎB�e���ꂽ���Վʐ^����{�ɂ��܂����B
�ƌ����Ă��A���ʂȘb�ł͖����AH27/8/24�`H28/8/3�W���́uZ-2�v��R02/10/31����W�������u�C�X�P���f�����v�Ɠ����W�������^�Ȃ̂ŁA�O2����r���̍쐬�ł��B
�ȉ��A�����̌o�߂́u���E�̊͑D�v�ʊ�310�����Q�l�ɂ��܂����B
Nikon D40�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
'82/05/02�A�u�w�l�����E�x���O���m("General Belgrano")�v��v�̓��ł��B
������4/2�`6/17�������̂ł����A�͒��̐�v��5���ɏW�����Ă���̂ł���ˁB
���X����5/4�ɂ́u�V�F�t�B�[���h("Sheffield")�v����e��5/10�ɒ��v���Ă��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1

2.
�u�V�F�t�B�[���h�v��A���R�͌��ߎ�������A�b���q���A�C��킪�J��L�����܂����A5/21�ɉp�R���R�}���h�[�̉B���g���ŗg���n�̒�R��r������ƁA�{�̂������Ɨg�����J�n����ǂ������܂��B
�����A���̗g���̌��ʁA�p�͑��͗g���n�̈ێ���㗤�����̉���̈ד����痣����Ȃ��Ȃ�܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
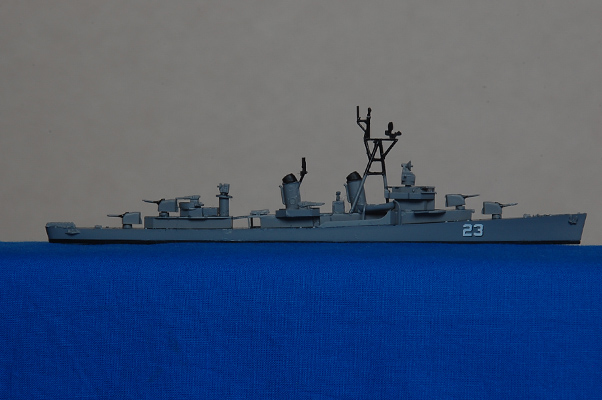
3.
���ׁ̈A5/22�u�A�[�f���g("Ardent")�v�A5/24�u�A���e���[�v("Antelope")�v�A5/25�u�R���F���g���[("Coventry")�v�ƁA�p�R���̐�v���������܂����B
�X�ɁA5/25�́A�傫���̓_�ł͍ő�̑r���ƂȂ����u�A�g�����e�B�b�N�E�R���x�A("Atlantic Conveyor")�v����e���A5/30�ɒ��v���Ă��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
���͎�g���~���O

4.
����ɂ��Ă��A�q�͔�10:1�A���㕺��2:1�A�X�ɏd�����ł��L���ƈ��|�I�Ɉ����R���D���������̂ɁA�ǂ����Ă����Ȃ����E�E�E�B���X�푈�͐��_�͂��Ƃł����������̂��B
�Ⴆ�ΑΔn�≂���A����̂����đ傫���Ȃ����̑��D�ɂȂ������A�p�������͒��X�����[����P�ɂȂ�̂ł��傤�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
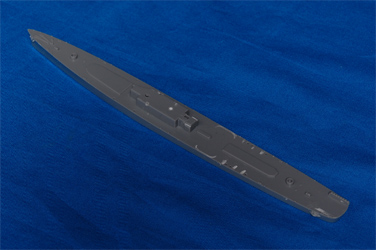
5.
��������́A�ʂ̑�����B�ƌ����Ă��A�u�C�X�P���f�����v��uZ-2�v�Ƃقړ����ł����B
�悸�́A�͑́A�f�̏�Ԃ��炠�ꂱ��藣���܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/30

6.
�����ˊԂ̎ˌ��w�����u���ڂ���b�������܂��B
�u�C�X�P���f�����v��26.�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/8
����4�����x�Ƀg���~���O

7.
�Z���������܂��B
�u�C�X�P���f�����v��29.�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/15
���E1���A��2���g���~���O
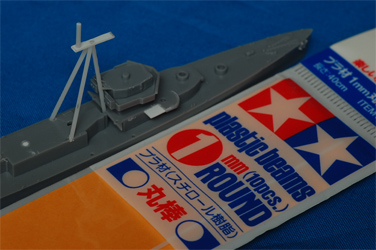
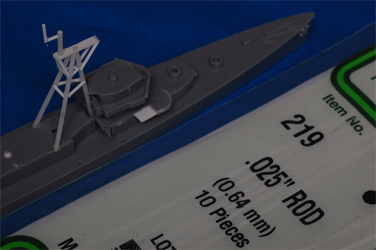
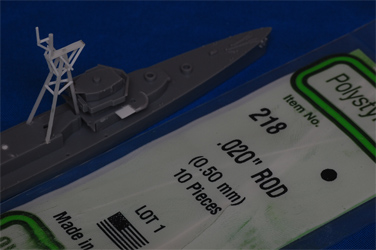
8.
�����g�݂܂��B���̎�̉����̍ۂ́A�ł���Ԃ��|����ْ������Ƃł��B
�u�C�X�P���f�����v��7,8,10,11�ƈꏏ�ł��B�ꏏ�ł����A������Ǝ菇���������A�ꕔ�̎��ނ�ύX���Ă��܂��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/8,1/2,1/4
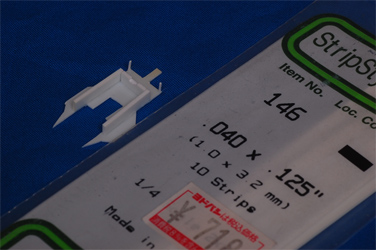

9.
����01�b�̊g�啔�������܂��B����ɂ��Ŏ�Ԃ��|����܂��B
�u�C�X�P���f�����v��23,24�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4,1/8
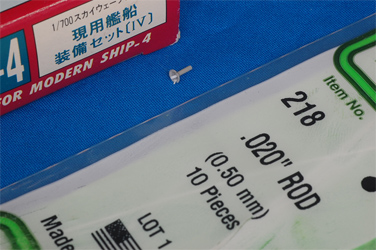
10.
�͋��V�W��̎ˌ��w�����u�̓d�T�AMk.4����Mk.25�ɂ��˂Ȃ�܂���B�Ȃ̂�P�Ђ̌��p�͑D�����Z�b�g4��23�𗬗p���Ăł����グ�܂��B
����܂��u�C�X�P���f�����v��17,18�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2

11.
��2���˂̃p�e���߂ƒ�����ECM����ESSM�����̑���ł��B
�u�C�X�P���f�����v��15��36�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/15
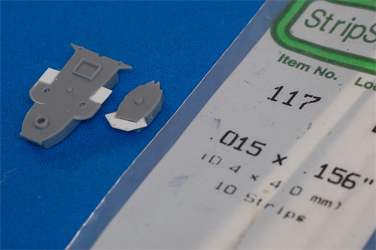
12.
�͋��̑���ł��B
�u�C�X�P���f�����v��6��12�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
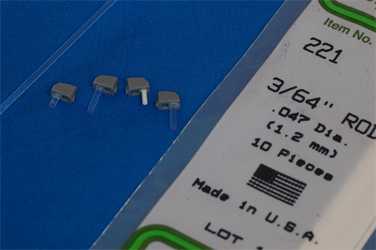
13.
��C�̐��߁A���ڂɍ����ւ��܂��B
�u�C�X�P���f�����v��33�Ɠ��l�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4

14.
�㕔��\�A53�Ԃ�40mm�@�e��3�D�A���C�ɍ����ւ����܂��B���ׁ̈A�Ɨۂ��FCS���ڂ���ˑ��݂����肵�܂��B
FCS�̉ˑ�́A������53�Ԃ̐���P�����Ă���A��2mm�̃v���_�𗧂Ă��肵�Ă��܂������A����͎������A���̏�Ƀ�3mm�̃v���_��Ƃߍ��ތ`�Ƃ��܂����B
�u�C�X�P���f�����v��13�Ƃ͎�Ⴄ���ɂȂ�܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
���E���1�����x�g���~���O
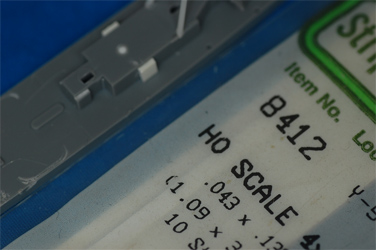
15.
9.�̒���01�b���x������y������t���܂��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/30


16.
�������̊e�쐬���ʂ�ς�ł݂܂��Ƃ���Ȋ����B���̌�AS-7�𐁂��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1,1/1
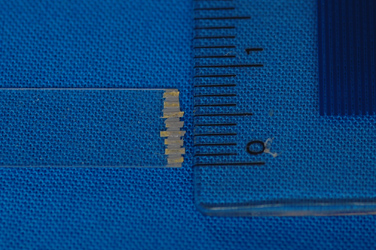
17.
�͋��O�ʂ��Ɏq���ŕ��Ղ���Ă���̂ŁAGM�̔L�b�g�p�̑����i�����ɘg�̕������͑̐F�ɓh���Ăł����グ�܂��B
�u�C�X�P���f�����v��37�ƈꏏ�ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
R04/03/28 �W�� R03�x�������̂��z�{�`���m��͂�!!
��R03�x�������̐V�K�ς݂ł��B
���ς�炸��1/700�͑D�ŁA����͑S���V���i��!!�ƌ����A�܂��A�u�t���v�͂����ł��Ȃ��ł��ˁB���������1�N�ȏ�͌o�߂��Ă��邩��??
�Ƃ���ŁA���m���??�u�C�����B���V�u��("Invincible")�v���������??�E�E�E����??����܂������ł�����ǁA�u�A���X�J("Alaska")�v���͉��X�ɂ��ď��툵������邵�A�u�t���v�͏���I�Ȏg�����̚���݂����Ȃ��̂����A�ԂԂԂB
����]�X�͂��Ă����A1143�^�q�m�́A�O����Ə������ʂ�ɂ��Ă��Ȃ����A�z�l�ɒ��B�����Ȃ������E�E�E�ƌ������A�s��X���ɂ������B���Ď��͂��������Ă��̋C�ɂȂ��ĒT����??�E�E�E�̂ŁA��芸�����������݂ł̐���͖��������ł��B
Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�悸�͑S�̂ł��B
���g�̑傫���ɔ�Ⴕ�āA�f���ɉ��ϔ��̑傫�����Ⴄ�B
�ォ�珇�Ɂu��^���m�́v�A�u��m�́v�A�u�ꓙ���m�́v�ł��B�u�C�����B���V�u��("Invincible")�v�ł���A����Ƃ͏����ĂȂ��B"Battle cruiser"�ł�����A����Ɛ퓬���m�͂����A"Battle ship"��"Battle ship line"�̏ȗ��ŗL�������j�܂���Ɓu��m�́v�ƌ����̂͗ǂ��\���Ɏv���܂��B
1/15

2.
�u�A���X�J("Alaska")�v�ł��B
�͑̂��ł����̂Ŕ����ł����Ȃ�͎̂~�ނȂ��ł����A��͂��������ł��B���[��A��肭�ςݏd�˂Ă����Ə������ł��Ȃ��������˂��B
���݂�2�Ԋ́u�O�A��("Guam")�v���\�肳��Ă��邩�����������ꂽ������Ȋ����ŁA�u�V�������z���X�g("Scharnhorst")�v�A�u�O�i�C�[�i�E("Gneisenau")�v�ƕ��ׂ��肷��Ɨǂ������ɂȂ肻���ł����E�E�E�B
1/15

3.
�u�C�����B���V�u��("Invincible")�v�ł��B
F�Ј���̕��i���ŁA��������ł�(��)�B
���^2�ǂ��o���肵����ǂ��������̂ł��傤�B�o�Ȃ���o�Ȃ��ł���2������??���₢��A����������t���Ċ����ŁA������Ɩ����ł��傤�B
1/8
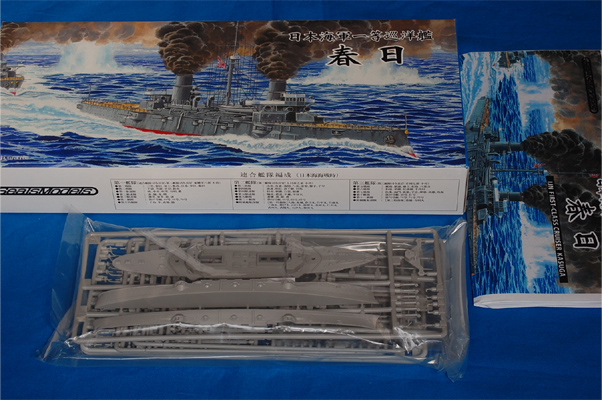
4.
�u�t���v�ł��B
���i�_���͑����ł����A����͂��Ȃ肱����܂�Ƃ��Ă��܂��B
���Ɂu���i�v����������Ă��܂����A�����10�D�A8�D���ڂ̊���������芸�����u�t���v�������B���Ă݂܂����B
1/8

5.
R3�x�������̏v�H��(����)�ƕ��ׂĂ݂܂����B�p�b�ƌ��A�v�H���̕������͂��Ƃ��̐ς��傫�����B
��̔@���v�����Ă݂����A�v�H0.011178m^3�A���B0.007078m^3�ŏo���B�f���Ɋ�������
1/8
R04/02/25 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̎l�`�u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v
����̊C���͒��A��́A���́u�����v���ŏI���ł��B
�\��̒ʂ�A�u��܂����v�O���^�́u���������v�A�u�݂˂����v���́u�ނ炭���v�A�u��܂����v����^�́u�䂤�����v�ł��B������e�ו��ނ̍ŏI�͂ł��ˁB
Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B
�Ƃ���ŁA�嗤�̓��̕��ō��Ƃ�����ł������ł��B����ȍ~��1982/4/2-6/17�̕�������40���N���E�E�E�ƍl���Ă��܂������A�ύX����1143�^�q�m�͂�1�Ԋ͂Ƃ�1135�^�x���͇V�^��8�Ԋ͕ӂ���܂����˂��B�O�҂͐ς�ł��Ȃ��A��҂͇U�^����̉�������ς��������A�����T�^�����ς�ł��Ȃ��B���`�ށE�E�E�B
|

1.
������u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B
��̔@���AASROC SUM�͖؍H�p�ڒ��܂ł̉����ł��B
������ƁA�R�ꂪ����܂��āA�͋��㕔�̊�����t���Y��B���`��A�����z�����Ԃɓ����Ă��܂��A�����Ƃ��܂������˂��B
1/1

2.
�ォ��u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B
�����ɐς�ł��铋�ڒ��́u���������v�̂݁u���p�͑D�����Z�b�gIII�v�ł��āA�����III��IV�ł͂��������`�قȂ�̂ł����A�g���@����Ԃ牺����ア�ڒ���Ԃ��ӂ݁A�����ł͂Ȃ������Ƃ����t���܂����B
2/1

3.
�ォ��u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B
�u���������v,�u�ނ炭���v�̃f�J�[���A���Z���̌�A�����グ�悤�Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��������܂����B�Â����̂炭�Q�����Ă���Ƃ��܂ɋN���鎖�Ԃł��˂��B
�܂��A����͕����Ԃ̓��������Őꂽ�̂ʼn��Ƃ��Ȃ�܂������A���G�ȑ͕W���Ƃ��������Ⴄ�Ƃ���グ�ɂȂ肩�˂܂���B
1/1
����œ_�����A����I�o��3�������

4.
�e�ו��ނōŏI�͂��v�H������ł����A���Ď��́A�u�����v�A�ڏo�x���S�͏v�H���`�`�����
�ƌ������ŕ��ׂĂ݂܂����B
���ƌ�������ƌ�����������u��܂����v,�u�݂˂����v,�u���������v�A
���i�A������u�܂������v,�u�Ȃ����v,�u���������v�A
��O�ƌ��������ƌ�����������u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B
����`�f���Ɋ������B
�Ƃ͌������̂́A�����ł��͔��̊��ƕt���Y��ɋC���t���Ă��܂��A�܂��������X�A�K���Ȏ����ɕ⊮���܂����ˁB
1/1

5.
������u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B
��̔@���A�g�p�h���Ƌ��ɁB
��̔@���A���͉����ŁA���[���͎��O���܂��B
1/1
R04/01/18 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̎Q�`�u��܂���v,�u���݂���v
���������C���͒��ł��B�u�����v���ł��B
�u����v�͑O��4�ǂƌ㔼4�ǂőO���̊O�ς��قȂ�̂ł����A����͑O���ƌ㔼����1�ǂÂł��B
�u���݂���v��P�А��K�́E�E�E�ł͂Ȃ��A�{��͌^���ʌ���ƌ����Ă��܂��āA������??�����Ŕ������̂��낤�E�E�E�B
�u��܂���v�͂����ƓK���ŁAP�Ђ����r�����i�E�E�E�W�����N����a��E�E�E�ł��B
|

1.
���u��܂���v,�E�u���݂���v�ł��B
2�Ԋ͂�8�Ԋ͂ɂȂ�܂��B
�u���݂���v�ɂ�5�`8�Ԋ͂̃f�J�[������������A�u��܂���v�͋���H30/5/29����W�����wJMSDF�͒��A���Q�e�̓�`�u��������v�x�œ����̃f�J�[���̎c�]���p�ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
F16
ISO200

2.
��ƌ��������ƌ������u��܂���v,���ƌ�������O�ƌ������u���݂���v�ł��B
��s�b�̒��͕W���A�u��܂���v�͓h���A�u���݂���v�̓f�J�[���ł��B
�u��܂���v�͂ւ�ւ�ł��˂��B
�O����u�͂܂䂫�v�͓h���A�u�����₫�v�̓f�J�[���ł������A�����2�ǂ̈Ⴂ�͏��i�\���̏��ׂł��āA�v��������r�����i�Ƀf�J�[���͕t���ė��Ȃ��̂œh����I��������Ȃ��ƌ������ŁB
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
F16
ISO200
���x����

3.
��������ׂĂ݂܂����B��u��܂���v,���u���݂���v�ł��B
��{�I�ɂ͕ς��Ȃ��̂ł����A�\�艺�Ŋ��q�̗l�ɑO�����قȂ��Ă��܂��B�����������i���͂���Ă���̂�����܂����˂��E�E�E�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
F16
ISO200
����̏�����2������

4.
��u��܂���v,���u���݂���v�ł��B���x�͉E���ł��B
�O���͊�ȊO�ɕ��ꉺ�i�̑�d�T��OPS14C����OPS24�ɕς���Ă��܂��B�ƌ������A���̓d�T�̕ύX����ɗL���āA���̕ύX�ɂ����������̕ύX�lj��ׂ̈ɑO�����ύX�����̂ł��傤�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
F16
ISO200
����̏�����2������
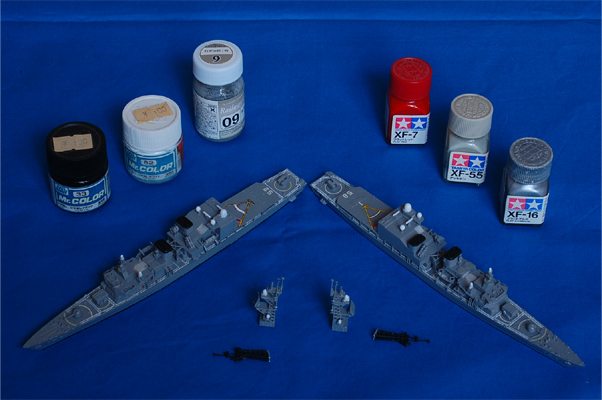
5.
���u��܂���v,�E�u���݂���v�ł��B
�g�p�h���ƕ����āB��̔@���O����͖؍H�p�ڒ��܂ɂĉ����߂ŁA�i�[���͎��O���܂��B
����܂��A�O��́u�䂫�v��5�Ɠ��l�ɓh���͌���������܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
F16
ISO200
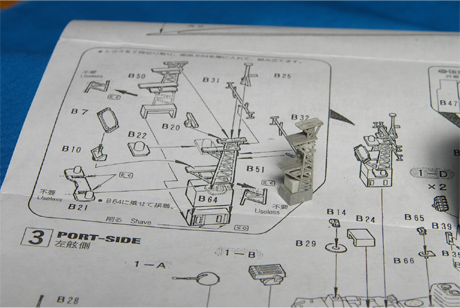
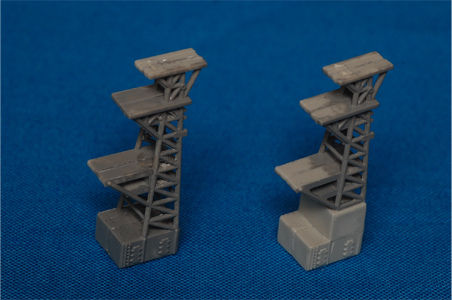
6.
��������͐F�X�Ɨ��ӓ_���B�悸�́A�O����̂��b���B
�悸���B�g�ݗ��Đ����̒ʂ�A�O���������ȉ��ƍb���Ԃ�ؒf���A���̕���B64�Œu��������Ď��ɂȂ��Ă��܂��B
�����}����B64�ƍb�����قړ�����ʐς������Ă��銴���Ȃ̂ł����A���ۂɍڂ��Ă݂��B64���������āA�O���g���X�̊ԂɛƂ荞��ł��܂��B
�����ł͂Ȃ��A�E�̗l�ɍڂ���ƒ��x�ǂ����A700/700�̉摜�����Ă������l�Ɍ�����̂ł���ˁB�Ȃ̂ŁA������̔z�u�őg�ݗ��Ă܂����B
PENTAX istDs(���ȉ����l)�ANikon D40(�E�ȉ����l)
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�ATAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/30�A1/1
F16
ISO200
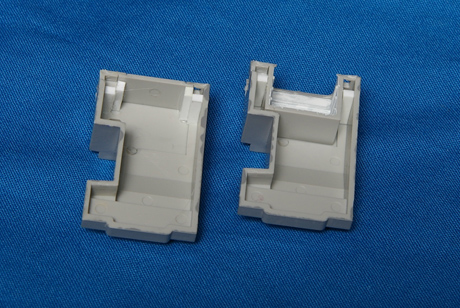

6.
�����Ċi�[�ɁB����́A�u��������v��7�̎��Ɠ��l�ɂ��̂܂܂��ƒ��g�������Ă��܂������v���߂ŕǂ����܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/30
F16
ISO200
����2�����x�g���~���O
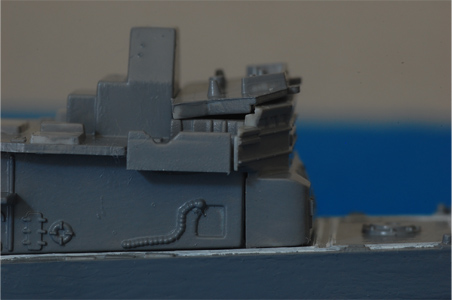
7-1.
���͊͋��ł��B
2�Nj��A���̂��O�ʕ��i�̍����ƁA���ʕ��i�̍��������킸�V�W�������Ă��܂��Ă��܂��B�u��������v�̎��A����Ȏ��N��������??
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
F16
ISO200

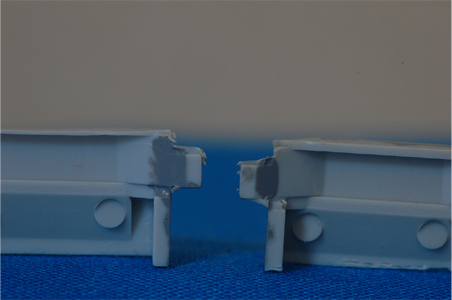
7-2.
�ߋ��ǂ����������͂Ƃ�����A�Ƃɂ����\�����̍���������Ȃ��̂ŁA�͋��O�ʕ��i������č��������킹�鎖�ɁB
���u��܂���v�͏�[���A�E�u���݂���v�͉��[������Ă݂܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1�A2/1
F16
ISO200
�ǂ��������2�����x�g���~���O

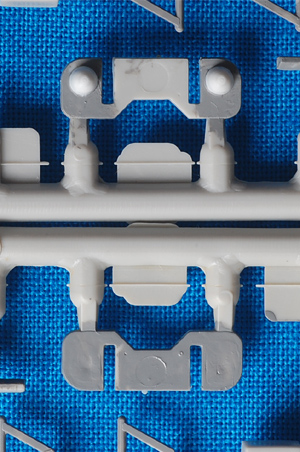
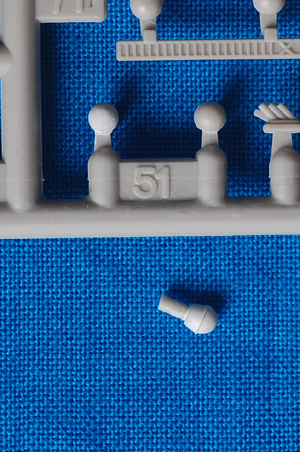
8.
���������r�����i�����r���鏊�ȂȂ̂��낤��??�Ǝv�����̂ł����A�O���̗�����OLT-3�A�����i�Ɛ��K�ł͂��Ȃ葢��ɈႢ���L��܂��B
���A���̕��i21����������̂ł����A�㐳�K�i�A�����r�i�ŁA����������̉~���Ȃ̂����r�i�͖��炩�ɕςł��B
���A���Ԃ��Ƃ���ȋ�B�㉺�͓����ŁA���K�i�͉~���ł��鎖������܂��B
�E�A�Ȃ̂ŁA���p�͑D�����Z�b�gV��SuperBird�p�A���e�i�𗬗p���鎖�Ƃ��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1�A1/1�A1/2
F16
ISO200
��������E1/4���x���g���~���O���ďc�\�}��
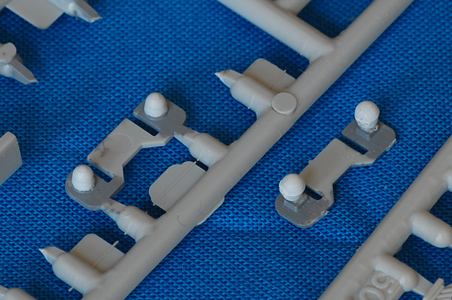
9.
�ŁA�����Ȃ�܂����B
���������Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��܂������A�܂��C�ɂ��Ȃ��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
F16
ISO200
R03/12/15 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̓�`�u�͂܂䂫�v,�u�����䂫�v
�O��ɑ����ĊC���͒��ł��B������݂́u�䂫�v���ł��B
�\��̒ʂ�A5,6�Ԋ͂́u�͂܂䂫�v�Ɓu�����䂫�v�Ƃ��܂����B����ʼn䂪�{�I�͑��ɉ����Ė{���v�H�͔����ɓ��B�ł��B�ʁ`�A��͖��������B
Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
���u�͂܂䂫�v�A�E�u�����䂫�v�ł��B
ASROC SUM�́A������ɑ��Ċp�x��t���Đݒu���Ă��܂����A����́A���O���Ղ��l�ɖ؍H�p�ڒ��܂��g�p���鎖�ɂ������̂����ږڎ��ŕ��ʂł���l�ɂƂ������̂ł��B
P�ЊC���͒����������i�Z�b�g�́u���p�͑D�����Z�b�gIII�v����u���p�͑D�����Z�b�gV�v�ɕύX����Ă���̂ł����A����Mk.112���ˋ@�̑��삪�傫���ς���Ă��܂��A��œ��^�͖��ɓ��ꂳ���悤�ƌ�����|�ł��B���̐ǐ��ɒB�����A�����́A�u���p�͑D�����Z�b�gIII�v���g����A��������钆�ÂB����\���������ƂȂ����i�K�ŊO���đg�ݑւ���\��ł��B
1/1
���x����

2.
��ƌ��������ƌ������u�����䂫�v�A���ƌ�������O�ƌ������u�͂܂䂫�v�ł��B
����A�����b�̕W���A�u�����䂫�v�͓h��������ǁA�u�͂܂䂫�v�̓f�J�[���g�p�B����???�E�E�E�Ɩ����E�E�E
���́AR03/08/30����W�����n���S���̉����W����>�n���S���U��>���o�ꐼ����������ɂ������܂������A����8������Ƌ��ƌ���������u���ƌ������A������Ղ��ς���Ă���܂��āA����͌����r�������̊��Ɏ�������Ŋ��H�����܂����B��ŁA���F�̕����Ɏg�p����GM��12�u���F5���v���������ݖY�ꂽ�̂ł���B
���႟�d�������A��������ăf�J�[���g�p�ŁA�ƂȂ�܂����B����܂��A�A�L�o�̃U�E�X�g�A�[�Ȃ胈�h�o�V�Ȃ�s���Ηǂ��̂ł����ˁB
1/1
����1����g���~���O

3.
��u�͂܂䂫�v�A���u�����䂫�v�ł��B
�E���A���[��A�w�LjႢ���L��܂���B
���ہA�L�b�g�̎w���4�Ԋ́`9�Ԋ͂��Č`��I�ȈႢ��������ł���ˁB�͔ԍ������ł��B
�����Č����ƁASSM�̉ˑ�B���H�ԍۂɋr�����܂�Ă��܂��A�Ƌ���Ɏ�������No.33�u����䂫�N���X�v���痬�p���܂����B
������A���˓�����̕��˂���\�����̗L���E�E�E�Ə����Ĕ�����̂��E�E�E���قȂ��Ă���܂����B
2/1
���œ_�A���I�o��2�������
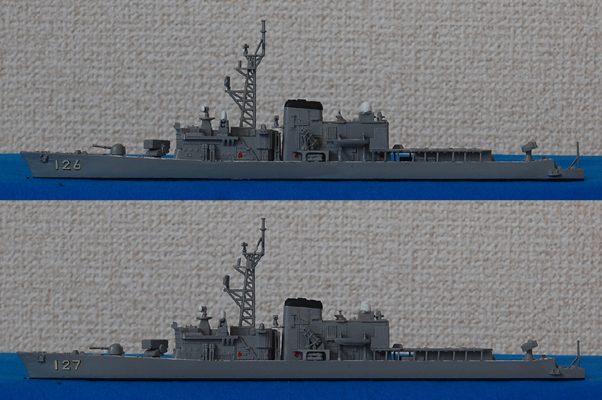
4.
��u�͂܂䂫�v�A���u�����䂫�v�ł��B
�����ł��B�������SSM�ˑ�ȊO���ق͖����B�����ɂȂ邩�s���ł����A�܂�2�Ǎ��ƁA�����ɍs����7,8�Ԋ͂ŁA����܂����ق��������Ď��ɂȂ��ł���ˁB
�ǂ��������̂��E�E�E�B
2/1
���œ_�A���I�o��2�������

5.
���u�����䂫�v�A�E�u�͂܂䂫�v�ł��B
�g�p�h���Ƌ��ɁB���āA��q�̒ʂ�A�h���͌���������܂��B���F5�������ł͖����A29�u���}�o�[�~���I���v���ѓ��R��ł��B
��̔@������͖؍H�p�ڒ��܂ʼn����߁B���[���͂��̗l�Ɏ��O���܂��B
1/1
R03/11/29 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̈�`�u�Ђ����v
�v���Ԃ�̊C���͒��ł��B��������A��ł��B�����B�O���H30/4�`8���ł����B�T��3�N�Ԋu�ŁA�ϊ͎����O�ɏv�H�ł������A��������N�J�Â����Ƒz�肳��Ă���O�ɏv�H�ł��A
�E�E�E�ƌ����A����K.O.���̈�����ɍ��킹�ĕғ����������������肷��B�܂��O��A�O�X����ғ����Ȃ̂ŁAK.O.���̈�삪��`��ς���R3/8�ȍ~�������ė����Ƃ������܂����B������A��芸����������̍���őł��~�߂ł��B�ł��~�߂ƌ������ŁA�ғ����̒����獡��͔�r�I���h���̂���DDH���B
|

1.
���̂�FRAM��ƂȂ�܂��B�u�͂�ȁv�����l�ŁA�����͊͂ɂ���č�蕪���Ƃ��͍l���Ă��Ȃ��炵���B
�l�I�ɂ�FRAM�O�̊i�[�ɓV�W��̂������肵���p�̕����D��ۂ������肵�܂����A�܁A�v���������ł��ˁB
�ǂ����A�ȑO��������Ă������I�����l�炵���A�ǂ����Ă�FRAM�O��!!���ėv���ɂ͎����ʼn��Ƃ����邵�����������ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
F16
ISO200
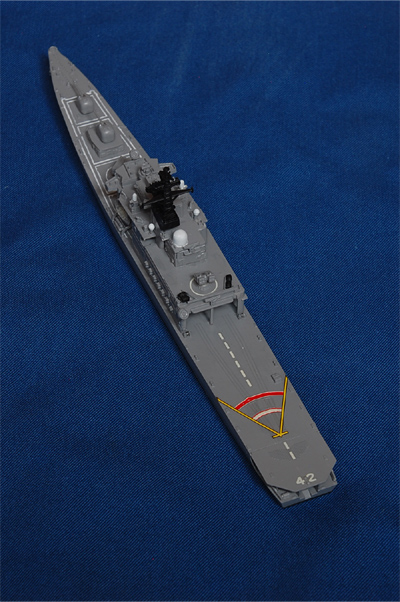
2.
��b�ɂ͐퓬�ʘH�̓h�����������̂ŁA�b�̓h���͂Ƃ��`���Ă��y�ł����B
�͔��ɂ�VDS�����̂ˁB�i�[�p�̉��݂͂��邯��ǁB�������Ă݂�ƁA�u����ˁv���ɂ͐ς��Ęb�͏o�ė��邯��ǁA�u�͂�ȁv���ɐς܂Ȃ��������Ęb��������Ȃ��B���`�ށE�E�E�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
F16
ISO200
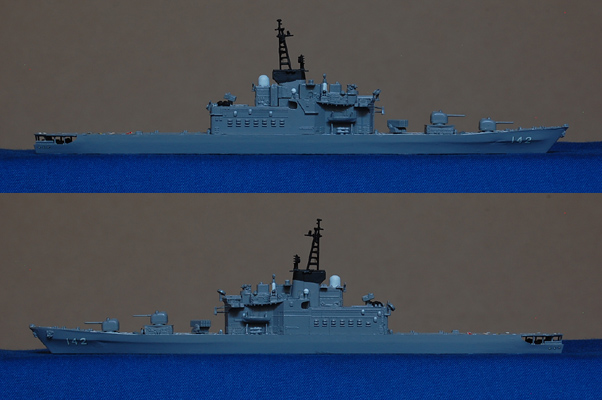
3.
���˂������Ɋ���Ă���_�͒����ȍ��E�����̍��قł����A���̑��ɂ�����낿���ƍ��ق��L��܂��B
�i�[�ɂ���̔r�C�����́A�d�T�E�E�EFCS-2����??�E�E�E�̊��Ƃ��ł��ˁB
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
F16
ISO200
����œ_�����A�I�o��2�������

4.
��̔@���A�g�p�h���Ɨ��߂āB
���������܂���̔@���A�؍H�p�ڒ��܂ɂĉ����߂ŁA���[���͊O���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
F16
ISO200
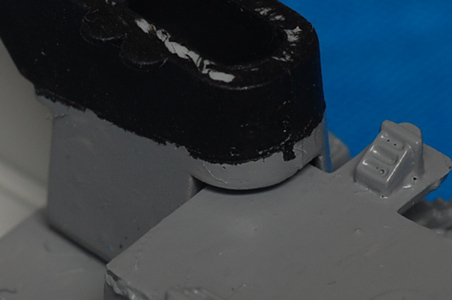
5.
FRAM�ł����Ⴒ����ɂȂ�����\�̑����ǂ�����܂���B�v�������蕂���Ă��܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
F16
ISO200
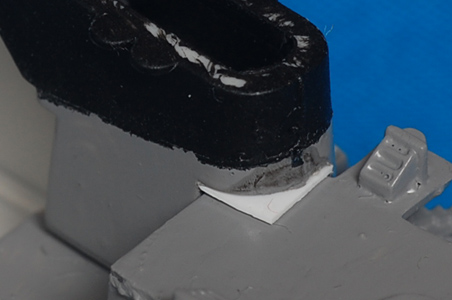
6.
�Ȃ̂ŁA���������0.5mm���̃v�������܂��Ă݂܂����B
��??���˒����̓h�����Ƃ��_������Ȃ���??���͂͂͂́A�C�ɂ��Ȃ��C�ɂ��Ȃ��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
F16
ISO200
R03/10/22 �W�� �ꉞ�����R���C�R�����͂̂��肾����ǁA�h���͖w�ljˋ�͂�42�^Batch�h
�O��A�uR03�x�㔼���̂��z�{�v��2.�ł������������c���������v�H�ł��B
����˂��A����ς̏d����̂���{�Ƃ��܂��āA�g�ݗ��Ă͖w�ǐi��ł��Ȃ�����ǁA�͑́A�h�����A�������i�͓h�����ς�ł���B�ς�ł���͗ǂ�����ǁA�ǂ��ɂ������C�R����͂Ƃ��Ă͊���ȓh�F�����B����ች��h�����̂��������Ȃ��ƁE�E�E�B
�ŁA�������Ă�����ɁA�Y��Ȃ����ɍ���Ă��܂���!!�ƂȂ�܂��āB
����Ȍo�܂ł��̂ŁA����Ƃ��Ă�42�^Batch�h�ɊԈႢ�Ȃ��̂ł����A�ّ�{�I�̉����C�R�ɂ����^�͂������ł����A�ǂ��ɂ��e�a�������܂���B�Ȃ̂ŁA�]��̃G�O�]�Z�����������ARA�ɉ����t���鎖�ɂ��܂����B
�ƌ����Ă���ARA�����͂������C�R�Ǝ����l�ȐF�����̗l�ŁA���ǁA�قډˋ�͏�ԂƂȂ�܂����B
|
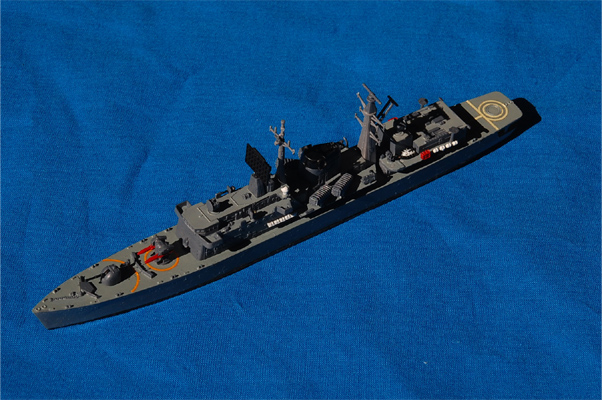
1.
�܂��A�K���ƌ����ׂ����A���N�O���ɂ�Falkland War 40���N�ł��B30���N�̍ۂɂ͉����C�R�͒��𐏕��Əv�H�����܂������A�����ARA��������ق�E�E�E�Ǝv��Ȃ����Ȃ��B���̚�����Ď��Ŕ@���ł��傤����??
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/125
F16
ISO200

2.
����30���N�̍ہA"USS PHOENIX"�̌�g���A�F�X2�R1�A3�R1�łƂ������������̂ł����A���X�ɕ��������̂ŁA42�^�h�Ɓu�t���b�`���[�v�����Ă̒�I�ȑI�����Ƃ��Ďc��A����̌܌��J�I���H�`�v�H�Ɏ����������������Ƃ������܂��B
�Ȃ̂ŁA����ƌ����Ă��A���s���ĉ�������̂��B���ǁu�t���b�`���[�v���ł�����??
���݂Ɂu�t���b�`���[�v���A�啪�ɂ����炵�ė��Ă��܂����A�����L�锤�Ȃ̂ŁA��������K���Ȏ����ɒ��肵�Ȃ��ƁB����ɂ��Ă��A10�N�O�͎�������o�Ȃ������ł��낤�A"ARA Almirante Brown DD20"���āA�ȒP�Ɏʐ^�E�E�E�N���ł͖������A�傫������������ǁE�E�E����ɓ��鎞��A����͂�A�֗��ɂȂ������̂ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/125
F16
ISO200

3.
�Ƃ���ŁA����AARA��2�ǍݐЂ���42�^�A�ǂ��炩�͂�����Ƃ͂����Ă��܂���B���͌��߂��˂Ă���܂��B
�ƌ����̂��A�o�̕��͒�����ۂ��A�ӔN�͌㕔��\�𒆐S�ɂ��Ȃ�̉������Ă��āA������Č�����̂��ꋻ�Ǝv��Ȃ����Ȃ��B�ł���������ƕ��������炩�Ȃ��̎p�ɂȂ��Ă��܂��B
����ƂāA���͖��ʼn����C�R�ݐЂٕ̈�o���B�ƍ��ق������A����ϋɓI�ɑI������i���͂������B���̏�L��������̃G�O�]�Z�����ɂ͖������ۂ���ł���ˁB�Ȃ̂ŁA�܂������������߂鎖�Ƃ��܂��āA�����͂���ӂ�Ȃ܂܂Ƃ��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
F16
ISO200
����2�����x�g���~���O

4.
�g�p�h���Ɨ��߂āB
��]���@�͍��܂���ł����Bwiki�Ƃ�����ƁALynx���ڂ����Ə����ėL��A���i�̐����㓖�R��������Ă���̂ł����A�h�F���S�R����Ȃ��B�܂��A�͑̂��A�{���͂قڐԓ��̔��Α��̎o���B�Ɠ����l�ȓh���Ȃ̂ŁA�����l�ȕ�����Ȃ�??�Ƃ��v���܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/125
F16
ISO200
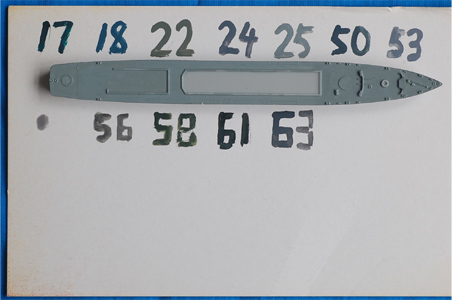
5.
��������́A���̓h���̘b�B
�O����uR03�x�㔼���̂��z�{�v��5��6�ł����̒ʂ�AK.O.���͓h���͖w��T�А��𗘗p���Ă����͗l�ł��B�b�����Ă��Ă��AC�Гh���œh���w��E�E�E�Ԃ����Ⴏ�A�����ŕ��ʂɗ��ʂ��Ă���͑D�ɂ��Ă�T��P�ȊO�̖w�ǁE�E�E���Ă���ꍇ�A���Ȃ薳������T�Дłɓǂݑւ��Ă����͗l�B
�Ȃ̂�T�ЃG�i�����ŐF���{������Ĕ�r���Ă݂���ł��B�e�ԍ��̑O��"XF-"��t����Ɣ���Ղ����ƁB
�ŁA�b��XF-25�Ɋm��ł��B
���݂ɁA�g���}�̎w���C�Ђ�337�B���`��A�m����XF-25�͋߂�����������̂ł����A����AD�Ђ̎w�肪�Ԉ���Ă��Ȃ�����??
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
F16
ISO200
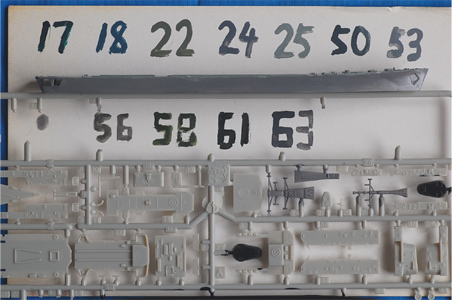
6.
�����ƑO����A���˒������h���ςł��B
���ˈȊO�̓h���͑�ϋ�킵�܂����BXF-24�A53�A63�ӂ���ۂ��̂ł����A��芸�������̎莝���̋߂����ȐF�����̒��ɂ͓I������������܂���ł����B
��������Ă����肷��Ǝ�̑ł��l���L��܂��A���\���������Ă����l�Ȃ̂ŁA����ȏ�lj����B���ēˍ�������̂̓����ɂ��āAXF-24�ōs���Ă��܂��`��!!�Ƃ��܂����B
���݂Ɏw���C�Ђ�31�B��������߂��ƌ����߂������B��͂�A�Ƃ͌����A���㉢�B�́A����ȔZ���h�F����Ȃ����B��͂�D�Ўw�肪�ʖڂȋC������E�E�E�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
F16
ISO200
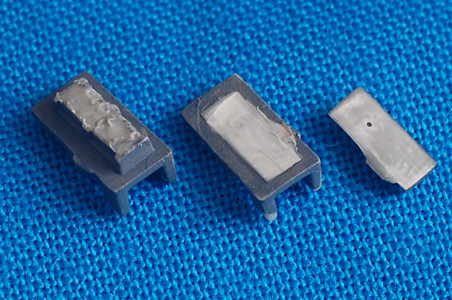
7.
�G�O�]�Z�ɂ��Ăł��B
���Ɣw�����߂���C������̂ł���B
H24/12/18�`H25/12/14�œW���́w�t�H�[�N�����h�����J�I��30���N�L�O��l�i�`1/600 �u�A�}�]�����t���Q�C�g("Amazon" class frigates)�v�x��A�Дł�D�Дł���������A���̃G�O�]�Z�A�w�������Ȃ��`�Ǝv���Ă����̂ł����A�ˑ�̏㕔��藣���Ă݂鎖�ɂ��܂����B
�������H�O�ŁA�^�͏㕔��藣���č̗p�����ˑ�A�E���藣�����㕔�����ł��B�X���Ă���̂Œ萫�I�ȕ\���ɂȂ��Ă��܂��܂����A�T�˔������x�ɂȂ����̂ł�??
�����Ƃ��A���̂��܂��܂Ƃ����w�͂�}���l�ɁA���ˋ@➑̂�����ł��āA�ǂ��ɂ������̎ʐ^�ɔ�ׂāA���ǔw���ɉ߂��܂��B�����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
8/1
F16
ISO200
�����������x�Ƀg���~���O
R03/09/16 �W�� R03�x�㔼���̂��z�{
��R03�x�㔼���̐V�K�ς݂ł��B�O�̔����Ɠ��l��K.O.���̈�i�ғ��ł��B�\��ł͂��z�{�ƋL�ڂ��܂������A���z�{�ł͂Ȃ��ł��ˁB������x�����Ă��܂���B
���ς�炸��1/700�͑D�B���S�ł��B�����ƍT����3��+���̒��B�ł��B�܂��A�O�̔����̕ғ����������Ȑ��ł����̂ł��������}�~���Ȃ��ƂˁB�ŁA���̕ғ�������ŏI���ł��BK.O.���̋���͊��ɔ��p����A8/18�i�K�łقڂ����ǂ��ɂȂ�܂����̂ŁB
�ŁA��2����K.O.���̂���t��(��)�ł��B�܂��A�㖼���͔ޏ��ł�����˂��B
|
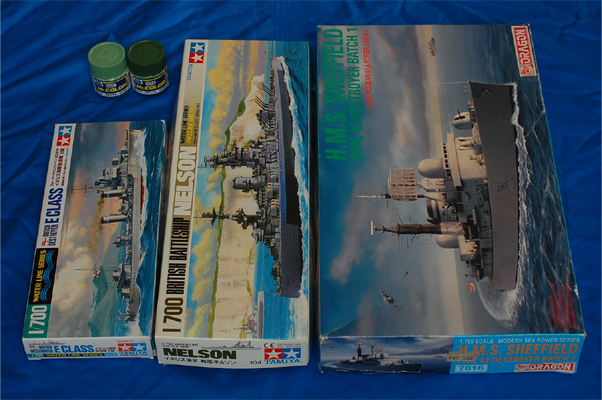
1.
����őS���B�O�̔����͕ψِ��L����32���ł������A����͑S�`���A�p���i���B�ł��B
�����A�h�����L��܂��ˁBMr.�J���[��604��605�ł��B������IJN�̋��̑��ʓ��̖��ʗp�ŁA�w�Ǐo�Ԃ������̂ł����A�B��T�Ёu����v���ɂ��Ă��Ă����Ɏg���Ă�낤���ƈ�����鎖�ɂ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
F16
ISO200
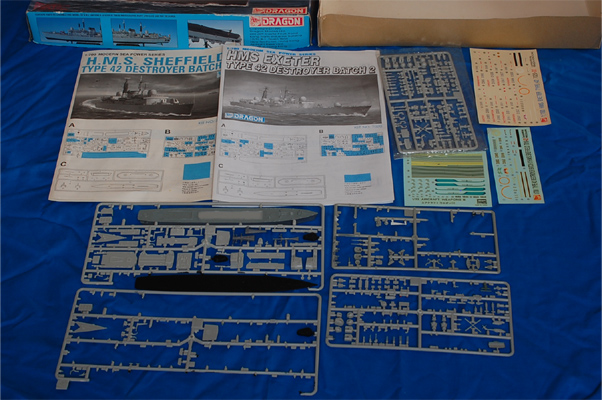
2.
����t���Ə����܂������A����Ȋ����B42�^Batch 1�̔��ɂ�2�Ǖ��̑g�ݗ��Đ����ƁA1�Ǖ��̕��i��1�Ǖ��̎c�[�������Ă���A���̂��f�J�[����2�Ǖ��ɉ����āA1/72�Ȃ̂������Ƒ�k�ڂȂ̂��q��@�p���B
�ŁA�{���̕����i�ł���1�Ǖ��͊͑́A�h�����A�ꕔ���͓h���ςȂ̂ł����A���[��A���Ȃ��a���̗L��h�F�őg�ލۂɂ͓�q�������ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
F16
ISO200
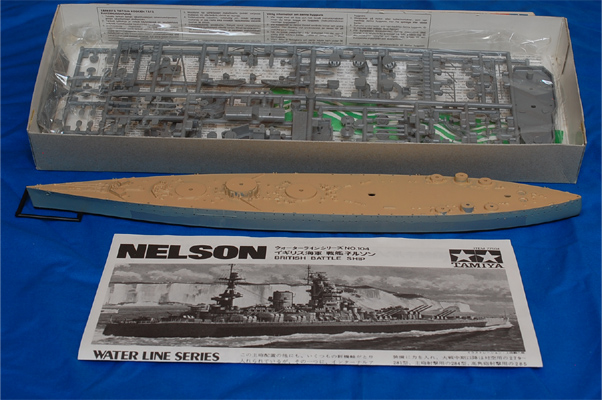
3.
�u�l���\��("Nelson")�v�̒��g�́A�����ɂ��Ă͕��ʂŁA�͑̂̂ݓh���ς݁B�b�̓f�b�L�^��(XF-55)�Ƃ��؍b��(XF-78)���炵���h�F�ŁA�C������̐ݔ��������F�Ȃ̂͂����h�ł����A���ɐ^�����Ȋ��������܂��B
�����́A���G�ɒ����ɂ��悤�Ƃ����̂��A������Standard Scheme "A"�œh���ςł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
F16
ISO200

4.
���āA���̔����̏v�H��(����)�ƕ��ׂĂ݂܂����B���b�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA���@�͐}���Ă��܂��͂���������ł��B
���₢��A���͂ł��ˁA���N�ȏ�ɓn����K.O.���̈�i��W�����ė����Ԃɒ��X�Ɛi�����Ă����ł���A�z���g�ł���E�E�E���ĒN�Ɍ����Ă���̂��B�܁A�������͊撣��܂��傤�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
F16
ISO200

5.
�O�̔����ł́A��ʂ̔��p���������������܂������A����͓h����ғ����������L���āAK.O.������ʂɕ����Ă����h���B���B
�悸�̓A�N�������BT�Ђ̃A�N�����ł��ˁB�����F����ʂɍɂ��Ă����Ⴊ�U������܂����B���̒��ł́A���Ɍł܂��Ă���XF-2��X-2��15�{(��!!)���BXF-5��XF-66�������L��܂��B
PENTAX istDs
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
26mm
1/500
F5.6
ISO200

6.
�G�i���������Ȃ����Ă��܂��B�A�N�������l��XF-2��XF-66�͂��Ȃ肽������B���b�J�[���A�ғ�����604�A605�͑���2�{�Âɂ��Ă����肷��B
�n�܂������ɂ��Ă��āA���[��A�����ǂ��l����Ƃ����Ȃ�̂ł��傤�B�n�܂́A�Ⴆ�Γh�������ڂ����ꍇ���|�p�ɑ�ʂɎg�p���čl�����܂����A�h�����̂��̂͂���Ȃɑ�ʂɂ͗v��낤�ɂƎv���̂ł����B�쐬�������Ă���ƂƂĂ��g����Ȃ����A�ł܂����Ⴄ���B
���ɂ����g�p�ʼnt�R�ꂵ�Ă����P�O���d�r�Ƃ��A�J�����Ă��Ȃ�5����10������̃m�[�g�Ƃ��A���������J�����g�p��HDD�A�l�N�^�C�A�d��A����(�܁A����͓��R���B�ł����������y���ɒ���)�A���a�V�c���^(@_@)�Ƃ����̂ɂ���Ă�10��20��������Ȃ������L������A�ǂ����������Ǘ����j�]���Ă����l�ł��B�v���ƂȂ����a�C�̏��ׂ������̂��A���������̐��i�������̂����Ȃ̂��A�ǂ�����܂��A���̂���Ӗ�����Ղ����H���R�Ƃ����ێ�I�v�z�v�l�Ƃ͕ʂ̐����҂Ƃ��Ă̑����Ȃ����������܂��B�܁A�U�ȂȈ����͂���ʂɂ��܂����B
PENTAX istDs
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/500
F8
ISO200
R03/08/14 �W�� ���B���쒀�́u�M�A�����O("Gearing")�v
P�Ђ�1/700�ł��B���̕ӂ�͒��N�A�w�Nj������Ж������Ђ̓ƒd�ꂾ�����̂ł����A���N�O����X�m�[�}�����f���Ȃ鏤�W�ł������A�����A�S�D�̕����o�ꂵ�Ă���܂��B
���A����͓��R(^^;;;;�A�����ČÂ��ėm���P�Дłł��B
�u�M�A�����O�v���A�s��92�ǏA�����Ă��܂��B�u�t���b�`���[�v��������WW2���ɉғ����Ă���IJN�쒀�͂̂قڑ����ɕC�G���A�x���\���n���T���i�[���ƍ����Đ�����Ɛ�債�܂��B�܂��A�u�M�A�����O�v���S�͂����ɊԂɍ�������ł͖����ł����B����Ȕޏ������̒����炩�狉���͂�I�����܂����B
Nikon D40�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|
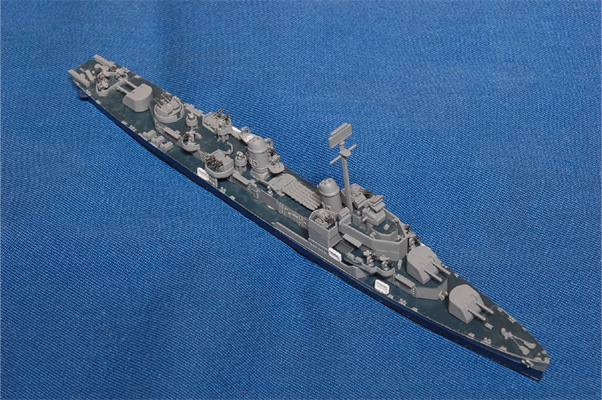
1.
����A40mm�@�e���@�e���Ɏ��܂炸�������܂����B��ꉌ�˗����̘A���́A������ɕ��s�ɏe�g���������������̂ł����A��O�����ɐU��܂����B
��ˌ���ŗ����������Ă���4�A���́A�ǂ������Ă����炸�A�@�e���̒�ʂ���̗����オ�蕔��������H�ڂɁB�@�e�����k�ڒ��ߋC���Ȃ̂ł��傤�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1

2.
�h���́A�f���Ɏw���Measure 22���̗p���܂����B
shipcamouflage�ł́A33a/28d/22�Ə����Ă���܂����A33a�͖ʓ|�L����ɗ����̐^���ɋ߂��p�x�ł̎ʐ^���������Ȃ��Ɩ��������ANavSource�ł�22�̎ʐ^�������Ȃ����A28d�Ɏ����Ă͑S�R����Ȃ��̂ň��S���Ė����ł��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
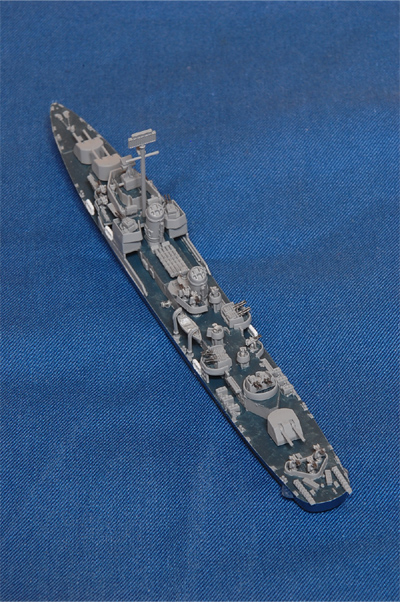
3.
���ڒ��A�u�t���b�`���[�v������p���ƕӂ�̋쒀�͂����Ă��A��̊͋������ꉌ�˗����ɂ��Ċ����ł����A�����ƌ���Ɉړ����Ă��܂��B���łł��傤�˂�??
�d�����Ȏ�C��O�b��2��u�����̂Ɠ������R�ŁA���Ƃ��Ă��O���ւ̑�Η͂𑝂₵�����B40mm�A���@�e�̂��O���Ɍ�������ݒu�ꏊ���������悤��!!�ĂȌo�܂ŁA���ڒ��ɉ������Ė���Ă̂ł�??�Ǝv���̂ł����E�E�E�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1

4.
��̔@���A�g�p�h���ƁB
��̔@���A�h������P�Ўw��ɏ]���Ă��A�g�p�h���̎w��͖������Ă��܂��B
��̔@���A�������FCS���͖̂؍H�p�ڒ��܂ł̉����߂ŁA���O���Ď��[���܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
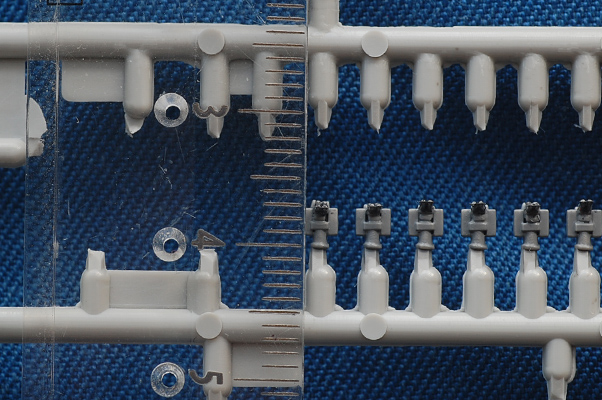
5.
1.�ŋ@�e�ނ̏k�ڂɂ��Č��y���܂������A20mm�A���@�e���@���Ȃ��̂�??�Ǝv���Ă��܂��܂����B
�����̒ʂ�A�w���ɉ߂���Ǝv���̂ł���B�h���̏�[��3mm�߂��A�����ɂ����ۂ͏e�c�������l�ȍ����ł�����A700/700�ł�2mm�O��̍����ɂȂ��ŁA�Ə��͑����e�g��艺���Ď��͖����ł��傤����A�g���ɂ��Ă�����2.3m�ʂ̐l�Ԃ�����Ȃ���Ȃ炸�A�@���ɃA���O���T�N�\���̔w�������ƌ����Ă��˂��E�E�E�B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
����1�����x�g���~���O
R03/07/11 �W�� K.O.�������14�e�`�n���A�M�R������
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������ė��܂��������ŏI��ƂȂ�܂��B
���́A�\��̒ʂ�B���Č������A�n���A�M�R??�F�����I�̐��E??22���I������23���I����???�����̐��E�̂Ȃ̂�????
����܂��A����R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v��14,15�Ƃ�����Έ�ڗđR�ł��ˁB����́A��r�I�ɂ܂Ƃ��ȏ������A������͐�͂Ə��m�͂𒆐S�ɂ��������܂��傤�B
|

1.
��O�����m�́A������͐�͂ł��ˁB�ǂ���������A���J�R���ł��B�o��������\100�ʂŁA���𑵂�����㕨�ł����B
�ǂ�����A�Ԃ����Ⴏ�A���u�ł��ˁB�u����v��u2�v�ł͊��S�ɔw�i�ł������A2202�ɂȂ�Ɨ��҂ɑ傫�������o�܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/30
F16
ISO200

2.
��O�����m�́A������͐�͂ł��B
��͐�́A�ꕔ�Ɍ͖��̂��ݒ肳�ꂽ�l�ł��B�������A�p�����ɐ擪������"D"�œ��ꂷ��l�ȁw�炵���x������āB
����ɑ��āA���m�́A���ƁA�o�ꂵ�܂���B
orz
�ǂ����Ă����Ȃ���??
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/15
F16
ISO200

3.
���ƌ��������ƌ��������m�́A��O�ƌ������E�ƌ�������͐�͂ł��B
�܂��A�u�A���h�����_�v����4��(�ȏ�??)�o�ꂷ��Ƃ��A�S�ʓI�ɑ������\���C���ŁA���荞�ތ��Ԃ��������������ł����˂��`�B
�ǂ����A2202�A�]�����U�X�ł��ˁB�ʑt�ቹ���݂����Ȕ������_�Ƃ��A�R���I���ʂ̋^�╄�Ƃ��F�X�Ɠ˂����݂ǂ��떞�ڂł��B
�܂��A�ˋ�̖������E�̘b�ł�����A�����Ă��ǂ����Č��������Ȃ̂ł��傤���E�E�E�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/15
F16
ISO200

4.
����͐�́A�E���m�͂ł��B
��͐�́A���ɌX���Ă��܂��B���3�Ŗ��炩�ł����A�������̎x���_���E���ɍ������ތ`�ɂȂ��Ă��܂��B�ł��̂ŁA��ɍ������������鈳���x�����Ɋ|�����Ă��܂��A�����Ȃ��Ă��܂��l�ł��B
����ɑ��āA���m�͂͏��1,2�Ŗ��炩�ł����A��ʒ��S����Ɏx���_���������Ă���A���肵�Ă��܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/15
F16
ISO200

5.
���܂��ƌ��������ƌ������A�����ǖʂɂ���Ȃ��̂��B
����������K�~���X�́~2�B2199�ł́u�f�X�g���A���v�������ȁB�E�͏�u�Ñ�́v�Ɖ��u���c�́v�A2199�ł͏�u�䂫�����v�Ɖ��u���肵�܁v�ɂȂ�܂��ˁB
�����A��������ɍ�������̂ł��傤�B�ǖʂ̍ŏ㕔�ɓ\��t���Ă���̂ł����A�����̑͐ϕ����s����ȈׂƁA�����ʂ蚺�������̂ƂŁA���O���Ď茳�ŋ��߂�ὂ߂��Č����̂͒f�O���܂����B
���ƌ������A�����������������X�P���Ɠ��l�ɍw���A������ʂ������W�����Ă���A�u�t�@�������v���u�q���[�x���I���v���ėp�l�^���핺������܂���ł����B
����ɂāA���N�ȏ㑱����K.O.����̈�i�W���͏I���ł��B
PENTAX K-7
TAMRON SP AF ASPHERICAL XR Di28�`75mm 1:2.8 MACRO
75mm
1/180
F2.8
ISO200
�⏕��
R03/06/24 �W�� K.O.�������13�e�`���B�������̃y���[���E�E�E�Ǝv������ˋ��
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
�͒��̑��e��1/700�́A�������B���C�R�́u�I���o�[�E�n�U�[�h�E�y���[("Oliver Hazard Perry")�v���̎p��Z�����ˋ�͂ł��B
����??�ˋ��??�ǂケ��???
����܂��A�ȉ��ɂ��������Ə����܂��̂ŁE�E�E�B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|
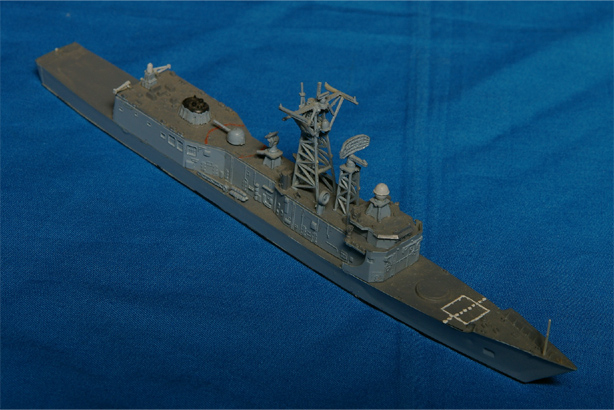
1.
�u�y���[�v���A���A���A��̓Ǝ��������܂߂�ƁA70�Nj߂��A�����Ă��܂����A���āA����͂��̒��̉��ɂȂ�̂ł��傤�B���Ŋ͔ԍ��\��Ȃ����˂��B�������ɂ�Ȃ��Ȃ����B
�悸�A���Ƒ�͓Ǝ����������Ă��鎖�ƁA���͑̌^�ł���ׁA���ěƂ܂�܂���B���́E�E�E�A�����ɂ͒Z�͑̌^�������ł���˂��B�������f�����Ǝ��������������A���f�ł��܂���B
�ƌ����A����AMk.13���ˋ@�ς�ł��Ȃ��B���Ď��́A�܂�21���I�ɓ����Ă��ݖ����Ă������B���C�R�����̒Z�͑̌^���Ď��ŗǂ������ł��B
1/30
���x����

2.
�E�E�E�Ǝv������A�ȂȂȉ��Ƃ�!!�Y���͖�����!!!
�Z�͑̌^�A2003�N4�����ɑS�͑ޖ��A�ꕔ���p����Ă����肵�܂��BMk.13�̓P���͌����ɂ�2003�N��v�N�x�ȍ~�炵���B���B���͏H���N�x�̋����??���Ď��́A�P�����n�܂�O�ɒZ�͑̌^�͋��Ȃ��Ȃ����Ǝv���ėǂ������B
�ƁA�������͊�{�I��wiki�̌�������M���Ă̘b�ł����B
�ꉞ�A�؋���ςݏグ��ׂ��A�u���́v�̒ʊ�605����673�����R�����Č����̂ł����A��͂�A�Z�͑̌^��Mk.13�P���͂͋��Ȃ������E�E�E�B
1/60
���x����
�㉺1�����x�ÂA��2�����x�g���~���O

3.
�Ƃ܂��A����Ȗ�ŁA���ƁA���̃t�l�A����Ȃ��������̗L��ˋ�͂ɂȂ��Ă��܂��܂����B����܂��AMk.13���ۂ����Ƃ����t���Ă��Ηǂ���ł�����ǂˁB
���̑f���m�F�Ƃ��āA���āA���������BF��P�y��P������^���o���D�Ƃ��ł�����������Ă���܂���B��ŁA����R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v��R02/09/29����W�����uR02�x�㔼���̂��z�{�v��F�Дł͑�ʑ������Ă��܂����A�ߋ���P�Дł�����Ă��܂��̂ŁA���������P�Дłł��鎖�͔������Ă��܂��B
1/30

4.
�{�͂́A�䂪�{�I�͑��֕ғ��������ł��B3.�ŋL�ڂ̉ߋ�1�N�Ԓ������ł����^�͂��R�����B���Ă���̂�����܂����A�����C�R�ւ̔��p�͂Ƃ��Č�����̂ɍD�s���Ȃ̂ł���ˁB
�Ƃ͌����A�O��̊C���u�ނ炳�߁v���̂ǂꂩ�Ɠ��l�ɔ�s�b�̓h�������S���Ȃ���Ă��Ȃ��Ƃ��A���Ă�Mk.13�Ƃ��A�lj���Ƃ����\�������ł��B
1/30
R03/06/09 �W�� K.O.�������12�e�`�C���u�ނ炳�߁v���̂ǂꂩ
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
����͒��ł��B
�͒��A10�ǒ��x�v�H���Ă����̂ł����A���̖w�ǂ��߂Ă���WL��IJN�͒��́A�����ڒ����Ă��Ȃ������ł��낤�C���������w�ǎc���Ă��炸�A�܂��A�O������j�����Ă��鎖�������S�ŁB�~�o�ł����̂͋͂��Ȑ��̌���͂ɗ��܂�܂����B�����̒�����悸1/700�̊C���́u�ނ炳�߁v���̂ǂꂩ�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
3�D�C�AMk.41VLS�AMk.48VLS�ARCS�ጸ�̊p���芎�@�ւ̃V�t�g�z�u���Î�����2�{�̉��ˁA��b���x���q��@�^�p�b�A�~�j�I�����_��E�E�E�ƁA��ڗđR�Łu�ނ炳�߁v���ł��鎖�͔������܂��B
�q��@��퓬�ԗ��ł���l�@�͂����ŏI���ł����A���Y����3����4�������Ȃ��̂ł�����͂����肵�Ȃ��������!!
�E�E�E�Ǝv�������̂́A�����̒ʂ�͔ԍ��\���Ă��܂���B�Ȃ�A�����i�̗L������ʒu�Ŕ��f���邵������܂���!!
1/30
F16

2.
�ŁA�u���́v���d�Ԃ��ł��낢�뒲�ׂĂ݂��̂ł����A�K���Ȃ��̂����X�o�ė��܂���B
�㕔���ˉE�����ʂƉ�]���@�i�[�ɍ�����NORQ-1�q���A���e�i�Ƃ��A�㕔���˒��O01�b������OE-82�q���A���e�i�Ƃ��A�ʐ^��ł͂���ق�Ⴂ���U�������̂ł����A�͎��ʂ̍��ƌ������A�����ɂ�鍷�̗l�ŏ�肭�s���܂���B
�d�ԂŁu�ނ炳�߁v�A�u���ʓ_�v�Ƃ��˂����Ă��u�Ȃ݁v�Ƃ̑���_�����o�ė��Ȃ���ł���˂��B
���nj͎��ʂ͂�������ƒ��߂܂����B
1/30
F16

3.
�����āA��������?
����͎����ĊȒP�ŁA��P���炵����������Ă��܂���B��ŁA���ЂƂ��u�Ȃ݁v�Ƌ��ʊ͑̂ɂȂ��Ă���܂��B�͑̐��@���ꏏ�ŏ�\���������Ă��邩��ł��ˁB
����R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v�̒��ŁA���͗��Ђ́u�Ȃ݁v��ғ��u�c�Ɋ܂߂Ă����肵�܂��B�Ȃ̂ŁA��������Q�Ƃ��܂����B
�ŁACIWS��Mk.41VLS�̑���A�퓬�ʘH�̓ʒ����A���̓_���炠������Ɛ��ŗL�鎖�͔������܂����B
1/30
F16
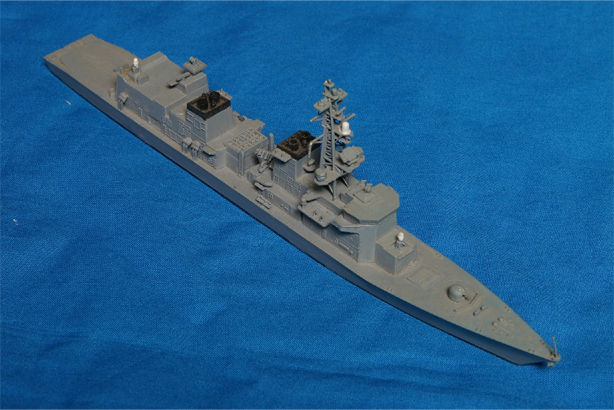
4.
�Ƃ���ŁA���2,3�ł����炩�ł����A����̉����ʼn��i�̉E�������܂�Ă��܂����A�ǂ����������Z���l�Ɏv���܂��B�܂��A��C���C�g�����ɒZ���A������܂ꂽ���ۂ��ł��ˁB
�ŁA�ّ�{�I�̊e���C�R�ɕғ����悤���ǂ����悤���Y�ݒ��ł��B
�����炱����ʑ����Ă���̂���_�ł����A����͒����Ȃ����Ȃ��B�J����͐퓬�ʘH���s�b�̕W�����A�b��̓h�������S���\������Ă��炸�A���ɐ퓬�ʘH�͊������Ă��܂��Ɠh����������ŏ�Q�ɂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�S�̂����œh�����Ă���̂��s���Ȃ̂ŁA�b���lj��œh�蕪�����ꍇ�A��������ƏC��������Ȃ�܂��B���āA�ǂ��������̂��E�E�E�B
1/30
F16
R03/05/23 �W�� K.O.�������11�e�`����F/A-18A�u�z�[�l�b�g("Hornet")�v
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
�����F/A-18�n��2�@�ڂł��B���p�R�p�@�A��l�e�ɂ��čŏI�@�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�����\���Ă��܂���B�����Ƃ��O�����Ƃ��̓����I�ȏ����S�R�L��܂���B
�E�E�E���āAF/A-18�ɂ͑O�����A�̗p����Ă��܂���ˁA�͂��B
1/30
F16

2.
�ƌ������ŁA�O��̋@�̂ƕ��ׂĂ݂܂����B���@�͓����ł��ˁB�Ȃ̂ŁA������"Super Hornet"�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B
���i�������قړ����ł��B
�����A���c�Ȓ���̊���̓ˋN���̌`���L���̈Ⴂ�������܂��B
1/125
F9.5

3.
�@���̓h�����������ɔ���܂��B�܂��A2�ł�����̂ł����E�E�E�B
���̑��F�����猩�Ă��A�O�l�ɕ��ʂɊC�R���͍ڋ@�Ȃ̂ł��傤�B
1/15
F16

4.
���������̒����������ɑO��ƈقȂ��Ă��܂��˂��B2�i�L��c��݂̓��A���̕��͕��ׂ������A�O�����͑O��ɕʂ�Ă��܂��B
�ȏ�̓_����A�d�Ԃ����X�Ɠ˂������̂ł����A���ǁA�\��̒ʂ�ו���A�ŁA�������ۂ��B
�ł���AD10��R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v��14��1�������ʂ荞��ł����肵����SS12���ď��i�Ȃ̂ł��傤�B
1/30
F16

5.
����Ȃ���ȂŊT�ˑf�����������܂����B
���ɂ�F/A-18�n���F-15���U�����ꂽ�̂ł����A�r��݉ˑ������U�킵�Ă���Ƃ���Ԃ������A�o��ł��܂���ł����B���݂ɂ����̑������h�������B���[��A�����@�̂���肷������������Ȃ������̂��E�E�E�B
�Ƃ�����A����ɂ�1/72�̌��p�R�p�@�͏I���ł��B����͊͑D�ł��B
1/15
F16
R03/05/08 �W�� K.O.�������\�e�`F/A-18C�u�z�[�l�b�g("Hornet")�v
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
���p�R�p�@�̑�O�e�ł��BF/A-18�n�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
��̔@���̐��ł��B
�܂�1/72�ł��ˁB
���āA�������ƍו��ނ�@���ɂ�!!
1/2

2.
F/A-18�A�����A���@�����܂�D�݂ł͂Ȃ��A���̋��͍ڋ@�������̋����@�A�d�q��@�A�x���@���̑��͂���F/A-18�Ŗ��ߐs������Ă���̂��R�Ƃ��Ă���܂����B
����ȓz����������ƍו��ނ��̐��������̔����Ȃ��B
1/8

3.
�E�E�E�Ǝv���Ă����̂ł����A���������̓����I�Ȉӏ��₻����������"400"����"NAVY"���̂̕\���̂��A�ŁA�\��̒ʂ�A���@�̑f���͂������蔻�����܂����B
���B���C�R��F/A-18C�u�z�[�l�b�g�v�ŁA���{��z���̋��u�~�b�h�E�F�[("Midway")�v���ɓ��ڂ���Ă������̗̂l�ł��B
1/15

4.
���āA�������͔@����??
�����Ƃ������Č������AC�Ɩ��m������Ă���̂̓t�W�~�A�n�Z�K���A�A�J�f�~�[�Ŕ�������Ă��܂��B
�ŁA�O�X��AR03/03/31����W���́uR02�x�������̐ς݁v��11.���̍w���X������@�̑������猩�ăn�Z�K����D8�̗l�Ɏv���܂��B
1/8

5.
�Ƃ���ŁA���������̓h���A�O�����͋@�̂̑��̕����Ɠ��l�̓h�F�ŗǂ��l�ł����A�ǂ����������͍��ɋ߂��h�F���������͗l�ł��B
1/8
R03/04/25 �W�� K.O.��������e�`F-16�u�t�@�C�e�B���O�t�@���R��("Fighting Falcon")�v
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
���p�R�p�@�̑��i�ł��BF-16�u�t�@�C�e�B���O�t�@���R���v�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
��̔@���̐��ł��B
�܂�1/72�ł��ˁB
�����̒��Ԃ̌��ݑ��u�A�����Ԃ牺�����Ă��Ȃ��B�E����ASM�Ǝv�����^�U���e���Ԃ牺���Ă��鏊�ł��ˁB�������Ԃ牺�����Ă������Ղ��L��A����ች�����ŗ��Ƃ�����??
1/1

2.
����́A��������Ƃ��ꂱ��\�荞��ł��āA������������������Ă��܂��B
���������̏�獇�B����R�̎O��z���̑�35�퓬�q��c�ł���|�A���������璼���o�ė��܂����B
�ו��ނɂ��ẮA�P���̎O��z�����Ď���CJ(�u���b�N50)���Ď��ɂȂ�l�ł��B
1/15

3.
����Ȓn���F�L���Ȑ��i�W�J�Ȃ�AAirfix����Revell���̒����̂ł͂Ȃ������Y�ł��傤�ˁB
���̔F���̉��ŁA���A�x�A�c��3�Ђ�HP��˂��������A�x��F-16��C/D�Ƃ���1��ނ̂ݔ����ŁA�������ǂ���璷���i�ꒆ�炵���B
���Ď��ŁA�����@�I�ɓc�ƒ��ɍi���܂����B
1/8

4.
�@�킩��嗃�t�����Ɋ|���āA�@�̏㉺�̕��i�������������Ă��āA��������Ă���ƒ��̕���??�Ƃ��v���ė��܂��B
�c�́A�Â����C�^�����ƐV�������ЊJ�����L��̂ł����A�ǂ�����@��d�T�~���͒P�ƕ��i�ɂȂ��Ă���炵���̂ł��āB
���݂ɁAR03/03/31����W���̑O�X���uR02�x�������̐ς݁v��12.��14.�ɓc�ƒ���CJ�̎p�������܂��B���ɂ�C����A���̓s��6���B�Ȃ̂ŁA�܂�����ȕӂ肩�������̂ł��傤�B
1/15

5.
�l�I�ɂ́A���s�R�p�@�̒��ł͔�r�I�D�݂ȕ��ł��āA�ғ����悤���ǂ����悤���A�Y�ݒ��������肵�܂��B
���́A���̎p�����Ǝv��������C�ɂȂ鍶���݉˂̋�聂��Ȃ��E�E�E�B
1/4
����1�����x�g���~���O
R03/04/12 �W�� K.O.������攪�e�`F-4�u�t�@���g��("Phantom")II�v
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
����͌��p�R�p�@�ł��B�悸�́u�t�@���g��II�v�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
��̔@���̐��ł��B�������K�ĂĂ݂܂����B
�Ƃ͌������̂́A�O�X�̐퓬�ԗ���1/72������������������A�������k�ڂ͗ǂ��������Ď��ō̐����܂������A����͂������1/72���Ɣ������Ă���܂��B
1/15

2.
�h�����������ŁA�����\���Ă܂���B���A�ŁA���Ђ�珊���R�킪�S�R����܂���B
�����Ȃ̂���??�݂����Ȃ�Ȃ��`�B
1/1

3.
�Ƃ͌����A�h���A���̔Z���ڂ̊D�F�ƌ������l�F�ƌ������A���ꂪ�吨���߂Ă���̂ł��傤�B
�ŁA�@��d�T�������E�E�E����͂܂܁A����E�E�E�̑g�ݍ��킹�œd�Ԃ����ꂱ��˂������̂ł����A������Ȃ���ł���ˁB
F-4�͉^�p���A�R�킪�����̂ŒT����Ă����ł͗L��܂��B
1/2

4.
�����A�����������@�����`��AFG.1�ł͖����낤�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����Ƃ��A���삾�̐�s�Ȃ炾�̂͑����̋@�̂̐��������ƈ��Ȃ��̂ŁA�������M�������ł����B
1/1

5.
�Ȃ�Α����i�Ŕ��肵�Ă݂悤��??
�ƌ������̂́A���̉���AIM-7�A�嗃�݉˂�AIM-9�Ƒ����ƁA����܂����������B
����Ȗ�ŁA����̓G���N�ς���Ȃ����ʂƂȂ�܂����B
1/2
R03/03/31 �W�� R02�x�������̐ς�
R03/04/25 ���ߏC��
�O��A�u����͍��B���̌���@���B�v�ƋL�q���܂������A�N�x�̒[�����ł��鎖�����O���Ă���܂����B
�ƌ������ŁA�\��̒ʂ�A�������̐V�K�ς݂ł��B�Ȃ�ƈꋓ32���̒��B�ł��B120������̂�H28�����ȗ��ł��B
�����b���A�v�H�ƒ��B�̋ύt??���t??�ɕ��S���Ă����̂ɂǂ����Ă����Ȃ���??
��������1�������Ă��܂���B����˂��A������i������������K.O.���̈�i�ł��B�Ȃ̂ōw���ł͂Ȃ��ғ��ł����ˁB����ł����I�����̂ł����G���C���ɂȂ��Ă��܂��܂����B
|

1.
�S���ł���Ȋ����ł��B�S��1/700�͑D�ł��ˁB�����ȏオP�Ђł��ˁB�p���ēƒ��̐V���F�X�ł��B
�A���u�����v�e���A�u�����v�e���AType42 BatchIII���͍����ғ��ɂ��A�����͊��ɕғ��ȑO������͑��ݐ��߂��Ă���܂��āA�����I�ɂ͗]��ƌ������Ŏ���������m��܂���B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4
f16

2.
���āAK.O.����A����������͌^���ł����B
����͌��֓����Ē����̌C���̏�ɓV��ɐڂ��閘�ςݏオ���Ă������̂ł��B
�����́A������ƍK���A�Ђ��[����45���b�g���̐o�H�܍s���Ƃ��Ă���܂����B
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/250
f11
ISO200
�⏕������
���x����

3.
������͊K�i�̕Ǎۂɐςݏオ���Ă������̂ł��B
�o�H�ܐ������ނƁA��i�����̏�����\400/�܂̊����Ōo��|�����Ă��܂��܂��āA�ƎҌ��ςŁA�Ƃ��镔���ł�200�܂��������̂��A���ђl�͑啝���߂���340�܂ɒB�����肵�Ă��܂��A�����\52k�]�v�Ɋ|�����ŁA���ɂ����̔��͑܂̒��Ő������ł���˂��B
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/250
f11
ISO200
�⏕������
���x����

4.
���ڎ��̋��ɐςݏオ���Ă������ł��B
����Ȗ�ŁA��������1F�̃u�c�͂قڐo�H�����Ő��|�H��̉��Ə������̂ł����A�����ʖڂ��A�������p&�����őܐ����炵�Čo��k���ɂ�E�E�E�ƍl������ł��B
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/125
f11
ISO200
�⏕������
���x����
���\�}�̒���1/3�Ƀg���~���O���ďc�\�}��

5.
�ƌ�����ŁA���������2F�ɗL���āA���E�������u�c�B�ł��B����͊K�i�オ�����x���(?)�ɐς�ł��������̂ł��B
�����͌��������̂́A�Ⴆ��2�́u�A���h�����_�v�̉����̎�O�ɗL��1/48��III�˂͂��Ȃ蔠�ɂ݂��݂�ꂻ���ŁA���̎�̔��͎c�O�Ȃ��炳��`�Ȃ�`�ƂȂ�܂����B
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/250
f11
ISO200
�⏕������
���x����

6.
�������2F�̒\�y�̏�ł����A��͂�A�p��̐��u���i�v�A���J��u�����v�͂������������ɂ�ł��܂����A���̉���Airfix"IronDuke"�Ɏ����Ă͍���(?)���Ă��܂��Ă��銴���ł��B
�܂��A�����̎ʐ^�ł͖����Ɍ����Ă��A��ʂ��ʂɑ��̔��̊p�̊ѓ����Ă����肷��̂�����܂��B
�X�ɁA��O�̍q��@�̕����i�Ƃ����m�̔��́A���������鎖�Ȃ���A�����̂��������A���p���i�������߂ł��B��p�Ό��ʂ����Ă���Ɛ摗��ƂȂ�A����ł����o�H�܍s���̌��Z��E�E�E�B
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/250
f16
ISO200
�⏕������
���͎�g���~���O

7.
����Ȓ�����A�^�ǂ����������͌y�ǂŒ��o�����u�c�B�ł��B
�����́u���I�i���hET�v�A�u���I�i���hLG�v�A�uHobbyOff�v�A�uD-Force�v���ɔ��p���܂����B���p���S�Ă��B�e���Ă����ł͗L��܂���̂ŔO�ׁ̈B
Apple A1723
1/356
f2.2

8.
���l�ɔ��p���B�ł��B
�퓬�ԗ��A���̎�̑�k�ڂ͑�O�鍑����̓ƈ��F�ł��B
Apple A1723
1/197
f2.2
���͎�g���~���O

9.
���p���͍X�ɑ����܂��B
�ǂ�����ƁA�����͂��d�����Ă��܂��˂��B�s�v�c�ł��˂��B
�u����v�A�u�\��v�A�u��v���͐������Ⴂ������ׂĂ݂悤�`���Ď�|������̂���??�ƍD�ӓI�Ȍ������ł��܂����A�u��J�v�͓������̂�2�L��B
���ꂪ�A��ה����i�Ŏ��̓��ׂ����҂ł��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ȃ痝���ł��܂���Water Line�̓c�{�̕W���i�ł�����˂��B
Apple A1723
1/155
f2.2
���͎�g���~���O

10.
�����������p���������܂��B
�����ł��u���߁v������Ă��܂����A"North Carolina"�͉���12.�ł��o�ė��܂��B
Apple A1723
1/157
f2.2
ISO25
���͎�g���~���O
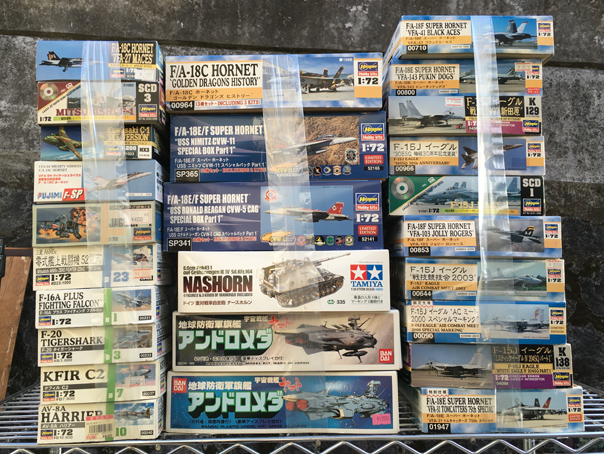
11.
5.�Ō����Ă����u�A���h�����_�v2���͖����~�o����Ă��܂��ˁ�
�������A�ԗ��A�͑D�A�q��@�ɕ��ނ���Ă���܂������A����͒P�ɕR�Ō��킭�s���㔠�̌`��̓��ꐫ���d����������ł��āA�Ȃ̂Łu�A���h�����_�v�Ɓu�i�[�X�z�����v��F/A-18���Z�܂鎖���L��ƌ������ŁB
Apple A1723
1/124
f2.2
���͎�g���~���O

12.
�E���ԉ��́u�F��v��10.�ŏo�ė��܂����ˁB���A9.�ɂ����܂����A�ǂ���琢��Ⴂ�̗l�ł��B
����ɂ��Ă��A����A����ȃu�c�������Ă����̂��E�E�E�B
Apple A1723
1/30
f2.2

13.
�u���߁v�����ǗL���??
�Ƃ���ŁA�R�p�@�����X���Ă��āA�قڐ��̍��B���퓬�@�ŁA���̒��ł�F/A-18�n�₯�ɑ����A����F-15���Ċ����ł��傤���B
Apple A1723
1/30
f2.2

14.
�����Ɂu�X��ہv���a�@�A�������łł��܂����A�͒��Ő퓬�͒��łȂ������̂͂���炾���ł��B���p���畺⋂��͏o�ė��ċ��܂���BK.O.���̓}�b�R�C�ꂳ��̂��A�ŕ⋋�̏d�v����m�����Ƃ�����Ă���܂������A���͂���Ȃɏd�����Ă��Ȃ�����??
�Ƃ܂��A�������Ȃ���������146�B�����B�e����ȑO�ɂ��m�F�ł��邾����50�_�O�㔄�p���Ă���܂��B���l���y��\100k�z���܂����B�����āA����ȏ�́A���肷��Ɣ{��������Ȃ������p����or�\����Ċ����ł��傤���B�����Ȃ��1F�͐ϕ��̖ⓚ���p�̔p���͐ɂ����������Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��ł����A��̍Ղ�ł��ˁB
Apple A1723
1/30
f2.2

15.
�����43�_�͖����p�ł��B�ƍ������������������ǂ��̉��ڎ��ɂۂ�Ƃ܂Ƃ܂��Ă��܂��B
�u�c�̒��o�A�I�ʁA���ɎR�͉z���Ďc�G�|����Ԃɓ����Ă��܂��B���������lj����Ă���Ō�̔��p��4�����Έȍ~�ɍl���Ă��܂��B�ʎZ��300�_���x�ɒB���邩���m��܂���B
�Ȃ̂ŁA�ғ���������邩���m��܂��A�܁A����͎������̘b�ł����ˁB
Apple A1723
1/15
f2.2
���͎�g���~���O
R03/03/13 �W�� K.O.������掵�e�`�ƈ펩���C�u���F�X�y("Wespe")�v
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
����͐퓬�ԗ��̍Ō�ł��B�{��������͓̂ƈ�̎����C�u���F�X�y�v�ł��B�O�l�A���̎�̎����C�͔����Ȃ�ʔ����Ȃ̂�wiki�ɂē��肵�܂����B
����͍��B���̌���@���B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�ŎB�e���܂����B
|
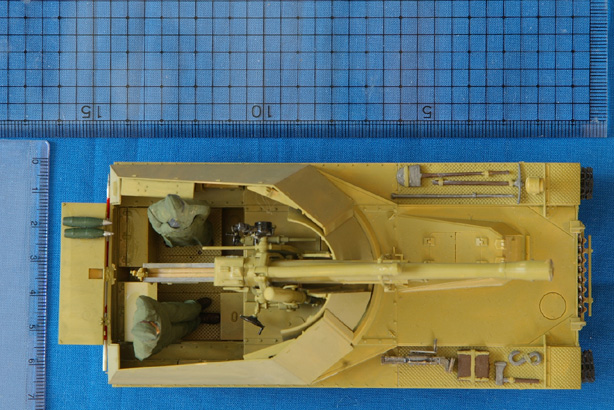
1.
��̔@���̐��ł��B�������K�ĂĂ݂܂����B
�T�ˎԑ̒�0.14m(�㕔�̖C�e���ڂ��Ă��镔���͐����ɓ|�������Ȃ̂Ŋ܂߂�)�~�S��0.065m�ł����ˁBwiki�ɂ���35/35��4.79m�~2.24m�ƌ������ŁA��͂�1/35�̗l�ł��B
2/1
ISO200
��A��1�����x�g���~���O

2.
�O��A�O�X��Ɗ��늳�̈�҂̒����ɂ��ď���Ș_�]�������ė��܂������A����͂��̗����҂����ɋL�ڂ��Ă���ߓ�����t�₻�̎咣�ɂ��Ăł��B
�Ǘ��l�͋ߓ���t�̐M��҂Ƃ��ł͗L��܂��A����2������A����StageIV�ł̉��w�Ö@�ɂ��āA�����Ɩւ��[����Ă��܂��܂����B���������ł����A�ȉ��ɗ����̒��Œ��j�Ə���ɔ��f�����L�q���e���A�ڂ��܂��B
1/1
ISO200

3.
�u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v����ł��B
�w�v�_�͑傫��2�_�A�����f�͌����Ă�����L���ł͂Ȃ��E�R���܂͈ꕔ�̊��ɂ��������Ȃ��E��p�̓K�p�͂����Ɛ��������ׂ����A�������E���Â̌��E��\�I�������ƁA���ɂ́u�������Ă�����Ȃ����v�Ɓu�������Ă����邵�A�������Ȃ��Ă��債�����������Ȃ����v���L�鎖�A�ł���B
�`�����`
����30�N�A���Ɋւ��ėl�X�ȉȊw��̐i���͗L���������f�����Â����ʂ��C�}�C�`�ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B���ɂ͐��ʂ͖�����Q�͗L���Ȃ̂ɁA�ƊE�̊������v��u�������Ȃ���ɂ��s���Ȃ�����v�ƌ��������@�E���R�łȂ���Ă��錟���E���Â�������B�f�f�Z�p�͔���I�ɐi���A��p�ƍR���܂Ɋւ��Č����I�Ȋv�V�͖����B��p�Ɍ����邪�A����ɒ����Ȃ��A�ƌ����͎̂E���ł���B���A���̓_�ł͕��ː���w�������l�Ȃ��̂Ȃ̂��B�ߓ��������̓_�Őg�ۛ����T���Ă�����A�_�q�̌������͍X�ɗ������镨�ł������낤�B
����B�m���Ɋ��ɂ́u�ǂ����悤���Ȃ����v�Ɓu���[���v������̂����A���̒��ԂɁu���i�K�̋Z�p�ł��ǂ��ɂ��ł������Ȋ��A�܂�^���ǂ���Ί������A�����Ă�����������������v�����\���邱�ƁA�������u���i�K�̋Z�p�v�͕��ː��Ȃ̂���Ɍ���Ȃ������w�E���Ă��������ǂ������B�x
1/2
ISO200

4.
�u��҂��������҂ɂȂ��Ă킩�������Ɓv����ł��B
�w�ނ̎咣�ɂ��ẮA�����߂��ł͂Ȃ����Ǝv��������^��Ɋ����镔�����L��܂����A��ʂł͌���̂��Âɑ���x���Ƃ��ČX�����ׂ����̂�����Ƃ��v���܂��B
�w��ł͋ߓ��搶�̗��_�͂��������Ɣ��_���o�Ă���l�ł����A�Ⴆ�Έ����̔]��ᇂŌ����A�ǂ�ȂɊ��҂��撣���Ă��A��t���ǂ�Ȃɗ͂�s�����Ď��Â����Ă��A���ʂ������Ȃ��ƌ�����ʂ��K���o�ė��܂��B���̒i�K�ł��A�������҂���ɓ����ƌ����͖̂����Șb�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�`�����`
�����ĉ��w�Ö@���̂��̂������ƌ����ς�͂���܂���B�R���܂̊J�����i�݁A�m���Ɍ��ʂ̏グ����^�C�v�̊������邵�A�܂��A�R���܂��ǂ��g�����Ď��Â���Έ�ԗǂ����ʂ������邩�Ƃ����������ǂ�ǂ�i��ł��܂��B���̌����w�͂���J���\����M���ĉ��w�Ö@��I������ꍇ���L��ł��傤�B
�������A������ƌ����āA����ł͎����������������m���ŁA���������҂���ɋ�ɂ�����^���Ă��܂����Â𑱂��鎖��ǂ��Ƃ��鎖�͂ł��܂���B�x
1/2
ISO200

5.
�܂��A�ǂ����20�N�ȏ�O�ɏ�����Ă��܂����A����2���Ř_�]����Ă���ߓ����_�̒��ő����ł��L���ȁu���҂�K���Ɠ����ȁv�Ɏ����ẮA1�̈ʂ��l�̌ܓ������30�N�O�̒���ɂȂ�܂��B�Ȃ̂ŁA�ŐV�̈�Î���f�����Ă��Ȃ��_�͗��ӂ��K�v�ł��B
���ʁAK.O.���A��ނ̑������R���܂╪�q�W�I��𗘗p�����ɂ��ւ�炸�A�����̏����ɋL�ڂ̓��e�Ƒ卷�����o�߂ƂȂ��Ă��܂��A2,30�N�̐i���͑債���������Ƃ������܂��B
���݂ɁA�����̕����͒��҂Ɗ��̊W�Ƃ��L�ڂ������������ׂ����_�]�����肵�Ă���܂��B���͂���̂�����ꂽ�̂ŁA����Ȃ��痪���܂����B
���āA�b�ς���āA�\��̒ʂ�A�퓬�ԗ��͂���őł��~�߂ł��B�퓬�ԗ���1/72�ӂ�̏��k�ڂ�����ق�U�����ꂽ�̂ł����A�h�������Ȃ�G��������j�����Ă�����ƍ�����L��Ȉ�����܂��B
1/2
ISO200
R03/02/28 �W�� K.O.�������Z�e�`�ƈ펩���C�u�}���_�[III�v
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
��Z�e�́A���������ƈ�̐퓬�ԗ��ł��B����͑ΐ�Ԏ����C�u�}���_�[III�v�ł��B
�����ȏ��A���̎�̐퓬���J���^�̎ԗ��ɂ��Ă͒m���������ĎU�Xwiki��˂����ē��肵�܂������A�Ԉ���Ă��邩���m��܂���B�������炸�B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�ŎB�e���܂����B
|
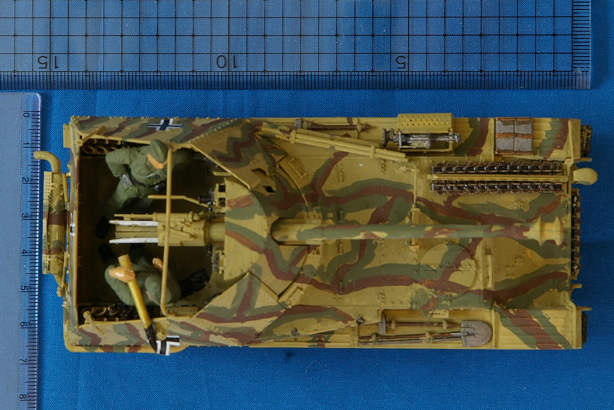
1.
���@�����Ď��ŁA����͒�K�ĂĂ݂܂����B
�T�ˎԑ̒�0.155m�~�S��0.065m�ł����ˁBwiki�ɂ���35/35��4.65m�~2.35m�ƌ������ŁA�S����������ł����A�܂�1/35���ۂ��ł��ˁB
�ו��ނ́A�퓬���͍̕\������M�^�Ǝv���܂��B
1/1
ISO200
������7,8���Ƀg���~���O

2.
�O��͐��_�Ȉ㗊�����̈�҂̕s�{�������ꂱ�ꏑ���܂������A�����āA�X�ɕs�{�����U��ɖ����̊|�������A�]�_�o�O�Ȉ��c���M���̒���u��҂��������҂ɂȂ��Ă킩�������Ɓv�����Љ�܂��B
��c���M���́AH09/01/29�ɂ܂����̔]��ᇂǁAH10/12��51�Ŏ������܂����B��������������ڂɒW�X�Ǝ��Ԃ��i�����ł��B
1/1
ISO200

3.
�]�_�o�O�Ȉオ�]��ᇂɜ늳�B�܂��A�l���Ă݂�A�����Ȉオ�����Ȍn�̜늳�Ƃ��A�j����t���w�l�Ȍn�̜늳�Ƃ��������A�Տ��オ�����̐�Ȃ̐��b�ɂȂ鎖�͕��ʂɗL�蓾���ŁA���̗������ƌ�����ł͖����ł��傤�B
���M���ׂ��́A��͂�A�����Ǐ�f�f���������ƁA���̌�̌o�߂��{�l�ɂ����炩�ɑz���ł��鎖�ł��傤�B
���҂�����ȓ��ɂŁu����̓N�������o���ł͂Ȃ����A������ƕ����Ă����Ȃ��ɂ݂����m��Ȃ��B�����N�����ȁv�Ɨ�ÂɎ��ȕ��͂��Ă��܂��B
1/2
ISO200

4.
�Ȃ̂ɔ����ȏ���u���āA�Q���V�K����MRI�̎��������ʼnf�����m�F���A���̒i�K�ň�����ᇁA�ň��̎��Ԃ̉\���������ƔF�����܂����B
�Ȃ̂ɂȂ̂ɁA2/22�ɗF�l��t���狭�����t�Őf�f�m�肳���ė×{�����ւƌ�����̂ɁA���f�����B
���ǁA3/31�Ɏ��Õ��j���m�肵�A4/15�Ɏ�p�ƂȂ�܂��B���Ljȗ�2����畏����Ă�����ŁA�u��҂̕s�{���v�����ڂł��B
���҂̈ӎ��Ƃ��Ắu�����A�Ƃ�ł��Ȃ����ʂ��o����ǂ�����B�`�����`���������狳���ւ̓�������Ă����ɂ��A���N���Q���ĂȂ����Ȃ��B�Ȃɂ����A�f�Ȃ���Ȃ�Ȃ����҂�����v�Ȃ̂ł��傤�B
1/2
ISO200

5.
�Ƃ͌������̂́A�����i�K�ŁA�ő��~���͊��҂ł��Ȃ������ł��傤�B�����̎��ÊJ�n�̒x���͊W���������Ƃ��v���܂��B
�E�o��p�ł̐����ł�GradeIII�A���̌�̐���������GradeIV�ƂȂ�A5�N������10%���x�������ׂł��B
����������������ł�����A�ʂ����Ĕ@���Ȃ�S���ɗ������������̂ł��傤�E�E�E�B
1/2
ISO200
R03/02/15 �W�� K.O.�������ܒe�`�ƈ�X�����
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
��ܒe�́A���������ƈ�̐퓬�ԗ��ł��B����́u�p���T�[�v�Ƃ��u�p���e���v�Ƃ��u�p���^�[�v�Ƃ��Ă��X����Ԃł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�ŎB�e���܂����B
|
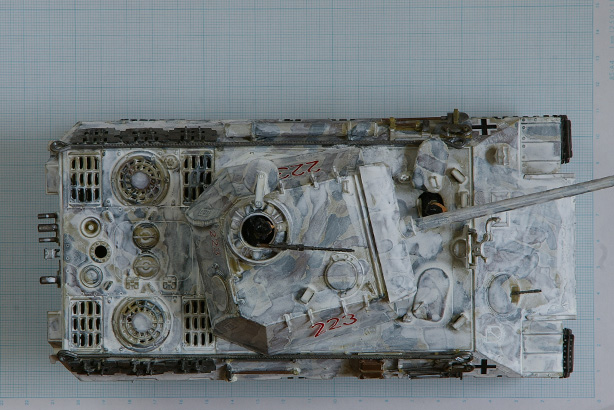
1.
���@�����Ď��ŁA�O�l�ɕ��ᎆ�ɍڂ��ĎB��܂����B
�����̒ʂ�A�T�ˎԑ̒�0.2m�~�S��0.1m���ď��ł��ˁB�ŁAwiki�Ɉ˂�A35/35�̐��@��6.87m�~3.27m�Ƃ̎��ł��̂ŁA����܂�1/35�ƌ������ɂȂ�܂��B
�ו��ނ́A�C���V�W�⑀�c�җp�̊J�����W�̊J���`������A�^�Ǝv���܂��B
2/1
ISO200
���͎�g���~���O

2.
�O��A�����a�����u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v�Ɍ��y���܂������A������������B
���҂�51��H11�ӉāA�咰�̋����z���ł��鏉���Ǐ�����o���܂����B
�X�ɁA��H12/6/13�Ɏ�p�AS���������������㕔�̑咰����؏����AStageIII���m�肵�Ă��܂��B
���̌�AH13/4�ɋ��N53�Ŏ������Ă��܂��B
1/2
ISO400

3.
K.O.����늳�̘b�������A�N��̋߂���a�ϕ��̋��ʐ�����^����ɗ��������v���N�����܂����B
�����Ƃ��A�f�f�m�莞�A��������StageIII�AK.O.�����StageIV��������ŁA���̓_���قȂ�ƌ����ΈقȂ�܂��B���A���Җ{�l�́A�؏����������̏�������I��StageIV�ł��낤�ƔF�����Ă���A�����͑卷�Ȃ������̂ł��傤�B
1/1
ISO200

4.
K.O.�����H31/1�Ɏ��o�Ǐ���AH31/4�Ɏ�f�����@����p�Ɛi�݂܂��B2,3�J�����u���Ă�����ŁA����������i�K�őΏ����Ă�����??�Ǝv��Ȃ����L��܂���B�ǂ������퐫�o�C�A�X���x���ꂽ�̂����Ȃ̂��B��ʘ_�Ƃ��Ă����f���̌��f���̂ɑ���������ł��ˁB�܂����ʂ͕ς��Ȃ����������m��܂��B
1/1
ISO200

5.
���ė�������H11/�ĂɎ��o�Ǐ���A�����ŞH���A�w���̎��_�ŏ����ǂ́u�ʉߏ�Q�v�Ƃ������N�ł��Ȃ��\���������狎��Ȃ��Ȃ����x�Ƃ��A�w�����炭���s���������s����������ɏo�����̕a�ς�����̂ł͂Ȃ��낤���B����ȂƂ���̕a�ςɃ��N�Ȃ��̂͂Ȃ��x�Ƃ��L�ڂ��Ă��āA�قڐ������Ă��܂��B�܂���҂ł�����ˁA���R��������܂���B
�ł���̂ɁA���N�ȏ���u�B��҂ł����Ă����f���f���ʂɂ͑��������Ȃ��̂����`�Ƌ���Ă��܂��܂��B�u��҂̕s�{���v�Ƃ͂����������ƌ������ł����B
1/1
ISO200
R03/02/02 �W�� K.O.�������l�e�`�ƈ�V���ˌ��CF�^?G�^??���ʑ������b�L��
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
��l�e�́A���������ƈ�̇V���ˌ��C�A���̑��ʂ̑������b(Schuerzen)�L��łł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|
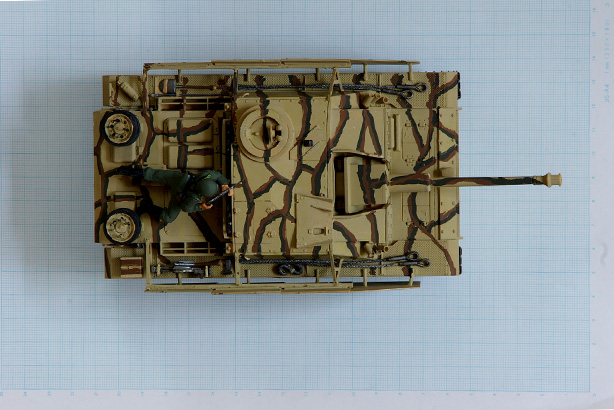
1.
���@�����Ď��ŁA���ᎆ�ɍڂ��ĎB�鎖�ɂ��܂����B
�����̒ʂ�A�O�l�A�T��150mm�~85mm(���ʑ������b������)�ł��鎖������܂��B
�Ȃ̂ŁA���l��1/35�ł��ˁB���Č������A2���ׂ�Έ�ڗđR�ł����B
4/1
���͎�g���~���O

2.
�咰���E�E�E�ƌ������S�����甭������Ō`���AStageIV�ł��ƑΉ���͉��w�Ö@�����I�������L��܂���B
�Ǘ��l�͂�����20�N�O�ɁA�����a�����u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v���璘���ȋߓ������u���҂�A����Ɠ����ȁv�ւƓǂݓn��A�R���܂̓��N�ł������ƔF�����Ă����̂ł����A20�N�o�Ɛ����ς����̂��Ȃ��`�ƉY�����Y�ł��B
1/2

3.
20�N�O�A�咰�ɓK������R���܂͑f�̃t���I���E���V���̈���������̂ł���ˁB���ꂪ���ɗL�����̂ŁA�ŏ���K.O.����u���ݖ��TS-1�ƐÒ��̃G���u���b�g�v�Ƃ̎|�������ɂ͉���?�����??�Ǝv���܂����B
�����Ƃ��ANHK�̑f�l�����Ȋw�ԑg�̉e���ŁA�����镪�q�W�I��Q�t�B�`�j�u�̓o��ɂ��A�x����StageIV�͊��S���������҂ł��鎖��������ĔF��(����F��)���Ă����̂ŁA�ӊO�ɉ��Ƃ��Ȃ��Ȃ���??�Ƃ��v���Ă���܂����B
�ŁA�����튯���ɂ��Ă��A20�N�̊ԂɁA�t���I���E���V����S-1�ɑ���A�I�L�T���v���`���A�C���m�e�J���A�x�o�V�Y�}�u�A���S���t�F�j�u���������A�F�X�Ƒg�ݍ��킹����P�܂ɂ����肵���������l�ɂȂ����ƁA�ւ��[����܂����B
1/2
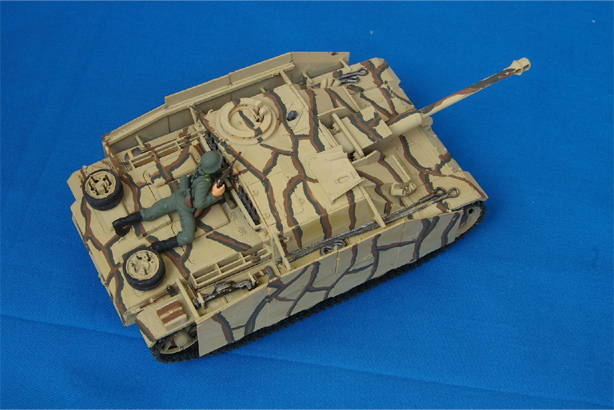
4.
�Ƃ͌������̂́A����ϐ����ł���A��܂Ɉ˂��Ă͂����������p�����̕���p�����Ղ蓙�A�����튯���̉��w�Ö@�́A���Njߓ����_�̐̂���{���I�ς���Ă��Ȃ���������܂��āA�c�O�Ȍ���ł��B
��̔x���ƃQ�t�B�`�j�u�ɂ��Ă��A����F�X�d�ԏ�ł��ꂱ��˂����܂���܂����B����ƁA�Q�t�B�`�j�u�ȍ~�̎����玟�ւƓo�ꂷ�镪�q�W�I�������ϐ�������������ۂ��A��肭�s���Ȃ����̂��Ɯ�R�Ƃ��Ă���܂��B
1/2

5.
�Ƃ���ŁA��L2.�ŋ����������a�����u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v�A�ǂ��{�ł��B�@�����Έ�ǂ����E�߂��܂��B
�Â��{�ł�����A��ÖʂŎ���x��̕����͑��X����ł��傤���A������StageIV��鍐���ꂽ���A�]���𑗂��̎w�j�ɂȂ邩���m��܂���B
�����A���ɔŌ���ł��ۂ��A�V�i�ł̒��B�͓�����ł��B���܂ɐ}���قɎc���Ă���l�Ȃ̂ŋ������L��Βn�������̗��}���ق̌����@�\��˂����Ă݂ĉ������B
1/2
R03/01/17 �W�� K.O.�������O�e�`�ƈ�V���ˌ��CF�^?G�^??���ʑ������b����
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�O�X��A�⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
��O�e�͓͂ƈ�̇V���ˌ��C�A���̑��ʂ̑������b(Schuerzen)�����łł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�A2/1�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�V�ʂł��鎖�͖��炩�ł��ˁB���āA�k�ڂ�??
�����A�T�ˎԑ̒�150mm�~�S��85mm�ł��B������?��wiki��˂��������A�ǂ�����C���݂̑S�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�������̇V����Ԃ̂��̂������Ƃ���A�ԑ̒�5.56m�~�S��2.95���ƁB
�Ȃ̂ŁA
1:X=0.15:5.65
X��37.67
�����́A
1:X=0.085:2.95
X��34.7
�ƂȂ�A�O��A�O�X��ɑ�����͂�1/35�ł��ˁB
���C�g�ł�����F�^��G�^���Ď��ł��ˁB

2.
���āAK.O.����A�O��ł͕����Ƃ̈��ʊW�����ꂱ�ꏑ���܂������A���͕��N��S�������������ŖS���Ȃ��Ă��܂��B
�����A�Ƒ�������Ȃ��̂�??���Č�����Ɣ��_�ł��܂���B�^�������Ă��Ȃ��̂ł����E�E�E�B

3.
���̕��N�A���N71�Ƃ̎��ł����A��U���S������ԂƂȂ�18�N�ۂ��������ł��B����ƁA������53��Stage��0�`2�Ȃ̂ł��傤�B
�ł�����AK.O.�����A�������E�E�E���ĉ�����������܂��E�E�E�ɔ��ǂ��A53���ɑ���Stage0�`2�A56�Ώ��f�i�K��Stage4�ƌ����o�߂͗L�蓾�������ł�??�Ǝv���܂��B

4.
�ȏ�̗l�Ȑ��_���������Ƃ���Ȃ�A����ׂ��͈�`�q�E�E�E�ƌ��������Ȃ�܂��B����ɂ��Ă��N��斘�ꏏ�Ƃ́B����̈�`�q�͉������Ă���̂ł��傤??
���́A�Ǘ��l�̋y�т��̌Z��o���̓s��5�l���A�����튯�Ǝ��ӂ̓�����n�̊��ő�����62�`75���ɑ��E���Ă���܂��āAK.O.����̏���F�X��������Ƃ��킟�`���Ċ����ɂȂ�܂��B
62�Ζ��c��5�N�ł���B
orz
R03/01/01 �W�� K.O.��������e�`�ƈ�W�����H�^?J�^??
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
�O��A�⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B
����͑��e�B�ƈ�̇W����Ԓ��C�g�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�A2/1�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�O�l�ɁA�悸�͏k�ڂƌ^���̓��肩��B
�O��̇W���Z�C�g�ƁA�ԑ̐��@���قړ����ł����̂ŁA1/35�ł��ˁB
�ו��ނƂ��ẮA�C�����ދ@�̌`��A�ǂ����H�^��J�^�̗l�Ɏv���܂��B

2.
K.O.����A�����A�ǂ�Ȍ����Ŕ��������̂ł��傤�B
F1�̎��̂̉e���Ƃ������ł��傤���B�e�����L�����Ƃ���ƁA�������Ԃ������Ă�8�N�ƂȂ�܂��B
�����łǂ�Ȑ����ɔ��I�����\�����L��̂��E�E�E�B�߂��ɍs������??�S����n����F1�ɋߕt���p���͍l�����܂���B
�Ƃ͌����A�S�Ă̍s���ɂ��ĕ����Ă����ł�����܂���B�֏�S�ɓ���K�₵�Ă���̂����m��܂���B

3.
���I�A���ʂƂ��đ咰�͗L�蓾��̂ł��傤���B������ƂŌ�����l�ȑ͐ϕ�����̕��˂��l�����܂����A���̏ꍇ�픘����̂͐悸�畆�ł���ˁB
�����オ�����o�H���z�����ޏꍇ���L�蓾��ł��傤���A����ƁA���@��A�ȁ`�㕔�����ǁA�ċz�킪�悸�픘�������ł��B�Ƃ͌����A���̕ӂ��f�ʂ肵�ď������f�ʂ肵�Ă��܂��ܑ咰�őؗ�������Č����͉̂\���Ƃ��Ă͗L�����m��܂��A���`��E�E�E���Ċ����ł��B

4.
�����ŁA�p�F�⏜���]���҂̘J�З��݂œd�Ԃ�˂����Ă݂܂����B
����ƁAH28�`H30�ӂ�̎�������A�b��B1���A�����a3���A�x��1�����������Ă��āA�����튯�͑S�R�o�Ă��܂���B
��͂�t�N�V�}�ƈ��ʕt����͖̂������L�肻���ł��B
R02/12/18 �W�� K.O.��������e�`�ƈ�W�����A,D,E�^?
�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������11/29�ɉi�����܂����B
���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B
���w�Z3�N���炾������5�N���炾�������A�͂��܂����̑O���炾�������A�Ƒ��e���Ɏ��������̕t�������ł����B
����b���̊ԁA���O�̈⓿�E�E�E�ł͂Ȃ����y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������܂��B
���e�͓ƈ�̇W����Ԃł��B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
��������?�k�ڂ�??
�͂��A�S�R����܂���B�����͌����Ă��A���i���킵�Ă�����b����1/35����1/45����1/48�������낤�Ɛ������t���Ȃ���ł͂���܂���B�܂��A���ۖڂɂ����1/72��1/24�Ŗ������͈�ڗđR�ł����B
�ƌ������A������������A�������v�����āAwiki�ӂ�̏��Ɠ˂�������Ώk�ڂ͔���܂��ˁ�
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1

2.
�ŁA�������Ă݂܂����B�S��173mm�A�S��82mm�ł����B
����ɑ��āA35/35����45/45�����́Awiki�Ɉ˂�Ǝԑ̒�5890mm�A�S��2880mm�ƌ����Ă��܂��̂ŁA�܂�1/35���낤�Ƃ̌��_�ɂȂ�܂����B
�܂��Awiki�˂��������łɁA�Z�C�g�����珉���^�Ƃ����������Ă��Ȃ������_���A�C���w��̎G������A�O�ʋ@�e�L����ē_����A����A,D,E�^�̉��ꂩ���낤�ƌ����������܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1

3.
���́A��i�������⑰����˗�����Ă��܂��A���ꂪ�Ƃ��A�Ɖ����Ă���܂����B
���̇W����Ԃ́A���̖��A��T���ƌ������A�|�C���Ă������A�ŏ��ɔ����������̂ŁA���̒i�K�ł́A���[��A���̍�i�͉����łǂ�������Ă���̂��??���Ċ����ł����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1

4.
����͉�??
����܂��A�����̒ʂ�eneloop�Ǝg���̂Ă̒P�O�A�P�l���d�r�ł��ˁB
�����̓d�r�͖��A�͐ϕ��̒�����@��o���������ł��B���݂ɁA����eneloop�A�ǂꂾ��������Ă����̂��s���ł����A�A�ꕔ����ނ����Ȃ���Ă��܂����B���N�O�ʂł�����??�Ƃ͌�������eneloop�BistDs�ɑ��U�������A���ʂɎg���܂��āA���1�`3�͂���ŎB�e���Ă��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
| R02/10/31 �W��
|
���̃t���b�`���[�B�`��l�e
|
|
�`�u�C�X�P���f�����v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�u�����v
|
������3�N���U��̑�l�e�ł��B
����́A
DD-544 �u�{�C�h("Boyd")�v���y���Áu�C�X�P���f����("Iskenderun")�v
DD-551 �u�f���B�b�h W.�e�C���[("David W.Taylor")�v�����lj�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X("Almirante Ferrandiz")�v
DD-631 �u�A�[�x��("Erben")�v����ؖ����u����("Chungmu")�v
�̈�C��3�ǂł��B�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͑�K�͂ȉ�����ɑݗ^->���n����܂����B���āA�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�́A��K�͉����O�ɑݗ^->�w���ƂȂ�A�풆�̎p��F�Z���c���Ă��܂��B
����ɂ��Ă��A�ݗ^�A���n�A�w���̊W�����ǂ�����Ȃ��Bwiki�ł͒P��transferred�Ƃ��A�Ă�decommissioned�A�ł����commissioned�Ƃ�����������ĂȂ����A���͂ł͖{�����ɂ͈ꕔ�ݗ^���甄�p�ƌ����镶�����L�邯��ǁA�ꗗ�\�͈ꊇ���ď��n�Ȃ̂ɖ{���͑ݗ^�Ƃ��������ėL������E�E�E�B
�Ƃ�����A����͊͋��\���̑��Ⴉ��A�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͓c�{�́u�J�b�V���O("Cushing")�v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�͓������u�t���b�`���[("Fletcher")�v��y��Ƃ��AP�Ђ̑����i�Z�b�g���v���_�����ʂɎg�p���č쐬���܂����B
ISO200,F16�ŎB�e���܂����B
|
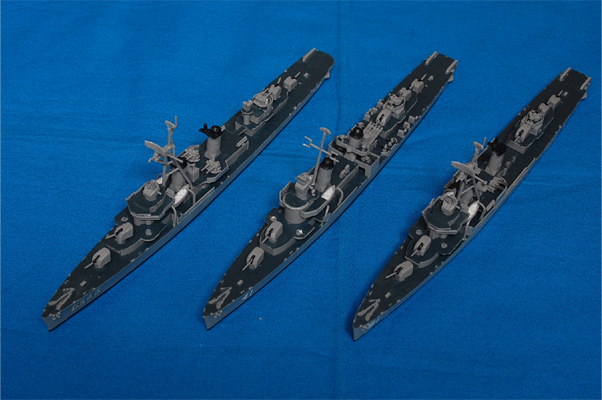
1.
������u�C�X�P���f�����v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�u�����v�ł��B�ȉ��A�����т̏ꍇ�͂��̏����ł��B
�u�C�X�P���f�����v�A�����ł͒n���Ǝv����낵���ł����ˁB���^�͂��C�X�^���u�[���Ƃ��C�Y�~���Ƃ������Ă��܂��̂ŁB
�ŁA�͕̂ʂ̘a��ǂ݂��[�Ă��Ă������ƋL�����Ă���܂��B�K�L�̍��A���E�n�}���̒n���C���݂ɂ�������������́A�Ƃ��`���Ă��h�����܂����B��}�[�����_�ȊO�ɗL�������`�ƁB�����āA���͂ł�������������́A��������낤�Ǝv���Ă���܂����B
�������Ƀi�o�e�A�̏����̖���t�����t�l�����Ȃ����̂ł��傤��?
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1

2.
�ォ��u�C�X�P���f�����v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�u�����v�ł��B3.�����l���ł��B
�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�͑̕\�L�͔̊ԍ���41->D22�ƕϑJ���Ă��܂��B
���́A�]��f�J�[���ɉe�t��������"D"�����Ȃ���ł���B���܂ł�"0"��"1"��g�ݍ��킹��Ƃ����ĝs�����Ă��܂��Bnavsource��˂����ƁA�����ĉ��B�͂�"D"�t���œ�Ă͐����������ČX���Ɍ����܂��B���̒��Ő��lj�֓n�����{���́A���lj�Ђł̓a�͈ȊO�͓�����"D"�����ł��鎖�������A���������͒P���Ȗ_���Ȃ̂ōH�삪�y�����B���lj���n�͂��W�����č��̂��L�肩���m��Ȃ��Ǝv���n�߂Ă��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
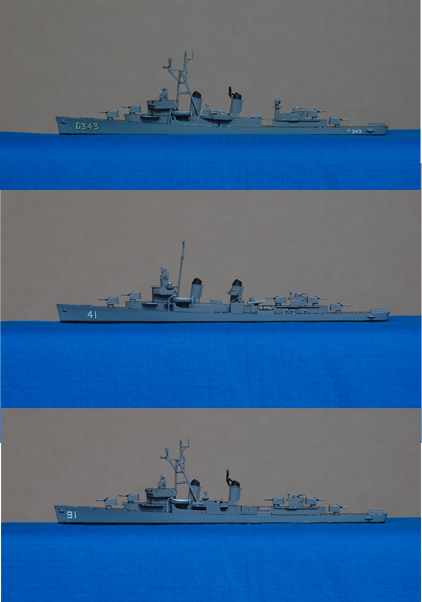
3.
�u�����v�A���ˊԗ����̖C�������ɔY�܂���܂����Bnavsource�ōł��V�����Ċ͎���̎ʐ^�ł͕s�N���Ȃ���3�D�A���C�Ɍ����܂��B���̐ς�ł̂قق�Ƃ��Ă�����ABofors��4�A��40mm�@�e��ς�ł���1/144�̍��������Ă��܂��܂����B
���āA�ǂ�����??
�킴�킴40mm�Ɋi�������ēn����?������A���̕�����l�@�����?�����͓K����3�D�̎����������đË��������??�ƌ������A�z���g��3�D�����l�����܂��B
���ʁA����520���Ɉ˂�A127mm�~5�A40mm���ڊ͂������ƌ����L�q���L��܂��āA�����������B
�ŁA���ǁA�]�蕔�i�̍ɗʂ̓_��40mm�~4��P��D�ő���40��Ƃ�50��Ƃ��\���ȗ]�T�������߂�̂ɑ��āA3�D�͏\����������A���̕ӂ�̑䏊�����40mm�~4�ɂ��鎖�Ƃ��܂����B�Ƃ͌����A����I��3�D�C�̏؋����������Ă��܂��ƍ���̂ŁA�؍H�p�ڒ��܂ʼn����߂ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
����I�o�A�œ_������3��������

4.
��̔@���A�g�p�h���Ɨ��߂āB����Ɗ͋��V�W��FCS�͎��O���\�ɁB
�����8��������F�X�Ɛ���ΏۑI��ׂ̈̒������n�߂āA�{�i�I�ȋN�H��8�����B��ŁA�ق�2�����|����܂����B
9���A�O�����X�������Ȃ�Ȃ�������1�T�Ԃ����o������ƌ����v�����L��܂������A�s�����ނ�H��B�ׂ̈ɔ��������悤�Ƃ��Ă��A���������ׂɓ���������I�Ȃ���Ȃ炸�A2,3���P�ʂō�Ƃ���������������̂��n���ɋ����܂����B�������A��������������ʋ@�֗��p�����������Ȃ��ėǂ������ɂȂ��ė~�������ł����A�늳�Ґ��̉��Ă̌����⍑�������킶��Q���������ƌ��������E�E�E�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1

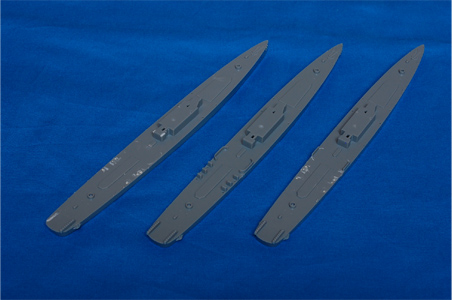
5.
��������͍쐬�ߒ��ł��B
�悸�A�͑̂���s�v�Ȕ����֘A�����������A��t�ē��E�߂܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����2/1

6.
3�ǂƂ��͋����01�b���g�傳��Ă��܂��B
����́A�g�p�����f�ނ͕����ŋL�ڂł͂Ȃ��A�z�l�ɍ\�}���Ɏʂ����ގ��ɂ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1


7.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͎�����O�r������Ă���ׁA��̊͋�����i�����ߌ�Ɏ和�ƎΒ������t���܂��B
�和�͑O��́uZ-2�v�Ƃقړ��l�̒����ł����A�Β��͌��ꍇ�킹�Œ������Ă��܂��B�܂��A���O����l�Ɋ͑̑��͖؍H�p�ڒ��܂Ɉ˂鉼���߂ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����1/1


8.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎���ɉ��������t���܂��B
Nikon D40
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����2/1

9.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎�����i�̑�d�T??�p�̑�������܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1

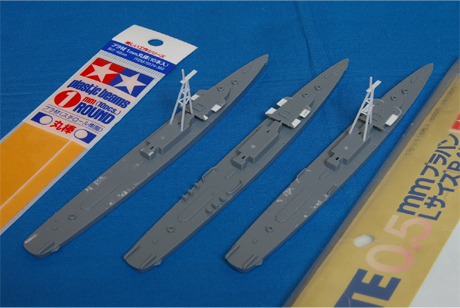
10.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎��������9.�̑�������t���܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
�����1/1
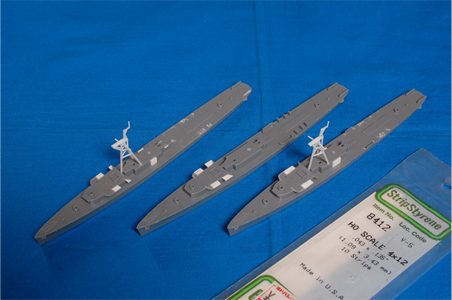

11.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎���Ɉ��������Ό���璸���������t���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����1/1
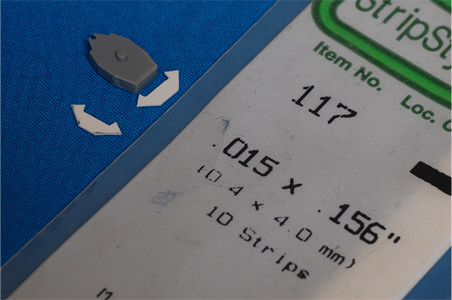
12.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̊͋��́A����^�̔��^�Ȃ̂ł����A�ꕔ�I�V�ɌŒ�Ǝv���鉮�����lj�����Ă���̂ł����삵�܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1

13.
�u�C�X�P���f�����v�̌㕔��\�́A53�ԂƘA��40mm���P������A����ɍb���̊g��AMk.33 3�D�C�ݒu�ƌ������������Ȃ���Ă��܂��B
�ł��̂ŁA53�Ԃ̖C���̏����A�Ւn�ɍb���A�����ɚƗےlj����������܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
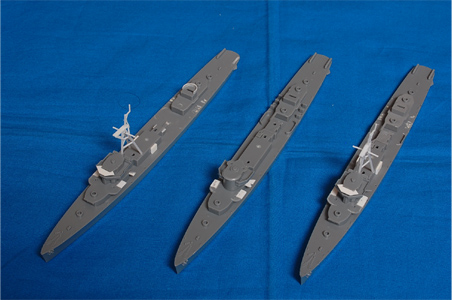

14.
�v���Ԃ��3�Nj��̐i���ł��B12��13���܂߂��͋���㕔��\�������߂��܂��B
����`�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�͌��^�ɋ߂��̂ŁA���X�����_������܂���B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����2/1
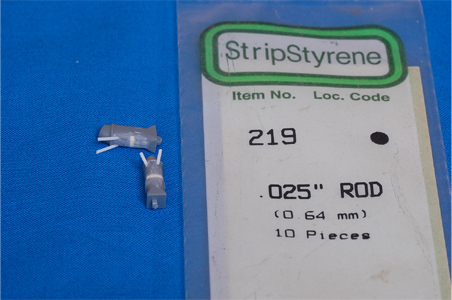
15.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̑�˂́A���i�̎ˌ������u�p���ꂪ�P������Ă���̂Ńp�e�Ŗ��߂܂��B
�܂��A������ECM?ECCM??ESM???�������������ݒu����Ă���̂ŁA���̎x�������t���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1


16.
3�Nj����˂������߂��܂��B
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͉��ˊԂ�01�b�������Ɋg�傳��Ă���̂ŁA���̊�������߂��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����2/1
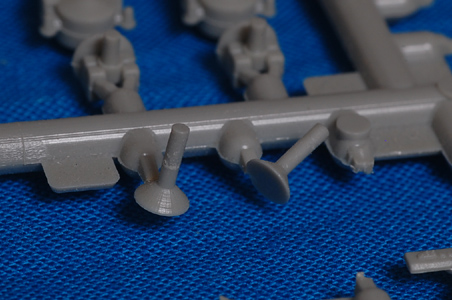
17.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̊͋��V�W��FCS�́A����g���u���ς���Ă��܂��B�Ƃ͌������̂́A�K���ȗ]�蕔�i�����������܂���ł����B
����͋ꂵ����ŁAP�Ђ̌��p�͑D�����Z�b�g4��23�𗬗p���܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
����2�����x�g���~���O
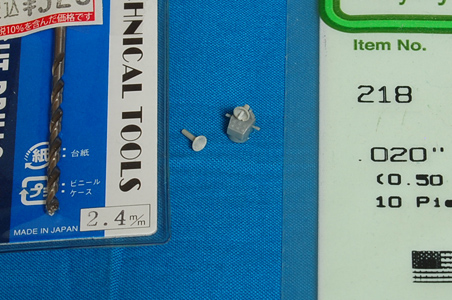
18.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v��FCS�ł��B
17�Œ̕��i�ɑ���2.4mm�h�����ŕ��ʂ��M��ɝP��A�������ɓˋN��ݒu���܂��B�܂��A�����r����K���Ȓ����ɐؒf���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
����2�����x�g���~���O
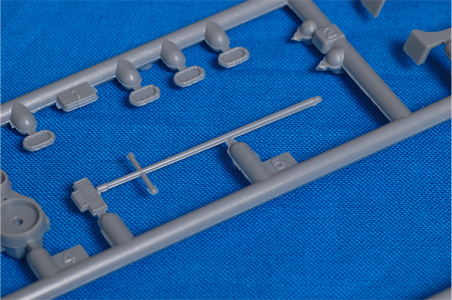
19.
�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�̎�������܂��B
��{�I�Ɍ��^���ۂ��̂ł����A�����̓d�T���ς���Ă���̂ŁA�d�T�̊��������藣���܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
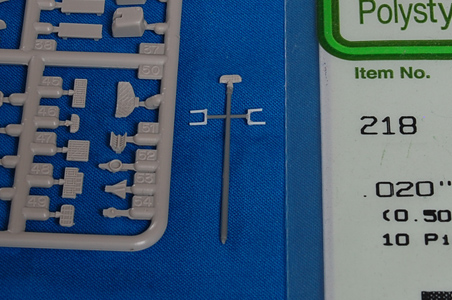
20.
�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�̎�������ɗ]�蕔�i���猩���U���čq�C�p?�Ǝv�����d�T(����46)�����t���܂��B
�܂��A������[�ɂ��A�ȗ����悤���ǂ����悤��畏�������x�̒lj������L��A�������ߏk�ڂ��ۂ����A�`����{��"U"�����|���ɂ��������Ȃ̂ł����A�lj����Ă݂܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
����2�����x�g���~���O

21.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎�������q�C�p?�d�T(61)�Ƒ�?�d�T(58��62)��]�蕔�i���璲�B���܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
���x����
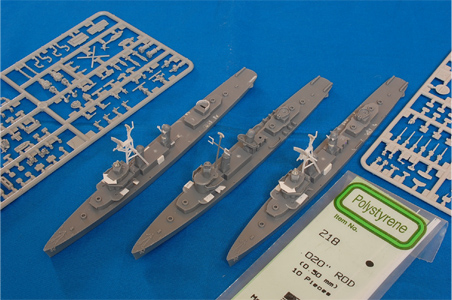
22.
17�`21�̐��앨�����A���L�e���i�߂܂�
�E3�ǂ̊͋���FCS������
�E�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�̎����������
�E�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎���d�T�����t��
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
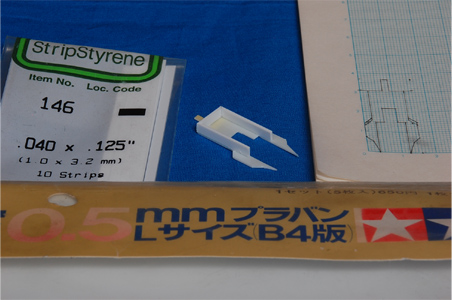
23.
�u�C�X�P���f�����v�̒���01�b�̊g�啔�������܂��B����͗��Ԃ�����Ԃł��B
��{�I�ɂ́A�uZ-2�v�ގ����ۂ��̂ŁA�uZ-2�v���畽�ʐ}���N�����č쐬���鎖�Ƃ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2

24.
23�́u�C�X�P���f�����v�̒���01�b�g�啔���ɚƗۂ����t���܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
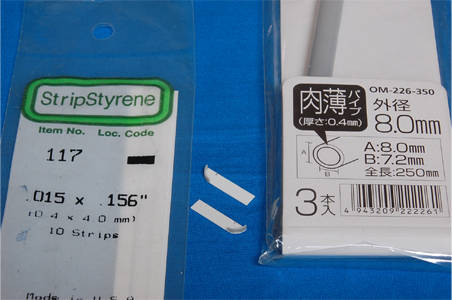
25.
�u�����v�̒���01�b�̊g�啔�������܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
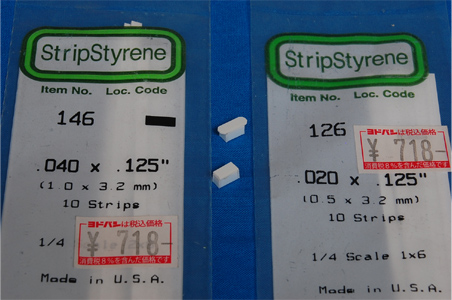
26.
�u�C�X�P���f�����v(��)�Ɓu�����v(��)�̑�ꉌ�˒���̎ˌ������u���ڂ��Ă���b�������܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
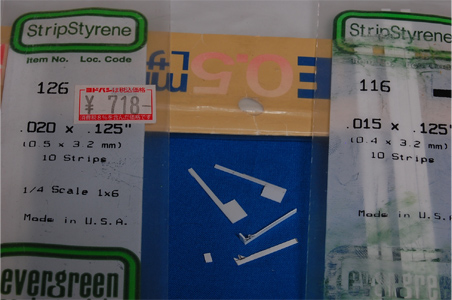
27.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̌����̚Ɨۂƌ������g�����ƌ����ׂ��ł����ˁA����������g�傾������Ă��܂��B
�u�C�X�P���f�����v(��)�ɂ��Ă͊ہX�V���A�u�����v(��)�ɂ��ĉ����������쐬���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1

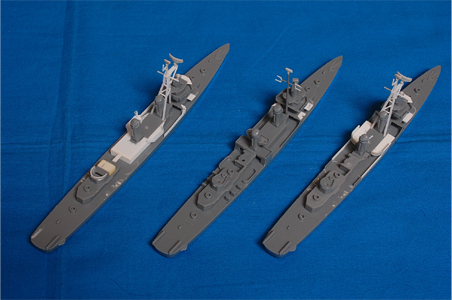
28.
23�`27���܂߂āA�������̍\�����������߂��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����2/1
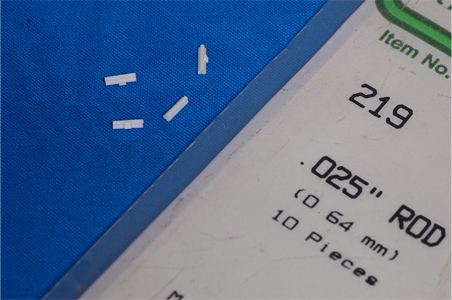
29.
�O�A���Z�������ˋ@�����삵�Ă݂܂����B
����30�Ŕ\���������ꂱ�ꏑ���܂����A�Ԃ����Ⴏ�A�]�T���������Ď��ł��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
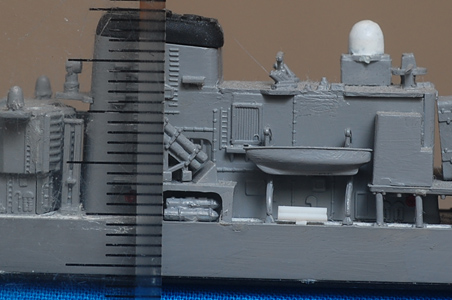
30.
�u�䂫�v���ɐς�P�ДłƔ�r�ł��B
��X�v���Ă����̂ł����A�Z�������ˋ@�A�w�����߂�����Ȃ���?�ƁB
�����̒ʂ�2.5mm���x�L��܂��B�܂�A700/700�ł�1.8m���x�̍������Ď��ɂȂ��Ă��܂��A���͏�Ō���A���X���������������̍����̈�ۂƃG���N�Ⴄ��ł���ˁB
�����Ƃ��A����̕���2mm�߂��̍������L��܂��̂ŖJ�߂�ꂽ�o���ł������ł����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
����2�����x�g���~���O

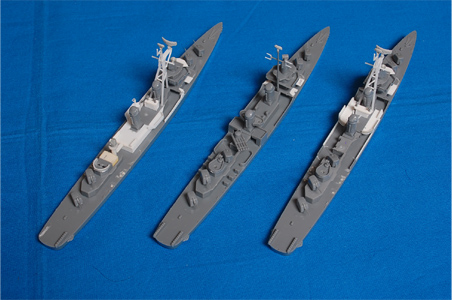
31.
29,30�̒Z�������܂߂��C�������������߂��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
�����4/1

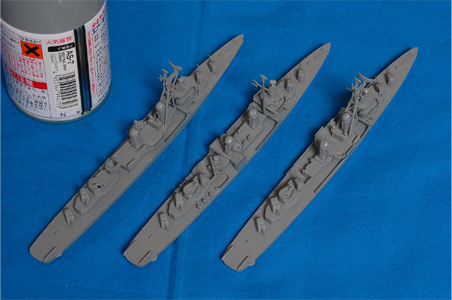
32.
3�ǂ܂Ƃ߂�AS-7���ǂ��Ɛ����t���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
8/1,15/1
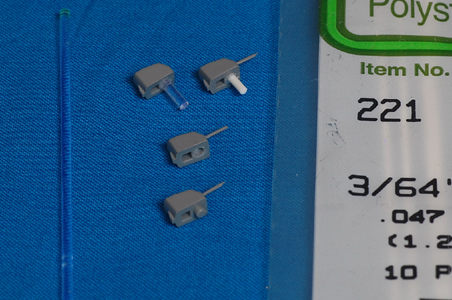
33.
��C�A����T�Ђ́u�t���b�`���[�v���͊�{�Œ������Ă��܂������A����͐���ł���l�ɂ��܂��B
�����Z�߂�&�߂��Ȃ̂ŁA��U���A51,53,54,55�ɂ͐̕ʌ��Œ��B������1.6mm�̃A�N�����_(��)���A52�ɂ�221�����t���܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
����2,3���g���~���O

34.
��C�A��]������͑̑���1.7mm�Ő��E���A�����ђʂ�������A�E���h�~���Œ������܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
����2,3���g���~���O
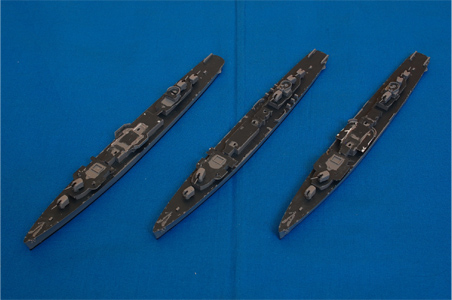

35.
�����߂���U�炵����A�b��h�����A�Ăёg�ݏグ�čs���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1

36.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̑�˂�ECM����ECCM����ESM���������t���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
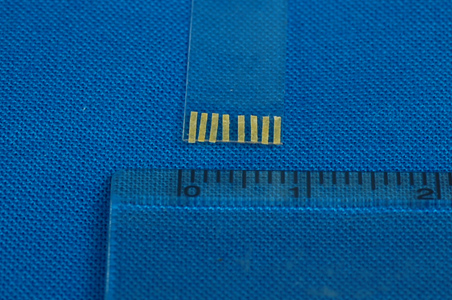
37.
�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̊͋��́A12�œV�W���������Ă��܂����A�O�ʂ��͂���Ă��܂��B
���e�́uZ-2�v�ł����l�ɂ��܂������AQM��1/150�L�b�g���K���X�p�̓������i�ő���\�����܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
����1�����x�g���~���O
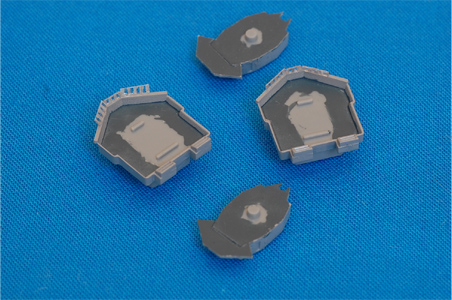
38.
37��h���A�ؒf���Ċ͋��O�ʂɎ��t���܂��B
���̐ؒf�̐��x��12�̓V�W��t�̐��x���s�ǂł��āA����������Ȃ��Ȃ�����]������Ə�肭�s�����A���͒�����傫���O�X�����Ď��t���鎖�ƂȂ�܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
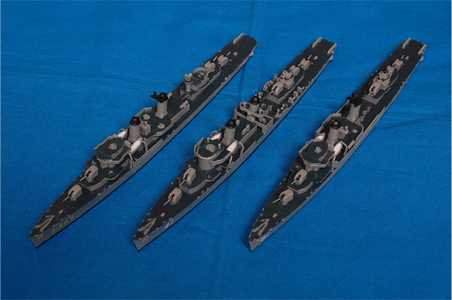
39.
36�`39�̐��앨���@�e�A�T�Ɠ��A���ڒ�����������t���܂��B
�c��͉����߂������AFCS�ƁA�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̉��ˊԗ��������ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
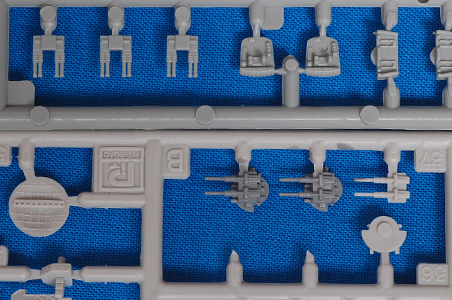
40.
39�Ŗ��ڂ́A��D��4�A��40mm�A��P�ИA��3�D�ł��B
����ɂĐ���L�I���ł��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
���͎�g���~���O
R02/09/29 �W�� R02�x�㔼���̂��z�{
��������Ȃ߂ł��B���ς�炸1/700�͒�����ł��B
�V������1���̂݁B�e�Ђɉ�����܂��ẮA�V�K�J���͂Ȃ�ׂ��ᒲ�ɂ��肢���������ł��B
Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�㍶����IBG Models�̔g���u�K�[�����h("Garland")�v1944�A�p�u�C�V�����G��("Ithuriel")�v1942�A
���i�A�V������Flyhawk�p�u�G�W���R�[�g("Agincuort")�v�A
���i�t�W�~�āu�A���_�[�E�b�h("Underwood")�v�ł��B
2/1

2.
�u�K�[�����h�v�A�u�C�V�����G���v�͍�N�x�O���ɂ��w�����Ă���܂��B������\3200���āA�����Ȃ��`�Ǝv���Ă���܂������A1�N�߂��o����\400���x�������ė��āA���A�lj����B���Ă��܂��܂����B
�u�A���_�[�E�b�h�v�́A���ւ��u�Q�A���[("Gary")�v���܂߂Ă�������ȂɁB����˂��A���ƍ��Z����ɓ���̕ӂ�����낤������Ă��邽��A���A����ȏ��ɖ͌^�����E�E�E�Ɠ�������A����??��������Ȃ�L���??�ƒlj����Ă��܂��܂����B���������v�H�����Ȃ��ƁE�E�E�B
2/1
���x����

3.
�O�����Ɠ������A�v�H���ƕ��ׂĂ݂܂����B�������B�A�E���v�H�ł��B���̏�ł͏o���ł��B
������������A�O�������l�ɉ��ϔ��̑̐ς��v�Z���Ă݂܂����B���B�� 0.009723 ���āA�v�H�� 0.0121425 ���Ăő̐ϓI�ɂ��o���őf���Ɋ������B
�v�H���̋��ɂ��ẮA���̌�A�e��ޖ���1�����W���������W�J��������Ԃɂ��đ��u�����A���͔p���ł��B
1/1
R02/08/24 �W�� �c�����������\���グ�܂�
�����ł��B
���̎����A���̓��y�͓�V�ł��B�L�@�n�܂ƕt�������s����A��ƒ��͊��C���������܂���B�ƌ������́A��[�̉��b�ɗ������ł���ˁB
�����͐^�~���ꏏ���낤�E�E�E�ƌ�����Έ�ʘ_�Ƃ��Ă͂��̒ʂ�ł����A�l�I�ɂ͐���Ƃ���ꏊ�����Ɍ����Č���������Ղ��A�t�ɖk���̒����͎Ȃ��̂Ő^�Ē��������ł͂���܂���B
�Ƃ܂��A����Ȗ�Ŕ~�J��������H�J����E�E�E���������E�E�E���A����ǂ��ł��B�ŁA���N�����{�I�ɕ�C�Ƃ��̌y���Z���ȍ�Ƃ𒆐S�ɂ��鎖�Ƃ��܂����B
�ƌ������ŁA�����P�Ђ̑����i�Z�b�g����SH-60J��4�@�A�C���@�Ƃ��ďv�H�����܂����B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|
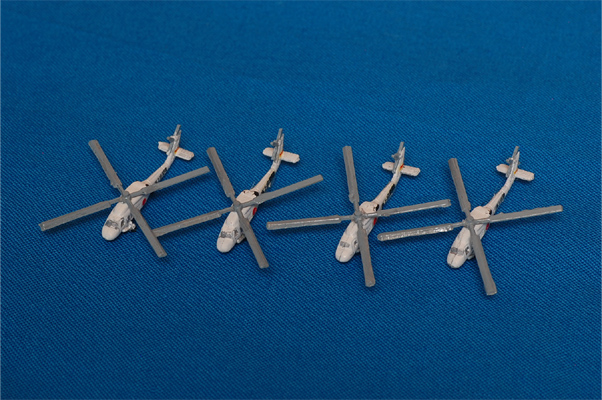
1.
���p�͑D�����Z�b�g3����̑I���ł��B
���̊p�x���ƍ�������̂ł����A�㕔�́u�C�㎩�q���v�̃f�J�[���̃t�H���g�A�O��2�@�͖������ŏ����ځA����2�@�̓S�V�b�N���傫�߂�2��ނɂȂ��Ă��܂��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2

2.
���v�H��4�@��HSS-2��SH-60J�̍��킹��4�@���ꏏ�ɂ��Ă݂܂����B
�v8�@�ɂȂ�܂����B�ƌ������A8�@�ɂ��܂����B����8�@��??�ƌ����ƁE�E�E
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2

3.
�E�E�E����ł���A����B
���@���͂������ł��B
������u����܁v�A�u�͂������v�A�u���킩���v�A�u��������v�A�u�䂫�v��1�`4�Ԋ͂ł��B
����˂��A����R01/10/31����W�����u�ϊ͎��v��3�ŕ��ׂĂ��鎞�ɁA�ӂƁA�w�܂萔���Ă݂���A����A�͂̕��͏[�����Ă���Ȃ��ƋC���t�����̂ł���ˁB�Ȃ�ΐ܂����ċ@�̕����[�������悤���Ǝv������ł��B
������Ǝc�O�Ȃ̂́A����Ȏ��Ȃ�DD�A�u��������v�ł͂Ȃ��u�䂫�v�ɓ��ꂷ������E�E�E���ĕӂ�ł��傤���B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/30

4.
�ƌ������ŁA�u�V�c�ہv�^�A�u�����ہv�A�u�Ƃ킾�v����������o���ĂȂ���ė`�w��g��ł݂܂����B���ۂɂ͂���ȋߕt���Ȃ��ł����A���D�Ƃ̎���ݒ肪�Ⴂ�߂��܂����B
���`��A����̏��D�����E�E�E�C������q�������ƂȂ�ƗL��̈�A��1/700�u����ӂ�킠�v������������܂��A��ł��ۂ��̂ł���˂��B���ꂪ�p����Revell����Qunard�̍��؋q�D�Ƃ��ς�ς�o�Ă���̂ł����E�E�E�B
�b�ς���āA�����肪DDG��2�ǁA���r�����i���܂߂Ăł����u�䂫�v�Ɓu����v���s��7�Ǖ��ɂ��Ă���܂��B���Ď���DDH�B����Ƃ���1�Q�o�����!!
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/15
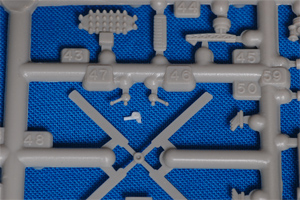
5.
���쒆�A1�@�̉E�r�����Ă��܂��܂��āA�r���G�o�[�O���[����218�ԁA�ԗւ��^�~���̃�1mm�łł��������܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
R02/07/14 �W�� �g���C�o�����A��`���́A�풆�����
R02/08/24 ���䕶�X�V
P�Ђ́u�q���[����("Huron")�v����A�f�̂܂ܐ풆�́u�q���[�����v�ƁA���A���́u�J���[�K("Cayuga")�v�ɓ]�p���쐬���܂����B
�u�J���[�K�v�A�l�r�Ό��̑O���ƑS��C��4�D���p�C���������I�Ɍ����܂��B����R02/05/22����W���̑O��u�g���C�o�����A��`�p�́A��O��ԁv�́A����3�ǂ���4�D�C��P�o���ׂ��A��O��Ԃœ��ꂵ�č쐬���Ă����肵�܂��B
�u�q���[�����v�́A�ꕔ�h���̂ݎ�����ւ��Ă��܂����A���͊�{�I�ɑg�ݗ��Đ����A�h���w��̒ʂ�ō쐬���܂����B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
������u�q���[�����v�A�u�J���[�K�v�ł��B
�u�q���[�����v�A�ύX�_�Ƃ��Ă͓h�������ŁA���ʂ�C308:C62=1:1�̎w�蕔����C338�ɁA�b��C14:C33=9:1�̎w�蕔����TS-4�܂���LP-27�Œu�����Ă��܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1

2.
�ォ��u�q���[�����v�A�u�J���[�K�v�ł��B
�u�J���[�K�v�A������AS-7�A�㕔�\����TS-81�A�b��XF-63�œh�����܂����B
�\��̎�C��O���ȊO�͔��ˊǁA�������293�^�d�T�A�͋��V�W��Mk.6FCS�����܂��܂ƘM���Ă��܂��B
�Ƃ͌������̂́A���X�Ɠd�ԓ˂����Ă��A�قڐ^������B��ꂽ���͔����ʐ^�������m�Ȏ�����������܂���B�Ȃ̂ő����^�͂̎��͂�modelshipgallery�̎ʐ^�Ŗϑz���Ă���̂Ő^�ɎȂ��l�ɂ�!!
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
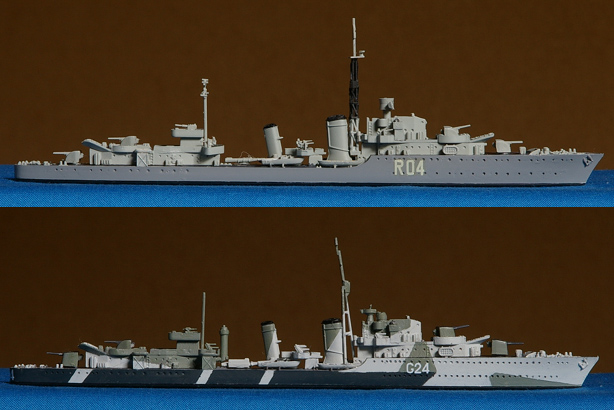
3.
�ォ��u�J���[�K�v�A�u�q���[�����v�ł��B
�u�J���[�K�v�A�O���̓h�����͂���܂��K���ł��B�B��̎��͎ʐ^�͑S�ʍ��Ɍ�����̂ł����A���˒�����艺�͕��ʍ������Ȃ���Ȃ��`�Ƃ��A���l����́u�A�T�o�X�J��("Athabaskan")�v���h�����Ă���ʐ^���L�邽�߁A�z�l�ɂ��Ă݂܂����B
�܂��A�͔ԍ��A������Ə㉺�����������̂��ʂ���ł����A�]��f�J�[���̒�����܂�܂�"R"��"0"�`"9"�̔�����������Ɍ����Ă��܂��̗p�ł��B�ł�����ɂ�"R"�͌͊����܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1(����I�o2��������)

4.
������u�J���[�K�v�A�u�q���[�����v�ł��B
��̔@���A�g�p�h���ƍ��킹�āB
�O����͉��~�߂ł��B�����؍H�p�ڒ��܂��ł܂��Ă��Ȃ������̂ŁA��\���āu�J���[�K�v�̑O���̂ݎ��O���܂����B���݂ɂ��̑O���A�Ӑ}������ł͖����ł����ڒ������U�ߍ��ݎ��ɂȂ�܂����B
����ɂ��Ă��A����͖w�Ǔh�����d�������A�lj��H��̍\������1�_���ɂȂ��Ă��܂��A2�Ǔ����̈Ӗ����L��܂���ł����B�܂��풆������2�ǂɂ���Ηǂ����������ł����A�풆�ɂ���ƁA�܊p�P�o����4�D�C�����ɕ����Ă��܂����A���ɂ���Ƃ���1�{4�r�Ό������Ȃ��Ƃ����E�E�E�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1


5.
��������́A�M�������ꂱ��ł��B
�悸�́u�q���[�����v�̓h���ł��B
������C308:C62=1:1�̎w�蕔���A���̒ʂ�A�����ŊT��1:1�E�E�E�C308���߁E�E�E�œH�����܂��āA���������܂����B
�ŁA�ߎ��������ȉ���ނ��̓h�������������ė��Ĕ�ׂ��̂��E�ŁA�܂�C338���߂�����??���Ď��ō̗p���܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1,8/1
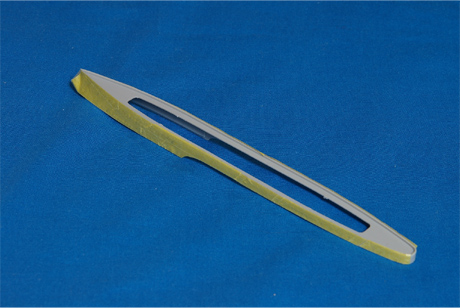
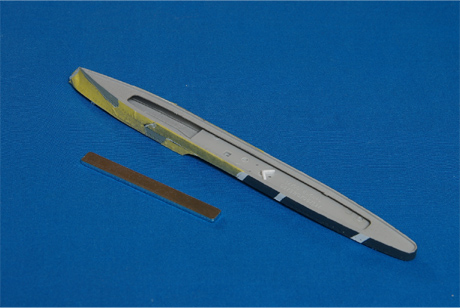
6.
�͑̂ɂ��ẮA�O�X��AR02/04/02����W�����w���߂Ă�IBG�`1/700 �g���C�R�u�N�����B�A�N("Kujawiak")�v�x�ŗp������@�P���܂����B
�����A�����[�̑S�ʔ핢��ԁA�E���Ō��C31��h�����I�������Ԃł��B
�E�A�������ۂ����ƍb�̗����ɖ��Ȕ@���ɂ��v���̒lj����L�邯��lj�?���Č����ƁA�悸�A���̍b�́u�J���[�K�v�̂��́B�ŁA9.�Ɍ�q�ł������ˊǘM���Ă��܂��āA���߂ɂ�����]����ی삷��ׁA�c�{��5mmL���v���_��ݒu���Ă��܂��B����˂��A����GM��18m���t���ԂɎg�p�̏d����͑̂Ɏd���肷���ł���B�ŁA���������œ����Ɣ��ˊǂ̉�]����܂肻���ȋC�������̂łˁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
��2/1
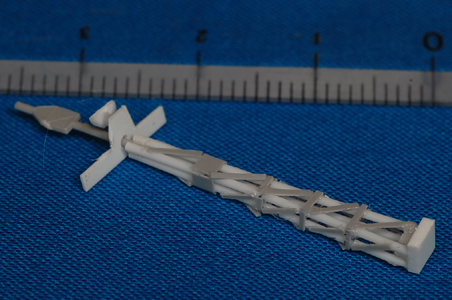
7-1.
�����ĉ��X�Ɓu�J���[�K�v�̍H��ł��B
�悸�͑O���B����͓�q���܂����B�G���@�[�O���[����219�Ŏx���𗧂�218�ʼn����A�Ό���g�����Ƃ����̂ł����A��肭�s�����A���ǁA�x����219�Ƃ��AWAVE�̃v������\��t���Ō���\�����܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
����3/4�Ƀg���~���O
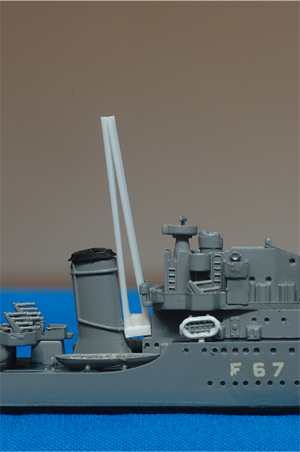

7-2.
��q�̂��܂�A�v���ň͂��Ă��܂��A�h���E�E�E�����Ă��镔�������ɁE�E�E�ŌӖ���������?�Ǝv���܂��āA���삵�����̂�O��́u�x�h�E�B���v�ɐς�Ŕ�r���Ă݂܂����B
�܂��A��͂蔠�ł���ˁB���̌�A�핢���Ă݂��̂ł����A�h�������̂���ς������Ď��ŁA�x���𗧂Ă�����֖߂��Ă��܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
��1/2
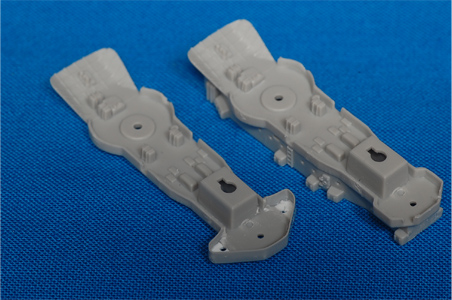
8.
�㕔��\�A�@�e��1����܂��B�ŁA�z�u���ǂ�����Ȃ��B���͓��^�͂́u�n�C�_("Haida")�v���L�O�͂��������ق����Ō������Ă��܂��āA���̎ʐ^��}�ʂ���ɂ���ȋ�ɘM���Ă݂܂����B
���́A����2���L��̂ŁA�ŏI��Ԃ́u�n�C�_�v���E�E�E���Ɗ��ł��Ȃ����Ȃ��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/8
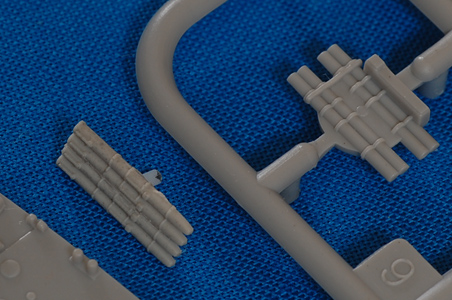
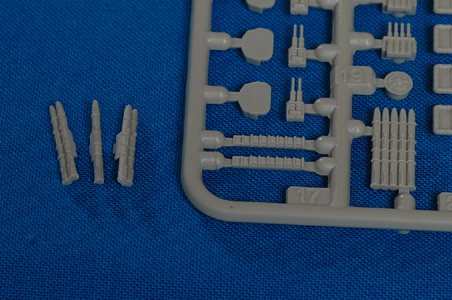
9.
���́u�n�C�_�v�̎��͎ʐ^���܂��ƁA���ˊnj`�s��v�Ȃ̂ł���B����������Ȃ̂��E�E�E�܂�P�Ђ̌�l�E�E�E��N��DDE����������Ȃ̂��s���ł����A�u�J���[�K�v�̂ݘM���Ă݂܂����B
���̍����M��ŁA���̉E���ʏ�ł��āA���̉p�͌��Ă�����Ȓ����Ɍ��Ԃ��L��l�Ȕ��ˊnj��Ȃ��̂ł����˂��E�E�E�B
�ŁA�ǂ�����ĘM��ł�P�o������?�ƌ����ƁA�E�AP�Ђ́uWWII�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�g[II]�v��5�A�ǂ�4�A�ɐ�\��������܂����B���݂ɁA�u�J���[�K�v�͋@�e���ύX����Ă���A�����uWWII�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�g[II]�v���痬�p���Ă��܂��B�܂��AMk.6FCS�����l�ŁAH28/7/20����W�������u�W���g�����h�C��S���N ��Q�e�v�̎�@�ɏ����č쐬���Ă��܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2,2/1
���ɒ���3/5�Ƀg���~���O
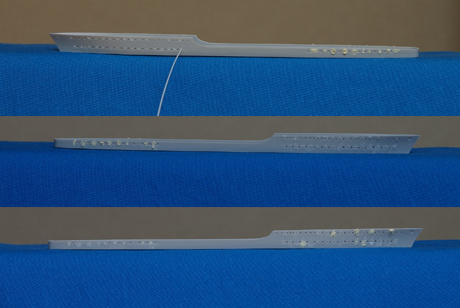
10.
�u�J���[�K�v�Ɍ��炸�A���͌��������x���Ă��܂��B
���ꎩ�̂͗ǂ�����b�ł����A����͏]���̃p�e���߂����ł͂Ȃ��A�ڒ��܂�218��219�ƌ������v���_���g���Ă݂܂����B
��i�A�����͎͊v���_�A�͔��p�e�B���i�A�E���͎͊͐ڒ��܁A�͔��̓p�e�Ƃ��܂����B
�ŁA�����ȏ��A�ڒ��܂͎��s�ł����B�g���Ă�����ɗn�܂��������ĔS�x�������Ȃ������̂��g�����̂ł����A�����̐[���ɗ��ꍞ��ōs���Ȃ����Ԃ��������A���ǁA���߂ăp�e���߂����̂����i�ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2,1/2,1/1��3�摜������
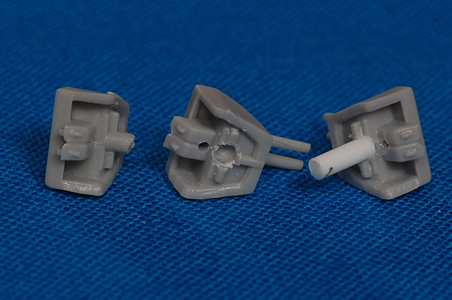
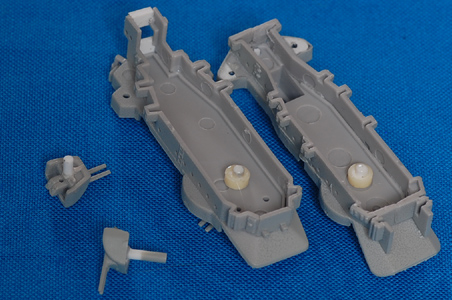
11.
2�Nj��ʂł����A4�D�C�A���S�����ׂ��A�Z���ׁA���邭���l�ɌŒ������Ȃ��ƒE���̊댯��ł��B
�Ȃ̂ŁA���A�G���@�[�O���[����221�Œu�����܂����B
�X�ɁA�E�AB�C����X�C���͓c�{�̃�3mm�̃v���_�����蔲�����E���h�~��U�ߍ��݂܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2,2/1
���Ɏ���2,3���g���~���O
R02/05/22 �W�� �g���C�o�����A��`�p�́A��O���
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
P�Ђ́u�G�X�L���[("Eskimo")�v��]�p���A��O�̎p��3��ލ���Ă݂܂����B
���͂��d�Ԃ��˂����ƁA�{���̐�O��Lnn��Fnn�͔̊ԍ���Z���Ă���A�O�҂͍������A��҂͔������ƍ�������������܂����B
�������̏ꍇ�͔����͑̓h�F�A�������̏ꍇ�͔Z���͑̓h�F�̗l�ɂ������Ȃ����Ȃ��B
�ƌ��������ʐ^�̖������Ȕ��f�Ɋ�Â��A����́A��"F"�ƔZ��AS-7�Łu�x�h�E�B��("Bedouin")�v�A��"F"�Ɣ���TS-81�Łu�K�[�J("Gurkha")�v�A��"L"�Ɣ���TS-81�Łu���z�[�N("Mohawk")�v�̑g�ݍ��킹��3�Ǎ쐬���܂����B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
������u�x�h�E�B���v�A�u�K�[�J�v�A�u���z�[�N�v�ł��B
�u���z�[�N�v�́A�{���o�����Y�����Ԃɑ�����摜�̑S�ĂɁA���lj�푈���̒������\����B�C���ɍs���Ă���A���l�ɁA�Ԕ��̌��F�̑я�ɓh�����܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1

2.
��ƌ��������ƌ���������A�u�x�h�E�B���v�A�u�K�[�J�v�A�u���z�[�N�v�ł��B
���̒������\���A���R�A�����ʐ^�ł͏������ǂ�����Ȃ��B���������ɁA�͎����->��->�Ɛ�->��->�Ԃ�2��ނ̋L�q������������A�����ǂ�����??
��҂�1����������������Ȃ������ׁA�O�҂̏����œh�����܂����B���ƂȂ��Ȃ̂ł����A����A���lj�̗����镧�������������咣����ׂɎ���������͂��ēh�������̂��n�܂�?�ƌ����C�����܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
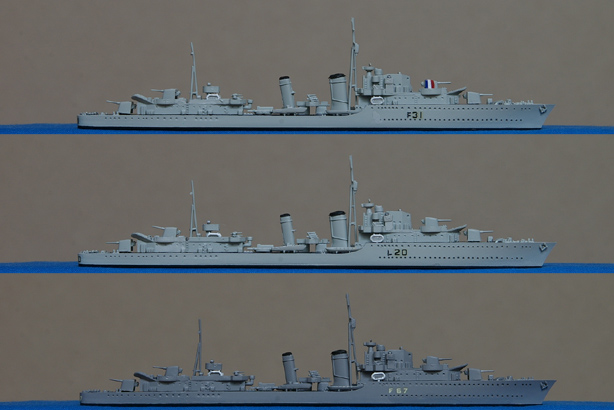
3.
�ォ��u���z�[�N�v�A�u�K�[�J�v�A�u�x�h�E�B���v�ł��B
�͔ԍ��ɂ͍���܂����B�K���ȑ傫���ŁA���A�p�����̎�ނɏ\���]�T�̗L��\�t���������X�����A���Ǎ��p���͓h���ŁA����H22/09/11�`H23/08/30�W���́u���B����q�쒀�́v�̎g�p�c�𗬗p�ł����A������Ə����������E�E�E�B700/700�͏㉺�̌������肬��̍����Ȃ̂ł���ˁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
����I�o�A�œ_������3��������

4.
������ƌ������擪����ƌ������u�x�h�E�B���v�A�u�K�[�J�v�A�u���z�[�N�v�ł��B
��s���A���C����p�ӂ�!!�݂����ȁE�E�E�B���Ŋ�s??���ʒP�c�w�����?���₾���āA�������Ȃ��Ď����ʐς��������B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
4/1
����1�����x�g���~���O

5.
������u�x�h�E�B���v�A�u�K�[�J�v�A�u���z�[�N�v�ł��B
�g�p�h���Ɨ��߂āB�ς�ł���XF-63����3�Nj��ʁAAS-7�́u�x�h�E�B���v�̂݁ATS-81�͑�2�ǁA�E�[�̌��F�͓��R�������W���p�ł��ˁB
�O����͗�̒ʂ�A���~�߂Ŏ��[���͂炵�܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
����1�����x�g���~���O
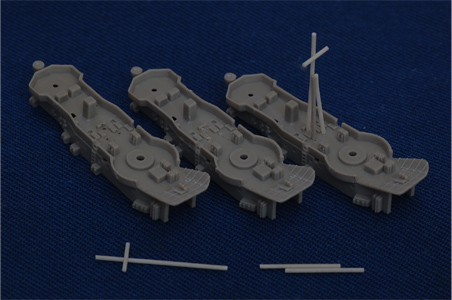
6.
��������́A�������A���H�v�A���ӓ_�����B
�x�[�X�́u�G�X�L���[�v�͐풆�ݒ�ł��B����͒P���Ȗ_���Ȃ̂ŁA����������̒ʂ�O�r�ɂ��˂Ȃ�܂���B
�ƌ������ŁA�㕔��\�̓V�W��ɁA�����珇�ɁA��t�ʒu�̌r���A���E�A��t�݂����ȁE�E�E�B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
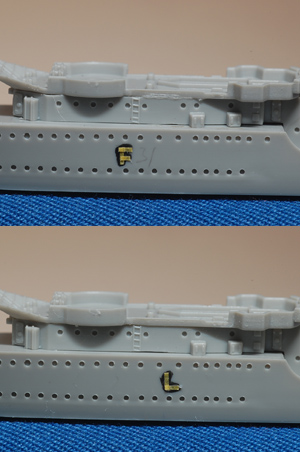
7.
��������"L"��"F"�͓K���ȌГ\�t�������������̂ŁA�����̒ʂ�A�h��->�h�F�핢�őΉ��ł��B
"L"����"F"���̂͂܂��A����ȋ�ɑΉ��o���܂������A���ꂪ"Q"����"R"���������ɂ́E�E�E�B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
����I�o�A�œ_������2��������
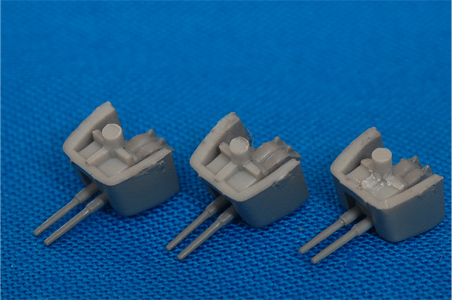
8.
��C���A��]���𒆐S�ɁAT����̐��グ����Ă��܂��B
���͑f�̏�ԁA���͐��グ�����̂ݍ폜�A�E�͍X�ɓ����ɍ�荞���̂ł��B
A�C���́A�f�̏�Ԃł͔w��̔��C�����Ɗ����Ă��܂��A�C�������܂���ł����B�����������邽�߉E�̗l�ɍ��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
R02/04/02 �W�� ���߂Ă�IBG�`1/700 �g���C�R�u�N�����B�A�N("Kujawiak")�v
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
IBG����o�Ă���p�u�n���g("Hunt")�U�v����q�쒀�͂̕ψٓW�J�̒�����A�g���ɑݗ^?���n??����A�g���C�R�Ђ̂܂ܐ��U���I�����u�N�����B�A�N�v���쐬���܂����B�����Ƃ��A�܂�܉p�n���g���Ȃ̂ł����ˁB���R�g���C�R�ƌ����Ă��A��g�����S���҂ō\������Ă��邾���ŁA�p�͑��ɑg�ݍ��܂�Ă�����ł�����B���̂��n���C�ōs�����ł������B�܂��A�Ȍ�̓��^�͐���͐��쉢��ƈ�A��O���E�ɏ��n���ꂽ���̓����L�肩����B
�������i�������Ȃ̂ł����AR01/11/25����W���́w1/700�u�h���b�h�m�[�g("Dreadnought")�v1907�v�H�x�ŋ�킵�����ׂ��L���Ĉ�ؖ������Ă��܂��A�����i�ő�ցB���āA�h���͔����Ɏw��ɐn�����������Ȗ��ʂ��w��ʂ�̗l���œh�����Ă݂܂����B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|
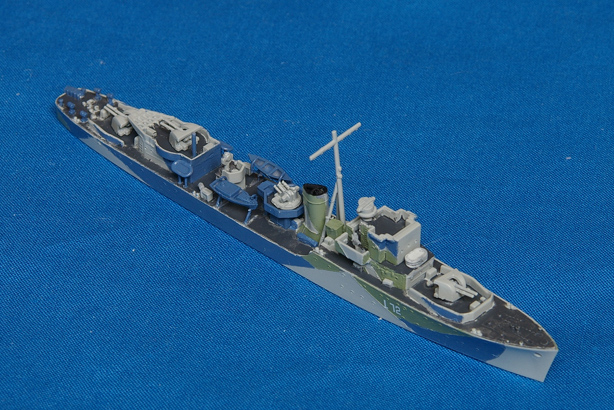
1.
�����́A���ɍׂ��������͗L�������̂́A�T�˕��ʂ��ď��ł��傤���B
�h���̓z���g�ɂ����??�ƌ��������Ȃ�l�Ȍ��F���݂����邢�F���ł̖��ʂł��B
�����Ƃ����ʂ͓h���ē��ɋL�ڂ��ėL��̂ł����A������ɒ��p�̖ʂ͊͋��O�ʂ̂݉��ϔ����Q�Ƃ��܂������A�͋��w�ʂ����͗����ʂ���̐���ł��B�܂����̕ӂ�͊���̑����ꏏ�ł����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
����1,2�����x�g���~���O

2.
��C�͉p�쒀�͂Ƃ��Ă͒�����IJN�쒀��(���^�A�b�^�A���^)�Ɏ����z�u�ł��ˁB
����4�D�C�͍��܂œc�{�u�t�b�h("Hood")�v�A���āu�d�c�v�Ɨ��āA����P�Ѓg���C�o�������쐬����4��ޖڂƂȂ�̂ł����AIBG�Ɓu�d�c�v�͖C���A�C�g�A�C����3���i�ōׂ����Ėʓ|�B�O2�҂�2���i�\���Ŋy�ł����˂��B����́A�����������Ƃ��͖��������̂ł����A�����������āE�E�E
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
������5�����x�Ƀg���~���O
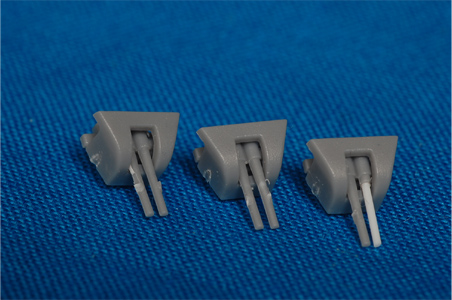
3.
�E�E�E�����Ȃ�܂����B���≽�A1����������`���ɖC�g��܂��Đ�������Ă��܂��܂����B�Ȃ̂ŁAEvergreen��218��(��0.5mm)�ŕ�C�ł��B���Ǝ߂ɂȂ����B
�������A���̂��A�łтт��Ă��܂��A�c���5��ɂ��Ă͐��`�������u�ł��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
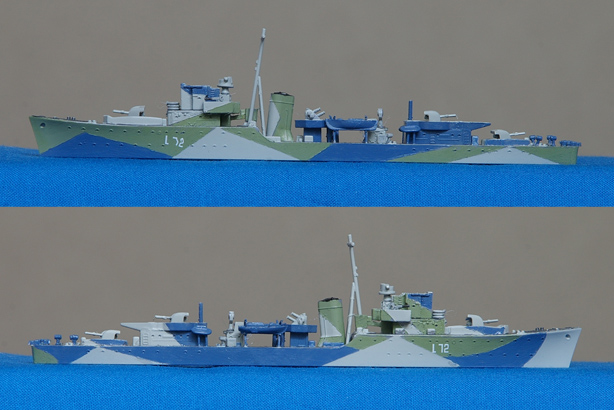
4.
���ʁA����̍��B����Measure 12���̉_�`�ƌ������s��`�ȗl���ł́A���E�����M���őe���r����������h�����Ēi���ł������A����͂���ȋ�œh���핢���Ղ��A�ƌ������A�핢���Ȃ��œh��Ƌ��E�����Ȃ�ւ�ւ�ɂȂ鎖���������ȈׁA�������Ɣ핢���܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
����I�o�̂��̂��������A����1�����x�g���~���O

5.
�g�p�h���ƁB
���͔g�����ł��āA�w��h����"Hataka Hobby"�Ƃ�"Lifecolor"�Ƃ����������������W����B��ɓ����̂͑�ς����B�Ȃ̂ŁA�d�Ԃ�˂����Ĉꕔ�͌݊��\����Ή��F����������A�����p�͂̍���������M��Y�t�̂��̂����ꂱ�ꋙ���Ď��͂̐F���̂���v���镨���E���o������A�Ȃ��Ȃ���ςł����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
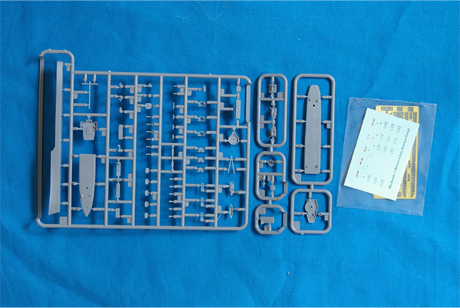
6.
�Ƃ܂�����͐F�X�Ǝ�Ԍ��A�V�K��@�����ꂱ�ꞌ�q����܂����ƌ������V�т܂����ƌ������B�S�̂̕��i�_���͂��ꂾ���Ȃ̂ɂ˂��B
���ʖ����ĕ��ʂɑl�F?�D�F??�n��1�F�Ȃ甼���Ŋ��H�������B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4
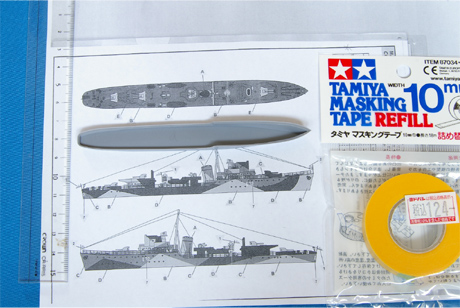
7.
3.�ŋL�q�̒ʂ�A�h���핢���܂��B
����́A�h���ē��}�������ɏk�����ʂ��A�����핢�\���ɌЂœ\��t���A�����ؒf���Ĕ핢���鎖�ɂ��Ď��ŁA�悸���ʂ��B������o���ĉE�̔핢�\���ɓ\��t�����ł��B����ȑ����\���A�ő��ɔ���Ȃ��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
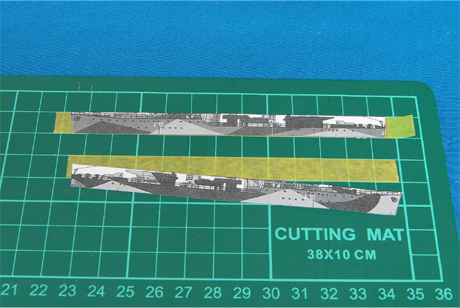
8.
�ƌ������ŁA�����̒ʂ�h���핞�\����\������ɁA��o�����h���ē����X�ɌЕt�����܂��B
�A���A�����ł͈ꗥ1cm���œ\���Ă��܂����A�Еt����Ɋ͑̕���������o���ē\��t���܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
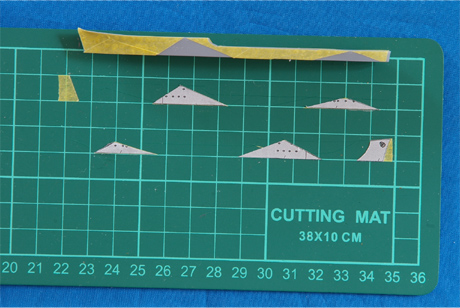
9.
�ƌ������œ\��t���܂����B�����Ă��镔���͂��̌�ATS-81�𐁂��t���镔�ʂł��B
�J�[�\�����摜�ɍڂ���ƉE���摜�ɕς��܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
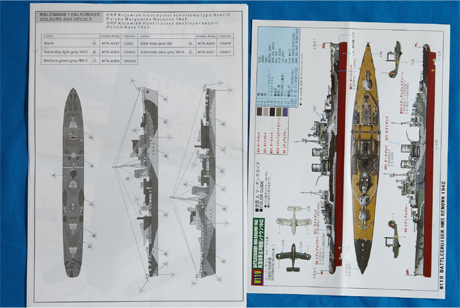
10.
�h�F�w��A�Q�l�ɂ����̂�P�Ђ́u���i�E��("Renown")�v�ł��B
���u�N�����B�A�N�v�A�E�u���i�E���v�ł��B
�J�[�\�����摜�ɍڂ���Ƃǂ̐F���ǂ��Ή����������ꕔ�g�債�܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1

11.
�ł́u���i�E���v�ł́A�e�F�ǂ����Ă��邩??
�ƌ������œh�F�w��}�Ǝg�p�h���ł��B
������13��62�͗����Ɏg�p���A5��B5�ɁA6��35��MS3�Ɏg�p���܂����B
�J�[�\�����摜�ɍڂ����9.�ŋ�����2�F�̒������e���g�傳��܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4
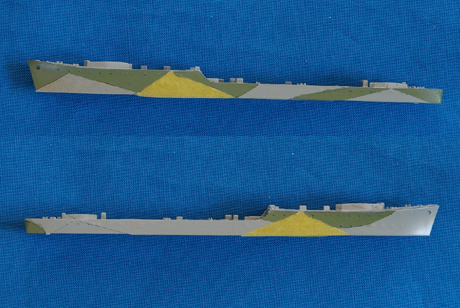
12.
TS-81��h�z����������핢���A�t��MS3�̕����̔핢���O���h��������ł��B
���̌�AMS3�������Ăє핢���AB5��h�����܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
����I�o�̂��̂��������A����1�����x�g���~���O

13.
��������͋������i�̖������̑�ւ��̂̎n���ł��B�܂��A�����͓��i�L�ڂ��閘�������ł����E�E�E
��ւ́A���ڒ��g���@�A���ˉJ�����핢�ē��g���ł��B
�ŁA���ڒ��g���@�͑傫���̓_����쒀�͋��̗]�蕔�i���p�ƍl���Ă����̂ł����A�ӂƁA����4���L��E�E�E���Ď��ɋC�����A���𑵂���ׂɁA����FineMolds���B�ƂȂ�܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/15
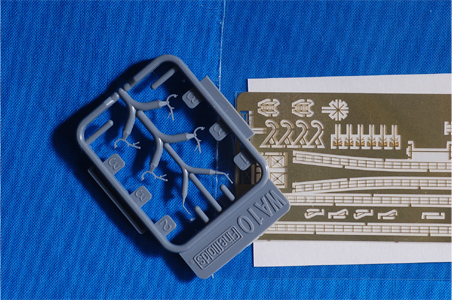
14.
�傫�����r����Ƃ���Ȋ����B�����߂��B�{����IJN�͒������Ȃ̂ł����A�܂�����ȍׂ������͋C�ɂ��Ȃ���!!
����ɂ��Ă��A�����ׂ����̂ɋh�����܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/15
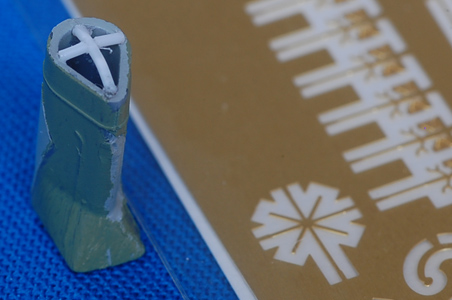
15.
���ˉJ�����핢�ē��g�͂���Ȉz�ŁA��C�C���Ɠ���218�Ԃ����܂��ܐ�o���Ăł��������܂����B
���K�������i�͂����̒ʂ�A�����ɐL�тĂ��܂����A�ł����グ�͎l���ɂ���̂�����t�B�܂��A���F�����X�W��ˁB
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
����3�����x�Ƀg���~���O
R02/03/20�W�� H31�x�������̂��z�{
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�ڏo�x�����ɏ��Ȃ߂ł��B
���ς�炸1/700�͑D����ł��B5���ł��B�����Ԃŏv�H7��7�ǂȂ̂ŁA��o���ł��B�f���Ɋ������B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�悸�͑S�̂��B
������AFV Club�́u�m�b�N�X("Knox")�v�~2�A
�A�I�V�}�u�R�[���E�H�[��("Cornwall")�v�~2�A
DreamModel�́u056/056A��q�́v�ł��B
�u�m�b�N�X("Knox")�v�͋����i�̍Ĕ�?�ē���??�ł��B����H29/8/5����W�����w�u�m�b�N�X�v���ψٓW�J�x�ł���Η��Ղ��Ă���܂��ˁB
�u�R�[���E�H�[���v�͌���łƌ������ŁAWW1����S���쒀�͂������ł��āA�����̏��ׂ�2�������H�ڂɂȂ����ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
�u056/056A��q�́v�A�u��q�́v���ĕ����̏��͂�����̊ȑ̎��Ȃ̂ł����AS-JIS�ł͕\���ł��Ȃ��̂Řa�Ă��܂��BNATO�R�[�h�ł́u�]���^�v�������ł����A60��!!�߂����^�͂̒��Ɂu�]���v�͋��Ȃ��l�ł��B
PENTAX istDs
TAMRON 24mm 1:2.5 01BB
1/4

2.
�u�R�[���E�H�[���v�̒��g�ł��B�ł������ϔ��ł����A��������l�܂��Ă��܂��B
�Ƃ͌������̂́A���Ȃ蕔�i���]�肻���B�Ⴆ��8�D�C�A�C�����ʼn��i�̍��܂�6�A���E�܂�4�A������2�i�ڍ��܂�6�����܂��B���ꂾ���œ��^��4�Ǖ����Ăǁ[��[��??
PENTAX istDs
TAMRON 24mm 1:2.5 01BB
1/4

3.
�u056/056A��q�́v�̒��g�ł��B
�����������ł������g���P�������B�܂��A���͂����1300t�Ƃ̘b�ł�����A�u�������v�Ƒ卷�Ȃ��A����Ⴛ������˂��Ċ����ł��B
�Ȃ̂ɁA�w���z�́u�R�[���E�H�[���v��1.5�{!!
�u�R�[���E�H�[���v�v�H�Ƃ�100�N�߂��J���Ă��܂�����A���̊Ԃ̊����̌o�ϋ��Q��푈�ɂ��ʉ݉����ƌ���͒��̍��l���m��܂��B
�E�E�E���Ĉ�
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4

4.
���������ł̏v�H���Ɖ��ϔ���Ŕ�r���Č��܂����B���B�A�E��v�H�ł��ˁB���\�����l�ȍ����ł��B
���[��A�ǐ��Ŕ�r����Əo���Ȃ̂�����ǁA���͑卷����??
�Ȃ�ƁA�̐ςŔ�ׂČ��܂�����A���B�� 0.0107���āA�v�H�� 0.0071���ĂŁA�������A�v�H�ʂ̕�������������Ȃ����B���[�ށA�v�������Ȃ������E�E�E�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/8
R02/02/10 �W�� ���^�쒀�͂̍����`�V���X("Sims")����
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���e�͍��B���C�R�́u�V���X�v���ł��B
�^�~��1/700�́u�n���}��("Hammann")�v�����ɁA�O��́u���t�v�^�Ɠ��l��3�Ǎ쐬���܂����B
�ꉞ�A���̂���ł̍쐬�͂���ŏI���ł��B�p�쒀�͂�u�V���X�v���ȑO�̕ċ쒀�͂ł́A����lj�����ɓ������Ĕ��ˊǂ����낵����͗ǂ�����̂ł����A��Ԋ��ɕ������̖�肩���K�͉����Ƃ��̗�͂��܂茩���Ȃ��̂ł���ˁB�B��A�u�|�[�^�[("Porter")�v���͊ǂ͉��낳�Ȃ����̂́A�͗e���傫���ς�苻���[���̂ł����A�f�ނ����I���������ׁA�ȒP�ɂ͎���o���܂���B�܂��A�ɏ����Ɖ��̎���ɂ���Ă͋C�������Ē��B���āA������ƑO���P�邩������܂��B
f16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
������A
�T.�������s�ǂ̏v�H���u�V���X�v
�U.���������P��A�X�Ɏ�������������f�g�́u�n���}���v
�V.��������́u�}�X�e�B��("Mustin")�v
�ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4
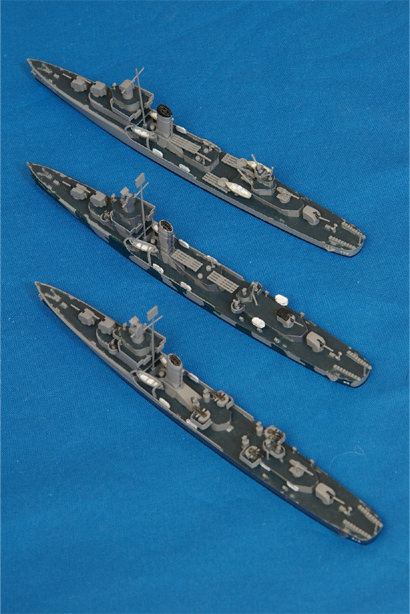
2.
��ƌ��������ƌ���������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�O��u���t�v�^�҂ł́A���X�e����ݒ�Œ���Ă����̂ŁA���̒ʂ�ɑg�݂܂������A����͇U��ɘM���ćT�ƇV���ł����グ�܂����B
���A�V�ɂ��ẮA�d�ԏ�̕s�N���Ȏʐ^����A�܁A����Ȋ���??�Ɩϑz�����ڂł��āA�^�ɎȂ��l�ɂ��肢���܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2

3.
�ォ��T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�T�ƇV�̊W�AH31/1/18����W�����u1938(�`41)�N�^���B���쒀�͘A����i�v��3.�ƁA�Ƃ��Ă����͋C�����Ă܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4
�������3��������

4.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�g�p�h���Ɨ��߂āB
��̔@���A�O���͍����������ŁA���[���͊O���܂��B
�e�C�������͂��邭����܂��B�܂��A�T�ƇV�͊͋��V�W�̎ˌ��w�����u���Œ������Ă��܂���B�U���E�E�E�Ǝv�����̂ł����A���ʓh���ƕ��i�����̊W����肭�Ȃ��A�f�O���܂����B�{���A��]���Ȃ��x���������ˌ��w�����u�{�̂ƈ�̂̕��i�ɂȂ��Ă��āA�Ǝx���̖��ʕ������Ȏ��ɂȂ����Ⴄ��ł���ˁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
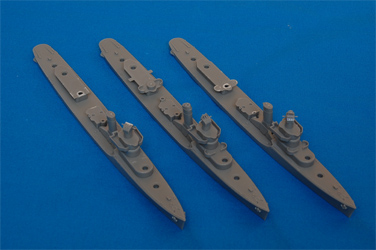
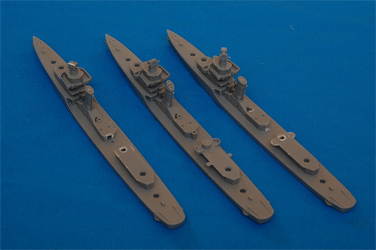
5.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
��������́A�쐬�ߒ��������B
�悸�́A�T�ƇV�̕s�v������藣���ł��B�����Ȃ��Ă��镔�����藣�������ʂł��B
�T��2�Ԋǂ̎x���A�㕔��\�̒T�Ɠ����12.7mm�@�e�����B
�V�͘A�ǎx���S���A�㕔��\�̒T�Ɠ����12.7mm�@�e���̋��ǂ��B��ɂȂ���40mm�A���@�e���ڂ�Ȃ��̂ŋ@�e���܂�܂���X�ɐ藣���H�ڂɂȂ�܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
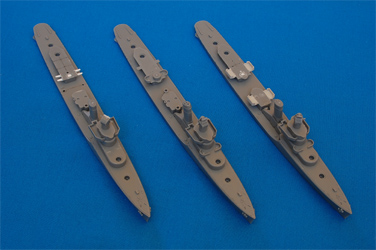
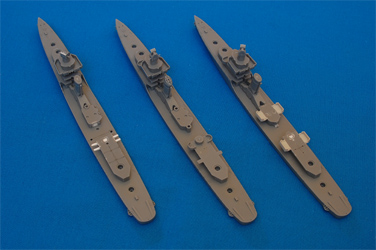
6.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�T�͌㕔��\�ɓ��Β��𓋍ڂ���ׂ̉�����K���ȃv���_�Őݒu�A�V�ɂ�P�Ђ̗]�蕔�i���p�ŋ@�e����ݒu���܂����B
�܂��A�㕔��\�ɐςޒT�Ɠ���ׂ̈ɁA�ʒu�����߂�r����������A��t�ē��p�Ő��E�����肵�܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1,1/1

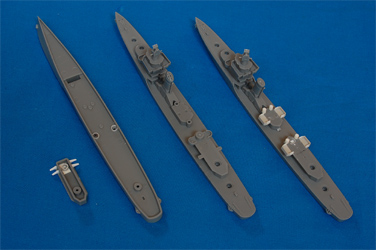
7.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�T�͗����̔��ː������邭���d�|��������Ɏd���݂܂����B
�V��2mm���������A�v���_��40mm�@�e�p�̎ˌ��w�����u�p�x����ݒu���܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
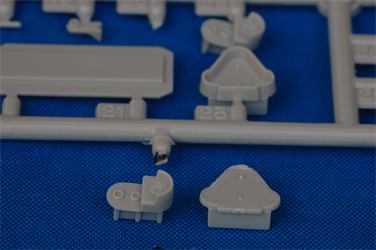
8.
�u�V���X�v�̌㕔��\�ɍڂ���T�Ɠ���́AP�Ђ̃x���\��/���o���A�̂��̂𗬗p�ł��B����_�Ƃ��ẮA���i���Œ�̋��ǂł͂Ȃ��A����ۂ��̂ŁA���ǂ�藣���܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4

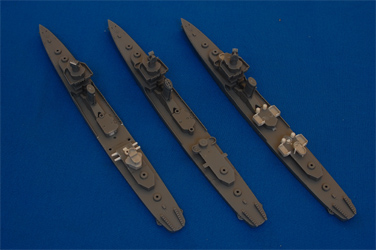
9.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�T�A�V�̌㕔��\�ɒT�Ɠ�����ڂ��A�V��52�Ԃ̒���ɁA��͂�P�Ђ̃x���\��/���o���A�E�O���[�u�X/�u���X�g�����痬�p�����@�e����ݒu���܂����B
�V�̒T�Ɠ���͂��Ȃ�������ł��B�ʐ^�ɂ���ẮA�x���ł͂Ȃ��͂��ꂽ�b���̗l�ɂ�������̂ł����A�T�̂��ꂪ�x���\���E�E�E�A���A���i�Ƃ��Ă͂��ꂪ�\������Ă��Ȃ��B8�̍����̕��i�̎��E�E�E�Ȃ̂ŁA���킹�Ă݂܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
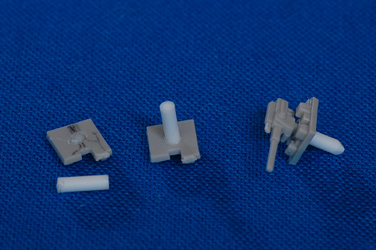
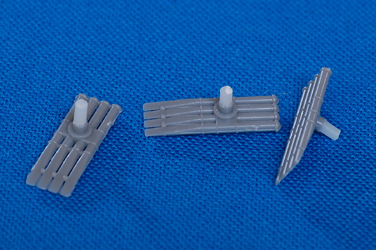
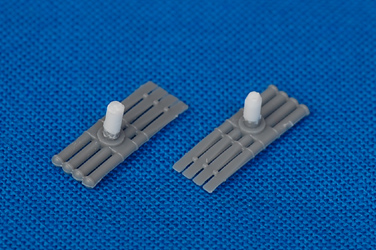
10.
�A�ǂ�P�З]�蕔�i����̗��p��C�ɐ���p�̎x�������t���܂��B
��C�Ɓu�V���X�v�̗����̘A�ǂ̓�1.2mm�A�u�V���X�v�Ɓu�n���}���v�̎������̘A�ǂ̓�1mm�̃v���_�Ŏx����݂��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1,2/1,1/2
���������2/3���x�Ƀg���~���O


11.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�C���������ڂ��Ă���AAS-7 Nutral gray���ǂ��ƁB
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
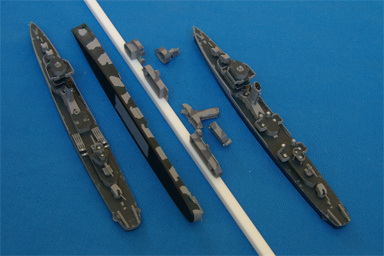
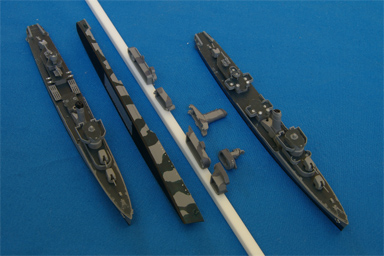
12.
������T.�u�V���X�v�A�U.�u�n���}���v�A�V.�u�}�X�e�B���v�ł��B
�b�A�w���XF-50��XF-9�̒��F�ł����A�u�t���b�`���[�v�����̊��v�H���ɍ��킹��XF-50�œh�����܂����B
�U�́A���ʂɂƂ��Ă��ʓ|�Ȗ��דh�����B������͎w��̒ʂ��XF-17,24�œh�����܂����B�A���A��C�͖����B����˂��A�ċ쒀�́A��C�ƘA�ǂ̏�ʁA�{���b�Ɠ����h���Ȃ̂ł����A�ォ�猩�����̐F����ς������āA���v�H�͑��ʂƓ����F�ɂ��Ă����ł���B�ŁA�����ő��ʖ��ʂ��̗p����ƁA�V�W�������ǂ��������Y�܂����Ȃ��Ă��܂��̂Ŗ������Ă��܂��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
R02/01/01�W�� ���^�쒀�͂̍����`���t�^��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���đ�U���ȕ\��ł��傤�E�E�E�B
�����h���C�R�R�k���ł́A���ꖘ������肾�����쒀�͂ɂ��āA�r���ʂł̏���ƁA��^(�������\)�͂̔䗦��ݒ肳��܂����B
���Ɉ˂��ẮA���̐����ɂ��S��炸�]�O�ɏ��������\�����߁A�������˂���̖����Ȑv�����肵�܂������A���ꂪ�M��A�����������B�������炽��ŖC���������܂��܍���Ă܂Ƃ��ɕ����Ă���l�ɉ��C���܂����B
���������Đ������ɔ������쒀�͒B�ł����A�W���J������ΐ���퓬����̂ɂȂ��Ă��܂��A���Ǐo�Ԃ����Ȃ��C���������X�ɍ���đΉ�����H�ڂɁB���̓w�͉͂���������??���ăI�`���t������ł��B
����Ȏc�O�Ȗ��B�̕ϑJ��1/700�ōČ����Ă݂悤�ƌ������ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�v�H�����̂�3�ǂł��B
�����畜�������P���̋����́u���t�v(P)�A�������s�ǂ̏v�H���u�q���v(A)�A���������u�����v(A)�ł��B(A)�̓A�I�V�}�A(P)�̓s�b�g���[�h�ł��B
�\��ł́A���ꂱ��\�����������܂������A�q�N�ɍ��킹�āu�q���v���쐬���A���łɋ����͂��u���t�v�Ȃ̂ŁA���x�N�n�ɔ�I����̂ɓK�������A�Ƃ���Ȏ����B��Ă����肵�܂��B�u�q���v���Č��t���͎̂q�N�ɂ͊W�����̂ł����A�܂��ׂ������͋C�ɂ��Ȃ��B
1/2

2.
��ƌ��������ƌ���������u���t�v�A�u�q���v�A�u�����v�ł��B
3�ǂƂ��A�T�˂��������Ƒg�ݏオ��܂������A
1.�u���t�v�̑O���A�B��?�g�[??���ˁA�������ڒ�������
2.�u�q���v�̋@�e���̑����b�ɓ͂���
3.�u�����v�͔̊��P���@�e�g���ē��������A�K���ɐݒu��������ƂƊ���
4.�͎�ɂЂ��L��
�ƌ�����������x�Ⴕ�܂����B�܂��A4�͂���܂�ł����A(A)��2�ǂ͒��������������Ȃ��̂ŕ��u������܂���ł����B
1/1

3.
�ォ��u�q���v�A�u���t�v�A�u�����v�ł��B
�u���t�v�Ɓu�q���v�̏������t�ɂ��A�͌^�̕ϑJ���ォ�牺�ɏ��������������܂������A��������ƁA�u�q���v�̒P���C����3�Ԋǂ��AWW2���̌����ꂽ���^��b�A���^���Ɣ�ׂĕςȂ̂���ڗđR�ł��B
1/2
����I�o��3�������

4.
��̒ʂ�A�O����͉����߂Ŏ��O���Ď��[���܂��B
����́A�͑̂Ɗ͋��A���ˁA��C�A�A�ǂƌ������ӂ�����g���Ă���ǂ���TS-66���Ԃ��܂��A�������ɓ��ڒ���g�����u�A�@�e���ׁ̍X����������LP-12�ŁE�E�E�Ƃ����̂ł����A����2�h���A�������C�R�H���F�ƌ����Ă���̂Ɍ��\�قȂ�A�������܂����B
�ŐV�̒m���A�����f���Ă����A�P�Ƀ��b�g�̖�肩����܂��A�������b�J�[�œ����F��搂��Ă�����獇�킹�Ă�`�^�~�����`��B
1/1
R01/11/25�W�� 1/700�u�h���b�h�m�[�g("Dreadnought")�v1907�v�H
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
H30/11/11����W���́uWWI�x��S���N�L�O�`�쒀��Admiralty V���v�ŋL�ڂ��܂������A�ꕔ���i���s���s�����������̂ŁA�摗��ɂȂ��Ă���܂����B�Q�������Ɏ���AWWI�x��100���N�E�E�E����1�N��2�T�ԉ߂��Ă̏v�H�ł��B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
���̐��i�A�o���Ђ��������̕s�s���͖w�ǖ��������̂ł����A�T�Ɠ�1�s���Ƃ��A���ڒ��̓h�F�w��ƈē��}�̐F�����Ⴄ�Ƃ��A���t���w���������ɂ��L�ڂ��Ă��Ȃ��̂ɉ����̊Ԃɂ����t�����Ă���Ƃ��A�����ɂ���ق���_���U������Y�܂���܂����B
2/1

2.
�O����̌����菊?�̉����́A�w��ł͊͑̂Ɠ���Ȃ̂ł����A������Ĕ��z�����??���ĔF���Ŕ������܂����B
���ڒ��A�������1.�ł��w�E���܂������A���̏�ʁA�w���Mr.311 ������O���[FS36622�܂���XF-55�f�b�L�^���B���ꂩ�Ȃ�Ⴄ��ł����A�ǁ[��[��??
�܂��A�h�F�ē��}�̐F���͔��Ɩ؍b�F�������肷��̂ŁA�f�b�L�^���̕����߂��̂��낤�B�܂��A���ƍb�ȊO�͂ǂ��ɂ����n���ɂ��������Ȃ��B�Ƃ܂�����Ȗ�ŁA�������������A�ڌ����ňē��}���ɊĂ݂܂����B
2/1
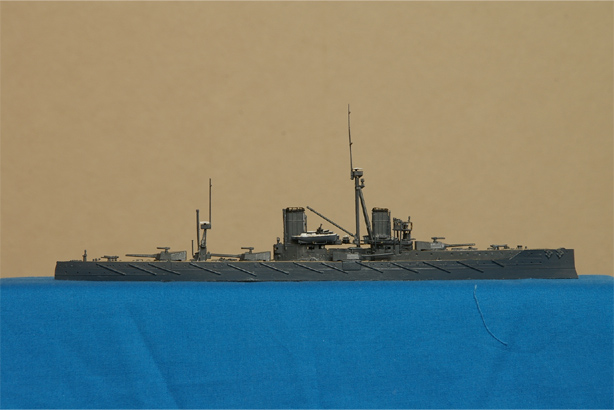
3.
�͋��\�����Ⓥ�ڒ��b�̈ꕔ���H���������i�ō\������Ă��܂��āA���ꂪ�₽��ׂ��B��o�����ɊȒP�ɋȂ����Ă���Ă��܂��A�����i�����ƍ���Ȃ�����Ȃ��B
����A���l�d�g�݂̐��쎞�͎��Ԃ��|�����Ă��v���_���ɒu�����������������ł��B
2/1

4.
�g�p�h���ƈꏏ�ɁB�O�����i�����ƌ���S�̂͗�̔@�������߂ŁB
�͎͑̂w��ʂ�Mr.333�ł����A���[��A���Ȃ�Z���ł��˂��B�莝���v�H�ς݂̉p�͂ƕ��ׂ�Ƃ��Ȃ�ِF�Ɍ����鎖�ł��傤�B
1/1
R01/10/31�W�� �ϊ͎�
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
700/700�̊C���ϊ͎��͑䕗�łۂ����܂������A�䂪�{�I�̊e���C�R�͈��������ϊ͎����s�ł��B
����́A4��4��4���O�̒���4�����B����ɂďI���ł��B����`���ׂ�̑�ςł����B
PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�O����1�����N�_�E���A��4�ʁA���ė������B����!! 135115t
12�`5�ʖ��Ɠ�����p�A�œ_�����ŎB�e���Ă����ł͂Ȃ��̂ŁA�P���ɔ�r���Ă��������͖����̂ł����A����ɂ��Ă����Ƃ�������l�܂��Ă��鎖�ł��傤�B
8/1
f16

2.
������1�����N�A�b�v�A��3�ʁA�ƈ��!! 187890t
���ʂ�1�i�オ���������ł����A��A��WW1���݂̏v�H�ň�C��150kt�������đ���i�ł��B
8/1
f16

3.
�O��ƕς�炸�A��2�ʁA���{��!! 210079t
�ƕĂƔ�ׂđ�^�͂����Ȃ����ׂōX�ɂ�������ł��B����Ŏ��́u�H���v�Ɓu�v�~�v���s���s���œ����Ă��Ȃ��E�E�E�B
8/1
f16

4.
�����A���ʂ�!!�A�O��ɑ����ĉp�g����!! 251139t
����`�A�A�e�ł��B�ƈ�Ƌ���WW1���݂ő������A���{��20kt���������̂�40kt���ɓ˂������܂����B
4/1
f16
|
|
|
��
|
|
|
|
��
|
��
|
��
|
| ��
|
�p�g��
|
����
|
����
|
����
|
| ���{
|
�h��
|
�h��
|
|
| �ƈ�
|
�h�R
|
|
|
5.
����������\������Ă݂܂����B���܂�t�]���N���Ȃ������ł��B
�p��SSM��8�����������Ȃ��ł����A�B��q�͂�����_�ƁA����C��͐V����͏���5�ǂ͈��|�I�ł��B
����SSM48������D�ł��B�����A�p�̓A�X�^�[64���A�V�[�_�[�g100���Ō}�����܂��̂ŁA�ʗp�������ɂ���܂���B�t�ɁA�ƕĂ͖w��SAM���ڊ͂����Ȃ��ׁA�˓I��ԁB
�ƕĂ͂ǂ����SSM��SAM�̎蔖�Ȃ͎̂��Ă���̂ł����A�Ƃ��₽���^�C��͂��������ł������ȕҐ��Ȃ̂ɑ��āA�Ă͎��������������܂�ł��Ēލ������Ă��܂��B�Ƃ��C��Ŏn�����悤�Ƃ��钆�A�Ă̐������P��ژ_�ށE�E�E�݂����ȋ�z�����Ă���͂���Ŋy�����E�E�E�B
�Ƃ܂��A����Ȃ���ȂŊϊ͎��I���ł��B����͂��āA�ǂ�ȏ��ʂɂȂ��Ă���ł��傤���B
R01/10/06�W�� �ϊ͎�
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
700/700�̐��E�ł�4�N�U��ɊC���ϊ͎��T�Ԃł��B�ŁA�O������{���܂�����������ّ�{�I�������n�Ƃ��Ă���1/700�̂�����ϊ͎������s���Ă݂܂����B(��)
�O�l���ʂƂ��Ă݂܂����B�O��͋K�͂̑傫�������ł������A����͉��ʂ���B�����̉��y�ԑg�̗l�ɁB
�����A�ǐ��������������Ă��܂��B�K�͂�E�Ƌ��Z�Ƃ��̋��㕗�Ɍ����ƁA4��4��4���O�Ƃł��Ȃ�܂����B����͉��ʂ�4���4���O���B
|

1.
��i�A��12�ʏ��o��A��������!!5100t�B������3�����N�_�E����11�ʁA�ɑ�������!!5360t�B
���i�A2�����N�_�E����10�ʁA���lj��!!6047t�B������1�����N�_�E����9�ʁA����������!6277t�B
�ƌ������ŁA4���O�ł��B���̒��ł�SSM��8�����ʼn��ʂ̕������Ȃ�L���ł��傤���B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
ISO200
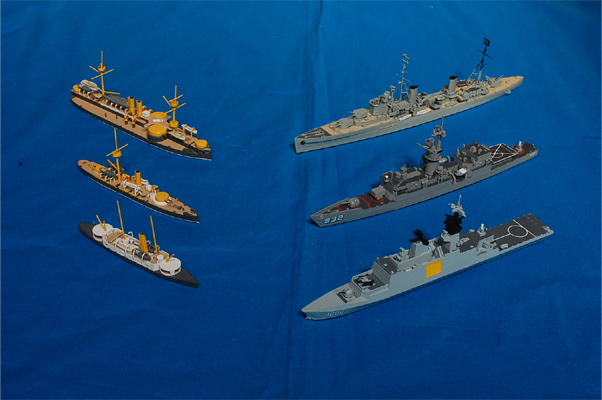
2.
���������4��ł��B
���A2�����N�_�E����8�ʁA����!! 10879t�B�E�A���o���7�ʁA���ؖ�����!! 12747t�B
���Č������A����A�Ⴄ���Ȃ�??
���[��A�Y�܂����ł��˂��B�嗤���̊͒�������҂��Őς�ł���܂�����A����炪�v�H�����ꍇ�A��k�ƈꏏ�ɂ͏o���Ȃ��ł���ˁA��퍑�ł�����B�܂��A���ؖ����������v���őœ|���Ă����Ȃ̂ŁA�p�����ł͂�����̂́A���[��E�E�E���Ċ����ŁA��芸��������͕ʂƂ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
f16
ISO200

3.
���A1�����N�_�E����6�ʁA�h�A/�I������!! 17520t�B�E�A���o���5�ʁA�ґ���/�^�嗘��!! 19698t�B
���݂ɁA�����100kt�ȏ���u���v�A10kt�ȏ�100kt�������u��v�A10kt�������u���O�v�Ƃ��܂����B�܂��A���܂��ܑΐ�(ln����Ȃ���log�̕���)�݂����Ȋ����ŋ敪�����Ă݂��炵������ƍs�����݂����Ȋ����ŁA�ꎞ�I�Ȓ�`�ł����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
ISO200
|
|
|
��
|
|
|
|
��
|
��
|
��
|
��
|
��
|
��
|
�h
|
| ��
|
�ґ���/�^�嗘
|
���s
|
�h��
|
�h��
|
�ɔs
|
����
|
���s
|
���s
|
| �h�A/�I����
|
�h��
|
����
|
����
|
����
|
����
|
�h��
|
|
| ���ؖ���
|
�ɔs
|
����
|
����
|
�h��
|
����
|
|
|
| ��
|
���s
|
�ɔs
|
�ɔs
|
���s
|
|
|
|
| ��������
|
�h�R
|
�h��
|
�h��
|
|
|
|
|
| ���lj�
|
�ɔs
|
�ɔs
|
|
|
|
|
|
| �ɑ�����
|
���s
|
|
|
|
|
|
|
4.
9���ŋ{�d���𗣂�A�ɁB�Ȃ̂ŁE�E�E�ƌ�����ł������ł����A���ɏ���Đ���\������Č��܂����B�u��v���猩�āu�ށv�ɏ��Ă邩�s���邩�ł��B�h�A/�I�����͑S���D���A���͑S�s�ł��B
�܂��A4��4���O�ƕ����܂�������ǁA��r�I��ʂ̚�/�^�����킵�Ă���A�ʼn��ʂ̕����������Ă���ӂ�A�����̐V�����A����SSM�̗L�����傫���e�����邾�낤�Ǝv������ł��B
�����Ȃ̂�SSM�͖��������DDG��FFG���܂߂Ă��鐼�A���ŁA���镧�A�䂪4���Â���SSM�����ĂȂ��̂ŁA�����̌̎���������ŁA���X�����ł��B����́A�ǔ��d�T��2��̍���1��̐��Ŕ����ɕ]����ς��Ă݂܂����B
| R01/08/28�W��
|
�������ׂ�����
|
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
|
�y�D�~�ĉp�z�ĉp�̋D�D��~���鎖�B�]���Ĕ��B
|
�ƌ������ŁA1���������ł����AH31�x�㔼���̐ς݂��B
���ς�炸1/700�̊͑D�ł��B�v���U��ɑ�ʒ��B�ƂȂ��Ă��܂��A�ώZ���������܂����B���������̂��B
���Y���ԂŊ��H�͋쒀�́~2�A�y���~1�A��́~2�ŁA�������쒀�͂����r�����i�Ȃ̂Ŕ��������Ă��炸�A���Ȃ�̓����ƂȂ��Ă��܂��܂����B�����B
|

1.
�悸�͑S�́B
����āA�c��̉E2��ƌ�����1��ƌ������A1.5��ƌ������A�p�ł��B
�Ă͑S�čݗ������i�ŁA�u�����@���A�v�Ɓu�����Z���v�͒��Âł��B
�p��3/4���V�K�J�����i�ł��B
��O�̂����Ⴒ����͉���?�ƌ�����A���r�����i�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200
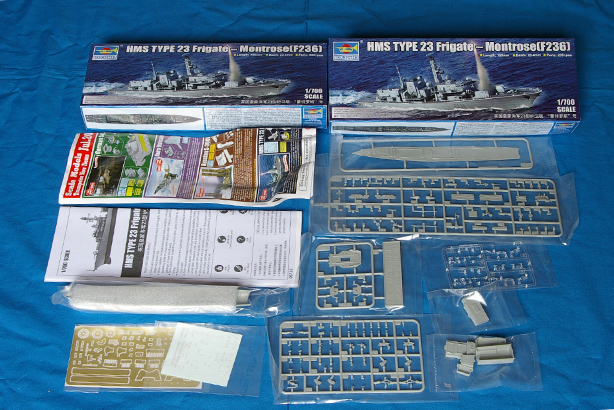
2.
��������͐��p���̐V���i���ȒP�Ɍ�Љ�B
�悸�̓g���y��23�^�t���Q�C�g�ł��B�����̒ʂ�2�ǒ��B�B����2,3�ǒlj�������肾�����̂ł����A�S�D�̂�m�㉻����ӂ���݂��L���đ�ς����Ȃ̂ł���őł��~�߂ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

3.
�A�I�V�}�̍��u�m�[�t�H�[�N�v�ƉE�u�h�[�Z�b�g�V���[�v�ł��B
���߂Ă̊��I�ɂ��L�ڂ��܂������A��҂͐��@�ԈႦ�Ă��āA����ᒲ�B�Ώۂɓ���Ȃ��ȁE�E�E�Ǝv���Ă����̂ł����A�O�҂��C���łƂ��Ĕ������₪�����B�Ƃ���ƁA��҂����e�C�N�Ƃ������Ă����������������B�Ȃ�A��r���������]�p�����ׂ̈Ɍ��s�ł̌�҂����B���邩�E�E�E�ƂȂ�܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
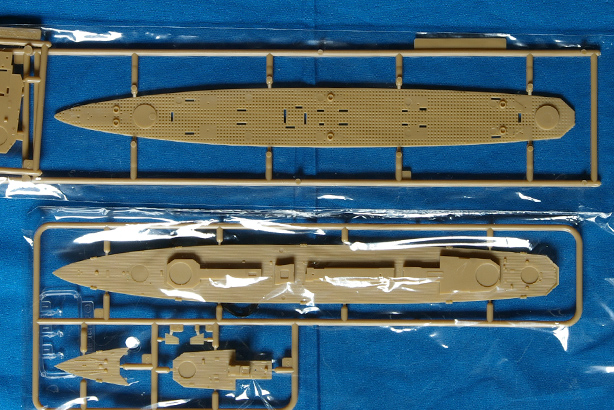
4.
���̐��@�A�܂��{���͊͑̂��r����Ηǂ��̂ł��傤���A�J�����Ȃ��Ɩ����Ȃ̂ōb���Ŕ�ׂĂ݂܂����B��u�m�[�t�H�[�N�v�Ɖ��u�h�[�Z�b�g�V���[�v�ł��B
�܂��A1/700��1/730���x�̍��Ȃ̂�5%���x�̍������������Ȃ���ŁA�������ĕ��ׂČ��Ă�������E�E�E���Ċ����ł��傤���ˁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
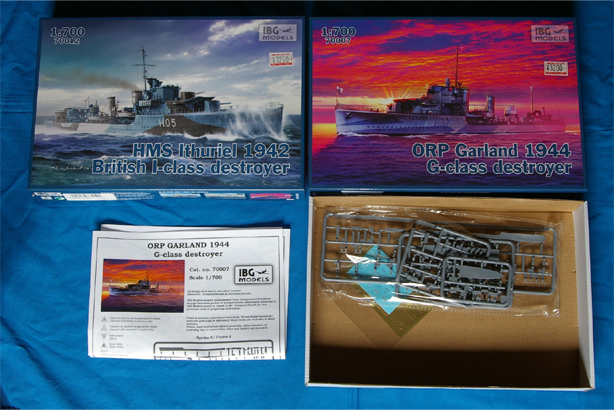
5.
IGB��I����G���ł��B
��芸����G�����J�����܂������A���[��A���2�`���ɔ�ׂĔ��̒��������������B�����\3200�����B���������B�̃^�~��E����2�ǂ�\2K�ȉ��Ȃ̂ł����E�E�E�B
G���͔g�����łȂ����A���֑ݗ^�A���n���AI���͓y�C�R�łƂ��ψِ��ŗV�ׂ�̂Ő��B���������Ȃ̂ł����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
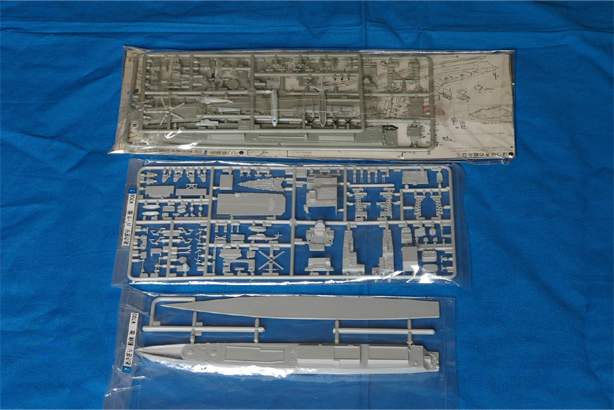
6.
�Ō�����r�����i�B
������͕ĉp�ł͂Ȃ��A��u�䂫�v�ƒ����u����v�ł��ˁB
�O�҂̓A�L�o����ƌ������A���L��?�E�E�E�̃��I�i���h�̂ǂꂩ�ŁA��҂�P�Ђ̔N2�x�����r�i�����s�ɂĒ��B�ł��B�u����v�͔�s�b�̐��\�t�����ǂ����B���邩�A�����Y�ݏ��ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
R01/07/29�W�� ���ؖ����C�R���m�́u�d�c�v
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
Flyhawk�́u�I�[����("AURORA")1945�v��2���ɂ��Ă���܂��āA���^�͗p�ɁE�E�E�Ǝv���Ă�����A���̓��^�͂́u�y�l���s�v�͏o�Ă��܂������A���p�C���قȂ�u�K���e�A�v���o���ƁB���ች��u�K���e�A�v�̔������Łu�A���V���[�U�v���o��̂��낤�B�����͏o�Ȃ��Ă��u�K���e�A�v���������������������낤�B�ƌ�������1���͔��Η]��ƌ������A�s�ǍɂƉ����Ă��܂����B
�ƌ����A��������ROC�ɈڐЂ�����́u�d�c�v�Ƃ��Ă��������Ă��܂��̂ŁA�Ȃ��1���͂�����ɁE�E�E�Ɣ��z����͎̂��R�ȏ����ƁB���R����Ȃ��̂͐�Ɂu�d�c�v�Ƃ��Ē��H�A�v�H�����Ă��܂������ł��傤���B�Ƃ܂�����Ȗ�Łu�d�c�v�v�H�ł��B
|

1.
����A�u�d�c�v�Ƃ��Ē���ł����̂́A�d�ԏ�őg���ē������������傫���ł��B���̌��ʁA�茳�́u�I�[�����v�̈ē��}�Ɠˍ������A����_���E���o���܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/30
f16
ISO200

2.
�\���I�ȑ���_�́A
A.�͋��O�̘E�\���̗L��
B.��2���˒���̒T�Ɠ��L��
C.�O���̌��\��
D.���p�C�b��(�X�I���̂ł�)��̒e��?�̐��Ɣz�u
E.�~�����̐��Ɣz�u
�ƌ��������ł��傤��?
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/15
f16
ISO200

3.
��L��5���̓��AA�`C�ɂ��Ă͍H���팸�̕����E�E�E�g�ݗ��ĂȂ��A����Ȃ��E�E�E�Ȃ̂Řb�͊ȒP�ł����BD�͈ꉞ�A��Ԍ��|���čX�V?�ύX??�����̂ł����A���̖w�ǂ��V�F���^�[�b��?�̉��ɉB��Ă��܂��ƌ����̂��炭�ŁA�قڈӖ�������܂���ł����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/8
f16
ISO200

4.
�g�p�h���ł��B
�\���Ƃ͕ʂɁA�h�F�ɈႢ������܂����B��͑̂�Mr.��338��31��6:4�Œ��F����ƁB���ꂪ�����̈�i��̕r�̒��g�ł��B
�����ȏ��A���F��ƒ����h�������A����AMr.��300�ԑ�̉����Œu���ł��Ȃ������̂�??�ƍ�����R�B���������\�]�点�Ă��܂��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/15
f16
ISO200
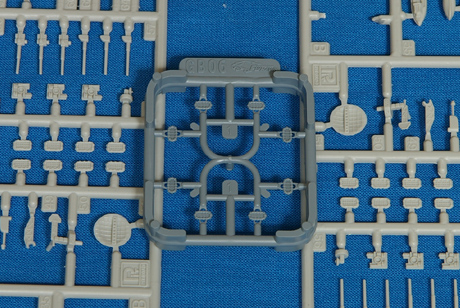
5.
��������́A�ׂ������������B
2.�Ŋ��q�̋~�����A���X���K���i�ł�8�Ȃ̂ł����A12�K�v�ɂȂ�B�ŁA���̊e��̗]�蕔�i�Ƃ͒����̍ז������傫���Ⴄ���߁A4�𑼂��痬�p�lj��ł͂Ȃ��A�S�Ēu�����Ƃ��܂����B
�������A���K���i�A�����̃J�[�\���I���Ŕw�i�F���ω����镔�������p�������̂ŁA���p����P�Ђ�E15�ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
����2/3�Ƀg���~���O
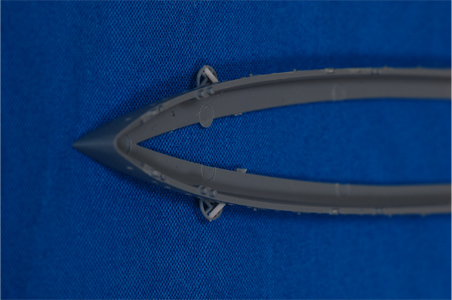
6.
�͔��̃X�N�����[�h��ށA���Ȃ̂ł���ˁB�ǂ��ɂ��ۂ���ƍs�������Ȃ̂ŁA��0.6mm�̃v���_�ŏ���ɒ���o���x����ݒu���鎖�Ƃ��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16
ISO200
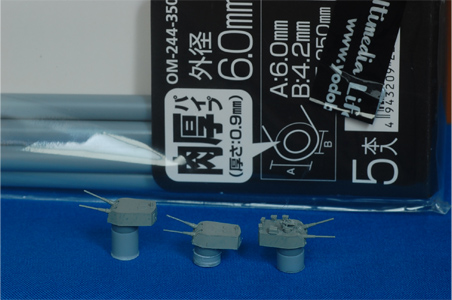
7.
��C���A�ڒ����Ȃ������ō쐬���܂������A����܂��ǂ��ɂ��ȒP�ɂۂ���ƍs�������ŁA�܂��傫������C���t���ł��傤���A�ꉞ�E���h�~�ׁ̈AWAVE��6mm�v���ǂʼn����������܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16
ISO200
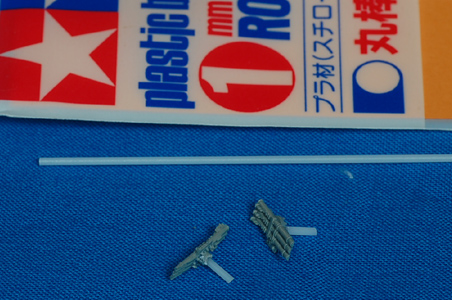
8.
���ː������l��1mm�v���_�ŐS�_�Ƃ��A����\�ɂ���Ƌ��ɁA�E���h�~�Ƃ��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
ISO200
R01/6/21�W�� Z��ԂƂȂ��S���N
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�������̓����̐l�X�́A�C��ɍۂ��āu�g���M��z���v�M����s��4��f���A��肭�s��������ȊO(2��ڂ͐헪�I�Ɏ��s�ƔF�����Ă���܂�)�͌����Ɏ��O?������������??���Ă���l�ł����A�n���̔��Α��̑嗤�̐l�X���S�N�O�A�ؔ������ǖʂŌf���������M�����͊o���Ă���̂ł��傤��?
�ƌ�����ŕS���N�ł��B�����ICM��1/700�u�P�[�j�q("Koenig")�v����́A���̋����͂�2�Ԋ͂́u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g("Grosser Kurfurst")�v���B
�E�E�E���āA�܂�WWI���݂̕S���N??����܂��A���ɂ���ł��I���ł���B
����ɂ��Ă��AShift-JIS�A�L���������͂���Ȃɂ��������`����Ă���̂ɁA���̂ɃG�X�c�F�b�g�Ƃ��E�����E�g�Ƃ������낤�E�E�E�B��?UNICODE�ŃR�[�f�B���O����??
|

1.
���u�P�[�j�q�v�A�E�u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�ł��B
�\���͊�{�I�ɑf�g�݂ł��B�ŁA���͂̍��فA�O����⍂�p�C�吔�A88mm���˖C�̗L�����F�X�ƍׂ����������L��܂����A�傫���ڗ��̂́u�P�[�j�q�v�̃x���^�ƃh�[���V�W��̑�W���ƁA�u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�̖h���ԓW�����ł����ˁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/4
f22
ISO200

2.
��ƌ��������ƌ������u�P�[�j�q�v�A���ƌ�������O�ƌ������u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�ł��B
��W���Ɩh���ԓW�����A����Ǝ�C���ʂ̔��̗L���̓_���l����ƁA�ǂ����u�P�[�j�q�v�͊J�킩��啪�o�߂�����Ԃ��A�t�Ɂu�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�͊J��O�T���J�킩��R���o���Ă��Ȃ������̐ݒ�Ȃ̂��낤�Ǝv���̂ł����A�@���ł��傤��?
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/10
f16
ISO200
���x����
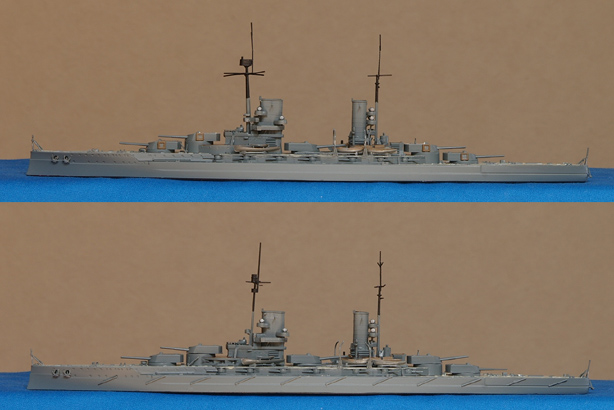
3.
��u�P�[�j�q�v�A���u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�ł��B
���[�ށA���͂Ƃ��O����Ƃ��ӂɂ�ӂɂ�̂ւ�ւ�B�和�̐������o�Ă��Ȃ��̂́A��̔@���؍H�p�ڒ��܂ł̉����߂ׂ̈ł����A�Ƃɂ����ׂ��̂Ő�o���ۂ̈��ł��ɂ���ƋȂ������Ⴄ��ł���B�Q��܂����B�^�J�ɒu������̂��ʓ|�����Ȃ��A�����ɂȂ邩�s���ł����A�O���l�����莞�͂ǂ��������̂��E�E�E�B
����ɂ��Ă��E�N���C�i�̐������ĉʂ����Ăǂ�Ȓ��x�Ȃ̂��E�E�E�Ƃ������ȋh����Ƃ��n�߂Ă݂�A�ꕔ�̓��Β��ȊO�͂��������Ƃ������A�ւ��[����Ă��܂��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200
����I�o��2�������

4.
���u�P�[�j�q�v�A�E�u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�ł��B
��̔@���g�p�h���ƁB
�͑̂̎傽��F������XF-20�ŁE�E�E�Ƃ̎w��Ȃ̂ł����A����́u�f�A�t�����K�[("Derfflinger")�v���ߋ���ƍ��킹��AS-10�Ƃ��܂����B�܂��A��C�V�W��XF-54�Ȃ̂ł����AAS-10�ƐF�����卷�����Ȃ��Ă��܂����̂Ŋ������Ă��܂��܂����B
�E�E�E���āA���ALP17�Y�ꂽ�E�E�E�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/8
f16
ISO200

5.
��f�Ŗ��O�����������̂ňꏏ�ɏ}�����u�f�A�t�����K�[�v�����ׂĂ݂܂����B
��u�f�A�t�����K�[�v�A�����u�P�[�j�q�v�A���E�u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�ł��B
����`����ȃ��m������ȋ�ɕ��ׂ���Ȃ�āA���ėǂ�����ɂȂ������̂��낤�B
PENTAX istDs
TAMRON 24mm 1:2.5 01BB
1/15
f16
ISO200
����1�����x�g���~���O
| H31/4/30 �W��
|
1938(�`41)�N�^���B���쒀�͘A���O�e
|
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
|
�`�ɑ������C�R�쒀�́u�A���e�B�G�[��("Artigliere")�v�A�u�A���B�G�[��("Aviere")�v
|
����͕��肪�t���܂����B
���r�����i����\��̒ʂ�A���ɑ������ɏ��n���ꂽ2�ǂ��쐬���܂����B
���݂ɁA�����Ƃ��ẮA
DD-442�u�j�R���\��("Nicholson")�v(�����@���A,�O���[�u�X,�u���X�g��?)���u�A���B�G�[���v
DD-460�u�E�b�h���[�X("Woodworth")�v(�x���\��,�x���\��,�u���X�g��?)���u�A���e�B�G�[���v
�ƁA�Ȃ�܂��B
���r�����i�A�͑̌ŗL�̕��i�����ō\������Ă��܂��āA������d�T�A�T�Ɠ��A���ڒ����͐��K���i�Ȃ瓯���p�[�c�Z�b�g����I���g�p�ł����A����̓p�[�c�Z�b�g���L��܂���B���Ȃ�̕����́A�ߋ�2��̑I������Ȃ��������i�̗��p�ōς݂܂������A���������O���Ǝ�C�̎ˌ��w�����u�̓p�[�c�Z�b�g�Ɏc���Ă��炸�A�ߋ���E�E�EH22/4/11�`H23/4/5�W���́u�y���V���o�j�A�v("Pennsylvania")��H27/4/15�`H28/3/30�W���́u�o�[�~���K��("Birmingham")�v�E�E�E�̗]��i�𗬗p���܂����B
|

1.
���u�A���e�B�G�[���v�A�E�u�A���B�G�[���v�ł��B
�����͊�{�I�ɓ���Ȃ̂ł����A�ψِ����������ƌ������A�P�ɋC���ƌ������A�قȂ�N��ݒ�ɂ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/30
f16
ISO200

2.
��ƌ��������ƌ������u�A���B�G�[���v�A
���ƌ�������O�ƌ������u�A���e�B�G�[���v�ł��B
�\����傫���قȂ�̂͑O���Ƒ�2���˒���̏�\�ł��B
�O���A���n���͂قړ��l�Ȍ����ڂł������A'60��㔼�Ɂu�A���e�B�G�[���v�̂ݎO�r������Ă��܂��B���̔N��ݒ�ɕ����āA�����͔̊ԍ���"D553"�Ƃ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/15
f16
ISO200
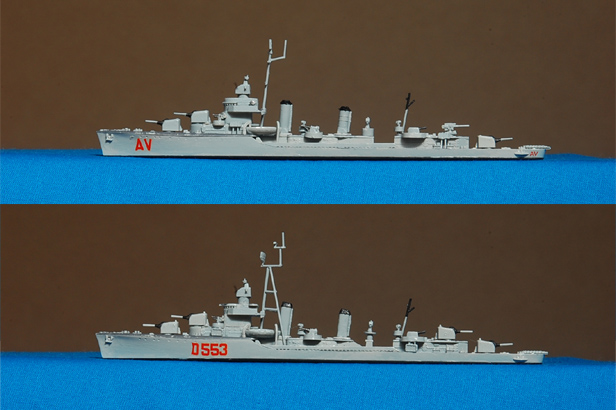
3.
��u�A���B�G�[���v�A���u�A���e�B�G�[���v�ł��B
�u�A���B�G�[���v�͏��n�����'50��O���Ƃ��A�͔ԍ��E�E�E�ԍ�?�L��??�E�E�E��"AV"�Ƃ��܂����B���݂ɓ������́u�A���e�B�G�[���v��"AR"�ŁA�܂��A�u�A���B�G�[���v�͂��̌�"D554"�ɏ����������Ă��܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/8
f16
ISO200
����I�o�������

4.
���u�A���e�B�G�[���v�A�E�u�A���B�G�[���v�ł��B
�g�p�h���Ƌ��ɁB
�O����͗�̔@�������߂Ƃ��A���[���͂����̒ʂ���O���܂��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/15
f16
ISO200
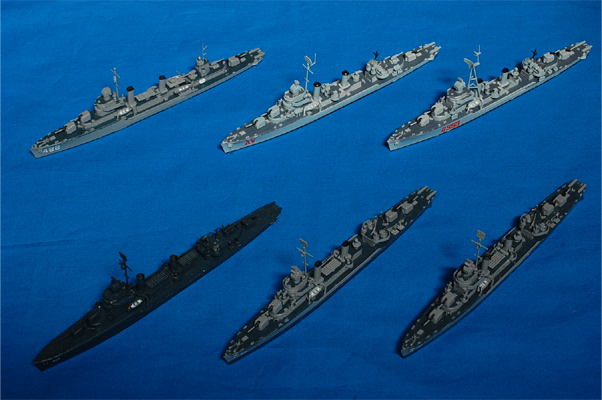
5.
�ߋ�2��̌�����������700/700�̏v�H�����ŕ��ׂĂ݂܂����B
��i������u���C���v�A�u�A���B�G�[���v�A�u�A���e�B�G�[���v
���i������u�E�[���[�C�v�A�u�}�N���i�n���v�A�u�}�h�b�N�X�v�ł��B
���̌�A�ǂ����܂����˂��B���r�����i�A����2�Ǖ��c���Ă��܂��B���������O���Ǝˌ��w�����u�̗]�肪1�Ǖ������c���Ă��Ȃ��̂ł���ˁB�O�҂͐��̏��n�͂Ƃ��͓P������������L���Ȃ���?�Ǝv���̂ł����A��҂͂ǂ��������̂��E�E�E�B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/15
f16
ISO200
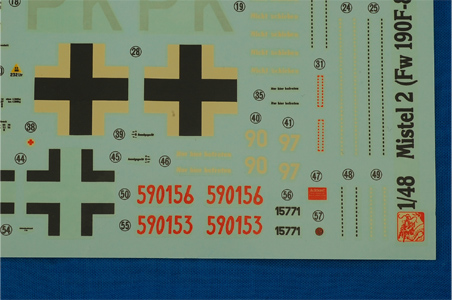
6.
��������͐��쒆�̂��ꂱ����B
�u�A���e�B�G�[���v�̌����͔ԍ��A���̐��\�t�䎆���璊�o����\��ł����B�J�[�\���I���Œ��o�Ώۂ̔w�i�F���ς��܂��B
�Ƃ��낪�A��o���Đ��v��������A���g���悤�ƃs���Z�b�g�ł܂݂����悤�Ƃ�����E�E�E���B
orz
����"3"�Ƃ����͎ʐ^�Ɛ����ǂ����Ă����̂ł����˂��E�E�E�B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/8
f16
ISO200
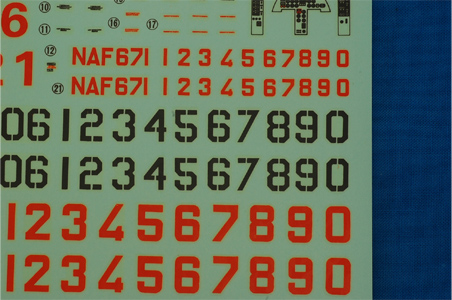
7.
�Ȃ̂ŁA��������2�ǂƂ����o���鎖�Ƃ��܂����B
�E�E�E���܂������Ă��A"D"��"V"�������A"5"������Ȃ����A�ǂ䎖??
�͂��A�J�[�\���I���Œ��o�����������ω����܂��B
�u�A���B�G�[���v�Ɏg�p�����͔̂w�i�������ɁA�u�A���e�B�G�[���v�Ɏg�p�����͔̂w�i���Ő����ɕς��܂��B
��������܂����ˁA"N"/3*2��"V"�A"0"��"D"�A("F"+"6")/2��"5"�ł��B����͂�A��J���܂�����B
��L3.�́u�A���e�B�G�[���v�A����"5"�A�p���ڂ̒i�����I�ł��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/8
f16
ISO200
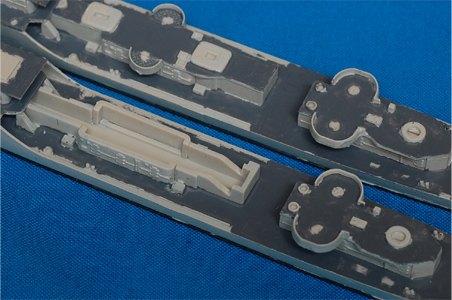
8.
��������́u�A���e�B�G�[���v�̉��H���B
�オ�A�����u�A���e�B�G�[���v�ŁA��\�̈ꕔ���߂ɍ폜���܂����B���̎�̍\���ɂȂ��Ă���͖̂{�͂����łȂ��A�u�o�[�g��("Barton")�v�A�u�}�[�t�B�[("Murphy")�v�����^�͂����l�Ɍ����܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
ISO200
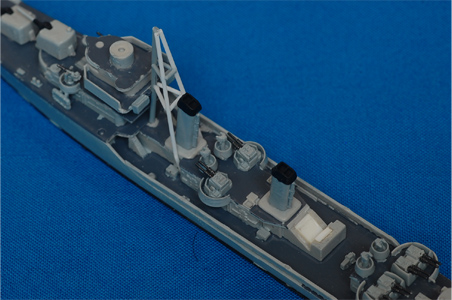
9.
��L8.�̍폜�����̓G�o�[�O���[����#147��148�Ŗ��߂Ă��܂��B
�O���̎O�r�O���g�ݗ��ĊJ�n�ŁAT�Ђ̃�1mm���͋�����̎和�ɁA���e���Ɖ����̓G�o�[�O���[����#219(��0.64mm?)���g�p���Ă��܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16
ISO200
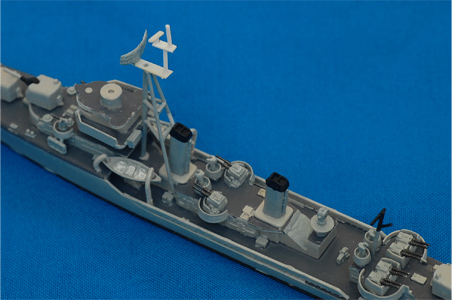
10.
0.5mm���̃v����2�i�̓V�����t���A���i�ɑ�d�T?��i�ɍq�C�p�d�T?�Ǝv�������̂��ڂ��܂����B
���̑O���̍\�����͕s�N���Ȍ���ꂽ�ʐ^�����ɐ��@��㕔�̍\�����͂قڑz���łł��������Ă��܂��̂ŁA�{�C�ɂ��Ȃ��l�ɁB
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
ISO200
H31/3/25�W�� H30�x�������̂��z�{
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���ς�炸1/700�̊͑D�ł��B
�v���U��Ɋ��I���܂܂�Ă��܂��B
������ԂŊ��H�͋쒀�́~6�A��́~1�Ȃ̂ŁA�o����!!
|

1.
�S���ł��ꂾ���B
�ƌ������A�{���͂����Ə�����܂�Ƃ��Ă������ł��āB��Ԍ��h���̂���u�W�����E�o�[��("Jean Bart")�v�͗\�肵�Ă��Ȃ������̂ł����AP�Ђ̃W�����N�s�Ŕ��l�ɁA�����E�E�E�B
�ŁA�ȉ��́A�����������Â��A���ɓd�ԏ�ł����}�̂ł��R���Љ�A���̗L�邻�́u�W�����E�o�[���v�ȊO���B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200

2.
���f���E���́uYT58��260t�^�g�D�v�ł��B
���g�A���ꂾ���B���A�ł��߂��B
���ƂȂ��AH24/9/27�`H25/9/5�W����RAYDEN MODELS�u�n��v�݂����ȏ��^�͑D&�V���̎Ђł����A���āA���삪�o��ł��傤���B�u�n��v�̌�͑����Ă��Ȃ����E�E�E�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

3.
���ŃR���R���́u���S�F���A���D�]��ہv�ł��B
���ւ��ő��̓��^�D3�ǂ��������Ă��܂��B
���ŃR���R���͑��Ɂu���v���A���͓����J�����Ă���A�����P�Ђ�A�Ђ̌��Ԃ��l�ȉ��������҂��������ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200
H31/2/23�W�� 1938(�`41)�N�^���B���쒀�͘A���j�e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���ς�炸1938�N�^�Ȃ�炾�̂Ɩ�̔���Ȃ��Z�ߕ������Ă��܂����A����A�F�X�ȌĂѕ����L��܂��B�u�x���\��/�����@���A("Benson/Livermore")�v���A�u�x���\��/�O���[�u�X("Benson/Gleaves")�v���A�u�O���[�u�X/�u���X�g��("Gleaves/Bristol")�v���ƌ������ӂ肪�l�����Y�t����Ă��鏊�ł��傤���B
�����P�Ђ�W-63�u�����@���A�v��1942����DD-437�u�E�[���[�C("Woolsey")�v�A������W-65�u�R�[���h�E�F���v��1943����DD-615�u�}�N���i�n��("McLanahan")�v�Ƃ��Đ��삵�܂����B
����Ő��K���i�Ƃ��Ă͑S�ďv�H���܂��āA�c���4�Ǖ��̗����i���A���āA�������v�H��������ł��傤���E�E�E�B
|

1.
���u�}�N���i�n���v�A�E�u�E�[���[�C�v�ł��B
����͋����ɂ��Ă��ꂱ��m�������U����B
�悸�́u�x���\��/�����@���A�v�����ނ���s���܂��傤���B���̋����ł����߂����̖���B�͈�Ԏ����ꂽ�����ł��傤�B���͂̑���43�W��P�Ђ̏��i�W�J������ɏ����Ă���܂��ˁB
���B���̊͐������_�������d���ł���A�N�x�P�ʂŔ������Ă��܂��B���j�I�ɂ�'38�ADD-421�u�x���\���v��M���Ƃ��Ĕ������ꂽ���Łu�x���\�����v�ƁB�ŁA�������́A�����������^��A�����悤�Ƃ��Ă�����A�������������u�M�u�X&�R�b�N�X�Ёv��'39�A'40�Ɖ���肵�Ď��������^�A���̏��ޏ�̕M����DD-429�u�����@���A�v�ƂȂ����E�E�E�݂����Ȉꕔ�ϑz��痂������Ă��܂����A�v����ɍs���̎��_���猩�����̖{���̓Z�ߕ������́u�x���\��/�����@���A�v���ł͂Ȃ���?�Ǝv���Ă��܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

2.
��u�E�[���[�C�v�A���u�}�N���i�n���v�ł��B
�����āu�x���\��/�O���[�u�X�v�����ނł��Bwiki��navsource�ƌ������d�ԏ�ł͗ǂ����镪�ނł��ˁB�@�v���قȂ�_����̋敪���ŁA�܂������͌����Ă��O�Ϗ�͉��ˌ`�����ق���������Ȃ��̂ł����B
����A�u����v���̇T�A�U�A�V�̍ו��ނƓ��l�Ȉʒu�t���Ō����̂����̓Z�ߕ��ƌ����ėǂ��ł��傤�B
�ŁA�u�x���\���v�͗ǂ��Ƃ��āADD-423�u�O���[�u�X�v�A��������o�ė���?�ƌ�����ƁA��L�́u�x���\��/�����@���A�v���̋敪���́u�x���\���v���Ɋ܂܂�Ă��܂��B
�܂�A���̖������ɂ����킸��炩�Ɂu�x���\���v���Ƃ��Č������n�܂��Ă������ɁA������킪�����܂�Ă����B���āA�A�d�������Ȃ��Ȃ����E�E�E�����ȁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

3.
��u�}�N���i�n���v�A���u�E�[���[�C�v�ł��B
�u�O���[�u�X/�u���X�g���v�����ނ͐�O�̏������\�ŏv�H�������A��ΐ��������������A�㏞�d�ʂƂ��ĖC���������팸������Ԃŏv�H�������ŋ敪������Ă��܂��B�܂��A�s���I�ȏ������l�������A�P���ɏv�H?�A��??�����ŋ����͂�I�����Ă��܂��B
�Ƃ͌����Ă��A��O�����͂�������v�͈ȊO�͉������������Ă��āA�ŏI�I�ɂ͂��܂�Ӗ��̖����敪���ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
��^��Ȃ̂��A�u�O���[�u�X�v�����ɗ��Ă��鎖�B���̏������\�͂́u�x���\���v�������ė��Ȃ��̂�?�u�x���\��/�u���X�g���v����Ȃ��̂�??���Ď��ł��B
�H���A�u�ނ̍��ł͏v�H��Ԋ͂������͂ɂȂ�v�ƌ����������z����Ă��܂����A���Ƃ���ƁA�u�t���b�`���[("Fletcher")�v���ł͂Ȃ��u�j�R���X("Nicholas")�v���A�u�A�����EM�E�T���i�[("Allen M. Sumner")�v���ł͂Ȃ��u�E�H�[�N("Walke")�v�����낤�ɂ�!!�Ɠ˂����݂����Ȃ�̂ł����E�E�E�B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
ISO200
����I�o��2�������

4.
���u�E�[���[�C�v�A�E�u�}�N���i�n���v�ł��B
��̔@���g�p�h�����B�����͗����ɋ��ʁB�e�X�̔w��̂͊e�X�݂̂̎g�p�h���ł��B
�����̒ʂ�A�u�E�[���[�C�v��Measure21�Ȃ̂ł����A����`����̓h���͊y�ł���BH25/2/6�`H26/2/7�W���́u1/700 ���B���C�R �u�t���b�`���[("Fletcher")�v���쒀�͋���v�̒��Łu�J�b�V���O("Cushing")�v�����l��Measure21�ɂ��܂������A���̎��͍b�F���ēh��܂����B����͂قډ��������B�����āA�h�蕪���Ă�����Ȃ����́B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
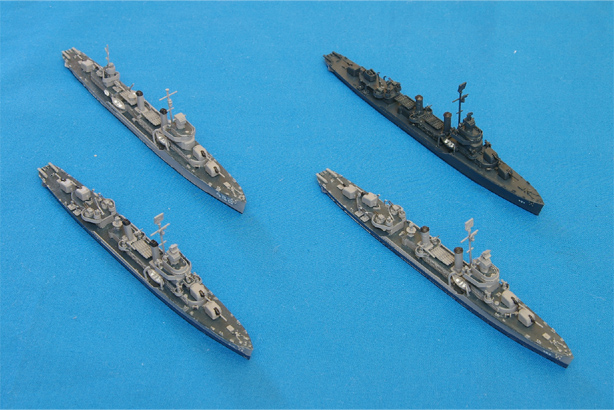
5.
�O���2�ǂ��܂߂āB
���ォ��s�ɁA
�u���C���v(�x���\���A�x���\���A�x���\��)�A�u�E�[���[�C�v(�����@���A�A�O���[�u�X�A�O���[�u�X)�ł��B
�u�}�N���i�n���v(�x���\���A�x���\���A�u���X�g��)�A�u�}�h�b�N�X�v(�����@���A�A�O���[�u�X�A�u���X�g��)�ł��B
���݂Ɋ��ʓ��́A��L3���ނʼn����Ɋ܂܂�邩���ڂ��Ă݂܂����B
�g�ݍ��킹�A���\�A�o���o���ł��B���\�ƌ������A�S�R����Ă��܂���B�͂��A���Ȃ��l�ɑΏۂ����߂č���Ă��܂��A���́B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
f16
ISO200
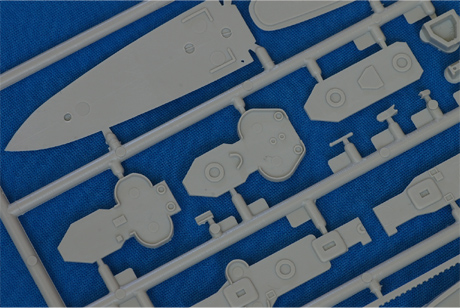
6.
�u�E�[���[�C�v�̌㕔��\�A����01�b�̕��ʌ`��Anavsource������ƁA��������Ă���3��ނ̂ǂ�Ƃ������Ă��Ȃ������ł����̂ŁA�L�荇�킹���i�Ƒg�ݍ��킹�Ď��삵�܂����B
�}�E�X�J�[�\���I���ŐF���ς��3�킪�Y�����i�ł��āA���̓��̗ɂȂ镨���̗p���܂����B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
ISO200
����I�o��2�������
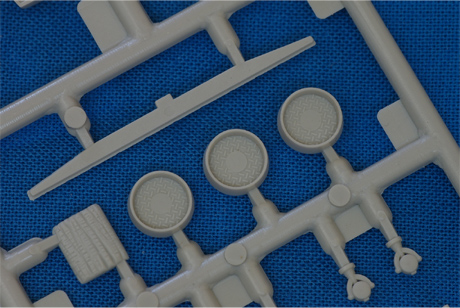
7.
������́AP�ЁuWW-II�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�g[II]�v����A����40mm�A���@�e��28mm4�A���@�e�p�̚Ɨۂ��̗p�ł��B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
ISO200
����I�o��2�������
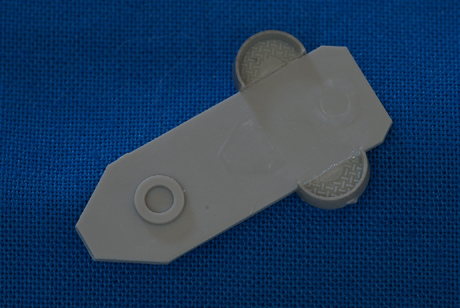
8.
�ŁA�����Ȃ�܂����B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
ISO200
����I�o��2�������
H31/1/18�W�� 1938(�`41)�N�^���B���쒀�͘A����e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
����?1938�^���B���쒀�͂���??�ƈ킶��Ȃ��̂�???
���₢��A���B���쒀�͂ł��B96�nj�������A��평���A��͋쒀�͂Ƃ��Ċ��A�������������ɋ��^����܂����B���́u���������v�A�u�͂������v�����̒��Ɋ܂܂�Ă��܂��B
���āA�����������A��������������\�������̂��E�E�E�Ƃ����蒸����������邩�ƁB
�ŁA�����P�Ђ�W-65�u�R�[���h�E�F���v���O�̏v�H����DD-422�u���C��("Mayo")�v�A������W-63�u�����@���A�v��1944����DD-622�u�}�h�b�N�X("Maddox")�v�Ƃ��Đ��삵�܂����B
|

1.
���u�}�h�b�N�X�v�A�E�u���C���v�ł��B
��O�̏v�H���ݒ�ɂ����u���C���v�͐��X������������������܂���B����܂��A��C�͋p90�������A�p���ӂ�̓���̊́A�C�ɔ�ׂ�Ƒ�z������\�͂������܂����A�@�e���S�R��������܂���B
��풆�ɏv�H�����u�}�h�b�N�X�v�͑��Ƒΐ�����������Ȃ�ɑ������A�㏞�d�ʂƂ���2�Ԋǂ�53�ԖC�A�������ڒ���ς�ł��܂���B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200

2.
���ƌ�������ƌ������u�}�h�b�N�X�v�A�E�ƌ��������ƌ������u���C���v�ł��B
�u���C���v���A���̑��̓��^�͂���평���ɐ�v���Ă��Ȃ���A�u�}�h�b�N�X�v�Ɠ��l�ȉ������Ă��܂��B���̕ӂ�A2�Ԋǂ��O����3�D���˖C��ςp�쒀�͂Ɨގ��̔��z�Ɍ����܂��B�C�͍~�낵�Ă��A�����ێ��ɂ͍S�������쒀�͂ƑΏۓI�ł��ˁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
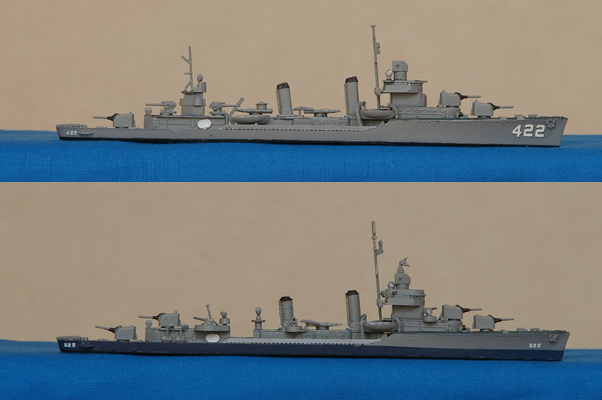
3.
��u���C���v�A���u�}�h�b�N�X�v�ł��B
�͔ԍ��A��Ԋ��͐����傫���A��풆�͐������������̂𐅓\���͕\�����Ă��܂��B
�ŁA�O�҂̃t�H���g�E�E�E�ƌ����\���ŗǂ����̂��E�E�E�͉e�t���̋Â������̂ŁA��҂͂̂��肵������C�̖����S�V�b�N���̂ɂ��܂����B
����̉��ϔ��w�ʂɂ́A�����e�t���̂��̂ő�풆���\��|�̋L�ڂ��L��̂ł����A�����̎ʐ^�𐢊͂�d�ԂŊm�F����ƁA����Ȋ����ł͂Ȃ��ז������܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

4.
���u�}�h�b�N�X�v�A�E�u���C���v�Ǝg�p�h���ƁB
P�Ђ̉��ϔ��ɂ͐F�X�Ǝw��h�����L�ڂ���Ă��܂����AG32�AG33�ȊO�͑S���������āAH25/2/6�`H26/4/5�W���́u1/700 ���B���C�R �u�t���b�`���[("Fletcher")�v���쒀�͋���v�y�ѓ�Vol.2�Ŏg�p�����h���ƍ��킹�܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
f16
ISO200

5.
���āA�A��ƌ����Ă��܂����A������������̂��B
����O�̑����ł��B�����Ƃ������i�Ƃ���4���A�͑̎�̂̕s�Ǖi������(�W�����N�p�[�c����a��)��4�ǂ̓s��8�Ǖ��ɂ��Ă���܂����B����8��?�ƌ�����ƁA���ꂪ�ӊO�Ɍ������B�������̑����i���s�Ǖi�������ɂ͖����̂ł˂��A4���͖��_�s���܂����A���̍ۂ̗]�葕���i�Ŏc��̕s�Ǖi���������������Ή��o���邩�E�E�E�B
�C�������Ƃ��T�Ɠ��Ƃ����\�]�肪����������̂ƁA�d�A�����O�A�]�肪�������Ȃ������ɕʂ�A��҂ɂ��Ă͂ǂ��������̂��A�Y�ݒ��ł��B����܂��A�ߋ���̗]�葕���i�ŗގ����L��Ή����Ȃ̂ł����˂��B
PENTAX istDs
COSINA 24mm 1:2.8 MC MACRO
1/1
f16
ISO200
H30/11/11�W�� WWI�x��S���N�L�O�`�쒀��Admiralty V��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�ƌ������ŁA�S���N�ł��B
�W���g�����h�ɖ��W�ȃt�l����낤���Ď��ɂ��܂��āA�C��u�����ɂ͂P�ǂ���Ƃ��A�����Ă��Ȃ�����Admiralty V ���쒀�͂��A�^�~���́u���@���p�C�A("Vampire")�v��p���č쐬���܂����B
����A�ɂ�2���L�����̂ŁA�f���Ɏw��ʂ��'30��̐ݒ�́u���@���p�C�A("Vampire")�v�ƁA��풆�̏�ԂŁu���@�����X("Valorous")�v�Ƃ��ĂŁA���ق͓h���A�͔ԍ��A���ˊǂŕ\�����܂����B
|

1.
���u���@�����X�v�E�u���@���p�C�A�v�ł��B
����́A�F�X�s��ۂ��L��A�ǂ������Ă��܂��܂����B
���́A���X�h�ڂ́u�h���b�h�m�[�g("Dreadnought")�v���E�E�E�Ǝv���Ă����̂ł����A�����d�v�ȕ��i����������Ȃ��Ǝ��ԂɎ���܂����B�͋��\��������̂�C�����i�[���������炸�A���[��A�������ɍs���Ă��܂����̂��A������R��Ă����̂��B���ꂪ���������̂�10�����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200

2.
��u���@���p�C�A�v�A���u���@�����X�v�ł��B
�ŁA�����]�����āAV�����E�E�E�ƌ����H���͒����������̂ł����A�����ł��AAdmiralty V/W���͚����^�͑��݂��Ȃ����Ċ��Ⴂ�����Ă���A�u���@���p�C�A�v�����ɓ��^��47�ǂ���I�ѕ����WW1���̎p��2�Ǎ�����ł����B
������A���Ɓu���@���p�C�A�v�͚����^�B�I�����͂����Ȃ�5�ǂɂȂ��Ă��܂��܂����B����܂��A�����������ǂ��Ƃ������܂����A���Ǝ����s���A���ԕs���B�ł����āA�X�ɑI��������襂ɂ����̂��͔ԍ��ɂ��鐅�\���ł��āA���ꂱ�ꌤ���������ʁA�u���@�����X�v�����I�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200

3.
���u���@�����X�v�A�E�u���@���p�C�A�v�ł��B
�ŁAWW1���̏��2�ǂ��ĘH���͒f�O���A����ƂāA����2�Nj����肵�Ă��܂������ƌ������ŁA1�ǂ̓^�~���̐ݒ肵��'30�́u���@���p�C�A�v�ɂ��܂����B
�܂��A���A��V/W���ɂ��Ă���Ȃ�ɒm���������̂ŁA�����WW2���̔��^��璷������q�^�A��^����蕪���ł����悤��??���Ɩϑz���Ȃ��������B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/2
f16
ISO200
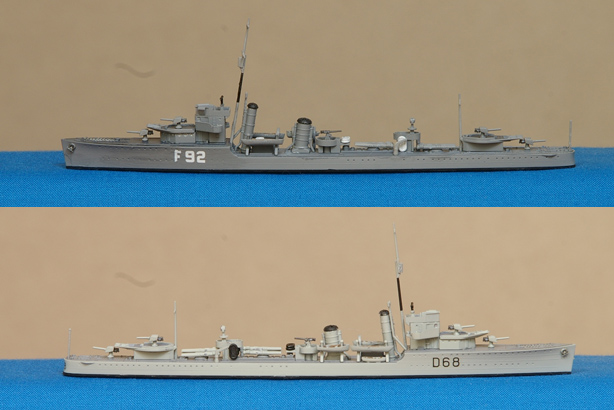
4.
��u���@�����X�v�A���u���@���p�C�A�v�ł��B
����_�́A���ƌ����Ă��͑̂̓h�F�ŁA����́A�l�F�̊͑��ɔ������͔̊ԍ��ƌ��������ʐ^�������A���̓_����AWW2���́u���@���p�C�A�v���^�~�����w�肵�Ă���TS-81�ł͔��߂���̂�AS-7�ɂ��܂����B���������Z���Ă��ǂ�������?�Ƃ��v���܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
����I�o�̕�������
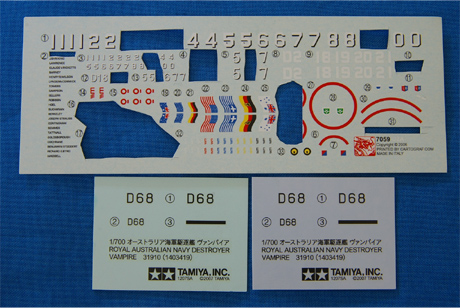
5.
���g�ƂȂ������\���ł��B����2���͒ʏ�u���@���p�C�A�v�ɓ����̂��̂ŁA�䎆���F�Ⴂ�Ƃ���傫�����Ⴄ�Ƃ����ȍ��ق��C�ɐ���܂��B
��́AWW1���p�ɍɂ���E���o�������ŁA�G�H�̒�����30,99,83,92�̉��ꂩ��g�ݍ��킹�č����Ęb�ɂȂ�����A�����A92(=�u���@�����X�v)�����I�����͖�������Č��_�ɒH�蒅���Ǝv���܂��B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
ISO200
H30/9/20�W�� H30�x�㔼���̂��z�{
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���ς�炸1/700�̊͑D�ł��B������Ƒ��ڂł�����?
������ԂŊ��H��4��7�ǂȂ̂ŁA�����ڂ̐ǐ��͈�v����B/S?�͋ύt���Ă��܂����A��3�ǂ͑|�C���ł�����˂��E�E�E�B
����ƁA���̊��ɋy��ŁA�^�~�������̂��r����̃��b�J�[�n�h�������܂��āA������3��ނ��w�����܂����B
|

1.
�悸�͑S���B
�ŏ�i�̓A�I�V�}�u�G�N�Z�^�[("EXETER")�v�~2
���i���̓J�W�J�́u�Y���v�Ɓu�����v
���i�E�̓t���C�z�[�N��"G-39"�~3
���܂��ň�ԉ����^�~�����b�J�[
PENTAX istDs
COSINA 24mm 1:2.8 MC MACRO
1/1
f16
ISO200

2.
�^�~�����b�J�[�ł��B
�w���͂�����3��ނŁA�܂��A�����̍쐬�u������݂��������Ȃ���Ċ����̑I���ł��B
�������b�J�[�͏]�O����L��A������g�������E�E�E������1�C���ɂȂ����E�E�E��ʐ�Ő��E�A�n�܂𗬂�����Ŏc�ʂ�������Ă����̂ł����A�ʂ����āA�F���̍���@����?
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
ISO200

3.
�u�G�N�Z�^�[�v�ł��B�A�I�V�}�̍ŋ߂̉p�͂̏[���U��͖ڂ�������܂��B���āA�u�����ہv��u�ԋ{�v�A�u���X�v("Wasp")�v���o�Ă��邯��ǁB
���^�́u���[�N("York")�v�͊͋��`��≌�ˁA�O������A����ɑ���_���L��A���p�͌������̂ł����A���̂�2���B
����˂��A���܂��́u�t�����[("Flower")�v���R���x�b�g�~�����ɁE�E�E�B
���[�ށA�܂�܂ƃA�I�V�}�̖ژ_���ɛƂ��Ă���B
PENTAX istDs
COSINA 20mm 1:3.8 MC
1/1
f16
ISO200
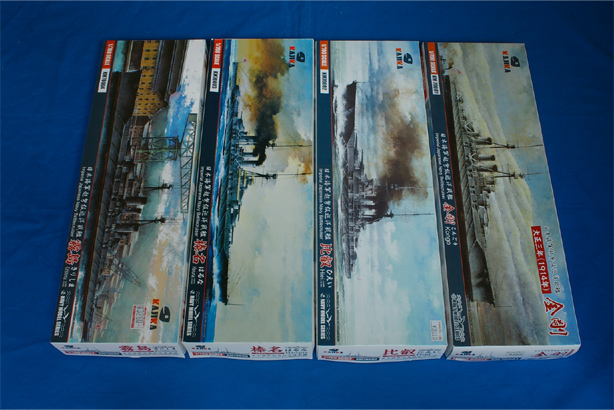
4.
����́u�Y���v�A�u�����v�ɉ����āA���B�ς݂̎o�B���B
�����b���̍w���A����s��������ƁA���͏��a����IJN�Ɋ��S�������ƌ������A����������ƌ����Ȃ̂����Ǝv���ė��܂��B
PENTAX istDs
COSINA 20mm 1:3.8 MC
1/1
f16
ISO200

5.
"G-39"�ł��B
H28/6/26����W���́u�W���g�����h�C��S���N ���e�v�œo���"G37"�̓��^�͂ł��ˁB
�쐬�����͉��̌����Ȃ�?�Ə������̂ł����A���ꂩ��X��2�N�o���A�ڏo�x�������B�f���Ɋ������B
���݂ɁA�t���C�z�[�N�A�����b����KG5����u�r�X�}���N("Bismark")�v�̗l�ɑ��ЂƎv�������蓖�����Ă���t�l���o���Ă���܂��B�o����Γ�����Ȃ��u�o�C�G����("Byern")�v��ƌy�����J�����ė~�����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200
H30/8/26�W�� JMSDF�͒��A���Q�e�̎l�`�u���킩���v
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���o��A�u���������v���A�a�͂́u���킩���v�ł��B���_�AP�Ђ�1/700�ł��B
�����܂ŁA�C���͒��́u����܁v�������ċ����͂��琻�삵�ė����̂ł����A����͉��̂������q����B
|

1.
���́A���X�́u���������v�̔����J���A����J�n�����̂ł����A�r���Ō�q�͑����͂̎����ɂ��悤��?�ƕ��j�ύX�������̂́A�ύX�_�E�E�E52�ԓP�����Ւn�Ɏw�ߕ��{�ݗp�̏�\�lj��E�E�E�̉E�����ʐ^���������炸�摗��ɁB�܂��A���肵�Ă��܂����������ƁA���^�Ŋ��ɒ��B�ς݂������u���킩���v�ɕύX���܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
1/1
f16
ISO200

2.
�u���킩���v�́A�f�̂܂܂ł��ƍŏI��ԂƂȂ�܂��B�ŁA���ɉ����l�����ɍŏI��ԂɁB���͓��^�e�͂̏A�����Č��̌������i����������Ă����肵�āA�����B�ł����u���������v���A�����ɁE�E�E���ƍl�������ł������B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
f16
ISO200

3.
�g�p�h���ƁB�܂��C���͒��Ȃ̂ŁA�����b���w�Ǔ��������ł��ˁB
ASROC�ɂ��Ă͗�̔@���A�����߂ł��B�O���+���˂���̔@�������߂ł��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5
2/1
f16
ISO200
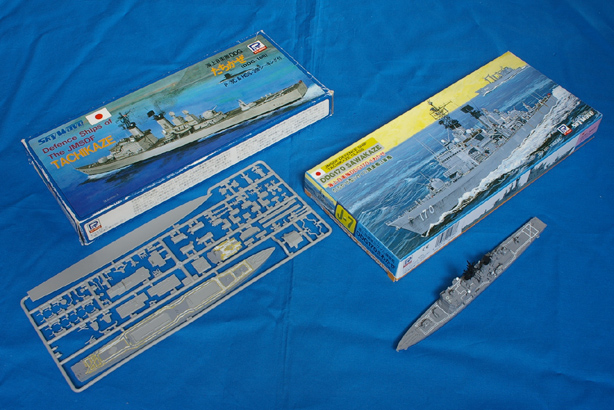
4.
������Q�e���ʂŁA�ʘH�h�蕪���p�̓h���핢�����ɁA���^�͂ɓ]�p���Ă���܂��B
���A��l�e�́A��͂荡��̓��^�͂���?
����ɂ��Ă��A���߂��ɑ��߂����ɁA�����E�E�E�h���A�ڒ����̗L�@�n�ܑ�Ŋ��C���K�{�ˋg�p�s�E�E�E�̂ŁA�����A�ǂ������̎����Ɋ��H�ł����Ȃ��Ǝ��掩�^���B
PENTAX istDs
COSINA 24mm 1:2.8 MC MACRO
4/1
f16
ISO200
H30/6/30�W�� JMSDF�͒��A���Q�e�̎Q�`�u�͂��܁v���~3
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�n�����`�ɁA�|�C���ł��B���_�AP�Ёu��܂����v�̂��܂��ł��B
�����3�ǁB3�`5�Ԓ����B
|

1.
������u�݂₶�܁v�A�u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B
�������ł��B���Ȃ�ڋ߂��ĎB���Ă��܂��B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
ISO200

2.
������u�݂₶�܁v�A�u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B
���́A�������ƁA�u�������܁v�ɂ͕t���Ă���܂���B�����𐮌`���Ă����牽�������ōs���܂����B�܁A���������A�v���_�ōČ����܂��傤�B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
ISO200
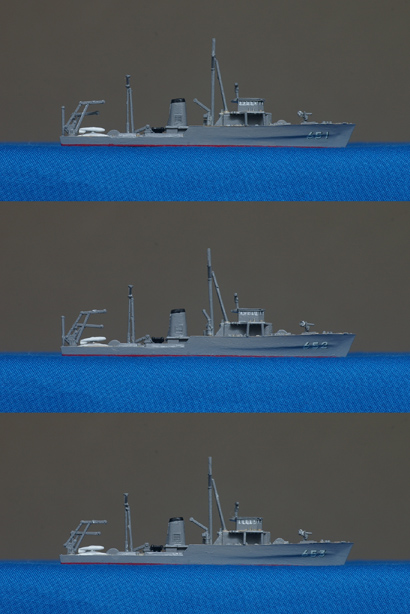
3.
�ォ��u�݂₶�܁v�A�u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B
�u�͂��܁v���͑S23�Ǐv�H�ł����A�c�O�Ȃ���䂪�{�I�͑��ɔz�������̂�7�ǒ��x�őł��~�ߌ����݂ł��B�ȂɂԂ�A�u�����v���̂��܂��Ȃ̂ŁB
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
ISO200
3������

4.
������u�݂₶�܁v�A�u���̂��܁v�A�u�������܁v�ƁA�g�p�h���ł��B
���AX-11����XF-16����������������ǖY�ꂽ�B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
2/1
f22
ISO200
H30/5/29�W�� JMSDF�͒��A���Q�e�̓�`�u��������v
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���o��A�u����v���A�����͂́u��������v�ł��B���_�AP�Ђ�1/700�ł��B
P�Ђɂ��Ă͒������A�ėp�����i�Z�b�g�����Ă���܂���B������ˌ��w�����u������p�̂��̂ŁA�u����v���̍�蕪���p�̕��i�ȊO�]�肪�o���A�L���ƌ����ׂ����A�������Ƃ����ׂ����A�����ł��B
|

1.
���������A�V�h<->���Â�����OER,JRC������̓��}�u��������v�A���t�̃_�C���̍ہA�u�ӂ�����v�Ɖ������Ă��܂����̂ł���ˁB���܂�ɂׂ��Ȗ�����ɋh�����܂����B
���ĊW�����ł����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/8
f16
ISO200

2.
���엯�ӓ_�ɘb�߂��܂��āB
���ڋ@�����b�ɕ`����Ă���̒��͗p���̕W���A�����A�u�䂫�v�ł́A�����Ă̓h���ł��������A����̓f�J�[�����̗p���܂����B
����˂��A���l�ɓh���ŁE�E�E�Ǝv���Ă����̂ł����A�u�䂫�v�Ɣ�ׂčb��̒����������ׂ��Ⴍ�A�h���핢����ɂ͍���ŁA�t�ɁA���������ăf�J�[���g������??�ƂȂ�܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/15
f16
ISO200

3.
�h�����݂ł�����B�b�ʘH�̔��������Ɏg�����h���핢�A2�ǖڂɍė��p���鎖�Ƃ��܂����B
���́AH30/4/21����W���́uJMSDF�͒��A���Q�e�̈�`�u�����v���v�œo���2�ǂɎg�p�������̂����l�Ɏ��́u�����v�ɓ]�p���Ă���܂��B����ŁA���������Ԃ̊|����C���͒��̓h�����������ł���̂ł�?�Ɩژ_��ł����肵�܂��B�Ƃ͌����Ă��A�S���͂͗���ł��傤����A��������������ė��p�͂ł��Ȃ��ł��傤����ǁB
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/8
f16
ISO200

4.
����ɂ��Ă��A�u����v���Đ����Ɨ����̍\�����Ⴂ�܂��˂��B
�܂��A700/700�ł����˂�����炪���S���ォ�炸��Ă���͔̂F���͂��Ă����̂ł����A�~������瓋�ڒ��̐ݒu�ʒu�Ƃ��A�����������Ȃ畽��s�����D���ӂ肪�����ɂ߂Ĕl�|���Ă������ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
ISO200
����I�o2�������

5.
�g�p�h���Ɨ��߂āB
������O����͌Œ��������A���[���͎��O�����Ƃ��܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/30
f16
ISO200
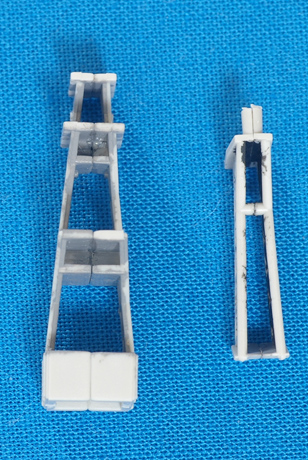
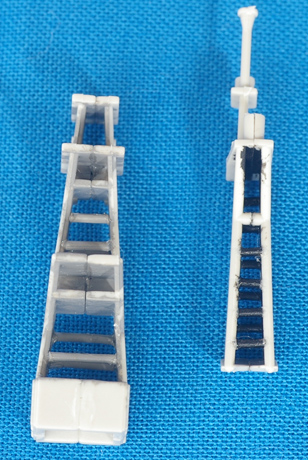
6.
��������͂���������ƒlj��̉��H���B
�u�䂫�v���u�����v���Ō����݂ł����A�����Ƃ��A�O��������������Ɣ����Ă��܂��Ă���̂ŁA��̔@����0.7mm���������̃v���_�ʼn����̂ݒlj��ł��B
�������H�O�A�E�����H��ł��B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1 , 2/1
f16
ISO200
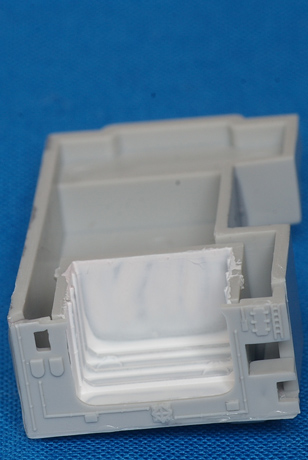
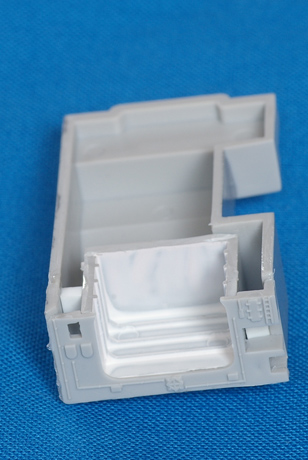
7.
�i�[�ɂ̌�[�͊J����������̂ł����A������(�����ĉE��)�͎��͕�����Ă���̂Ńv���ōǂ��܂����B
�܂��A�E�������A�ʘH�������J���Ă��܂����A����������Ɏd���ݒu���܂����B
�������H�O�A�E�����H��ł��B
PENTAX istDs
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1 , 1/1
f16
ISO200
H30/4/21�W�� JMSDF�͒��A���Q�e�̈�`�u�����v��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
H26-27�̑O��ȗ��v���U��̊C������퓬�͐���ł��B���̍X�ɑO��H24�ł��āA������C���ϊ͎��̔N�ł��B�����������N���E�E�E�ƌ����������ł����A���N�͓����ܗւ̉e���ŗ����ω{�ƍ����ւ��炵���A���Ǝc�O�B
�ŁA�u�����v���Ƃ��Ă�3��ڂł��B����́u�Ȃ����v�Ɓu���������v���B����œs��6�Ǐv�H������ŁA�S�[���͋߂�??
|

1.
���u���������v�A�E�u�Ȃ����v�ł��B
�Ӑ}���Ă�����ł͖����̂ł����A�G�ߖ�+�u�_�v���Ċ͖��ɂȂ�܂����B
�ӂƎv�����̂ł����A�t�Ɠ~��?����A���C�R�̒����A�z���A�[�_�̊e���ɂ����Ȃ���ł���ˁB
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
ISO200
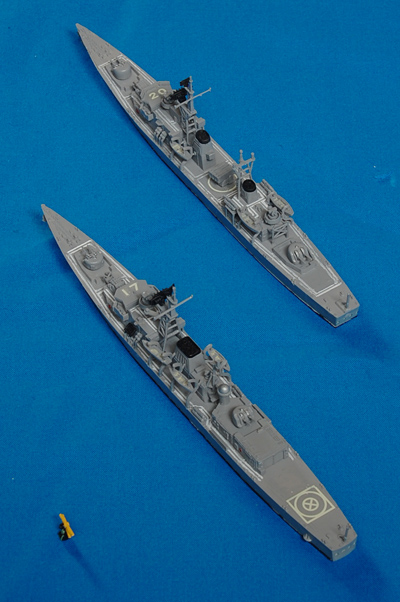
2.
��u���������v�A
���u�Ȃ����v�ł��B
��������DASH�ł��B
�b�̑�W���ł�����ʂ�A�u�Ȃ����v��DASH���ڂ̎����ݒ�ō쐬���܂����B
�������A���l��DASH�ɒ��͗p�̑�W�����ĈӖ�����̂ł��傤��??
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
ISO200
����1���Âg���~���O
���x����

3.
���v�H�ς݁u�����v������ׂČ��܂����B������u��܂����v�A�u�܂������v�A�u�݂˂����v�A�u�Ȃ����v�A�u���������v�A�u���������v�ł��B
���[��A�f���Ɋ������B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
f16
ISO200

4.
��u�Ȃ����v�A���u���������v�ł��B
�����̒ʂ�ADASH�A�w�����߂��ł��B�ǂ��݂Ă��i�[�ɂɊi�[�ł������ɂ���܂���B
�n���ɂ�����������č��������悤��?�Ƃ���u�v�����̂ł����A���ꂾ������Ȃ��Ɩ��ʂȓw�͂��Ǝv�������ĕ��u���鎖�Ƃ��܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
8/1
f16
ISO200
����I�o��2�������

5.
���u���������v�A�E�u�Ȃ����v�ł��B
�g�p�h���Ƌ��ɁB
�E��3��ނ̓h����DASH�Ŏg�������̂ł��B���̐^����H30/2/25����W���́uArt Nouveau? Art Deco?? �䕧�����ӏ��̌R�́v��9�œo��̒�������Mr.color 58���ǂ��ł��B
�u���������v�͗�̔@���O����������߂Ƃ��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
1/4
f16
ISO200
H30/3/28�W�� H29�x�������̂��z�{
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�㔼���ɑ����ė}���I�Ȓ��B���ł��B
Nikon D40,ISO200
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
f16 �ŎB�e���܂����B
|

1.
���ꂾ��??�͂��A���ꂾ���B
�������A�����Ƃ������ȐV���i�ł͂Ȃ��A���ω��łȂ̂ŁA���ɒ��g���I����K�v�������A���ꂾ���B

2.
���āA���ꂾ�����ች�Ȃ̂ŁA���^�͂���������o���Č��܂����B
���A���Ɂu�����v�͔����ς݁B�u�}�[�N�E�O���[�t�v("Markgraf")�̔�����4���ƍ��m���s�Ȃ��Ă��܂����A�u�Y���v���u�����v�̉��ϔ��ɋL�ڂ��L��A�ǂ�����S���^�͂��s��ɓo�ꂷ�鎖�ƂȂ肻���ł��B
H30/2/25�W�� Art Nouveau? Art Deco?? �䕧�����ӏ��̌R��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
������ARCS�ጸ�ׂ̈̋ɗ͒��p�ƋȐ���r�����ӏ���Z�����A���ؖ����́u�N��v("Kang ding")���t���Q�C�g�ƕ��u�A�L�e�[�k�v("Aquitaine")���쒀�͂��A�e�X1�Ԋ͂̐ݒ�ō쐬���܂����B
�O�҂�Bronco model�A��҂�Freedom model�̔����ŁA���炭10�N�ȏ�Â��O�҂̕����g�݈Ղ��A��҂͏��d�|�����̈ӗ~�͗����ł�����̂́A���ꂪ���肵�Ă��銴���ł����B
|

1.
���u�N��v�A�E�u�A�L�e�[�k�v�ł��B
����2�`���A�o�ꎞ����20�N�߂��Ԋu���Ă���܂��B�S�̂̊͌`�͋��ʂ̊T�O�ɂ��ӏ��Ō`����Ă��܂����A�Â��u�N��v�ɂ͑��݂��锍���o���̘o�^�̓d�g����M�@���A�u�A�L�e�[�k�v�ɂ͗L��܂���˂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
1/1
f22
ISO200

2.
���u�N��v�A�E�u�A�L�e�[�k�v�ł��B
�㕔��s�b�̒��͕W���́A�܂����R�قȂ�܂��B
�E�E�E�ƌ������A�u�A�L�e�[�k�v�̓��ڋ@�͂ǂ�����??
����˂��A�����i�[�܂邲�ƍs���s���B
orz
�ŏ���������Ă��Ȃ�������?�ƈ�u�v�����̂ł����A����ὂ߂����L��������̂ŁA��͂����ɂčs���s��??
���[��A�������B�I��ɑI���āB�܂����ւ���UH-60�n���HSS-2���ڂ����ɂ͍s���Ȃ����A�ǂ��������̂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
1/1
f22
ISO200

3.
�䂪�{�I��������RCS�ጸ�͌`�̃t�l���E���ĕ��ׂČ��܂����B
������p�u�f�A�����O("Daring")�v�A�u�A�L�e�[�k�v�A�u�N��v�A�āu�C���f�B�y���f���X("Independense")�v�ł��B
�����狭�����ɕ��ׂ��ς���B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
1/1
f22
ISO200
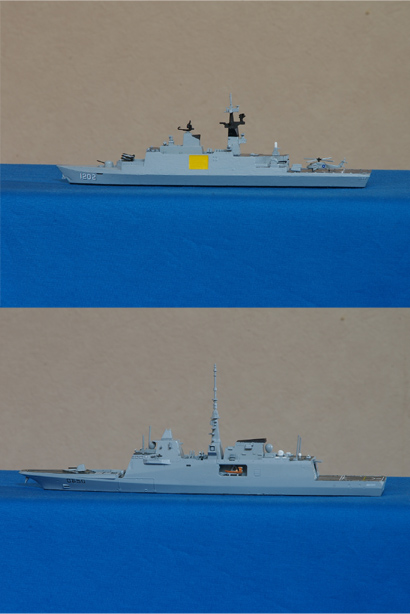
4.
��u�N��v�A���u�A�L�e�[�k�v�ł��B
�ǂ�����������̓��ڒ��g�������ڂ������܂��B
�u�N��v�͕���ԂŐ��^�B���̔h��ȉ��F�͕t���̓\�t���ɑI��܂����A���͂ɔ�ׂĂ��Ȃ蕂���������ŁA�h���̕������͂Ɠ����ŗǂ������B
�u�A�L�e�[�k�v�͊J�I�����ł��āA����͂����̒ʂ�J����ԂƂ��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
2/1
f22
ISO200
����I�o��2�������

5.
�u�N��v�Ǝg�p�h�����B
�g�ݗ��Đ������ƁA�͎�̎O�p�`�̕��ʂƂ��A"Dark gray"�łƏ����Ă���̂ł����A700/700�̊ɘ��Ղ̎ʐ^���́A���炩�ɐF�����Ⴂ�A�͑̑��ʓ���Mr.308�ƑR���ς��Ȃ��Ǝv��ꂽ�ׁA�w�����Mr.308�œh�����܂����B
����Dark gray����̓I�Ȏg�p�h���̎w�肪���������肷��̂ŁA�܂��@����ŗǂ����E�E�E��XF-24���B
�܂��A����͗�̔@���Œ��������A���[���͎��O�����ɁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
1/1
f22
ISO200

6.
�u�A�L�e�[�k�v�Ǝg�p�h�����B
���܂�o�ꂵ�Ȃ����ȐF�������L��܂��˂��B����ƉE�[�͉���??
����͗�̔@���Œ��������A���[���͎��O�����ɁB
PENTAX istDs
smc PENTAX-A 1:3.5 35-105mm
1/1
f22
ISO200
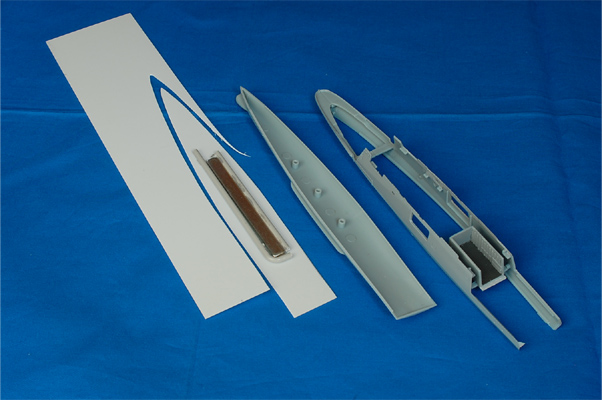
7.
��������́u�A�L�e�[�k�v�̍쐬��̂��ꂱ����B
�悸�A�h�����̎���B�u�N��v�͗m��A�S�D�̌��p�ł������A�u�A�L�e�[�k�v�͑S�D�݂̂̂ł����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
f16
ISO200
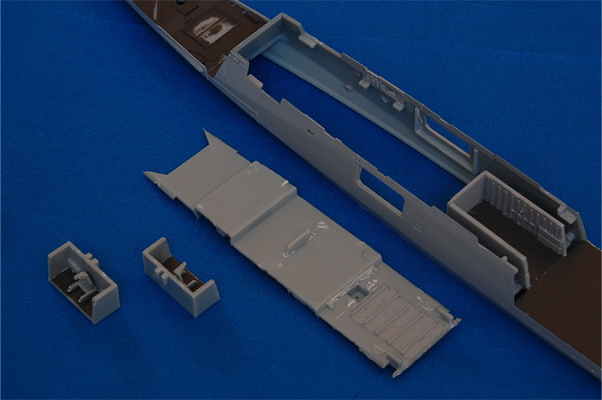
8.
�u�A�L�e�[�k�v�A�������Â�������A���������������肩�Ȃ��킵�܂����B�����D�O�����̍ŏ�b��t�ō����̕s�����C�ɕ\�ʉ����܂��āA�����炱������H�ڂɁB
�}�E�X�J�[�\���̉摜���O�ʼn摜�ϊ����܂��āA�Ԃ��̉����̂̕����͂�����������Ă���܂��B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
ISO200

9.
�u�A�L�e�[�k�v�̓��ڒ��AMr.58�u��v�œh��ƁB����Ȃ̔����Ă��Q�x�Əo�Ԃ͂Ȃ��������Ď��ŁAGM�̋��}�Ƒ���������ł����グ�܂����B���ꂪ�O�L6.�̉E�[�B���\��肭�s�����Ǝ��掩�^���B
���A�O�L6.��XF-15�͂��̓��ڒ��D�������Ɏg�p���܂����B
Nikon D40
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16
ISO200
H30/1/31�W�� ���k�m�����u���E�vor�u�g�Ёv
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
S-models�́u���E�E�g�Ёv��2�Ǒg�݂̓�1�ǂ��쐬���܂����B
2�ǂ��u���E�v�A�u�g�Ёv�A�u�}���v�̂ǂ�ɂ��悤���A��芸����1�Ǖ���f�ō�낤�ƁA�{�d�������̋���12���n�߂ɒ��肵�A�L����x������T���č�蕪���\�Ȃ�u�}���v�ցE�E�E�Ǝv���Ă�����A12/25����Ăы{�d���B�����E�E�E�ƌ����Ă��A�d�ԂƎ莝�����͂ł����E�E�E�W�߂Ƃ����Ă���Ǝ��Ԃ����`�B�ƌ������ŁA�S�ʓI�ɐ����ۗ����悤���ǂ����悤�����S�O�����̂ł����A���i�_�������Ȃ�����芸����1�ǂ�����C�ɍ�����Ⴆ��!!�ƂȂ�܂����B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|
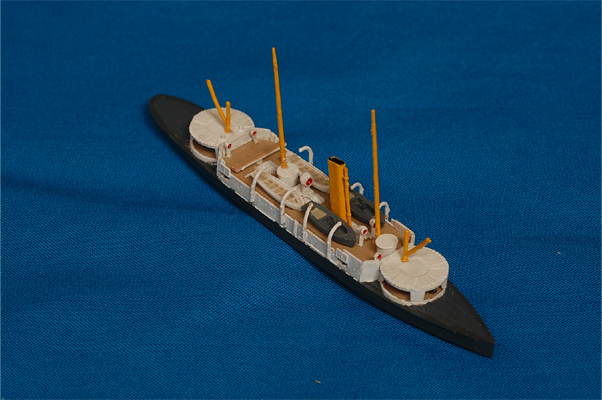
1.
�f�ō��E�E�E�ƌ����Ă��A�h�������ł�1881�ł�1894�ł��L�ڂ���Ă���A����͊�{�I��1881�łƂ��܂����B
���āA��{�I��?��??����B
����˂��A�ǂ���牻�ϔ������̎�����`���Ă�����ۂ��̂ł����A��C�V�W��̋N�d�@�A�����D�O��̎i�ߓ�?�炵���~���\�����̓h�F���Ⴄ��ł���˂��B����͂ǂ��������̓h�F�Ƃ��Ă��܂��܂������A��������ǂ��炩�Ɋ������ǂ�������??
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
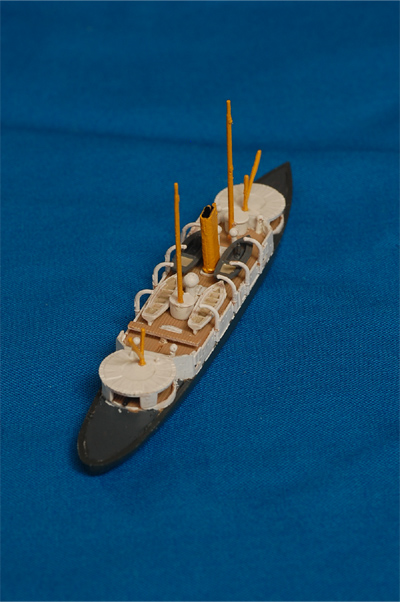
2.
�\����ƂĂ��s�v�c�Ȃ̂��O��̎�C�B
10�D/25���a�ƌ���������ނ�����ȖC���A�O�������㉽�������̓������݂��~�`�̉����̉��ɘI�o��ԂŐݒu����Ă��܂��āA�����ł���[�����������Ɗ���o���Ă��܂��B
�ŁA�����E�E�E�V�W?�E�E�E�͂ǂ��݂Ă��Œ�Ȗ�ŁA����ƖC�g�����̗l�Ɋ���o���Ă���ȏ�͍��E�̓V�W�̎x���ɓ�����̂Ŏx�����z���đ��ʕ����ɂ͌������Ȃ��B
�K�R�I�ɁA�ˊE���G���N����������ɁA���̂������ɎˊE�p�̊J�������ʂɂ���B�ǂ������炻����ɖC������������̂ł��傤?
�C�g����ނ�����l�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł��傤��?
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16

3.
H26/9/17����H27/9/7���u���C�C��120���N�L�O�v�œW���́u�艓�v(��)�A�u�ω��v(��)�ƕ��ׂĂ݂܂����B
�����ƈӏ����قȂ�܂��˂��B�u�艓�v�A�u�ω��v�͓Ɛ��A�u���E�v���͉p���ƌ������ł̈Ⴂ�Ȃ̂ł��傤��?
�������u�艓�v�A�u�ω��v�̕����v���I�ƌ������A����ӂꂽ�ӏ��ƌ������A��s���Ɍ����Ă���ƌ������A������Ă���ƌ������A���������p������Ȃ���??���ċC�����ė��܂��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16

4.
�g�p�h���Ƌ��ɁB
�����D�O�̍b��TS-68���h�o�b�Ɛ����|���A����������Mr.339�A�O��̖ؒ���łȂ��b��Mr.333�ŁB���ˁA�N�d�@�A���A�ʕ��ǂ̓�������GM�̊Y���F�Ŋe�X���܂��܂�
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
8/1
f16
H29/9/27�W�� H29�x�㔼���̂��z�{
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���̔����������C���B�P���ɔ��������Ŕ�r����Ȃ�A�v�H7�ɑ��Ē��B5������o����
�Ƃ͌������̂́AH29/4/25����W���́uJ,K,N����蕪���v�Ƃ���3���Łu���@���A���g�v��u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v��1���Ƒ̐ϓI�ɂǂ������ǂ��������Ċ����Ȃ̂ŁA�������������Ȋ����B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�ƌ������ŁA�\��Ŋ��Ɉꕔ�����Ă��܂��܂������A�S����5��6�ǁB
������P�Ёu���@���A���g�v�~2�AICM�u�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�A�A�I�V�}�u�n�[�~�[�Y�v�AP�Ёu���[�N�v�ł��B
�u���[�N�v�̂ݒ��Õi�ŁA���͐V�K���^���A�ŋ߂̓o��̓��^�͂ł��B
SIGMA 28mm 1:1.8
2/1
f16
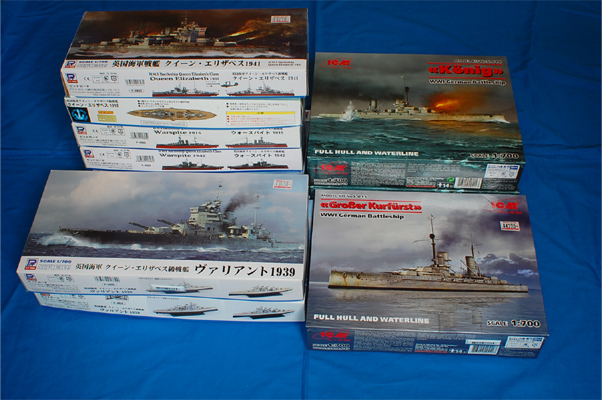
2.
���ɓ��^�͂B�ς݂́u���@���A���g�v�Ɓu�O���b�T�[�E�N���t�����X�g�v�^�͒B�Ƌ��ɁB
Q.E.���͖��`��S���^�͒��B�����ł��B����ɂ��Ă��A�u���@���A���g�v�A���̔����ł����Ȃ���??
�u�P�[�j�b�q�v���͋߁X�u�N���[���v�����c�v�̔��������m����Ă��܂��̂Łu�}���N�O���[�t�v���o�Ă����Γ������S�͒��B�B�ƌ����Ă��A���m�ɑO���̈قȂ�u�P�[�j�b�q�v�͂��Ă����A���͉������Ⴄ��??
SIGMA 28mm 1:1.8
1/1
f16

3.
���S�V���^�́u�n�[�~�[�Y�v�ł��B1��5��6�ǂƋL�q���܂������A���̉��ϔ����ʂŔ���ʂ�A���܂��t���ł��B
���݂ɁA�A�I�V�}�͂��̑��ɂ��u���B�N�g���A�X�v�A�u�܂��イ�v�A�u��~�v�Ɨ��Ă��āA�����A�ڂ𔒍��B�����Ƃ��A�u�A�[�N���C�����v����n�܂�����A�̊O���́E�E�E�ƌ������p���́A�d�ԏ��Ȍ̂ɐ^�U�̒��͒肩�ł͖����ł����A�s��ɔ���Ȃ������Ƃ̎��ō���͏o�Ȃ��Ƃ��ǂ��Ƃ��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
H29/8/5�W�� �u�m�b�N�X�v���ψٓW�J
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
AFV CLUB��"Knox Class Frigate FF-1073 Robert E.Peary �����z�����h�� 932�Z�z��"��3�ǂ��A
�@ ���B���u�t�����V�X�E�n�����h�v("Francis Hammond")��'70��̎p
�A ���B�����璆�ؖ����ɏ��n���ꂽ�u�`�������v("�Z�z")
�B ���lj��FFG�Ƃ��Đv�A�������ꂽ�u�o���A���X�v("Baleares")�̕��������ȑO
�Ƃ��č쐬���܂����B
��s�b�������ׂɁu�o���A���X�v�ւƉ��������̂ł����A��͂�厖�ł����B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
������B�u�o���A���X�v�A�@�u�t�����V�X�E�n�����h�v�A�A�u�`�������v�ł��B
���X�A�A�ɂ��Ă�10�N�ʑO�ɒ��肵�Ă����̂ł����A��s�b���s���s���ɂȂ�����A�v���ŕ������悤�Ƃ��Ă�����Ɏ���̂����炱���炪�ۂۂƑ���������ŕ��u���Ă��܂����B�Ƃ͌����������B���̔�s�b�ɂ��Ă͋ߏ���K.O.���̏����i����̐������Ė���Ă������̂́A��ɂȂ��āu�o���A���X�v���̑��݂�m��A�����ɕ��������ɐ��lj�łɂ��Ă��܂����ƁB�܂��A����̌����ɂ��ẮA���łɑ��̍ɂ��쐬�����^�Ƃ��ĎQ�l�ɂ��ĕ��������Ă��܂����ƌ������ʼn��̂���C��3�Ǐv�H�ƂȂ�܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
���x����

2.
�������A������B�u�o���A���X�v�A�@�u�t�����V�X�E�n�����h�v�A�A�u�`�������v�ł��B
�u�o���A���X�v�A�d�Ԃ�˂����ƁA'90��̉�����E�E�E�ڗ����قƂ��Ă�SSM��CIWS�𓋍ڂ��A����㕔�̍\�����ω��E�E�E���쐬���Ă����͑��������̂ł����A����͋��炭�A��Ǝv����A�Ԃ��~������ς�ł����Ԃɂ��܂����B����˂��A��������ƁAH27/8/24-H28/8/3�W���́w���̃t���b�`���[�B�`���i�uZ-2�v�A�u���p���g�v�x�œo��́u���p���g�v�������l�ȐԂ�����ς�ł����̂ʼn��ƂȂ��e�a�������܂邩?�Ǝv�������̂ŁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
���x����
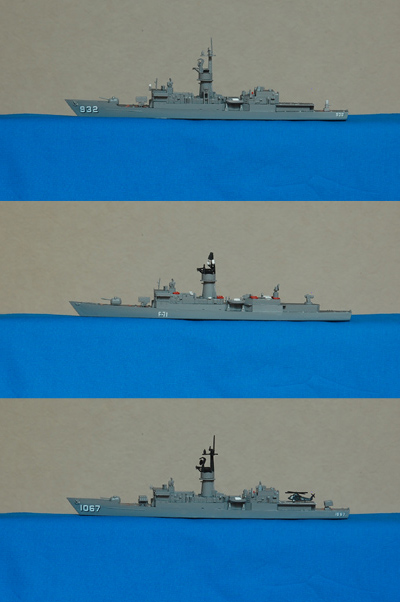
3.
�ォ��@�u�t�����V�X�E�n�����h�v�A�B�u�o���A���X�v�A�A�u�`�������v�ł��B
�u�t�����V�X�E�n�����h�v�A�͖����ǂ�����Č��߂���?�ƌ����ƁE�E�E
1.�͎�ۗېݒu��
2.�q���ʐM�A���e�iOE-82�ݒu
3.RIM-7����
�͉̊e�̂���t�l�̉摜��d�ԂŒT���A�X�ɁA
4.���L�b�g�̃f�J�[���̑g�����Ŋ͔ԍ���ݒ�ł���
5.�u���o�[�g�EE�E�s�A���[�v("Robert E Peary")->�u�`�������v�̗l�ȓ]�Ђ����Ă��Ȃ�
�ƌ��������̊͂Ƃ��܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
f16
����I�o��3�������

4.
������B�u�o���A���X�v�A�@�u�t�����V�X�E�n�����h�v�A�A�u�`�������v�ł��B
�u�`�������v�͑�p�ɓ]�Ђ����u�m�b�N�X�v����8�ǂ̒��̋����͂ŁA�{�͂̂�'00��́u���i3�v�Ə̂���������Ă��炸�A��������ʂɁu�m�b�N�X�v���̏�Ԃł��B
�Ȃ̂Łu�t�����V�X�E�n�����h�v�Ɓu�`�������v�A����_�����܂薳���A����̓h���ƁA�͔���RIM-7<->CIWS�A�ׂ�������OE-82�̗L���AESM/ECM/ESSM�̗L���Ŗ�����������Ă��܂��B
���ڋ@�͂�����ƍ����Ă���܂��BMD-500�Ƃ��������Ȃ菬�^�̉�]���@��ς�ł���A���ꂪ�ǂ�����܂���B��芸�����͖����ŁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

5.
�g�p�h���ƁB���̐ςݏd�˂Ă���ӂ��3�Nj��ʂł��B
��̔@���A���˂ƌ���������ƌ������A�Œ��������A���[���͊O�����ɁB����̑O�ɍׂ������̂��]�����Ă��邯��lj�?
���́A���@�u�t�����V�X�E�n�����h�v�ƒ����A�u�`�������v�A�i�[�ɂ̎��k���������O����l�ɂ��܂����B����˂��A�u�o���A���X�v�Ɏv���������Ԃ��|������ł����A�u�`�������v�Ɓu�t�����V�X�E�n�����h�v�ɂ����H���悤���ƌ������ŁB�Ȃ̂ŁA���͏��2��4�ō����ւ��Ă��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
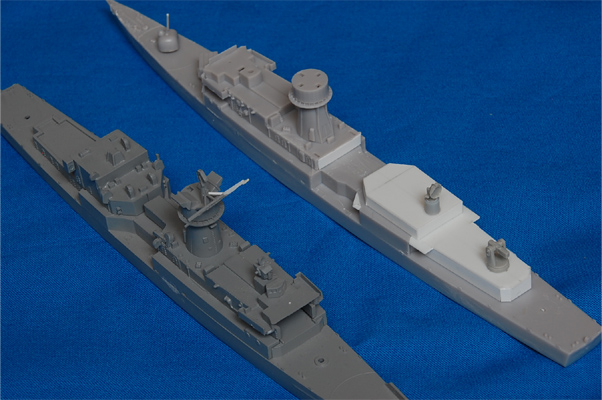
6.
��������́u�o���A���X�v�̑�����Ƃ�����Ƃ����u�`�������v�̕�C���B
���ƌ��������ƌ�������O�ƌ��������u�`�������v�A�E�ƌ�������ƌ��������ƌ��������u�o���A���X�v�ł��B�v���A�v���_�̕���������܂��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16

7.
�u�`�������v�A����������|�b�L���B
���݂ɁA�G�o�[�O���[���̃�0.7mm�ۖ_�𑽗p���Ă���܂��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
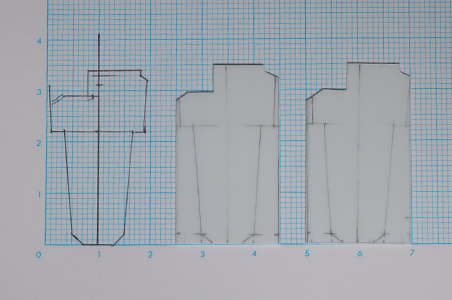
8.
�u�o���A���X�v��01�b�ł��B���ᎆ�Œn���ɁB
�ŁA����2��?�܂��A���đO�Ƃ��Ă͕����Ή���琸�x���B�{���I�ɂ̓L�b�g������1���L��Ȃ��`�ƌ������ŁB
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
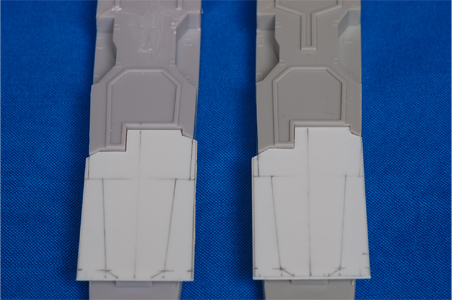
9.
8��{�̂ɍ��킹�Č���ƁA�܂��ǂ������B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16

10.
SAM���ˋ@�͗ǂ�����Mk.13�łȂ�Mk.22�B�����A�`�ǂ�����Ȃ��̂ł����A��芸������Օ������Z�\�^�ł͂Ȃ��~�`�̗l�Ȃ̂Ŏz�l�ɐ�o�����Ƃ��܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/4
f16
����2,3���g���~���O
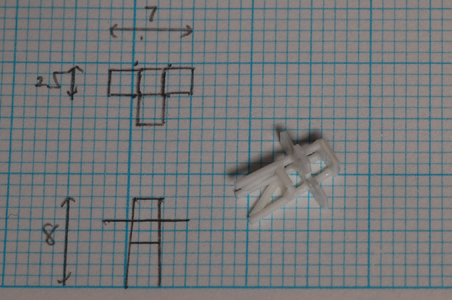
11.
����́A���d�ɂ��v���_�őg�ގ��ɁB�������G�o�[�O���[����0.7mm�劈��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/30
f16
����2,3���g���~���O
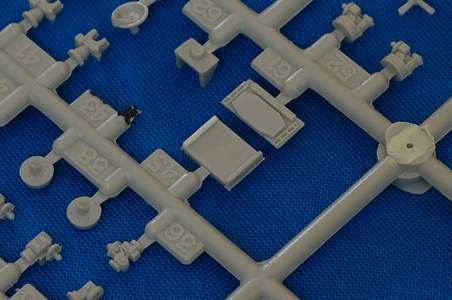
12.
���������SPS-52B�A����SPS-49�Ƃ��Ɣ�ׂĂ�����ƈႤ�����B��̓I�ɂ͗����̉����o�������Ă���l�ŁA�v���[��ʼn��H���Č��܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
����2,3���g���~���O
H29/6/15�W�� ���b��(�|�P�b�g���)����� ��Q�e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
��Q�e�ł��B�ŏI��ł��B�s�b�g���[�h�́u�A�h�~�����E�O���[�t�E�V���y�[("Admiral Graf Spee")�v�ł��B
����`�A���i�����A�������܂����B�Ȃ���1.5�����|����܂�����B����܂��A���̊ԁA�k�C�������������ɏo�������肵�Ă͂��܂������A�����͌����Ă��A����͖��x�����݂Ȗ�ł�����˂��B���̋K�͂ł��ꂾ�ƁA��͋�����ǂ��Ȃ��Ă��܂���?�ƶ������فB
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�V�������i�����Ɍ�q�̕��C�ȊO�͂��������Ƒg�߂܂����B
�͑̂͋h�����A�����A�b�~2�ƂȂ��Ă��܂��B��������̍\���Ȃ͍̂����Ɋ�^���đ�ϗL�����ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
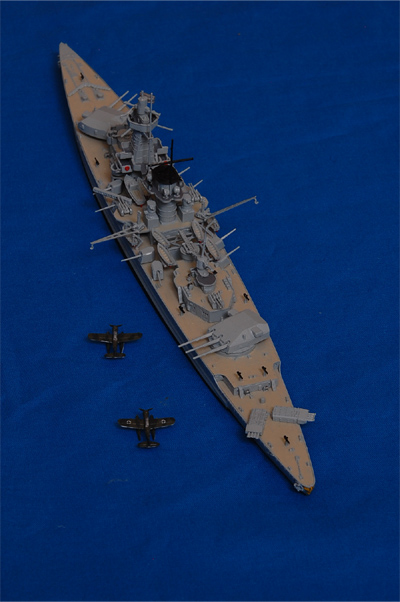
2.
��̔@���ғ�����S���U��Ƃ���Ȋ����ł��B�O����̑����V���A�ꉞ�ŏ�����g�ݍ���ł݂͂����̂́A���i�\����͒��X��肭�s���܂���ł����B
���ڋ@�͉��̂����i��2�@���Ȃ̂Ƀf�J�[����1�@���B�ǂ����Ă����Ȃ���?
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16

3.
�g�p�h���Ɨ��߂āBMr.308�A33�͂قڎw��ʂ�B���ڋ@���w��ʂ�B�b�͎w���Mr.44�ł����A���{�I�͑��̓ƈ�͍b�h�F��XF-55�Ɍ��߂Ă��܂����̂ł���ŁB
�ł�700/700�̏����A���B
��r���� 12100t
�S�� 186m
�ő啝 21.7m
'36/1/6�v�H�A'39/12/17��v�ŁA�o�B�����������Ă��܂��Ă��܂��B�ƌ������A3�o���A�t���ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
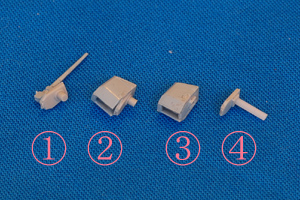
4.
��������͏��d�|���Ƃ����ꂱ����B
�悸�͕��C�B
�@�͖{���̑g�ݕ��ŁA�C��(���?)�̏�ɖC�g���悹�A�����C�|�Ŕ킹��̂ł����E�E�E�B
�A���̖C�|�ƖC���������܂���B���摤�͓���̂ł����A���𑤂������B
�B�C���̕\�����Ђ�����Ԃ��ƖC�|�ɂ���Ȃ����܂��B
�C�����ŁA�C���̊͑̑��̃_�{��藣���A������ɖC�g���B�ŁA�V���Ɋ͑̑��Ƀv���_�Ń_�{��t���܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16
�S�̂�1/2���x�Ƀg���~���O
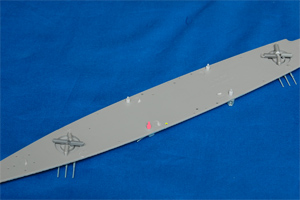
5.
��C�ƕ��C����E�h�~������l�ɍb�̗������珬�H�ł��B
�}�E�X�J�[�\���̉摜���O�ʼn摜�ϊ����܂��B
���C�̃_�{�������Ȃ����̂ŁA���邭����Ƌ��ɁA�O��Ȃ��l�ɗ��ߋ��t���܂����B
�Ƃ͌������̂́A�������ɑO����ƒ������Ŕ����Ɍ����Ƃ̋������قȂ�A�������͗��ߋ�����Ɋ�����̂ŕt���Ȃ����ɁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
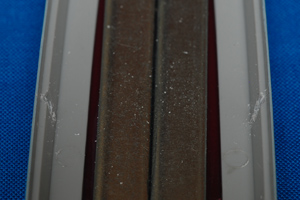
6.
���C�̒������_�{�A�X�ɑf�̂܂܂ł��͑̂Ɋ����鎖���������A���肪��ƍ��܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
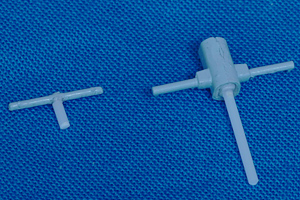
7.
�����V�A���ƌ���ł����A1mm�̃v���_���͑̂ɍ����l�ɂ��܂����B
����͎w�ߓ��V�W��(��)�Ɗ͋��ŏ�i(�E)�ŁA�����̂͂����ɂ͍ڂ��Ă���܂��A�\����̓s���Ŋ͑̑��Ƀv���_���Œ����A�ʉ��W���t�]�����܂����B����ΐ���ʂƋR��
�A�D(�K�B)��=(�_�^)�o�L�b
�E�E�E�C�����Ȃ����āE�E�E
�Ƃ͌������̂́A�������o���̂����\��q���܂��āA���ǁA�͋��ŏ�i�E�E�E�܂�呪���V�A��Ԗڗ��z�ł��ˁE�E�E�́A�����O�X���Ă��܂�����ƏC�s���K�v�����ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
�S�̂�1/2���x�Ƀg���~���O

8.
�ƌ������ŁA�ڏo�x�����b�͑S3�Ǐv�H�Ł`����!!�p�`�p�`�p�`��!!
����`�f���Ɋ������B
�ߋ��A���m�͋���3�Ljȏ㓯�^�͂�g�̂́A�K�L�̎����AIJN��6�����4�ǁE�E�E���Ă���A���^�͂���Ȃ����E�E�E�Ƃ��A���ƂȂ��Ă͂ǂ̌^�����Ǎ�������L���ɂȂ�IJN��5500t���Ƃ��Ȃ̂ł���ȗ��ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
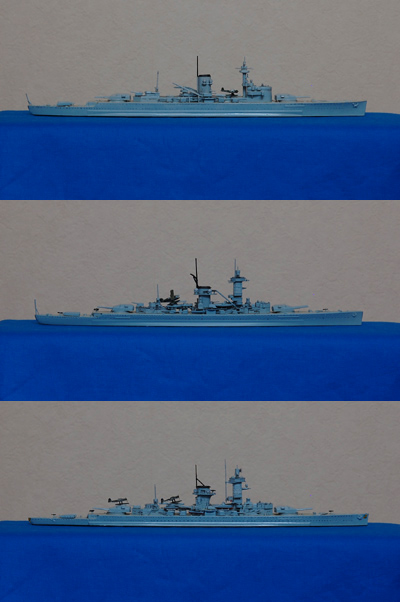
9.
�{���́A�x���T�C����ۗ̕L�����Ɋ�Â��A�����O�h����͂��ւ���ׂɓo�ꂵ�����͍L���m���Ă��܂��B
�ő呬�͂�IJN�������������͂��傫���A�q�������͑��̋쒀�͂�1.5�`2�{�ɋy�сA�ő�˒��͑��̏��m�͂𗽂��܂��B�Ȃ̂ŁA���肪������苭����Γ����邵�A�ク��ΎP�Ɋ|�����āE�E�E�Ɗz�ʏ�͌����܂����A����Əo���킵����ǂ������?���Ď�_�͂ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B�܂��AIJN��RN���킹��7�ǂ������Ȃ��̂�����R���S�z�ɂ͋y�Ȃ��Ƃ͌������̂́A���肪�A���ɏ��m�͂�������������?�ƌ����̂̓��v���^���C��̌��ʂ��ؖ����Ă��܂��ˁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
����œ_�����A�I�o��3��������

10.
�Ȃ̂ŁA�v���̂ł����A��͂�A��͂̑�͂Ȃ̂�����A�����g���ׂ��������̂ł�?
28cm�C�~6��~3�ǂ��ĉΗ͂͋������1�ǂ𗽂��̂ł�??
�Ǝv���ė��܂��B�ق�A�r���ʂ����č��Z����Ǝ����l�Ȋ����ɂȂ�܂����B�܂��A���ƂƂ��Ă̐헪����������͖������Č����Ă���̂�����d�������ł����B
AF Nikkor 28mm 1:2.8
1/2
f16
H29/4/25�W�� J,K,N����蕪��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
MATCHBOX�Ƌ��^�ڍs���Revell��"HMS KELLY(HMS KIPLING)"��3�����܂����B
2�ǂ�J,K���̊e�X�쒀�͌^�ƚ����^�̏v�H���ŁA1�ǂ͍��ɏ��n?�ݗ^??�����u�l�X�^�[("Nestor")�v�Ƃ��č쐬���܂����B
�d�ԏ�ł��������˂����Ă�����A�u�l�X�^�[�v��Measure 2�ƌ�����Measure 22�ƌ������A�ĕ����ʓh�������܂����B�܂������ʐ^�Ȃ̂ŁA���͓��F�Ǝ���2�F�h���̉\��������E�E�E����ȁA���ʂ́E�E�E�̂ŁA�X�ɂ��ꂱ�ꂤ�낤�낵�Ă�����A�T�Ƃ���Tribal class��Measure 2 ?����Measure 22 ??�������L�����炵���A�܂�����͗L��Ȃ̂��낤�ƌ������ŁA�ł͂��łɒʏ�̋쒀�͌^�ƚ����^����낤��?�ƌ������ł����Ȃ�܂����B
|

1.
�����皌���^�A�쒀�͌^�A�u�l�X�^�[�v�ł��B
�u�l�X�^�[�v�ȊO�͓��Ɍ͂��m�肳���Ă��Ȃ��̂ŁA�͔ԍ���\�t���Ă��܂���B�u�l�X�^�[�v�͍��B�����G02��t���̃f�J�[������"G"�A�L�荇�킹�̒�����"02"���e�X�P�o���ē\�t�ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
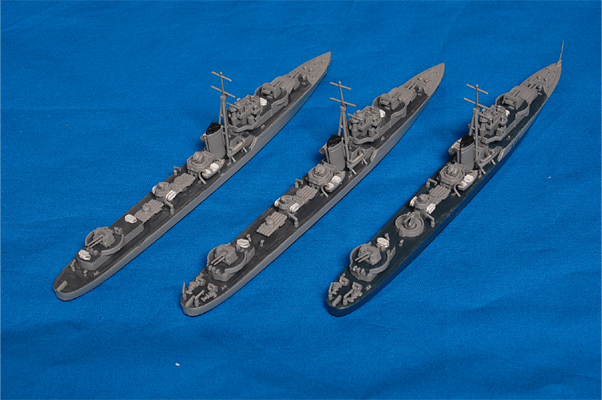
2.
�����皌���^�A�쒀�͌^�A�u�l�X�^�[�v�ł��B
3�ǂ̑���_�A�h���͂��Ă����\���I�Ȃ����1�Ԋǂ����ɗL��܂��B
�u�l�X�^�[�v�͑�2�ǂɑ���2�Ԋǂ̑����4�D�P�����p�C�ɒu���B
�����^�͌㕔��\���j�H�����ɒ����Ȃ�A����ɑ|�C�p������P���ƂȂ��Ă��܂��B
�Ƃ͌����Ă��A�쒀�͌^�̊e�́A���u����A�o���Q������ŗ���Ɓu�l�X�^�[�v�̗l��2�Ԋǂ𗼗p�C�ɒu�����čs���܂��̂ŁA���ǁA�����^�Ƌ쒀�͌^�̍��ق����c��Ȃ��Ȃ�܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16

3.
�ォ��쒀�͌^�A�����^�A�u�l�X�^�[�v�ł��B
�ł͂�����Ƃ���700/700�̂��ꂱ����B
J,K,N���͑O��Tribal class���A����쒀�͋쒀�́E�E�E�쒀�͎͂̊�a���o�܂��猩��Ό����������͔���Ǝv���܂����E�E�E�Ƃ��ēo�ꂵ�A�Η͏d���ɑ傫���U�ꂽ�̂ɑ��A�������̊g��łƌ��������ɐU��߂����ƌ����܂��B�Ȃ̂ŁA�Ǐd���ɖ߂��Ă��܂��B
K,J��16�ǂ͗��đ�����1936�N��1937�N�Ɍv�撅�H���ꂽ�̂ɑ��AN���͊Ԃ�L,M���������1939�N�Ɍv��A���H����Ă���A���ɏv�H�������P�̑�Η͊g���܂荞��ŗ��p�C��ς�ŏA�����܂����B
N���͉��̂��w�ǂ��ΊO�����p�ƂȂ�A�펞���͍��B�A�g�����ɓn����܂��āA�u�l�X�^�[�v�͍��B�͂Ƃ���'42/6/15�ɐ�v���܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
�ォ��1/1 , 1/1 ,1/2��3���
f16

4.
�g�p�h���ƁB
��C�Ɣ��ˊǁA�e�X����ȕ������������Ă��܂����A�����́A�����ɒE���h�~�p�̗֊����t���ċ��܂��B���ȏ��ŋÂ��Ă����MATCHBOX�B
����ɂ��Ă��A�������A���݂��A�����Ƒ�炩�ȏo���ł����B�Ȃ̂ŁA�Ǘ��l�����^�������╔�i�����������܂�C�ɂ�����炩�ɑg�݂܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/15
f16
H29/3/28�W�� H28�x�������̐ς�
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
����1�N�Ԃ͐����Ɣ�������ł��܂��܂������A�������͂����Ɨ}���I��
�������A�������A5��6�Ǐv�H�ɑ��āA5���w���Ȃ̂�B/S�ύt�B�悢�˂��`�B
�ŁA����͑S�ĐV���i��!!����͂���Ő����B���A�Ŕ����̊��ɍ����t�����̂����B���́A1/700�̑�^�͒������ł��A�t�W�~�u���v�A�A�I�V�}�u�n�[�~�[�Y�v�A�u�C���X�g���A�X�v�A�s�b�g���[�h�u���@���A���g1939�v�A�u�J���t�H���j�A1945�v�Ƒ��ɐH�w?�G��??��L�������Č��͑��X��������Ă���̂ł����A�P�ɉ䖝���Ă��������Ƃ������A�������AⰂ��O��Ȃ���ǂ�����ǂƎv��Ȃ��������B
|
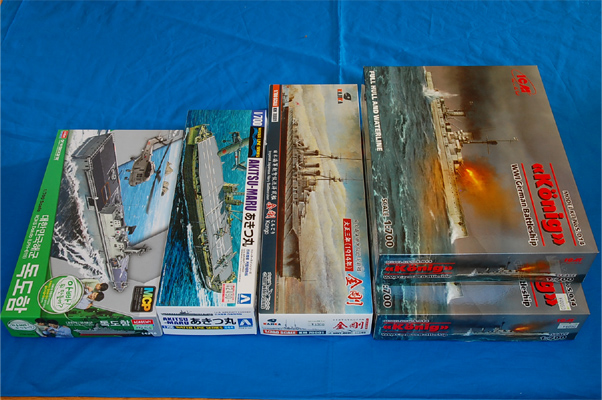
1.
��ςɒP�������ł��B��������5���B�S��1/700�͑D�B
������A�J�f�~�[�u�h�N�g("Dokdo")�v�A�A�I�V�}�u�����ہv�A�J�W�J�u����1914�v�AICM�u�P�[�j�q("Kaenig")�v�~2�ł��B
���[��A���Ɩ����A2�̏W�c�ɕ�������l�ȁB���ł����Ȃ����̂��낤�B
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
1/1
f16
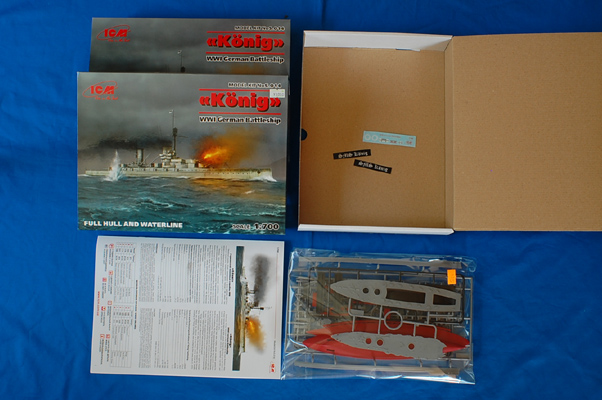
2.
�悸��ICM�u�P�[�j�q("Kaenig")�v�B
�u�P�[�j�q("Kaenig")�v�̓W���g�����h�펞�̓ƍ��C�͑����͂ł��B
ICM��10�N�ʑO����ł��傤���A�{����1/350�Ŕ������Ă���A���ꂪ1/700�Ȃ�Ȃ��`�Ǝv���Ă���܂����B�Q��1/700�����ł��B�ς��ς��ς��B
�Ƃ͌������̂́A�����͂ɕs�����L��̂�2�����B�ł��B
���͊O���̉��ϔ��ƁA���̒��̒i�{�[���̋��x����2�d�\���B�g�ݗ��Đ����͓V�R�F�ƁA�����̍����ȍ\���̊O�����i�̒��ł������ł��B
AF Nikkor 28mm 1:2.8
1/1
f16

3.
�J�W�J�́u����1914�v�ł��B�J�W�J�̓t���C�z�[�N�̕ʏ��W�������ł��B������͈��S�̋����͂Ȃ̂�1���݂̂̒��B�B
�ƌ������A���G�O���Ɂu��b�v�A�u�Y���v�̗\�����L��A���̈Ӗ����܂߂�1�����B�ł��B���A�܂蓯�^�͂Ŕ������Č����Ă���?
�E�E�E�܁A�܂��A���[��[���ł����˂��B�ł��A���^�͂͏v�H�����牌�˂̍������قȂ��Ă��āA����C�ɓ���Ȃ��̂ŁA���āA�ǂ��Ȃ���̂��B
AF Nikkor 28mm 1:2.8
1/1
f16

4.
�A�I�V�}�u�����ہv�ł��B1�N���x�O����̓R���ŁA�O���^�łƓo�ꂵ�Ă���܂������A�O�Ϗ�Ƃ����y�I�ɂƂ��̓_�Ŏ˒��O�B�������Ă���܂����B�W���ł��Q���o�ꂵ���̂ōw���\��ɓ���Ă���܂������A���f�u�h�N�g�v�ɐ�����l�ɑ����ɒ��B�ł��B
���g�́A�܂��A���cWL�̕W���I�ȓ��e�Ƃł������Ηǂ��ł��傤���B
AF Nikkor 28mm 1:2.8
1/1
f16

5.
�A�J�f�~�[�́u�h�N�g�v�ł��B�u�|���v�ł��ˁB
����A�S���\�肵�Ă��Ȃ������A�ƌ�����葶�݂����������F�����Ă��Ȃ������̂ł����A�u�P�[�j�q�v�̗\��i��������ɏo���������k��Ŕ������Ă��܂��A�Փ������ł��B
���F���^�A�V�R�F�g�ݗ��Đ����Ɛ����R�̍\���ɂ��S�炸�A����ň��l�̖�\2400�B
���[��A���̃A�J�f�~�[�B���̊؍��́B1�ǂ������Ƃ��Ǝ₵���B���������w�b�Ƃ����@�剤�Ƃ������Ă��܂�Ȃ��ł����˂��B
AF Nikkor 28mm 1:2.8
1/1
f16
H29/2/23�W�� �і�C�^ �����D�u�����ہv
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�t�W�~��1/700 �R���D�D�u���{�ہv��і�C�^�u�����ہv�Ƃ��ďv�H�����܂����B
�ƌ����Ă��A���������u�����ہv�u���M�ہv�u�ɓ��ہv���̓��^�D�p�ψʕ��i����������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA���i�I�������̘b�Łu�����ہv�Ƃ��Ă̓������撣���Ď��삵���ƌ�����ł͗L��܂���B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�u�����ہv�A���D�Ƃ��Ă͒������A���^�D��13�nj�������A�t�W�~�����ւ��Łu����ہv�u�ɓ��ہv�u�����ہv���A�������Ă��܂��B�w�ǂ��C�R�ɒ��p���ꂽ�������͂Ƃ��Ăł����A�u���{�ہv�̂ݏ��D����Ƃ��Ă��o�ꂵ�Ă���A����͂������u�����ہv�Ƃ��č쐬�ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
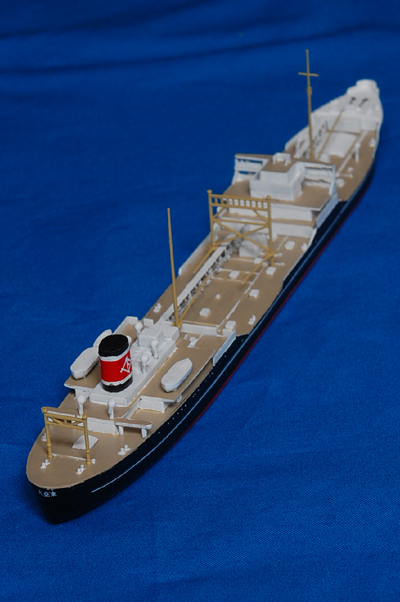
2.
�Ƃ͌������̂́A�h���w��́u���{�ہv�Ƃ��Ă̂݁B�u�����ہv�͖����B���́u���{�ہv�ɂ��Ă��A�����ʂɂ��Ă͈ꕔ�����w�肪�����A�����Y�݂܂����B
�ł����āA�d�ԏ�����ꂱ��˂����܂����B������A���Ɩؒ���Ǝv���钃�n���̍�����!!�E�E�E�������̂́A���n���́u�F����ς������āv�Ƃ������Ă��邵�A���͉����l�������ʂƂ܂Ƃ߂ēh�����Ă��܂��Ă��銴���ŁA���`��A�ǂ���������`�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

3.
�g�p�h���Ɖ��ϔ��ł��B
�ł����āA����͓d�ԏ�ō��ł͂Ȃ��A�u�i���G�t���ł݂�^���J�[�̐i���v�Ȃ� pdf �̃t�@�C�������A���Г��^�́u���M�ہv��O���ߏォ����Ղ��Ă��čb�͔����F�B�Ȃ�A��XF-57�u�p�t�v�ŁB
�������Ȃ���A�^����c��̂ł���˂��B���n�����Ƃ���Ɩؒ��肩���m���E�����ĉ\���������Ȃ��ł����A�ǂ�����قڍŌ㖘���h���̂܂܂ł����B�������A�������͂Ƃ��ĊC�R�ɒ��p��͐����ʂ������ʂ��R�͐F��F�w��Ŋ�d���������l�������肵�܂��B�Ƃ���ƁA�|�唍���o���������̂ł�?�Ƃ��v���ė��܂��B�܂��A���m���E���ɂ��Ă��؍ނɂ��Ă��ǔR���̑f�ނł���A�����D�ɂ͂�����Ȃ��C�����܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

4.
���̍����̔����A�����̂��������ł��B���`��1���̃f�J�[���ɂȂ��Ă���܂��āA���݂₸������������Ē������Ă�����ɂԂ��Ԃ���Ă��܂��܂����B�E���͒��肽�̂ŗ\��3�������đΉ��B�����B
�ł́A700/700�̏����E�E�E��芸�����茳�Ɂu�����ہv�̂���͖����̂ŁA�u���m�ہv�Ɓu���{�ہv�̂�����E�E�E�����ꂱ��B
10026����,9974����
����152.4m�E�E�E���āA���D�͐�����?
�ő啝19.8m
�ő呬��19.5knots,19.2knots
S9/6/23���_�˂ɂďv�H�AS16/9/1�ɊC�R���p�AS18/11/25��v
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16

5.
�䂪�{�I�A�������Ċe���̊͑������łȂ��A�D�c���Ґ��\�ɂȂ�܂�����!!�ς��ς��ς��B����`�f���Ɋ������B���āA��������2�ǂ�����ǁB
�ƌ������ŁAH26/7/21�`H27/6/26�W���́w���D���o��`����ꓬ�́u�V�c�ہv�^�x�œo��́u�V�c�ہv�o���̂ǂꂩ��H28/2/4����w���{�C�R�̌�q�͒��B�x�œW���̓��U�^�C�h�́A�C�́u�����v�𗍂߂āB
AF Nikkor 28mm 1:2.8
1/1500
f22
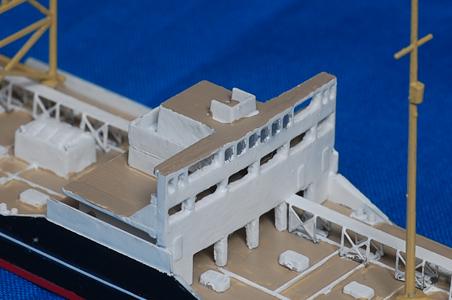
6.
��������͏��S����B
����A�D���ۗ̕�?����??���Č����Ă݂܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16

6-1.
�D���̑O�ʁA�J������Ă��镔���������Ă��Ȃ��̂ł���B�Ȃ̂ŁA�H��Z�p�I�Ɏ�ɕ�����͈͂ŊJ���\���ɂ��Ă݂܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
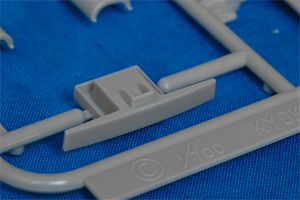
6-2.
�D���̔w��ɐڑ�����A�D���ŏ㕔�̕��i���A���N�ɂȂ��Ă���̂ŁA�O�ʂ��J�����Ă��������Ή����Ȃ���Β���ɕǂ��o�����邾���B�Ȃ̂ŁA��������荏�ގ��ɁB
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
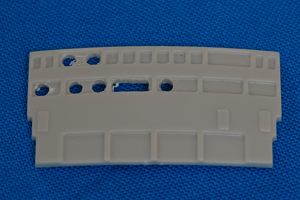
6-3.
����ȋ�ɐ��E���āA������q���鎖�Ƃ��܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
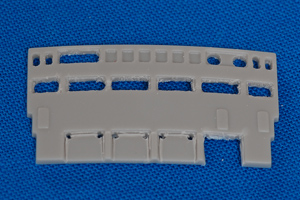
6-4.
�ǂ�ǂ�荏�݂܂��B�ŏ�b������6�ӏ��͑��ǑD�������������ŁA�ǂ����Ɏq�������ĕ͍\�����ۂ��̂ŁA����͐��E���Ȃ����ɂ��܂����B�w��̍H�삪��ςɂȂ肻���Ȃ̂Ŋ��������Ƃ������܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
4/1
f16
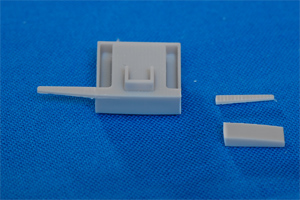
6-5.
�w��&�ŏ�b���i���A�v������ǂ�������ؒf��A�b��ɔ�����o���ċ�Ԃ����܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16

7-1.
�h���ł�����������̂��A���ˁB�u���{�ہv�Ƃ��ẮA���G�̒ʂ��n���œh��ƌ����Ă���̂ł����A�і�͕s���B�Ȃ̂ŁA����͎v�����āA����́E�E�E�����A���̍�����C�^�s���������Ĕі�C�^���݂ł��E�E�E�і�̃^���J�[�Ɍ�����䌅?�i�q�H??�Ɂu�g�v�̈ӏ��ɂ��Ă��܂��܂����B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16

7-2.
���ˁA�h�����ł��B0.4mm��1mm���̓h����\�̑g�����ňӊO�Ə�肭�s���܂����B�Ǝ��掩�^�B
���݂Ɂu�g�v�͑n�ƎҔі�Ћg�́u�Ɓv���Ӗ����Ă���Ƃ��ǂ��Ƃ��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/2
f16
H29/1/18�W�� �C����LST�`���{�̗g���͑��e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
P�Ђ́u���݁v�^����2�Ԋ́u���Ƃԁv��3�Ԋ́u�˂ނ�v�A�������u�݂���v�^���瑽�������͂́u�݂���v���B�u���݁v�^�̓W�����N�Ɛ��K���i�̊͑�2�Ǖ��ƁA���K���i1�Ǖ�+�u�������v���쎞�]��̋��ʑ����i�����ɍ���Ă���A3�ǂł�����ƂÂs���ӏ����������Ă���܂����A�܂��C�ɂ��Ȃ��B
�܂��A700/700�E�E�E�܂�{���E�E�E�ɂ��Ă��A�������ƌ������ŁA
���o���ߋ�������̓W����>
�ߋ�������͑D
�ɂ��W���ł��B
�������͐���Vol.596,600,660���Q�l�ɂ��Ă��܂��B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
������u���Ƃԁv�A�u�˂ނ�v�A�����u�݂���v�ł��B
����A�u�݂���v�͎̊�͔ԍ���? ����˂��A�f�J�[���s���s���Ȃ̂ł���B�ǂ����Ă�������Ȃ��Ȃ�u����v������]�p���悤���E�E�E�B���A�ǁ[��[��?����ȂɁA�u����v���͔͊ԍ���151�`158�A���āu�݂���v����4151�`4153�Ȃ̂ŁA��3���͗��p�o���邵�A154����4�����p�ł��邵���Ď��ŁB�Ȃ̂ŁA���ۉ��Ԃ�U�邩����ׁ̈A�w�����u�݂���v�x�ƕ\�L�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16

2.
�ォ�瑽���u�݂���v�A�u�˂ނ�v�A�u���Ƃԁv�ł��B
�u�˂ނ�v�A�u���Ƃԁv�͉E���̓��ڒ���LCM�ɂ��Ă���܂��B���K���ڂ�LCVP�Ȃ̂ł����A����Ȃ��̂�LCM�ɁB�ꉞ�A���ډ\�炵���̂ł����A�g�����u�ɔ�ׂĂł��߂��B
�����u�݂���v�͑����u�݂���v�Ō��L��܂���B�u�������v�Ŏg����������̂�ˁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

3.
������u���Ƃԁv�A�u�˂ނ�v�A�����u�݂���v�ł��B
�g�p�h���͂���Ȉz�B�̖͑̂w�ǂ�GM-9�ŁB����́u�������݁v���ł����A�h�����̓h���͍��т����������K�~�߂̐ԂȂ̂ŁA���{�I�͑��W����GM-29�ŁB��3�F���˒����A�b�̕��s�сA40mm�@�e�̏e�g�ɁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

4.
�ォ��u���Ƃԁv�A�u�˂ނ�v�A�����u�݂���v�ł��B
�ł�700/700�̏�����炠�ꂱ����B
|
�_
|
���^
|
�݂���^
|
|
��r����
|
1480�`1550t
|
2000t
|
|
�S��
|
89m
|
98m
|
|
����
|
40mm�~�A���~2��
|
3�D�~�A���~1��
40mm�~�A���~1��
|
|
����
|
13�`14knot
|
14knot
|
|
1�Ԋ�
|
�u���݁v
S47.11.27�A�� H10.2.13����
|
�u�݂���v
S50.1.29�A�� H10.4.7����
|
|
2�Ԋ�
|
�u���Ƃԁv
S48.12.21�A�� H11.4.12����
|
�u�������v
S51.3.22�A�� H13.8.10����
|
|
3�Ԋ�
|
�u�˂ނ�v
S52.10.27�A�� H17.5.20����
|
�u���܁v
S52.2.17�A�� H14.6.28����
|
�������ĕ��ׂ�ƁA�͔ԍ��̖��������͊Ԕ����Ɍ����܂��˂��B�ƌ������A���`��A���������ď��Ќ�E�E�E??
���X�ɉ��Ƃ����Ȃ��ƁE�E�E�B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
����I�o��3��������
H28/12/21�W�� ���b��(�|�P�b�g���)����� ���e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���������e�ł��B����̓t�W�~�́u�h�C�b�`�������g("Deutchland")�v�ł��B���b�͂̑�ꒅ�ł��ˁB
���X�AFryhawk�́u�����b�c�H�[("Lutzow")�v���݂ŁA��A�u�����b�c�H�[�v�Ɖ��������{�͂𗍂߂悤��?�ƌ�����|�ōw�������̂ł����A���ޑ���͑��Ђ̑��b�͂ƂȂ�܂����B
����Vol.405�����Q�l�ɂ��Ă��܂��B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
���́u�h�C�b�`�������g�v���̏o���A���������͑�D�]�������炵���ł��B�l�I�ɂ��ꖘ�̃t�W�~�ɂ��Ắu���߁v�A�u�����v�A5500t���ŁE�E�E�E�E���Ċ����ł����̂ŁA���\���҂��ĊJ���A�g�ݎn�߂��̂ł����A�o���A�q�P�����A�ꕔ���������A�����?���Ĝ�R�B
�o���͋��^�V�����̏��ׁB�q�P���C���͗e�Ղ������ƌ������ŁA�o�ꎞ�����l����A�܂��A����Ȃ��̂ł����ˁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

2.
�ł�700/700�̏����������B
��r���� 11700t
�S��186m
�ő啝20.7m
�ő呬��26knots
1933/4/1�v�H�A1945/4�픚����A1945/5���j�����Ɨ��A���̌�h�A�̎�ŕ��g����܂�����1949���
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

3.
������S���U��Ƃ���Ȉz�ɁB�O��̑����V�����l�ɂ��܂����B���āA�x����M���Ă��܂����P�Ɏh�����܂܂Ƃ������܂��B
�u�A�h�~�����E�V�F�[�A("Admiral Scheer")�v(�ȉ��u�V�F�[�A�v�Ɨ�)�ł͉��Ƃ����������ˊǁA�g�ݗ��ď����Ɏ��s���A�Œ���������܂���ł����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

4.
�g�p�h���͂���Ȉz�B�u�V�F�[�A�v�̎��́A�ɕ�������Ȃ�����ǂ����Ɍ��\���肵�܂������A����͎傽��͑̐F�͎w���Mr.308�ŁB
��̔@�����[�p�̉����߂̑����V�ƁA�������h���������̋N�d�@���O���Ă݂܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
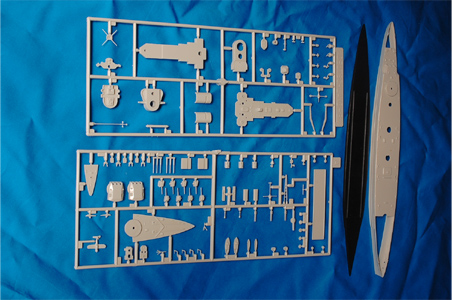
5.
��������͔�r�ҁB����͕��i�����B
�悸�͂��́u�h�C�b�`�������g�v�ł��B
���i�_����102�ł��B�͎���ƂƓW���p�͖̊��\���D?�̂ݔ�g�p�ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
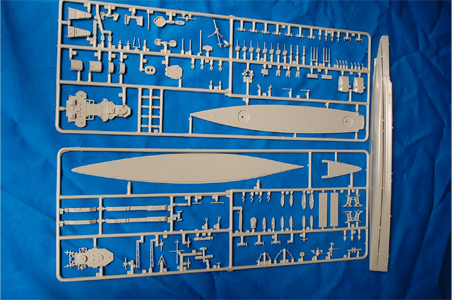
6.
H28/11/27����W���̃C�^�����u�V�F�[�A�v�ł��B
���i�_����168�ł��B�t�W�~��肩�Ȃ葽���B�����Ƃ��A�m��S�D�̌��p�ŁA���������^�͂Ƌ��ʂ̏��ׂȂ̂��A��g�p�������ł����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
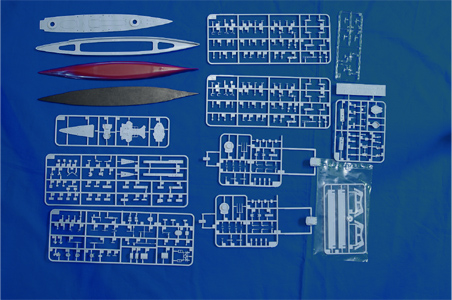
7.
���肵�������P�Ёu�A�h�~�����E�O���[�t�E�V���y�[("Admiral Graf Spee")�v�ł��B
���i�_����308�B�O��2�ǂɑ��Ċu�₵�Ă܂��B�m��S�D�̌��p�Ȃ̂Ŕ�g�p���o�Ă��锤�ł����A�ׂ������i�������A�v�H�͐�ɂȂ肻���ł��B
Nikkor AF 28mm 1:2.8
1/1
f16
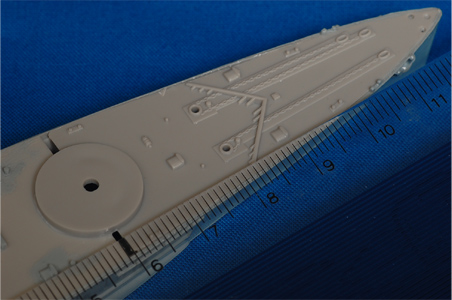
8.
�o����q�P�ɂ͊Â��_��t���܂������A�ɂ��ꕔ�̍����̈����ɂ�焈Ղ��܂����B
��\���Ċ͎�d�b�Ɗ͑̕����̌��Ԃ��B1mm���J���Ă��܂��B�����������ɍ���Ȃ��ƏC���͋p���Ċy�ł��ˁB���x1mm�Ȃ̂Ń^�~��1mm�p�_�������Ď����܂��Ă��I���ł��B
���̕����E�E�E�͋��̑O�ʂƂ���C�������V�Ƃ��E�E�E�͍���Ă͗l�q���A����Ă͗l�q���ƒn���ȍ�Ƃ�n���Ɏ��Ԃ�������܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
H28/11/27�W��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V |
�W���g�����h�C��S���N ��l�e(�ŏI��)�@�@��
���b��(�|�P�b�g���)����ב��i |
�W���g�����h�S���N�L�O�̘A����ŏI��B�Ō��Italeri��1/720�u�A�h�~�����E�V�F�[�A("Admiral Scheer")�v(�ȉ��u�V�F�[�A�v�Ɨ�)�ł��B
�u�A���\��("Anson")�v�ɑ����āu�n�E("Howe")�v���Ǝv���Ă��܂���?�܂�����ł��ǂ������̂ł����A���ꂾ����͂������Ƃ��Ƃ���ǂ��ł��B
�ŁA���̌�͒f���I�ɂ��̃|�P��B���ۂۂ쐬���悤���ƁB�ƌ����Ă�3�ǂȂ̂ł���ȂɈ��������b�ł͖����ł����B
����Vol.316�����Q�l�ɂ��܂����B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
Italeri��H22/7/27�`H23/6/28�W���́u1/72 SAAB�̒������@�B�̌n���v�̒���JAS39�u�O���y���v("Gripen")�ȗ��̓o��ł��B
�S�̓I�ɂ͍����͈����Ȃ��A�o���������Ȃ��A��Ƃ��ċN�d�@�W�Ń_�{���ƃ_�{������Ȃ��E�E�E�����E�E�E���Ē��x�ŕ��ʂɂ��ݏグ���܂����B
�Ƃ͌������̂́A�����A�b�A�h������4�����̊͑̂͂ǂ��炩�ƌ����Γ�f�ނ̏��ׂ��L���đg�ݍ��킹�ČŒ�������͖̂ʓ|�ł����B���̕ӂ�͐̂�WL�̗l�ɗ����Ɩw�ǂ̍b����̉�����Ă�������y���i�@�B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

2.
700/700�E�E�E����Ȃ���720/720�̏��������͈ȉ��̒ʂ�B
��r���� 11700t
�S�� 186m
�ő啝 21.3m
�ő呬�� 26knots
��C 28cm�~3�A���~2��
���C 15cm�~8��
1934/11/12�v�H1945/4/9�������픚��j���]
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16

3.
������S���U��Ƃ���Ȉz�ɁB
�������ˊǂ̂ݍ����������ł����A��C�͂��Ƃ��A���C���N�d�@���E���h�~�[�u���u���Ă��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16

4.
�g�p�h���͂���Ȉz�B
��̔@���A���̗ނ͖؍H�p�ڒ��܂ʼn����߂ł��B
����ɂ��Ă��A�ӊO�������͓̂��ڋ@�ł��āA���t�BAr196����Ȃ����Ď��ł���˂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16

5.
��������͍���ׂ́u��ׁv�̕������B��ׂ�̂͂���3���i�ŁA�u�V�F�[�A�v�ȊO��1/700�ł��B�t�W�~�͂��ꂱ��30�N�ʑO�́A�s�b�g�͂������N�̐��i�ł��ˁBItaleri�͉������������m��Ȃ�(^^);;
�ŁA����͑D�k�ɂ��āB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
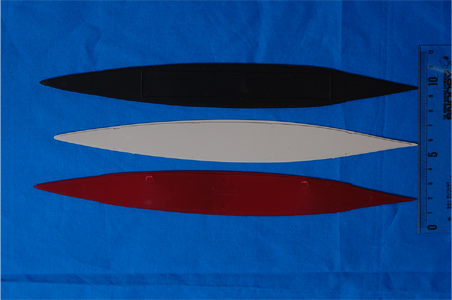
6.
�悸�͋h�����B�ォ��F�Ёu�h�C�b�`�������g�v("Deutschland")�AI�Ёu�V�F�[�A�v�AP�Ёu�A�h�~�����E�O���[�t�E�V���y�[("Admiral Graf Spee")�v(�ȉ��u�V���y�[�v�Ɨ�)�ł��B�����͈ȉ������l�ł��B
�܂������ł�1/700��1/720�̈Ⴂ���x��������Ȃ��ł��ˁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
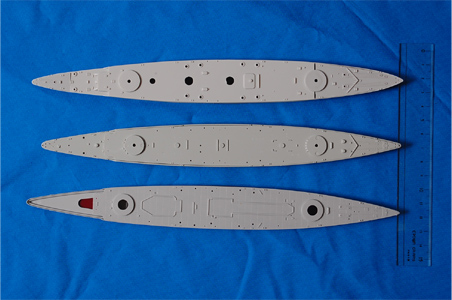
7.
�͑̂�g��Ŕ�r����ƁA�u�V�F�[�A�v�Ɓu�V���y�[�v���O�㋤�Ɏ����l�Ȕ䗦�Œ������Ɍ����Ėc���ōs���Ă��܂����A�u�h�C�b�`�������g�v�͎͊����ɑ��������Ȃ銴���ł��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
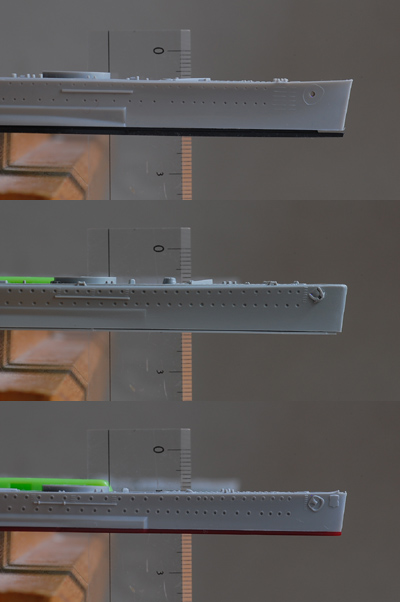
8.
�傫���قȂ�̂������̍����ł��B
��K�̖ڐ��������Δ���ʂ�A�u�h�C�b�`�������g�v>�u�V�F�[�A�v>�u�V���y�[�v�ƂȂ��Ă��āA�T��1.5�`2mm���x�̍����o�Ă��܂��Ă��܂��B
���͂ɂ��A�u�V���y�[�v�͑���2�ǂ��h�����傫���̂ł����A����ɂ�������9cm�ł�����A1/700�ɂ�����0.16mm���x�B�ƂĂ�����ȍ��ɂ͂Ȃ�܂���B���`��A�ǂꂪ�������̂ł��傤���B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
2/1
f16
����I�o��3��������
H28/10/11�W�� �쒀�͑�W���`H28�x�㔼���̐ς�
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���������܂������ȑ��ʂł��˂��B�Ƃ͌������̂́A�\��̒ʂ�쒀�͂�����ł��B����A��O�����邯��ǁB
�܂��AIBG��HuntII�͑����Ă�����̂́A���̂��ڌ����Ƃ������̐V���i�͊�{�I�ɖ����B�ڏo�x���ڏo�x���B
���āA�S�R�ڏo�x���Ȃ��킢�B�ǂ������A����ȂɁB
����܂��A���͂ł�������ǁA�g�ݏオ��Ώ������̂ł�����Ƃ̉䖝��B
��Ȗ�L�邩����!!
|
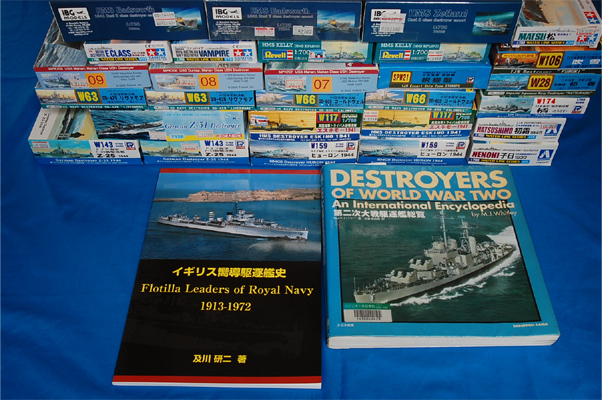
1.
�ƌ������ŁA�ȉ��A��i����s�A��̒ʂ�ɁB
IGB��"HuntII"��(�p�͔�)�~3�AT�Ђ́u���v�B
T��"E Class"�A"Vampire"�AR��"HMS Kelly"�~2�AP�Ёu����v
Midship��"Mahan 1942"�A"Mahan 1938"�A"Dunlap 1938"�AP�Ёu�𑨌^�v�A�u���t�v
P�Ёu�����@���A�v�~2�A�u�R�[���h�E�F���v�~2�A�u�k�v
D��"Z-31"�AP�Ёu�G�X�L���[�v�~2�AA�Ёu�����v
P��"Z-25"�~2�AP�Ёu�q���[�����v�~2�AA�Ёu�q���v
�ŁA��O�͎���o�ł́u�C�M���X�����쒀�͎j�v(�ȉ��u�����͎j�v)�ƁA�}���قł݂����u����쒀�͑����v(�ȉ��u�����v)�ł��B
Nikon D40
TAMRON 17-50mm F/2.8 A16
2/1
f16
ISO200
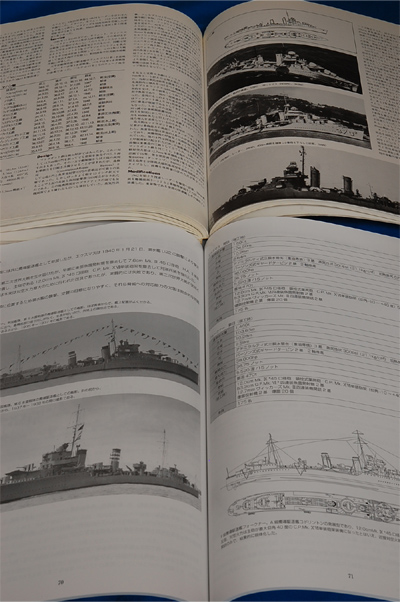
2.
�u�����v(��)�Ɓu�����͎j�v(��)��R�����Ƃ���Ȉz�B
���āA���ł���Ȃɋ쒀��?�ƌ����ƁA�悸��H27/10/21����W���́u�ϊ͎�(����)�v���O���ɗL��A�����ւ����b���̃W���g�����h�S���N�̉p�Ƒ�^�͏v�H��������āA���`��A�p�Ƃ͋쒀�͂𑝂₳�Ȃ��ƕ��ׂ����ɋύt�����Ȃ��i�@�`�ƁB�ŁA���@�ǂ��u�����v���B���������ꂱ�꒭�߂Ă�����ɁA��������������l�ɓ��A�āA�������邸�锃������?��������??����ɁB
�ŁA8�����ɏ���ɂāu�����͎j�v���B����Ȃɑ�����ł͖������̂́A�ڍא}�ʂ�����L�낤��1/700�Ōf�ڂ���Ă��āAE�AF�AO�AP�e���̚����^�ƈ�ʌ^����蕪����ꂻ���`�Ǝ~�߂ƂȂ�܂����B
�����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16
ISO200
H28/9/8�W�� �ɑ������쒀�́u�t�@���e("Fante")�v���C ���e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�w�ɑ������쒀�́u�t�@���e("Fante")�v�x��H27/6/26����A�w���̃t���b�`���[�B�`���i�uZ-2�v�A�u���p���g�v�x��H28/8/3���W���́u�t�@���e�v�A�����͔̊ԍ��͖��\�t�������̂ł����A�n���ɒ��Ãf�J�[����T�������ʁA�ڏo�x���\�t�ƂȂ�܂����B1�N�z���Ő���Ċ��H�ł��B
|
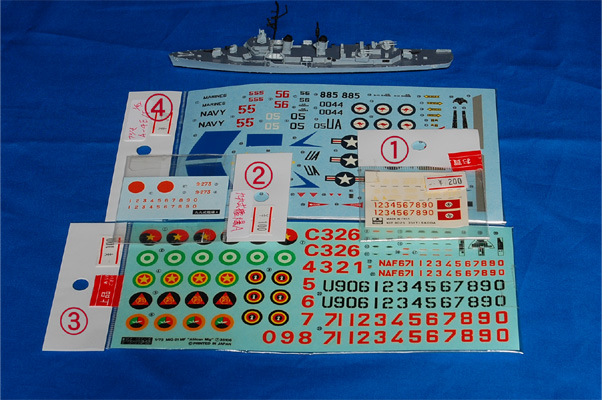
1.
�悸�͒��B�������Ãf�J�[���Ɓu�t�@���e�v���B
�����a�p��ɓ��芴��ł����A4�������B���Ă��܂��܂����B�����\100�`300���x�Ȃ̂ł��B�ƌ������A���@���K���Ŏz�l�ȐԂ��������Ė����˂��`�`�B�H�t���ƌ�������k���ƌ������A����A�Ŋ�͖��L�����낤��!!�ƌ������A���É�����4���őS���ʼn��S�������邾�낤�ɁA���߂�ὂ߂��Ă���ƈӊO�ƌ�����Ȃ��B������T���H�ڂɂȂ�܂����B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/15
f16
ISO200
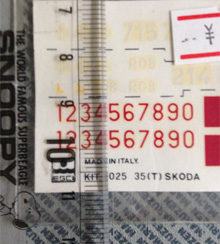



2.
1.���̐Ԋې����̏����Ŋe�X����k�ڂɊg��ł��B
�菇�O��ł������K���B�ɑ������́A�͔ԍ��̕\�L���Ԃ���ł��B�ŁA����ȃf�J�[���������A�h����ɂȂ��Ă��̎��������������ׁA�핢���āA�ƌ����̂��K�p�s�\�B�d�������̂Œ��Ãf�J�[���T���ƂȂ�����ł��B
�@�A�͏������ׁA�f�����Ӗ�����������Ɠ��荞��ł����肵�܂��B�B�����c�Ȍv��Ղ��ʂ荞��ł����肵�܂��B�v����ɂ����͔�r�I��k�ڂ̎��q�ƍq��@�̃L�b�g���o���Ȗ�ł��ˁB
����ɂ��Ă��A�C��"5"��������ĉ���?
Apple A1456

3.
�ŁA�@���̗p���鎖�Ƃ��܂����B
�����̒ʂ肩�Ȃ�Q��Ă��āA���ݓ��̘V�������i��ł������ƁA"561"�͔̊ԍ��ɂ͕K�v�[���Ȏ��ނł��鎖�A"0"����"D"���쐬����ɁA��r�I"0"���p�����Ă��č��Ղ����̓_����ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/8
f16
ISO200
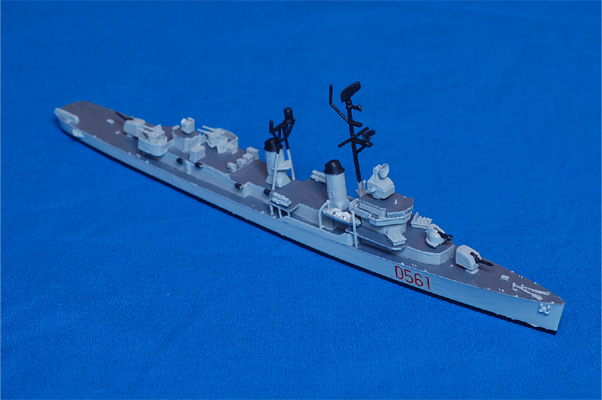
4.
�ƌ������Ŋ��H�ł��B(��)
���āA�c�����f�J�[���͂ǂ�����?
����˂��A����A�ɑ������ɂ͕ċ쒀�͂��s��5�Ǔn����Ă��܂��āA�u�t�@���e�v���܂�3�ǂ��u�t���b�`���[("Fletcher")�v���A2�ǂ��u�x���\��/�����@���A�v("Benson/Livermore")�O���[�v�B�܂�A�f�ނ͈����Ɏ�ɓ���B�����A�܂������̓��X�ł������`?
�Ƃ͌������̂́A���͔̊ԍ���552,553,555,562�������肷��B�܂�A�₽���5�������̂ł�����Ƒ���Ȃ��B����҂āA�f�J�[���C�͊m���E�E�E
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
ISO200
H28/7/20�W�� �W���g�����h�C��S���N ��Q�e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
7/20�A���b�T�C��150���N�������肵�܂��B�ƌ����Ă��A�u���E�f�B�^���A�v���u�t�F���f�B�i���h�E�}�b�N�X�v���ˏo���^�ł͓��R�̗l�ɏo�Ă���܂���B���I�Ȃ�A���h����͂́u�J�C�U�[�E�t�F���f�B�i���h�E�}�b�N�X�v�Ƃ��Ă͏o�Ă��܂����A����ȕ��A�茳�ɖ����B
�ƌ������ň��������A�W���g�����h�B��Q�e��1/700�A�p��́u�A���\��("Anson")�v�ł��B�u�L���O�E�W���[�W�X��("King George V")�v(�ȉ�KG5�Əȗ�)����4�Ԋ͂ł��ˁB�^�~����KG5�����Ɏ���H���Ăł��������܂����B
�d�Ԃ�˂����Ă�����A'46�ݒ�̍������A�܂��A�L����x���̐������𗠕t������͂̎ʐ^���U������܂����B�ł���Α��̎o���ƕ��ʂ��Ղ����Ǝv���A'46�ݒ�Ƃ��A���̓��������_���̗p���ĉ������Ă��܂��B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�u�A���\���v�AWW2�̎����̃t�l�ł����āAWW1�͊W�������?�ǁ[��[����??
�悵��!!��������!! ( �ƁA���������Ɏ��@���� )
���́u�A���\���v���C��ɎQ�����Ă������炾��!!
���Ⴂ�܂��B�m���ɑO�h����͂����݂��Ă��܂����A�C��O�ɏ��ЁA��̍ς݂ł��B
���Ⴀ�A����KG5�͎Q�킵�Ă��邩��A�����Ɋ|���č����!!
���Ⴂ�܂��B����Ȃ�f����KG5�Ƃ��č��܂��B
���`��A�Ȃ�A�u�A���\���v�ƌ������O�̏������������ɏ�͂��Ă���??
���ے肷��ޗ��͖�������ǁA���R�Ƃ��鎑���������Ă���܂���B�����Ƃ����Ȃ��Ƃ��������A������ƃl�^�̍����ɂ͂���ł��˂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

2.
���́A�u�A���\���v�A�ʂ͖̊����\�肳��Ă���܂����B���ꂪ���ʌp���̂ǂ����ŕς���Ă��܂��A���X��2�Ԋ́E�E�E�܂�u�v�����X�E�I�u�E�E�F�[���Y("Prince of Wales")�v�E�E�E�ɗ\�肳��Ă����u�A���\���v������ė���4�Ԋ͖͂̊��ƂȂ��Ă���܂��B
���Ⴀ�A�v�ɂȂ�������?�\���??�͖��͉����ƌ����ƁE�E�E�����u�W�F���R�[�v��������ł��B���_�A�u�W�����E�W�F���R�[("John Jelicoe")��v����̂�ꂽ��ł��B
���݂ɁA���ʌp���]�X�̏ڍׂ́u�G�h���[�h8��("Edward VIII")�v�A�u������q�������v�Ƃ��ł������Ē�����Ώo�Ă��邩�ƁB���̉e����KG5���͖����ǂ��Ȃ������́A���ʂɐ��͂ɂ��L�ڂ���Ă��܂����AKG5���ł������Ă��o�ė��邩�ƁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

3.
700/700�̏����������B
��r���� 36727t
�S�� 227.1m
�ő啝 31.4m
�ő呬�� 28knot
���� 14�D�~4�~2+14�D�~2�~1�A5.25�D�~2�~8��
1942/6�v�H�A1957���Ё���̂�
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

4.
KG5����H21/10/17�`H22/10/10�W���́u�k�����C��v�Łu�f���[�N�E�I�u�E���[�N("Duke of York")�v(�ȉ�DoY�Ɨ�)�����������Ă���܂��B�ƌ������ŕ��ׂĂ݂܂����B
����`�ǂ������ł���
��͊͋��A���^�͂��Ėw�Ǎ������������ł���B�K�L�̎����́u�M�Z�v�A�u��a�v�A�u����v�A�u�����v�A�u�}�K�v���̂ǂ��炩�A�u���߁v�A�u����v�A�u����v�A�u�G���^�[�v���C�Y("Enterprise")�v�A�u�T���g�K("Saratoga")�v�ƂĂ�ł���B�Љ�l�ɂȂ��đQ���u�A���]�i("Arizona")�v�A�u�y���V�����@�j�A("Pennsylvania")�v�ƑO�X��́u�f�A�t�����K�[("Derfflinger")�v�A�u�����b�c�H�[("Lutzow")�v�Ɨ��Ă����3�g�ځB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

5.
�g�p�h���͂���Ȋ����ɂ��܂����B
�͑́ATS-32�B
��\�̐����ʓ��ATS-81
��b�ATS-68�B�C����XF-78
��C�V�W���\�̐����ʁAXF-53
�܂��A�O����͒P�ɍ����������Ƃ��āA��̒ʂ蕁�i�͂炵�ĕۊǂ��鎖�ɁB���������̋��x�ێ��ƎO�r�̊Ԋu�ێ��ׂ̈ɏ���ɉ�����lj����܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16
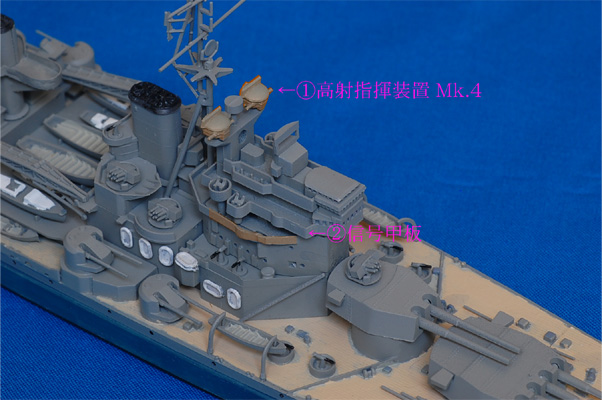

6.
�h���͂��Ƃ��A���ڒ����Ί�̔z�u���⌽���̕��ƌ��������H���s�Ȃ����̂ł����A���Ɏ�Ԃ̊|�������ύX�_�ɂ��āADoY(��)�ƕ��ׂāA����F�ɐF�������Ă݂܂����B
�@��5.25�D�C�̎ˌ��ǐ��p�̍��ˎw�����u�B��{��KG5�ł�Mk.3�Ǝv�����\���ƂȂ��Ă��܂��B����ɑ���'46�́u�A���\���v�ł�Mk.6�ƂȂ��Ă���͗l�ł��B
�A�͊͋��M���b�̑���ύX�B���Ȃ�g�傳��Ă����A4�A���|���|���C���ڂ����Ă���܂��B�ƌ����Ă��A�莝���]�蕔�i�̒���4�A���͖����ׁA8�A���ő�ւł��B
���������TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B�ŎB�e���܂����BF16�Œ�Ŗ�����1/2�`2/1�ł��B
6-�@.
���ˎw�����uMk.6�A��������4�g���Ȃ���Ȃ炸�A�p�e�łƂ��A�v���_�A�v����荏��ŁE�E�E�ł͂��Ȃ�쐬�������o�����B�Ȃ̂ŁA�]�蕔�i�𗘗p���܂����B
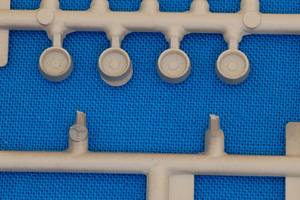
|
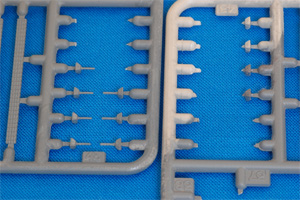
|
P�ЁuWWII�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�g[II]�v���
20mm�P���@�e�p�̚Ɨ�
���ˎw�����u�{�̂̏㔼����S�����܂�
|
�V�[���Y�u���p�C�R�͒������Z�b�g�v���
47mm�C
�h�|��2�g���ēd�T����g����A
�C�g��2�����������V��S�����܂�
|
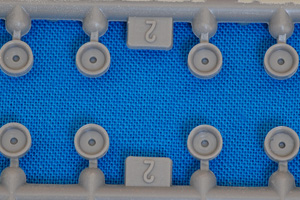
|
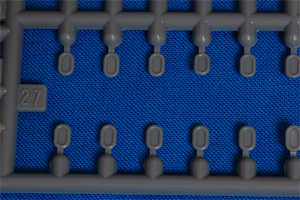
|
KG5�̑���12.7mm�P���@�e�p�ۗ�
���ˎw�����u�{�̂̉�������S�����܂�
|
KG5�̋~����
1/3�ɐ��Ďx�����̏�ɓ\��t���E���h�~
|

|
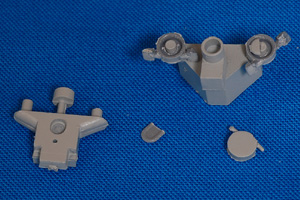
|
4��쐬���܂���
��3�͉������A�E3�͏㔼��
�����͏㉺��g�ݍ��킹�܂���
|
�x�����Ƒg�ݍ��킹��
���͊͋���̂ŁA�x���������߂��ŗv�ؒf
�Е��͐ؒf�ς�
�E�͌㕔��\�̎x����
�������ĉE���͔��ɔ���t�ς�
|
6-�A.
�M���b�͂���ȋ�Ƀv����荏��ŁB
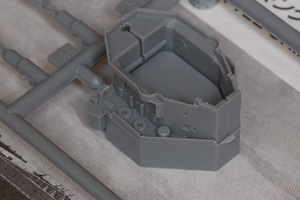
|
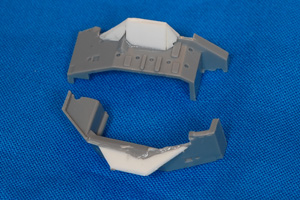
|
�悸�f�̏�Ԃʼn��g��
�����ʍb����2�w���̕��ɍ��킹�鎖��
|
�����ʂ͐}�ʂ��N�����Đ�o���Ď��t��
���ǂւ̌X�������t���͑S�����ꍇ�킹
|
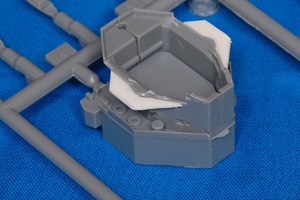
|
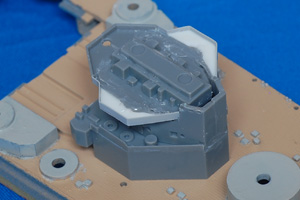
|
|
�e���i�ڒ�
|
�X�Ƀv�����ŚƗۂ����
�b��ɍڂ��Ă݂܂����B
|

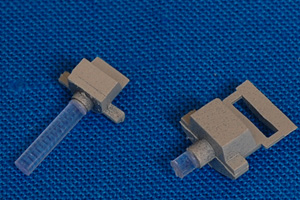
7.
���̑��A���K�͂̉��H���B
���͔͊��̓d�T�x�������~���ł͂Ȃ��A�l�p����Ȃ̂�3mm�p�v���_����āB���݂ɁAKG5���{���͎l�p����炵���B
�E�́A6-�@�ō��ˎw�����u�����H���ʂŔh���I�ɂ��邭����l�ɂ��Ă��܂����̂ŁA��C�ˌ��w�����u��������Ŏx���������ĉ��l�ɂ��܂����B�����Ƃ��A�͋��̎�w�����u�́A�����ʂ��������A���]������Ɠ]��������E�E�E�B
H28/6/26�W�� �W���g�����h�C��S���N ���e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�u�����b�c�H�[("Lutzow")�v�ɂ��܂��œ�����G37���������ł��B
���e�ňꏏ�ɁE�E�E�̐ς��肾�����̂ł����A2�_����Q�ɂԂ�����A�Ԃɍ����܂���ł����B
Nikon D40,TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
���̈��ʂł��܂���?�ƌ����ƁA���^��G38���u�����b�c�H�[�v�̎������Ɏ~�߂̗��������A�܂��A�i�ߕ����ڏ悵���ƌ������Ȃ炵���ł��B
����ɂ��Ă��A�ʔ��肹��̂ł����˂��B���������ȗ�2�N���O�o�Ǝv���̂ł����A�����Ɏ�����ʔ��肹���B�ǂ����Ăł��傤�˂��B�����Ǝv���̂�����ǁB
1/2
f16

2.
700/700�̏������B
���ڔr���� 1051t
�S�� 79.5m
�ő啝 8.36m
�ő呬�� 34Knot
��Ԋ�G37��1914/6/29�A���ȍ~�A���Ԃ�G40�����^4�ǏA�����AG37��1917/11/4�ɐ�v�A���̓X�J�p�[�t���[�ň�Ď������܂����B
1/2
f16

3.
���ʓ���AS-10�A�b�̑啔����XF-63�A�h������GM-29�ŁB
�v�H�x�̏�Q����1�͂���AS-10�ł��B�{����WEM Colourcoats��RN23�œh��ƁB���������?�^�~���ƃO���[�̎w��͖����B�Ȃ̂ŁA�d�Ԃ�˂����Ă݂�ƁE�E�EWhite Ensigen Models�������ŁA���`��!!����Ȃ�A�������������`�B
�ƌ������ŃA�L�o�A���W�قցB8�K�ł͑S�R�m��Ȃ��ƁB6�K�ł͐̈����Ă�������ǔ���Ȃ��̂ŁE�E�E�ƌ������ŁA���Ⴀ���e��2�ǂƓ����ɂ��Ă��܂���!!�ƂȂ�܂����B
1/1
f16
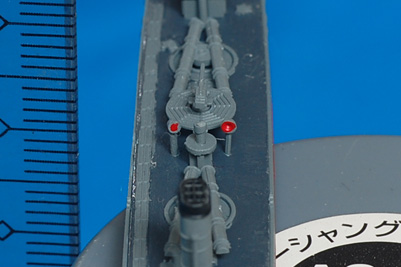
4.
����1�_�A�������̂͂��̒������̉��nj^�ʕ��ǁA���E�ňقȂ��Ă��܂��B1���ōs���Ă��܂��܂����B
orz
�v���������A�v���_�łł��������܂����B���̍���(�E��)�ł��ˁB
��0.5mm�Œ��������A��1mm�ŊJ�������B�J�����A2������E�����݂��̂ł����A��肭�s�����f�O�B���ʂ̒�����Ԃ����Ă�����������Ċ����ł��B
TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B
1/1
f16
H28/5/31�W�� �W���g�����h�C��S���N ���e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���N�w���C�C��120���N�L�O�x�A��N�w���{�C�C��110���N�L�O�u��ցv�u�֎�v�v�H�v�x�Ɨ��ăg���̓W���g�����h�C��ł��B
�C���'16/5/31��12�����ɉp�Ƃ̒�@�������m�Ō��J�n���A���������ɏI���B�傫�ȑ��Q?���??�͓Ƒ�����~1+����~1�A�p������~3��r�����܂����BWW2�̃��C�e�C��Ɏ�����K�͊C��ł����A���C�e���L�͈͂ɓn��A�e�X�X���K�I�A�T�}�[���A�G���K�m�ƌ������ŋ敪���ꂽ�C��̏W���̂ł��鎖�����Ă���A�j��ő�K�͂̊C��ƌ����ėǂ��ł��傤�B
����A���̂̓t���C�z�[�N�̓Ə���u�f�A�t�����K�[("Derfflinger")�v�A���u�����b�c�H�[("Lutzow")�v�A�s�b�g���[�h�̉p��́u�E�H�[�X�p�C�g("Warspite")�v�ł��B
��҂́A���Ƃ��Ắu�E�H�[�X�p�C�g�v���J��������ǁA���o�Ƃ��Ắu�N�C�[���E�G���U�x�X("Queen Erizabeth")�v���̎Q���͂̂ǂꂩ���Ĉʒu�t���ł��B
�Q�l�����Ƃ��Đ��͊e���Q�Ƃł��B
Nikon D40,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�悸��3�Ǖ��ׂāB
������u�N�C�[���E�G���U�x�X("Queen Erizabeth")�v��(�ȉ�Q.E.�Ɨ�)�A�u�f�A�t�����K�[�v(�ȉ�DFG�Ɨ�)�A�u�����b�c�H�[�v(�ȉ�LTW�Ɨ�)�ł��B
�s�ςł��B���ɒZ���ԂŊ��H�o����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ŁA���莩�̂�3�����ł������A���Ԏ����̉E���������L���āA���ǂ�����5/27�ɑ����Ğ��̑g�ݏグ���I��芮�H�B5/28�ɎB�e�ƂȂ�܂����B
����A�O��́u�t���b�`���[�v�Ȃ��Ȃ���Ηǂ��̂Ɂ`���āA����Ⴛ���ł����A�������3�����ɂ͂قڏo���オ���Ă���܂����B�܂������݂��Â��������Ď��ł��ˁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

2.
Q.E.�͂�͂���{�C�R�̋�����͂Ɩʉe���d�Ȃ�܂��˂��`�B�O���O�r�O+�͋��Ƃ��A���͎�O�ƘL�s�̕��C�Q�A����ƋN�d�@�ƒZ���Q�Ƃ��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

3.
���̋K�͂̊͂ł���Ύ�C���邭��͎d�|���Ƃ��Ă͕��ʂł��ˁB���C���Œ��̕K�v�������Č����̂͂Ȃ��Ȃ��V�N�ł����B���̎�̋�����͂͑�w�ɏオ��O�E�E�E������35�N�ȏ�O�E�E�E�ɍ�����u����v���u�}�K�v���̂ǂ��炩���Ō�œ��R�����^�B�����Ɠ\��t���銴���ł����B
�Ȃ̂ŁA�̂͂��傭���傭�����|���Ă����܂��Ă��܂��Ă����̂ł����A����͂��܂����͏��œh���핢�\���ŕی삵�Ă��܂���̂ŗL���ł��B�ƌ������A���쒆�͂������Ă��܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

4.
700/700��Q.E.�̏����ł��B
�S��196.8m
�ő啝27.6m
����r����27500t
��C15�D�~2��~4��
���C6�D�~12��
����24knot
���925�`951��
1�Ԋ́u�N�C�[���E�G���U�x�X�v '15/1/19�A�� '48���� (���A�C�펞�͏C�����ŕs�Q��)
2�Ԋ́u�E�H�[�X�p�C�g�v '15/3/19�A�� '46����
3�Ԋ́u�o�[����("Barham")�v '15/10/19�A�� '41/11/25��v �C�펞Q.E.��4�ǂ̑�5��͐������
4�Ԋ́u���@���A���g("Valiant")�v '16/2/19�A�� '48����
5�Ԋ́u�}���[��("Malaya")�v '16/2/19�A�� '48����
����ɂ��Ă��A���C�A����Ɍ����Ȃ��B�����ޔ𒆂ɋ쒀�͂ɒnj����ꂽ�肵���ꍇ�͂ǂ�����̂ł��傤?��C�őΉ�??�܂����Ќ�������1���8cm���p�C???
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16

5.
DFG�ł��BDFG����1�Ԋ͂ł��B
���b�E�E�E�ƌ����������͘O?�E�E�E�A�ኣ���̏��ׂ��A�V�����Ȋ����ł��B�O������P���łȂ����WWII���̊͗e�ł��ʂ肻���B
��2���˂��Ԃ��̂��ڂ��䂫�܂��B����A�z���g?���Đ��͂�����ὂ����̂ł����A���`��A����������˂��`�Ƃ͌����A��1���˂ƐF�������Ɍ������ł�����ǁE�E�E�B�܂��ǂ����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

6.
������̕��C��Q.E.�Ɠ��l�ɌŒ肵�Ă��܂���B�Ȃ̂ʼn�E�E�E�Ƃ͍s�����A�}����藣���̍ۂɂۂ��ۂ��܂��B�߂��Ȃ̂˂��`�B
�܂��A��C�A�C�����邭��ɉ����čX��2��͕ʁX�ɘ�ł��܂��B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

7.
700/700��DFG�̏����ł��B
�S��210.4m
�ő啝29m
����r����26600t
��C12�D�~2��~4��
���C15cm�~12��
����26.5knot
���1112��
'14/9/1�v�H�A'19/6/21�����B�����͋x���̉p�ɂ��}�����̈�Ď����ł��ˁB
���C�A2�傾���͔������Ɍ����܂��B����Œǂ��|�����Ă����S?!
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/2
f16

8.
LTW�ł��BDFG����2�Ԋ͂ł��B
���^�͂ł����A�O����̌`����Ɉ���Ă��܂��B�܂�����A�z���g?�Ɛ��͂�R��������A������͂�������A�z���g����!!�ƂȂ�܂����B�Ƃ͌������̂́A������?�̍����h�������̎w�肪���Ȕ͈͂ɂȂ��Ă���܂��āA���ˊJ��������㕔�ɓ��ꂵ�܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
f11

9.
LTW�A�W���g�����h�펞�͏�����̊��͂ł����B�ŁA�p�������2�ǁE�E�E�u���C�I��("Lion")�v�Ɓu�v�����Z�X�E���C�A��("Princess Royal")�v�E�E�E����W���ˌ���H������肵�đ�j�q�s�s�\�ƂȂ莩�R�������ɂ�莩�������ƂȂ�܂����B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

10.
700/700��LTW�̏����ł��B�ƌ����Ă���{�I�ɂ�DFG�Ɠ����ł��̂ő���_���B
���C15cm�~14��
���1112��+�i�ߕ��v��76��
'14/9/1�v�H�A'16/6/1��v�B��v�ƌ����Ă��A��L�̒ʂ�̎��������Ȃ̂ʼnp����̔h��Ȓ��ݕ��ɔ�ׂ�Ɛl�I�͔�Q�͏��Ȃ������ƁB
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/4
f11

11.
H22/1/2�`H23/1/1�A�wHappy new year!! �p�����܂�̌ՒB�x�œW���́u�^�C�K�[("Tiger")�v���ꏏ�ɁB
���ォ��A
DFG �A�u�^�C�K�[�v
LTW �AQ.E.
�ł��B
�u�^�C�K�[�v�A����Ώۂ̐ݒ莞����'20��Ȃ̂Ŏ����Ȃ��̂ł����A�܂��C�ɂ��Ȃ��B
�����������������p�ƍ����C�핔���A�p3���ŏ���10�ǁA�������4�ǁA�Ə���5�ǁB���ꂱ��L�^��˂������̂ł����A�s�v�c�Ƃ���4�ǂ͖C�����킵�Ă��Ȃ��炵���B
AF-Nikkor 28mm 1:2.8
1/2
f16

12.
�u�^�C�K�[�v����������o���ė����̂ŁA���łɂ���Ȕ�r���BDFG��LTW�̃J�G�T���ƃh�[���̊Ԃ��Ă��܂��B�u�^�C�K�[�v��P��X�����l�ł��ˁB
�ǂ���������ɂ͋@�B���������Ă��邻���ŁA���ȏ�������i�@�Ɗ��S���܂����B�����l�Ȏ�C�z�u�́u�����v�����ł��ˁB�܂�������́u�^�C�K�[�v�ƈٕ�o���݂����Ȃ��̂ł����玗�ē��R�Ȃ̂ł��傤���B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

13.
Q.E.�̎g�p�h���ł��B
�b��TS-68�𐁂��Ă����܂��B�͑̂��㕔�\����Mr.��333���w��Ȃ̂ł����A�����É߂���w�Ǎ�����Ȃ����B���`��A������������߂ɂ�������!!���Ď���Mr.��305���g�p���܂����B�g���y�́u�h���b�h�m�[�g("Dreadnought")�v�����l�Ȃ̂ŁA������͎w��ʂ�ɂ��Ĕ�r����??
�܂��AXF-15�͒Z���̏�ʂƁA�b�̔����ȏC���Ɏg�p���܂����BXF-78�̕����ǂ��̂ł��傤����ǁA�����A�N�������ď�肭�h��Ă���Ȃ��̂ł���B
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
1/1
f16

14.
DFG��LTW�̎g�p�h���ł��B
�t���C�z�[�N�A��{�I��Mr.��XF�ƕ��L�ł͂���̂ł����A�s�v�c�Ȏ��ɁADFG�̓^�~����{�ALTW�̓O���[��{�ŋL�q����Ă��܂��B
�܂��A���̕��L���e�A���\�F�������قȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�Ί͑̂͑O��XF-66�A���337��62��3:1�Œ��F����ƁBXF-66��337�ɔ�ׂĂ��Ȃ�Z���ځB������337�ɂ͔�����������āA�S�R�Ⴄ�W������!!
�Ƃ܂�����Ȗ�ŁA�g������(���ƑS�ʑ��V�R�F)�̐F����^�Ƃ��Ď莝���̐F���{�Ɣ�r�̏�A�͑̂�AS-10�A��\��AS-26�Ƃ��܂����B
���˂�XF-7��XF-1�̒��F�ƌ����Ă��܂����A�������������o�Ԃ��Ȃ����낤�ƌ�������GM��27��29���B�ǂ��ł��ǂ��ł����A�O�Ґ������b�h�A��ҋ��}�o�[�~���I���Ɩ��t���Ă��܂����A�F������P���ɔ�r����ƁA�����o�[�~���I���Ƌ��}���b�h�Ƃ��������ǂ����?�Ǝv��Ȃ��������B
AF-Nikkor 28mm 1:2.8
1/2
f22
H28/4/25�W�� ���̃t���b�`���[�B�`��Q�e�u�X�v���[�A���X�v���u�t���b�`���[�v
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
��������Q�e�ł��B���̂��L�䂪��u�������������u�X�v���[�A���X("Spruance")�v�ꑰ�̒�����w�������u�t���b�`���[("Fletcher")�v�ł��B�S�͑̂����A���������Ȃ�Â��̂ŁA���X�͎��R�^���ł����グ���̂Ƃ��čl���Ă����̂ł����A���ƂȂ��Ă͕�̂̎�ނ������������L��A����Ă��܂��܂����B
�E�E�E���āA������ƈႭ�Ȃ���?�u�X�v���[�A���X�v���Č����Ă��邶��Ȃ����B�u�t���b�`���[�v������Ȃ����B
����܂��A�\�肪�u�t���b�`���[�B�v�ł����āu�t���b�`���[���B�v�łȂ��͎̂��͍����O��ɂ��Ă���܂��āA�܂荞�ݍς݂�������ł��B
�Q�l�����Ƃ��Đ��͊e���Q�Ƃł��B
Nikon D40,Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5,ISO200�ŎB�e���܂����B
|

1.
�u�X�v���[�A���X�v���A���X�͊͋��̒��O��Mk.16ASROC8�A�����ˋ@�𓋍ڂ��Ă���A���i�Ƃ��Ă͓�������Ă��܂����A�g�������ł�Mk.41VLS�ɂ���ƁB
�܂��A�O����͉��˒����̍��������͍����h������Ƃ̎w��Ȃ̂ł����AVLS������ď��Ȃ��Ƃ��O���͊͑̐F�Ɠ������ۂ���ł���ˁB�Ȃ̂ł������Ă݂܂����B
1/2
f16

2.
700/700�̏������ł��B
�S��171.7m
�ő啝16.8m
���ڔr����8040t
1980�A��
2004����
�u�X�v���[�A���X�v���A�����i�̋@�\�̊g���lj��ɔ����ė]�T���������v�ƌ����G�ꍞ�݂ł����A��ʌ����́u�A�[���C�E�o�[�N�v���ɉ����o�����l�ɑ��߂ɑޖ����Ă��܂��B�������ɁA���̗l�Ȕz�������ꂸ�Ɍ������ꂽ�uO.H.�y���[�v���̕����������������Ȍ��ʂɁB
4/1
f16

3.
H25/4/30�`H26/4/5�œW���́u�t���b�`���[�v���̐��u�t���b�`���[�v�ƕ��ׂāB
�u�t���b�`���[�v�ƌ����ƁAWWII�̑����m���ɖڂ��s�������ȗ��j�I�ȗ���Ȃ̂ŁA���@�������𗦂���F.J.Fletcher���v�������т܂��B����̕��͂���F.J.Fletcher���疼�t�����܂����B�����͖��ł������̖������͂��̏f���ɓ���F.F.Fletcher����ł��āA�w�����ɏ��Ȃ��炸�����쒀�͂����߂��ł��낤���Ƃ��Ă͂ǂ�ȋC���������̂ł��傤�B
1/1
f16

4.
�g�p�h���ł��B�͑́A��\�ɂǂ���AS-7������A�b��XF-24�A���͂��܂��܂ƁB
���ڋ@��324�őS�́AXF-1���r���B
X-11�ŗ����̑��B�����AXF-2��Y�ꂽ�B
1/2
f16

5.
��̔@���A�O����Ƒ�2���˂̃z�C�b�v�A���e�i�͖؍H�p�ڒ��܂ʼn����߂Ƃ��A���[���͊O�����Ƃ��܂����B
1/1
f16
H28/3/30�W�� H27�x�������̐ς�
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�O1�N�Ɠ�����22�������ł����A���Ԃ͔����������A�����ł��鎖�܂��Ă��v�H���͋t��1/4�Ƒ啝���ƂȂ��Ă��܂��Ă��āA���Ȃ�̓����ł��B
������˂��`�B
|

1.
�ł́A��i����A�e�i��������B
1�i�ځAAFVclub�u�m�b�N�X�v�AR�Ёu�A���A�h�l�v
2�i�ځAFryhawk�u�i�C�A�h�v�AR�Ёu�A���A�h�l�v�A�t�W�~�u�Ìy�v�A�R���z�r�[�u����vI�^
3�i�ځAFryhawk�u�I�[�����v�~2�AP�ЁuZ-28�v�AIBG�u�X���U�b�N�v1943
4�i�ځAP�Ёu�N�C�[���E�G���U�x�X1941�v�~2�AP�Ёu�A�h�~�����E�O���[�t�E�V���y�[�v�AIBG�u�N�����B�A�N�v1942
5�i�ځA�t�W�~�u�R��v���a13�N�AP�Ёu�A�X�g���A�v�AITARELI�u�A�h�~�����E�V�F�[�A�v�AFREEDOM�u�A�L�e�[�k�v
6�i�ځAP�Ёu�E�G�X�g�E���@�[�W�j�A�v�AP�Ёu���V�������[�v�AP�Ёu���[�}�v�AFREEDOM�u�A�L�e�[�k�v
Nikon D40
AF Nikkor 28mm 1:2.8
2/1
f16
ISO200

2.
��������͒��ڂ̐V���i���B
�悸��P�Ёu�N�C�[���E�G���U�x�X1941�v�B
����1918�ł͔�������Ă���܂������A�N�Ⴂ�ł̓o��ł��B��{�̃��b�p�ł͍�N���ɂ͔�������Ă����̂ł����A���{�����d�l���ׂ̈�10�����߂��|�����Ă��܂��A���H�����ŁA2�����B���܂����B
���b�p�ł͂قړ������Ɂu�o���A���g1939�v���������Ă���̂ł����A������͂����Ɏ����P�Ђ��̍��m�����A�ʁ`�B
Nikon D40
AF Nikkor 28mm 1:2.8
4/1
f16
ISO200

3.
Fryhawk�́u�I�[�����v�ł��B���m�́u�i�C�A�h�v������ŁA�u�f�A�t�����K�[�v�Ɠ������������̂ł����A�u�i�C�A�h�v�̌�o��q���Ă��܂��܂���
�ł����āA���ЁA�����啗�C�~���L���Ă���A���N�̔����\��́uJ,K,L���쒀�́v�A�u�n�[�~�[�Y�v�A�u�����g�P�v�A�u�G���f���v�A�u�o�C�G�����v���X�B����Ȃɖ����ł��傤?�ƌ������A�o��������炱�����̍������E�E�E�B
Nikon D40
AF Nikkor 28mm 1:2.8
2/1
f16
ISO200

4.
IBG�́u�N�����B�A�N�v�u�X���U�b�N�v�ł��B
�pHunt II����q�쒀�͂̓��A�|�[�����h�ɏ��n���ꂽ2�ǂł��āA�߁X�X�ɏ��n1�ǁA�p��1�ǔ����\��ƕ����܂��B
����`�h�����܂�����A����ɂ́B�������A�����Ȃ��`�B���̖w�ǒ��������������̔��ɓ�����\2k�㔼�̒l�t���ł��B�����l�Ȉʒu�t���ɂȂ�u���v���DDE��3�Ǖ����x�����Ă��܂��܂��B
�ƌ����A���̕ψʓW�J��2�i���������Ⴄ�낤�Ȃ��`�B����ʼnp���Ă̌�q�쒀�͂���ׂ��p��z������Ƌ��M�ł��B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
f16
ISO200

5.
����܂��h����FREEDOM�u�A�L�e�[�k�v�ł��B������ƒ������k���C�����ł��āA����Ŕ̔����i\4k�䔼�ł����A�����ł����E�E�E�B
���́A�Ĕ̂̊|�������u���V�������[�v�Ɓu���[�}�v�A�w���͔����������̂ł���B�ł����A�قړ������ɂ��́u�A�L�e�[�k�v�̘b����яo���Ă��܂��āA���H�̊ϊ͎��݂����Ȏ���3�N����E�E�E�Ǝv���ƕ��͑��A�u�A�L�e�[�k�v�����ł͎₵���B�Ȃ�u���V�������[�v���ꏏ�ɕ��ׂ悤�B�ŁA�ŎM�Łu���[�}�v���B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
2/1
f16
ISO200

6.
�R���z�r�[�́u����v�ł��B�V���Ǝ҂Ƃ��Ă͗B�ꍑ���ł��B
���^I�^�͎�C�`��Ɖ��˗��e�̒ʕ��nj`���̓_�ŁAWWII��IJN�쒀�͂̒��ŋ��w�̍D�݂ł��āA�܂����������Ď��Ŕ�ѕt���܂����B
T�Ђ�P�Ђ̍ɕi�Ƃ̋���Ƃ��y�������B
Nikon D40
Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5
4/1
f16
ISO200
H28/2/4�W�� ���{�C�R�̌�q�͒��B
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
���āA���Ƒ�U���ȕ\��BP�Ђ̉L���^��^�|�C����^�Ə̂��Ă���u���U�v�^�C�h�͂�A�Ђ̖C�́u�����v���쐬���܂����B
|

1.
������u���U�v�^�A�u�����v�A�u�����v�ɂ��܂��ŕt���ė���95���y��ԁ~2�ł��B
��O�Ɍ������ꂽ�u�����v�́A�ؒ���̍b�A���Z���̗ǂ������Ȓ����͎�O�A�h���̕t�����@�e�Ə��^�͂̊��ɍ��ȑ����ŁA���āA���̗ʎY�C�h�͂ƂȂ����u���U�v�^�́A�H���팸�̊p�^�͔��Ⓖ���̑����͌`�A���g���ɋ^��̎c��Z���͎�O�A���̊��ɋ@�e�A�����������ߑ��ŋ��Z���̂���ǂ����v������܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-AF ZOOM 1:3.2-4.5 28-105mm
4/1
f22
ISO200
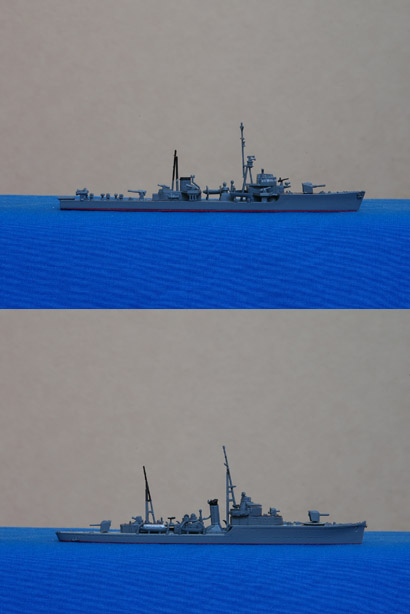
2.
��A�u���U�v�^�A���A�u�����v�ł��B
�u���U�v�^�A�����͑���10�N�ȏ�O�Ǝv���܂��B���āu�����v�͂������N�̕��ŁA�����ׂ̍����́u�����v�������Ă��܂����A�u���U�v�^�̕�����������Ƒg�ݏオ��܂��B
PENTAX istDs
smc PENTAX-AF ZOOM 1:3.2-4.5 28-105mm
4/1
f22
ISO200
����I�o�A�\�}2�������������̓g���~���O

3.
���A�u���U�v�^�A�E�A�u�����v�ł��B
�b�h�F�A�u�����v�͘b���ȒP�������̂ł����A�u���U�v�^�̓��m���E����������������Ă���ɂ��ւ炸�A���ϔ��ɋL�ڂ̓h�F�w��͑S�ʌR�͐F�̂݁B�����������猩�Ă��ǂ�����L�蓾�����Ŗ����܂������A�F���̕ω����������ƌ������Ń��m���E�������̗L�镔���̓��m���E���F�Ƃ��܂����B
PENTAX istDs
smc PENTAX-AF ZOOM 1:3.2-4.5 28-105mm
4/1
f22
ISO200

4.
����܂��A����2�ǂ�g�̂͂��ꂪ�����������̂ˁB
�ƌ������ŁAH26/7/21�`H27/6/26�W���́u�V�c�ہv�^�������āB�u�����v�͂Ƃ������Ƃ��āA�u�V�c�ہv�^�̒��p������u���U�v�^�̏A�����������Ă���ƗL�蓾�Ȃ��\�}�ł����B
PENTAX istDs
COSINA 1:2.8 24mm
4/1
f22
ISO200
H27/12/13�W�� �C���u�������݁v�`���{�̗g���͑��e
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
T�Џ��E�E�E�ƌ������AWL�ł͂���Ɠ��^�́u���������v�����o�Ă��Ȃ��E�E�E�̊C���͂ł��B�����Ƃ��ẮA���̕��b�͓o��ƌ������Ő��ԓI�ɂ�����ق�b��ɂȂ����E�E�E���E�E�E�Ƃ͌����A���Ȋ͂��J���������̂ł��B
�ł����āA�V���[�Y���ƌ����Ă�����Ȃɑ����̂������?�Ǝ����ł��^�△���͂Ȃ��ł����A�v���o�����l�ɓo�ꌩ���݂ł��B
|
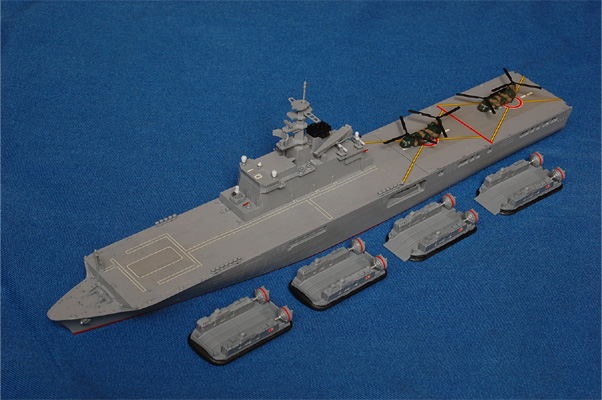
1.
�悸�͓�����LCAC��CH-47�������āB
LCAC��2�Ǔ��ڂł����A�q��(��O�ƌ����������ƌ�����)��ԂƊi�[(��?�E??)��Ԃ�2�ǂÂ����Ă��܂��B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
1/1
f16
ISO200
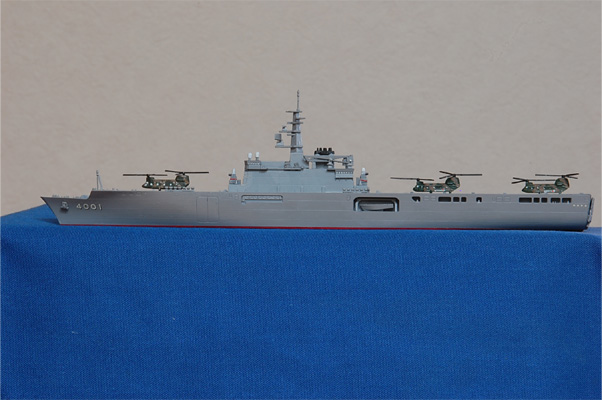
2.
P�Ђ�CH-47�����܂��Ŋ͎ɏ悹�Č��܂����B
�͑̂Ɗ͋��̓h�F���قȂ��Č����܂����A����̒ʂ�{���͓���ł��BRCS�ጸ�̑��njX�������̊W�ł�����������Ď��Ȃ̂ł��傤�B�ƌ����Ă�����Ȃɑ傫���p�x�ŌX���Ă����ł��Ȃ��̂ł����˂��B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
8/1
f16
ISO200
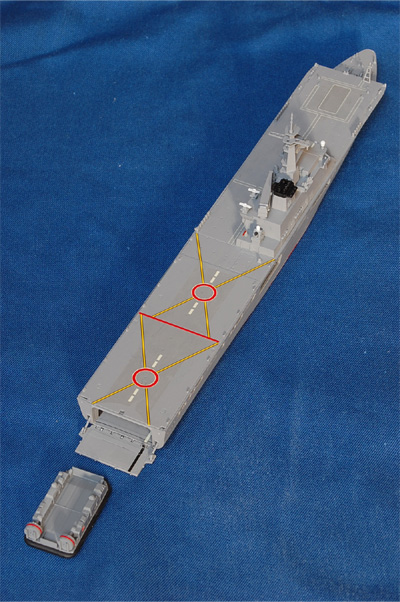
3.
������Ǝd�|�����L���āA�͔����������J����l�ɍ��܂��B�����Ƃ��A�g����������������A�ߐ莞�Ɏ���Ԃ��o�����ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
2/1
f16
ISO200
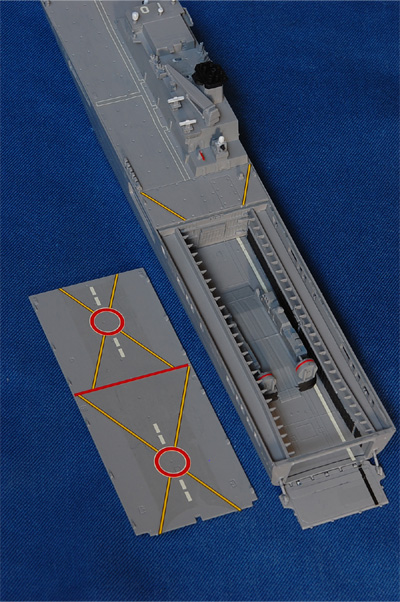
4.
�X�ɁA�b�㔼�͌Œ�����������ȋ�ɂ��鎖���B���ׂ̈ɂ킴�킴�b���b��̃f�J�[������������Ă��܂��B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
2/1
f16
ISO200
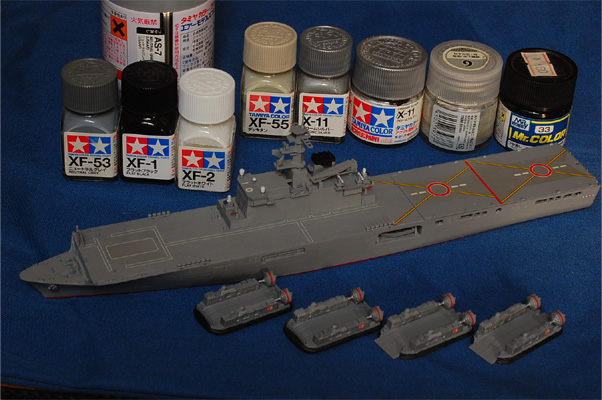
5.
�g�p�h���ƁBT�Ђ̓h�F�w��͎v�������薳�����܂����B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
1/2
f16
ISO200
���x����

6.
CH-47�̓h�F�͊͑̂ƈقȂ�̂ŕʓr����Ȋ����B��������A������P�Дłō쐬�������̂ƍ��킹������ɂ��܂����B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
2/1
f16
ISO200
H27/10/21�W�� �ϊ͎�(����)
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
�ƌ������ŁA�����őS�v�H�͑D���A�ϊ͎��ł��B
�S�����܂Ƃ߂Ă��Ĕz�u�ʐϓI�Ɍ������̂ō��ʂƂ��Ă݂܂����B
�ŁA�o�ꏇ�����ǂ����悤���E�E�E�B������?�Ƃ��v�����̂ł����AJapan��Nihon�Ƃ�U.K.��Great Britain and �E�E�E�Ƃ��Y�ނƂ�����L��̂ŁA�K�͂̑傫�����ɁB�K�͂͂ǂ����f���邩??�r����+���g���ōs�����ɁB�܂���������ڔr����10000t�Ɗ�r����5000t�{5000��t�Ƃǂ������傫���Ƃ������ɔY�݂����ŁA���ہA�p���́E�E�E�B
|

1.
��芸�����A���ʂ͉p���B
��r����83297t�{����r����71100t�{���ڔr����28050t��182447t�ł��B
�őO��͑����̋쒀�͂���̂ɁA���i3��͌���́A���͑�^��͊͒B�ł��B
�������Č���ƁA�K�͂����łȂ��A�V���̋ύt�����Ă��āA�B���ꂪ����Ƃ��A��^�C�핔�����r���Ƃ����͂��ŋ��Ȋ����ł��B
�͍ڋ@�͏ȗ��ł��B�t�l��{�I�����������o���ĕ��ׂ邾���ő厖�ł����̂ŁB
Nikon D40
SIGMA HIGH-SPEED WIDE 28mm 1:1.8
4/1
f22
ISO200
���͎�g���~���O
���x����

2.
���ʂ͓��{�B
��r����86669t�{����r����56040t�{19871��t��162580t
�p���������͑����A���ׂ�̑�ςł����B�܂��A��ƒ��v�~���]�����Ă��܂��A�O��������̏��j�B���^�͒��������ċ����ł��B
�ψʐ��͈�Ԃł��ˁB�����19���I��������21���I�A�𒆖��A��ނ͓�Ɋϑ��D����DDG���A�R�p�͒����Ȃ��͂Ƃ������狋�͂Ƃ������A�y�����ł��B
Nikon D40
SIGMA HIGH-SPEED WIDE 28mm 1:1.8
4/1
f22
ISO200
���͎�g���~���O
���x�A���Ô䒲��

3.
��Q�ʂ͍��B���B
��r����111198t�{���ڔr����7615t��118813t
��͂�ƌ������A�ӊO�ɂ��ƌ������A�ؐ��ڗϓ֗����̎Q������ʂ��߂܂����B
���B���̓����͌���͂����Ȃ����ł����ˁB�ݑ��͂ƍ����͂ɂ͂�����ʂ�Ă��܂��Ă����܂��B�Ȃ̂ŁA�����+���m��+�쒀�͂̍����O�q�����Ɛ��+��q�쒀��+�g���͂̍U�������݂����ȋ�z���o���Ă���͂���Ŋy�����B
Nikon D40
SIGMA HIGH-SPEED WIDE 28mm 1:1.8
4/1
f22
ISO200
���͎�g���~���O
���x����

4.
��l�ʂ͓�(�E�A��r����45129t)�Ƒ�܈ʂ̑h/�I(���A���ڔr����17520t)�ł��B
�K�͂�����������܂�Ƃ��ė����̂ł܂Ƃ߂Ă݂܂����B��ʎQ�����Q���Ȃ炱���͓��ł��傤���B
���ɈӖ������������킹�Č����̂ł����A���̑o���A�Ό�������ǂ��Ȃ�܂����˂��B�K�͂〈���ڂ̔h�肳�͓Ƃł����A���͂͝h�R�ł��傤���B
�u�i�k�`���JIII�v��SSM�����邩�A�����邩���A�������肵�����ł��B
�Ƒ��͐�ɑ�������Ď��͂����͂�ł��܂��Ƃ��A�ꕔ�̋쒀�͂��Q�S�C�ɂ��Ă��܂��Ď˖Ղ����Ă��琅��C����Ɏ������ނƂ�����B
�h/�I���͋t�ɑ�^��3�ǂ��]���o��őO�������āA�Ƒ��ɔ�������邩�A�������邩����O�ɔ��˂��Ă��܂��B����ȂƂ���ł��傤���B
�����Ƃ��A���ɂ������h/�I�̕���̐��x�A�M�����ł�����A�r���ōs���s�����������o�����ł͗L��܂����B
Nikon D40
SIGMA HIGH-SPEED WIDE 28mm 1:1.8
8/1
f22
ISO200
���͎�g���~���O
���x����

5.
��Z�ʂ̒�(�E��A����?�r����9605t)�A�掵�ʂ̍�(����A��r����3370t)�A�攪�ʂ͓����Ő��lj�(�E���A��r����2100t)�ƈ�(�����A��r����2100t)�ł��B�����܂ŏ�ʂ͎Q�����Ɨ��ċ���̂ŁA�l���O�ƕ]���ׂ��ł��傤���B
���̒��Ŏ��͖ʂ̏��ʂ�t����Ƃǂ��Ȃ���̂��B���ȊO�̎Q���A���ڂ��Ă��钆�����a�C����ԑ����ς�ł��ė������c���Ă��鐼�lj傪��������Ă��銴���ł��B�Ƃ͌����A����5�D�C�̕����˒������������肵�܂����AFCS���V���������x���ǂ������B�Ȃ̂ŁA�ɂ��ʼn��ʂŐ��lj�vs.���͔����ȏ����ƁB
�Y�܂����̂͒��ł��ˁB�˒��͒Z�����ݑ������ŁA��p�^���I�ɂ͐U�������ŏI��肻���B�����A�u�艓�v�͎���ő�ʂ̒������a�C�e��@�����܂�Ă��ς������т��L��܂����A��Nj���_����u�艓�v���ڂ������������Ă���ԂɁu�ω��v���ԍ������l�߂�Ƃ��E�E�E�������B
����������Ȃ��₵���̂ŁA������Ƒ��������Ă��������C�����Ă��܂����B�ƌ����Ă��A���ʂ�"Flecther"����lj�������x�����E�E�E���A�ɂ͐�͂��ɂ��Ă������B
Nikon D40
Zoom Nikkor 35�`105mm 1:3.5�`4.5
4/1
f16
ISO200
����2,3���g���~���O
���x����
H27/10/14�W�� �ϊ͎��`��
R02/07/14 ���䕶�X�V
R02/08/24 ���䕶�X�V
700/700�̐��E�ł͊C���ϊ͎��T�Ԃł����A�ّ�{�I�������n�Ƃ��Ă���1/700�̂�����ϊ͎������s���Ă݂܂����B(��)
|

���`��A�������ׂ�ƁA�Ƃ��`���Ă��C�����ǂ��B���E�E�E�p�ēƑh���X�E�E�E�����ׂĂ݂悤�������B
�ŁA�s��ʂ�ɂ����Ɨ���ƁA
�u�Ƃ킾�v�A�u����܁v�A�u�͂������v
�u�䂫�v���~4
�u�����v���~4
�u�������v�A�u�͂��܁v���~2�A�u�Ȃ݁v���~2
�ł��B�u����Ȃ݁v�͖����ł��B
Nikon D40
SIGMA HIGH-SPEED WIDE 28mm 1:1.8
4/1
f22
ISO200
H27/9/23�W�� �h���~�̉́`H26�x����������H27�x�㔼���̂��z�{
H28/8/29 �폜
|
Top�ɖ߂�